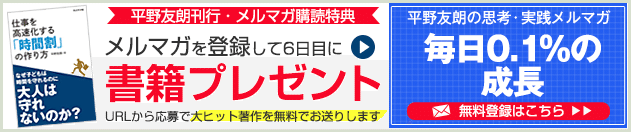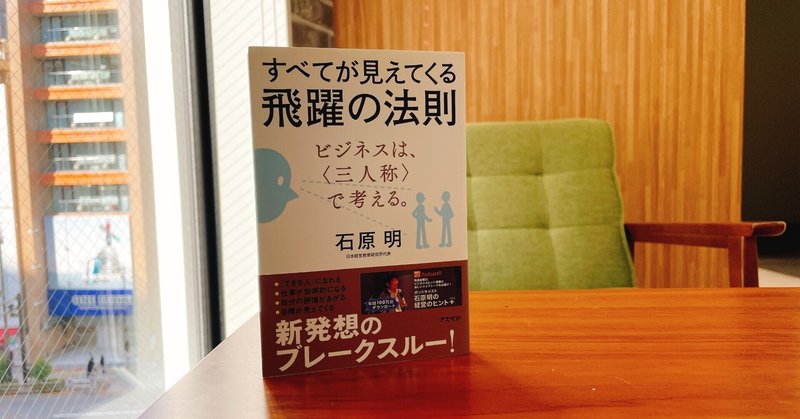
【読書録】すべてが見えてくる飛躍の法則(石原明・著)
なぜ、読んだ本を公開するのか
毎週日曜日7時~『ビジョナリー読書クラブ』というオンライン読書会に参加しています。そこでは、読んだ本の一部を引用し、自分の気付きを伝え、最後に何をするのかを宣言します。
いつも発表するときに、引用箇所を入力したり、Kindleでコピペしたりするのですが、それを消すのってもったいない。
あ!noteに残しておけば一石二鳥。
ということで、発表内容をまとめた記事を書き続けています。
お試し参加もできるので、興味のある方はぜひ!
読書が苦手な方も、きっと好きになりますよ。
今回読んだ本はこちら。
尊敬する経営コンサルタント石原明さんの書籍。石原さんには、「トップ3%倶楽部」で講演をさせていただいたり、実践塾の対談にでていただいたり、色々と教えていただいたことを思い出します。
【引用その1】一人称は自分だけの視点
一人称視点の人がビジネスで独立し、何かの商品を開発しようとしても、自分の作りたいモノを一生懸命に作っているけれど、それがはたしてまわりの人に喜んでもらえるかという思考に欠けています。まるで芸術家みたいに人の声に耳を貸さない状況に陥ってしまう、ということがよく起こります。
実を言うと、経営者の中にも一人称でしか物事を考えられない人がたくさんいるのです。横で見ていて、「それを言ったら社員の気持ちが離れてしまう」ということを、場面をわきまえずに平気で口にしてしまう社長を私は何人も見てきました。
自分視点というのは、集中していたり、熱中していたり、いいことかもしれません。しかし、その視点から離れることが出来ないと、協力を得られません。天才肌の社長で、我が道を行く……そんな人もいますが、成功よりも失敗している人が多いのではないでしょうか。
私自身、常にメタ認知をして高い視座から自分を見るようにしています。特に企業研修や講演の時は、天井から見下ろすイメージでバランスを取るようにしています。
【引用その2】三人称でバランスが取れる
「三人称」とはどういう状態かというと、自分が誰かにしていることを行動の対象者だけでなく、まわりがどう見ているかということも含めて考え、思考できる状態を言います。
先ほどの新入社員のクレーム対応の事例でいうと、もう一人、この状況を冷静に見ている自分がいるとして、その第三者の視点に立った状態です。
この視点を持ったなら、お客様の怒鳴り声に反応して、こちらも大声を上げたり、「バーン!」と電話を叩き切るような態度をとることもないでしょうし、その場しのぎで誤魔化して済ませるようなこともありません。
もし上司から「お客様が第一」と教えられているなら、極力、親切な対応を心がけることでしょう。たとえお客様の側に非があったとしても、誤解をさせてしまったことに対して、会社の代表としてお詫びするといった丁寧な対応ができるはずです。その人は、お客様への小さな対応の一っひとつも、長い年月の間には、会社全体の評価につながることがわかっているのです。
この視点でお客様に接することができたら、その社員は三人称視点による仕事になっていると見ます。この三人称が、現場とマネジメント層を分ける境界線なのです。
二人称で、自分と相手しか見えていないと、問題が大きくなる可能性があります。目の前の相手だけを強引にでも納得させたらいい、説得することが重要だ。そう考えてしまってはNG。他に見ている人がいるかもしれないし、時間軸で見ると将来問題が起こる可能性があります。
たとえば、目の前でお客さんに怒られている店員さんがいたとします。その場はしっかり謝罪して、お客さまの怒りも収まって帰って行った。その後、その店員さんが帰ってお客さまに対しての暴言を吐いたらどうでしょう。これって、人からどう見られているかという視点が欠如しています。
その後の対応も含めて、その人の評価につながるのです。
【引用その3】できる人は、視点を変える
その相手との関係によって、目線を上下自在に変えているのです。相手や場の状況によって、人称視点を変えているということですね。
六人称思考ならば世界マーケットと最低10年後、できれば30年後の世界を見通した上での判断の基準を持っている人です。
七人称になると、マーケットを外して、世界が自分や自社をどう見ているか?という経営的な判断によって、30ー50年後の我が社のブランドがどうなっているか、といったものの見方になるのです。
このレベルになると、自分が死んだ後のことも考えた上での判断ができるようになります。
一人称、二人称、三人称から始まって、最後には八人称までいってしまいます。そのくらい高い視座で物事を考えているかどうか。最近よく聞くSDGsもそうですよね。売上アップのために環境破壊するのはNG。10年後、50年後、100年後の世界のためにやるべきことをやる。こういった視点を持っていかないと行けません。
私も、自分の事業が世の中にプラスの影響を与えると思って、仕事を続けています。未来の誰の役にも立たない仕事は、すべて断ってきました。そうできるようになったのも、視座が変わってからです。
【引用その4】一人称に陥らないために
どうすれば感情に揺さぶられることなく、高い人称を保つことができるのでしょうか。まず、あなたが経営者なら、本業が不調に陥っても余裕を持っていられるように、事業や業態を増やしておくことです。
一つの事業に依存していては、それがうまくいかなくなったときに感情が揺らぎ、一人称になりやすいのです。心の動揺を抑えるためにも、事業のリスクを分散しておくことをお勧めします。
もう一つは少し精神論になりますが、目標は自分で努力して達成するものと考えて、何事にも過大な期待をせず、一見、矛盾するような感じですが、今ある状態で満足する心を持つように心がけることです。
(中略)
こうなりたいという高い目標を持つことは大切ですが、同時に自分が置かれている状況にも満足することが大切です。
今、体が健康であることだけで感謝ですよね。社員が侮日、会社に来て働いてくれることだけでも、それ自体、ありがたいではありませんか。
高い人称を保っためにも、他人や外部環境に過大な期待をするのはやめましょう。そして、感謝できる自分でいるように心がけてください。
ビジネスメール教育事業、メール配信システム事業、コンサルティング事業、ウェブサイト制作事業、コンテンツ開発事業……いろいろな仕事をやっていますが、これもリスク分散を考えています。
もともと私はコンサルタントとして、一人でやっていました。その後社員を雇って多少拡大してきました。しかし、「私が死んだらみんなに迷惑がかかる」と考え、リスク分散をして事業を作ってきています。
今では、私以外にも話せる講師がたくさんいます。良質なコンテンツを拡散してくれる人が増えたというのは本当に大きな財産です。講師業をやるにしても、自己満足の一人称はもってのほか、目の前のお客さまの納得、その後の第三者視点も含めて培っていきたいものです。
まとめ&宣言
自分だけの目線、相手と自分の目線、周りからどう見られているか。
その先には、会社がどう見られるか、世の中にどのような影響を与えるか、100年後はどうなのか。このようにもっと大きな視点で考える必要があります。
もっと知りたい!&プレゼントのお知らせ
仕事のスキルアップにつながるメルマガを平日日刊で配信しています。読書、仕事の高速化、思考法、コミュニケーション、様々なヒントを受け取りたい方は、メルマガに登録してくださいね!
今なら、書籍『仕事を高速化する「時間割」の作り方』をプレゼント中。
記事を読んでいただくだけでも嬉しいです。さらに「いいね!」がつくともっと嬉しいです。さらに……サポートしていただけたら、モチベーションが10倍アップします!