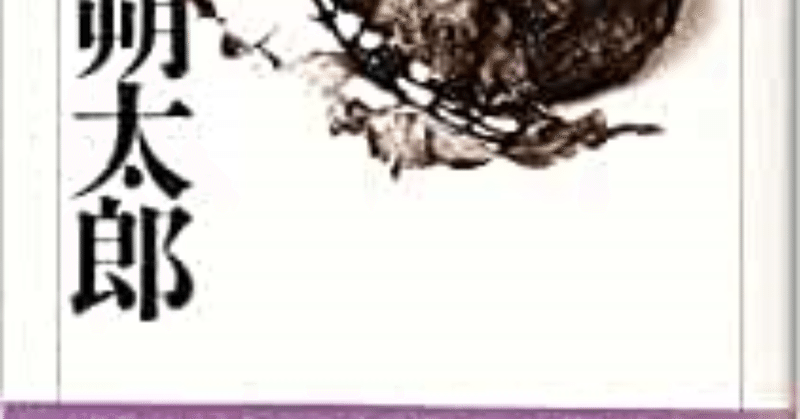
題:大岡信著「萩原朔太郎」を読んで
萩原朔太郎の詩は好きであるが、文庫本の全集一冊と復刻版「蝶を夢む」を読んだぐらいで、それも詩の内容は殆ど記憶がない。このため、彼の詩がどうしてどのように生まれて、どんな詩があるのか知りたくて読んだ本である。著者は萩原朔太郎の文学的な経験と人生における体験とを重ね合わせながら、簡明にかつ明確に萩原朔太郎を論じている。特に時代を経て変遷する朔太郎の詩の形式と内容を上手に捕らえていて良い本である。あまり関心はないが、朔太郎の父や妹たち、それに自らの家族のことにも触れている。無論、思い人なる馬場カナや親友三好達治につても当然述べている。ただ、書き続けると長くなるため、簡単に朔太郎の詩の形式と内容の展開を、詩を加えて紹介したい。
実は朔太郎は短歌に思い入れていたのである。「ソライロノハナ」なる歌集(1913年発刊 なお朔太郎は1886年生まれ)が短歌作家としての朔太郎の一時代の終わりということになる。次のような歌は好きである。単純に言葉を繋ぎ合わせて何でもない歌に思われるが、「しののめ」とういう明け方、「人妻」という他者性、動く「列車の窓」から見える「ひるがお」という植物が繋ぎ合わさることによって、何も述べられていない作者の心情がなぜか推測されるのである。無論、分かるものではない、でもある種の感慨・情感を生み出させる客観性でもある。
しののめのまだきに起きて人妻と汽車の窓より見たるひるがお
こうして朔太郎は、古の「古今集」などの短歌を基礎として発展させ語の独特のリズム感を生み出している。こうして、客観的な描写の内に主体の心情が含ませる詩の表現に容易にたどり着けるはずである。無論、初めは思わずに心情を吐露した詩も多いが、この独特の主観の心情を含んだ客観性が朔太郎の詩の大きな特徴の一つであると思っている。以前感想文を書いた「紫式部日記」の冒頭の文章と同じ質なのである。なお、初期の「愛隣詩集」ではこの人妻は「夜汽車」という詩の中に出てくる。大岡信はこの詩の語法を詳細に解説している。そして、「愛隣詩集」の後に「浄罪詩編」を助走として「月に吠える」が書かれるのである。なお、「愛隣詩集」の後期作品として、大岡信が紹介している詩から一つ引用したい。
再開
皿にはおどる肉さかな
春夏すぎて
きみが手に銀のふほをくはおもからむ。
ああ秋ふかみ
なめいしにこおろぎ鳴き
ええてるは波瑠をやぶれど
再開のくちずけかたく凍りて
ふんすいはみ空のすみにかすかなり。
みよあめつちにみずがねながれ
しめやかに皿はすべりて
み手にやさしく腕輪はずれしが
真珠ちりこぼれ
ともしび風にぬれて
このにほい舗石はしろがねのうれひにめざめむ。
大岡信はこの語彙の特異性と結びつきをシュルリレアリズムの先駆的な前衛性を持っていると述べている。即ち、突飛な表現を形作っている、物理的にはありえないけれども心理的、創造的には自然に結び付けられる詩法の現代性を海外詩や哲学書、それに公演や音楽会にあると推測している。それにしても朔太郎には詩の理論に関する文章も多く、哲学的な思考を持つ一面もあったようである。「浄罪詩編」では著者は「竹」、「地面の底の病気の顔」などを紹介しているが、それほど評価はしていない。「光る地面に竹が生え/青竹が生え/地下には竹の根が生え」、「地面の底に顔があらわれ/さみしい病人の顔があらえあれ」などは高校の教科書にもよく載っていたものである。著者は朔太郎の「叛逆性」と「超俗性」と「思想性」を論じているが、ここでは触れない。それほど重要ではないためである。
むしろ『この視覚像には、それの性質上、分離しようもなく触覚的な性質が内在している』と述べていることは重要である。ドゥルーズのベーコン論でも論じられており、視覚が物を見るのではなくて、物に触るのである。それに光が外側から来るより内側から発せられる、かつ手の指先などの鋭い神経が触れて感じ取るのである。また「草木姦淫罪」と述べる至る朔太郎の精神神経の病的な戦慄状態である。著者はどっぷりと生理の闇につかっていると述べているが、言い得て妙である。「月に吠える」の中の「蛙の死」を紹介したい。良く分からいところが、良い詩であるためである。
蛙の死
蛙が殺された、
子供がまるくなって手をあげた、
みんないっしょに、
かわゆらしい、
血だらけの手をあげた、
月が出た、
丘の上に人が立っている。
帽子の下に顔がある。
この奇妙さには触れないでおこう。「くさった蛤」も良い。こうして何年か活動のほぼ停止した時期があり、「青描」や「蝶を夢む」が続くのである。富裕な家の厄介者であった朔太郎がやっと娶った妻との破局があり、そして思い人馬場カナ、即ち洗礼名エレナの精霊化した女が脳内に住み着いているのである。著者は「懺悔」から「祈祷」を詩に結びつける課題を自らに課したと述べているが、この経緯については省略したい。ただ、散文に近づいていくとの指摘は述べておきたい。更に、妖しい美しさをそなえた女がよぎり、肉体がねばねばと溶解していく性行為を伴っていると著者は述べている。詩は死姦者の心理を演じており、朔太郎は自ら「邪淫詩」と呼んでいるとのこと。「くずれる肉体」の一部を紹介したい。
「くずれる肉体」の一部
蝙蝠のむらがっている野原の中で
わたしはくずれていく肉体の柱をながめていた
それは宵闇にさびしくふるへて
影にそよぐ死びと草のやうになまぐさく
ぞろぞろと蛆虫の這う腐肉のように醜かった。
この詩が微妙に肉体の腐乱する凄惨な表現を逃れ、抒情を含んでいる点に注意したい。比喩の形式と主体の視線がバランスを取り、心情の吐露へと変換させる表現となっているのである。「邪淫詩」をもっと紹介したいが省略する。「詩の原理」で朔太郎は、詩は文学における音楽と述べている。また、小説は美術であるとのこと。こうした朔太郎の詩論は興味深い。「蝶を夢む」が情緒過多の水っぽさを持ち、締まりがないと著者は評しているが、同時期に掛かれた「青描以後」では、ある種の諦め、倦怠、断念が含まれて現実をやや遠目から眺めていると著者は述べている。著者の「蝶を夢む」の評価が低いことに私は異論を持つ。締まりのない冗長さと著者は述べるが決してそうではない。「青描」の旋律的な鮮明さと異なった緩慢さが静止画にダイナニズムを与えていて、物憂い気だるさが幻想を伴ってより確かに伝わってくるのである。視覚的な触角としては、これらの詩の方が優れているのである。ただ、ここでは「蝶を夢む」ではなく、「青描以後」における「猫の死骸」を紹介したい。
猫の死骸
海綿のような景色のなかで
しつとりと水気にふくらんでいる
どこにも人畜のすがたはみえず
へんにかなしげなる水車が泣いているようす。
そうして朦朧とした柳のかげから
やさしい待ちひびとのすがたがみえるよ。
うすい肩かけにからだをつつみ
びれいな瓦斯体の衣装をひきずり
しずかに心霊のようにさまよっている。
ああ浦 さびしい女!
「あなた いつも遅いのね」
ぼくらは過去も未来もない
そうして現実のものから消えてしまった。・・
浦!
このへんてこに見える景色のなかへ
泥猫の死骸を埋めておやりよ。
こうして1934年に「氷島」が出版される。著者によれば、虚無と寂寥と漂泊の悲傷を見て取れるのである。望郷の念が深まっているのである。「漂泊者の歌」の一部を紹介したい。
「漂泊者の歌」の一部
ああ 悪魔よりも孤独にして
汝は氷霜の冬に耐えるかな!
かつて何物をも信じることなく
汝の信じるところに憤怒を知れり。
かつて欲情の否定を知らず
汝の欲情するものを弾劾せり。
著者の言葉を借りれば『朔太郎は「抒情詩」を語りつつ、ほとんど彼自身の現実における生存形式そのものを語っていることがわかる』さらに、著者は『夏目漱石が近代日本の開化の「外発」性をいい、森鴎外が同じく「普請中」といったこの「過渡期」の諸様相は、自覚した「エトランゼ」である萩原朔太郎において、わけても鋭く感受され、反応されたのである』と結んでいるが、後者の文章は正確な見方ではない。彼は「外発」性から内発したのではない。無論、外発性に触発はされているけれども、内発性が表現として外発せざるを得なかったはずである。「エトランゼ」という自覚は「過渡期」の諸様相に反応したのではなくて、内発性が生み出した結果であると考えるほうが良い。なお、漱石は外発性と内発性の両方を持ち合わせている。それらが相互に深く絡み合って表現に奥行きを与えている。両者ともに優れた知性を持ちながら、知性に頼ることのできない内発する精神的な葛藤の持ち主であることは確かであろう。なお、萩原朔太郎を論じるにはほぼすべての作品に目を通している必要がある。最後に、著者大岡信は最近亡くなっている。冥福を祈りたい。
以上(本日記は、2017/05/05に記述している)
詩や小説に哲学の好きな者です。表現主義、超現実主義など。哲学的には、生の哲学、脱ポスト構造主義など。記紀歌謡や夏目漱石などに、詩人では白石かずこや吉岡実など。フランツ・カフカやサミュエル・ベケットやアンドレ・ブルドンに、哲学者はアンリ・ベルグソンやジル・ドゥルーズなどに傾斜。
