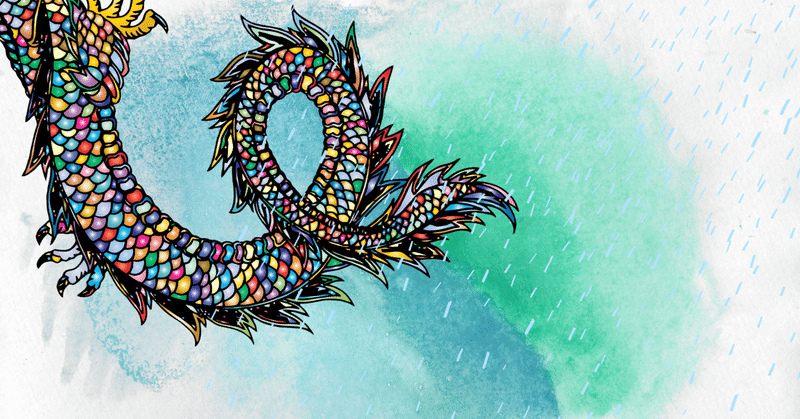
童話「滝でひろわれた、おたきの話」
この小説は3,521文字です。
村のはずれの林の中に、ちいさな滝がありました。滝壺は泉になっていて、村の人たちはみな、そこから水を汲んでいます。
雨上がりのある日のことでした。村の老夫婦が水を汲みにいきますと、泉のほとりにたくさんの蛇が群がっておりました。
「おや。あんなに蛇がいるとはめずらしい」
「さっきまでの雷雨で、山から流されでもしたんだろうか」
二人がながめておりますと、中からなにか突き出されました。
「じいさん、あれは赤ん坊の手じゃないかね」
「や。ほんとうだ。こりゃいかん」
老夫婦は落ちていた枝を手に取ると、蛇を追い払いました。蛇がすべていなくなると、はたして赤ん坊がおりました。あれだけの蛇に囲まれていても噛まれもせず、こわい思いもしなかったとみえて、泣くでもなく、にこにこわらっているのでありました。
「なんとまあ、肝の据わった赤ん坊だ」
「しかし、こんなところでどうしたことだろう」
村にも赤ん坊のいるうちはありますが、この子はどこの子でもありません。まだ歩ける歳でもないですから、迷子というわけでもないでしょう。
「おーい。この子の親はおらんか」
辺りを見回してみてもだれもいません。老夫婦はひとまず赤ん坊を連れて帰ることにしました。
しばらくして気がついたのですが、赤ん坊は声が出ないようでした。どうりで蛇の群にうもれていても泣き声がしなかったはずです。
「もしかしたら、声が出ないせいで捨てられたのかのう」
「それは気の毒に。こんなにかわいい女の子なのに」
老夫婦は赤ん坊を育てることにしました。
その日はてぬぐいに浸した重湯を吸わせたりしましたが、このまま育てるならもらい乳をしなければならないでしょう。明日にでも村の人に頼んでみようということで、その日は床につきました。
ところが翌朝、老夫婦は足音で目が覚めました。
「おやまあ。じいさん、ちょっと起きてくださいな」
「なんと。一晩でこんなに育ったのか?」
みっつほどの女の子が裸ん坊で家の中を走り回っていたのです。口を開けて笑っていますが、やはり声は出ていません。
それからも娘は毎晩眠るたびに育ちました。このままでは自分たちよりも先に歳を取ってしまうのではないかと心配になったりもしましたが、娘は十六ほどの見た目になると成長が止まりました。
老夫婦は、滝でひろった子なので娘を「たき」と名づけ、「おたき、おたき」とかわいがりました。
おたきも老夫婦のことを真の両親のように大切にしました。おたきは、声はなくても笑顔の絶えない、優しくて働き者の娘でした。また、おたきが育てた作物はよく育ちました。
姿顔立ちも美しく、村の若者はこぞって嫁にほしがりました。
「おたきや、わしらもいつまでも元気ではいられまい。おまえを一人ぼっちにしてしまっては心残りだ。どうだ、嫁にいく気はないか?」
おじいさんは結婚をすすめましたが、おたきは首を横に振るばかりです。
「嫁に行くのはいやかい?」
おばあさんがそうたずねると、おたきは着物の袖を少しまくり腕を見せました。肘の辺りの肌がかたくひび割れておりました。おばあさんは、おどろいてたずねます。
「これはどうしたことか。いつからだ? 痛むのかい?」
おたきはこれにも首を横に振りました。
「この肌を気にして嫁の誘いを断っていたのかい?」
「痛みがないのなら気にすることはない。このくらいで嫁に行けなくなどならないから」
二人はなぐさめました。気休めではなく、ほんとうにたいしたことではないと思ったのでした。けれども、おたきはやはり嫁に行くつもりはないようで、首を横に振るのでした。
ところが、日を追うごとに、肌のひび割れは広がっていきました。袖口や襟から見えるほどでした。それは痛々しいものではありませんでしたが、鱗のようにも見えました。言い寄る若者は少なくなりました。鱗が首をおおうほどになると、もうだれも嫁にほしいと言ってこなくなりました。
老夫婦はひどく心配して、傷を治すという薬草を教えられてはおたきに塗り、病に効くという丸薬を無理して手に入れてはおたきに飲ませました。
そのたびにおたきは、そんなものはいらないと押し返すしぐさをするのですが、老夫婦はどうしてももとの姿にもどしたがりました。見た目が変わっただけで、痛みもなければ困ることもないということを、おたきがいくら身振り手振りで伝えても変わりませんでした。
老夫婦はおたきの言うことを聞くどころか、しまいにはまじないやお参りまでするようになりました。大切なおたきをかわいそうに思ってのことでした。
ところが二人がおたきをもとにもどすことばかり考えているせいで、畑仕事などまで手が回らなくなりました。おたき一人が作物を育てても、暮らしは苦しくなるばかりでした。
そんなとき力になってくれるのは一人だけでした。近くに住む庄助という若者です。
庄助だけはおたきの姿が変わっていっても今までと変わらずに接してくれています。肌が鱗におおわれていくことも気にしていませんでした。
ただ、首まで広がったころ、一度だけたずねられたことがあります。
「痛かったり困ったりしてないかい?」
おたきが首を振ると、庄助は大きくうなずきました。
「そうかい。そりゃあよかった」
それきり、鱗など見えていないかのようになにも聞かなくなりました。おたきはたいそう安心しました。庄助が鱗のことをおたきと同じくなんでもないことと思っているとわかったからです。
広がっていく鱗は病のようにも見えるので、うつるかもしれないと心配して、村人が離れていくのもしかたないと思いましたし、老夫婦がもとにもどそうとしてくれるのもありがたいとは感じていました。けれども、おたき自身が、姿は今のままでかまわないと思っているのです。それよりもまた老夫婦と畑仕事などをしたいのでした。ただ、声を持たないおたきですから、なかなか伝えることができません。
老夫婦は歳をとり、やがて亡くなってしまいました。おたきがひろわれたころから歳をとっていましたし、いつかはこうなるとわかっていたことです。
それでも悲しくて、さみしくて、おたきはたくさん泣きました。声もなく泣きました。おたきが泣くと、空もつられたかのように雨を降らせました。
おたきは三日三晩泣き続け、雨は三日三晩降り続きました。
見かねた庄助が言いました。
「一人はさみしかろう。なにかと不便もあるだろう。どうだい。よかったら、嫁にくるかい?」
おたきは庄助と夫婦になりました。
嫁入り先でも、おたきが世話した作物はよく育ち、おたきが汲んできた水で煮炊きしたごはんはたいそうおいしくなりました。
多くの縁談を断ってきたおたきが嫁にいきましたが、かつて言い寄ってきた男たちがうらやむことはありませんでした。なぜなら、鱗は手足や顔までおおうほどに広がり、今はもう、男たちが嫁にほしがった美しい娘ではなかったからです。
二人の家は村のはずれにありましたし、しだいにおたきを知る人も少なくなりました。
二人は静かに穏やかに日々をすごしました。春がすぎ、夏がすぎ、秋がすぎて、冬もすぎました。また春が来て、何年も何年も穏やかにすごしました。
庄助がおじいさんになったころには、おたきの肌はすべて鱗におおわれてしまいました。けれども庄助が気にしていたのは、そのことではありませんでした。
「おたき、おまえはなぜ歳をとらないのだい?」
全身が鱗におおわれているので、ほかの人からはわからないかもしれませんが、ずっと一緒にいる庄助にはよくわかるのです。おたきは、庄助と初めて会った十六のころから、少しも歳をとっていないのでした。
おたきはほほえんで、首をかしげました。
「おれはこんなに歳をとってしまったよ」
庄助のしわだらけの手が、おたきの鱗だらけの手をにぎりました。
それからしばらくして、庄助は亡くなりました。
おたきは泣きました。声もなく泣きました。空もつられて雨を降らせました。大雨になりました。おたきは七日間も泣き続け、雨は七日間も降り続きました。
それから、おたきは庄助の亡骸を抱きしめました。そして空を見上げます。すると、鱗におおわれた体がすうっとのびて、龍になりました。降りしきる雨の中、龍が空へと舞い上がります。
その姿が雨雲に隠れたころ、ぴかりと光りました。稲妻は二匹の龍に見えました。
がらがらごーんと雷鳴が響きました。何度も何度も響きました。龍の声でした。二匹の龍が語らう声でした。心なしか、楽しそうな響きでありました。
それからというもの、その村では、作物が実るころに二匹の龍が空に現れると、その年は豊作になるそうです。
