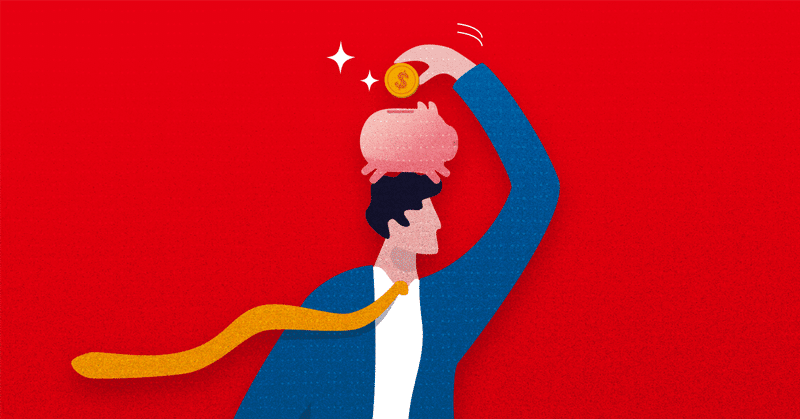
インボイスで変わることのあれこれ -1-
はじめに
良いタイトルが思いつきませんでしたが、現在見知った事一通りをまとめておきたいと思います。一度では書ききれなかったため、複数回になる予定です。
正直末端の税務署では大きな影響があるといった受け止めではない印象です。
説明は義務という言葉に貫かれており、一般市民には一種の切り替えに関する圧力のようなものを感じますが、経過措置や切り替え期間・チェックの緩さなど制度の厳格な印象は幾分和らいでいます。しかし逆に、では何のためにこの制度へ変える意味があるのか?という疑問が生じます。
真面目に行えばたいへんな手間になりますし、言葉は悪いのですが適当で良いなら消費税の申告は従来通りで良かったと思います。
従来通りで行きたい場合
この方法は用意されていますが、納税事業者として申告しなければ良いです。ただし、取引相手が納税事業者として登録している場合、消費税の納税負担はそちら側になりますから、多くの場合取引先から、そちらも納税事業者登録を行ってくれ(1000万未満の売上でも消費税を納付する申告を行ってくれ)と言われるようです。
国税庁からは何も言わず、取引相手から能動的に消費税納税者となるよう依頼させている(そのため行政は批判を免れる)とも言えますが、こちらに対応する方法は次の通りです。
1.消費税を請求しない
消費税は頂いていないので、納付金額がゼロになるという事を相手に告げます。例えば10,000円の商品なりサービスに対する消費税は1,000円(10%)ですが、こちらは請求しません。請求額は11,000円でなく10,000円となります。
取引の相手は 1,000円(消費税額分)安く購入します。この本来支払うべき消費税は相手側が納付します。
つまり、消費税は、発注先には支払わず、直接納付するという事です。
相手側の費用はプラスマイナスゼロになります。
相手側のメリットは消費税の申告までの期間、消費税額分の費用を浮動資産として利用できるということです。
この方式に問題があるのは、相手側の都合で、次の場合です。
A.税理士・経理から処理が面倒なので一律税は請求してほしいと言われる可能性
B.素性を抑えたい・取引先を公開したいなど何らかの理由で発注先に納税事業者登録して欲しい社内的都合(主観的な倫理)がある場合(後述)
C.取引先を事業者登録させたとして税務署に覚えめでたくアピールしたい場合
D.発注先に税負担させた上で納税事業者でないとして虚偽の申告をし差額の利益を得たい場合(普通は損になりますが事業により得するケースがあります)、逆もある
E.その他。執筆中の今思いつきませんが、ここは仮想的な取引であるため、その他の不正が入り込む余地がありますし、その可能性を考える人は出てきます
2.消費税額分を商品・サービスからあらかじめ差し引いて販売する
受注側が相手の支払う税額を負担します。相手側は経理上は税の請求を受ける事ができます(制度的にはアウトですが、言い訳ができるため相手側の判断によりあり得るという事です)。
このような事をするメリットがあるのか?という事ですが、一つは従来型の申告で良い点で、二つめは一般へ直販の場合、商品の価格を上げずに済む(税なし価格で提供できる)という事です。顧客にメリットがある事と、販売側は市場を維持・拡大できます。
そもそもインボイスが何なのかを考えた時、一つは今まで1,000万未満の売上の年に消費税を利益化していた所が、それを納税するという意味がありますが、便宜上の内税方式含め税を受け取ってない場合は何も変わりません。
その場合、何が変わるかというと、この制度は税務署が徴税する代わりに、事業者に徴税を代行させるという意味だけがあります。入った税はそのまま納税する訳ですから事業者はただの納税窓口として無報酬で使役されるという事です。ただ、一年間の支払期限までは運転資金などに流用する事はできます。
この場合、年次の一時資金を除けば、顧客にも事業者にもメリットはありません。言い換えると利益が1,000万未満の年の事業に取っては余計な経理の負担が経済的労働的に増えるだけになります。
個人事業主の名簿流出
納税事業者登録をした(させられた人が多い)個人事業主の所在や芸名の場合本名などが名簿形式で公開されました。
報道で問題視された事を受け、国税庁は公開内容を限定すると発表したそうですが、なぜこんな事になったのでしょうか。
背景には企業が発注先の素性を知りたがっている事があります。企業と省庁は関係性が密接で霞が関には企業から出向の形で多数人員が入っており、要請を受けています。特に現在リモートワークや経営状態の低迷から個人事業主に業務を依存する割合が年々増えており、企業側は虫の良い事に社員と同レベルの監視対象として、業務依頼先の個人情報を把握したいと考え要求しています。フリーランスの方が法人化するよう要請を受ける事が多いのもこのためです。
しかし、このような荒っぽい事を行った理由は別にあるようです。
インボイスには新たに不正が可能になるなど様々な制度上の欠陥があるように思えますが、問題の一つとして、納税事業者登録をしても、登録証明書を発行しないようになっています。
しかしながら、経理に於いては相手が納税事業者である事を確認してから取引をせよとの文言があります。
確認を強制(実際には文言のみで請求書・明細書に警告文を一行入れるだけ)されているのに確認方法を提供していないのです。万一相手が口頭で虚偽を伝えた場合、事後に経理の大幅な修正と再申告を迫られるリスクがあります。
当然、ここは国税庁が責任を追及されたと思いますが、一度登録証明書を発行しないとして制度を決めたので、では発行しますとはしない。スケジュールも予算も狂うからか(大した事ではない筈ですが)頑強にやり方は変えない、だが、対応としては名簿を公開するからそちらで登録番号と本人を氏名住所ほか個人情報にて確認してくれ、となったのではないでしょうか。
要するに制度上の欠陥は保管した個人情報を流出させるからそちらで対応して埋め合わせてくれという対応をとった訳です。
しかし問題なのは
個人情報を流出させ、私生活やプライバシーをリスクに晒す点を事業者登録の事前に一切説明せず、登録を促していること
です。有名人であれば致命的な事件に発展する可能性もありますし、企業が業務の失敗責任を個人に転嫁して訴訟を起こす確率が高まったと言えます。登録される方はそのリスクが隠されていますのでよくお考え下さい。説明会等でも一切触れないようですので、記事や報道でチェックするよりありません。
以上です。ありがとうございました。
サポート頂けると嬉しいです。
