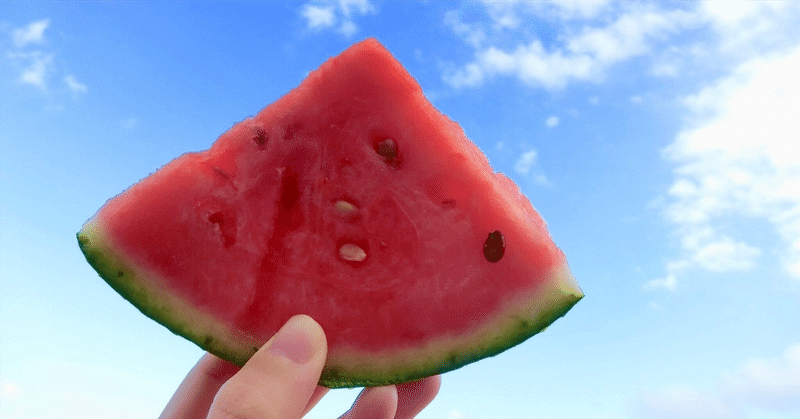
感染拡大を防ぐテーゼたち
感染拡大を防ぐテーゼたち
日本に於いて(もしくは一部の国を除き)再び感染拡大傾向に入っています。
様々な立場の方から「○○すれば拡大を防ぐ事ができる」との発言がなされていますが、過去の例から難しいのではないか、もしくは持続性に乏しいのではとの懸念、もしくは根拠の説明が欲しい人が多いのではないかと思います。私も、それでたまたま感染が収まる事はあるかもしれないが持続性はないのではと感じています。この感染には確かに波があり、波は繰り返されています。周期的な傾向を消滅させる根拠は現在ないように思います。
WHOの見解
接種によって感染は収束させられる。そのためには人口の70%が接種を終え検査体制を強化すること。公正な接種医薬品の分配が必要。新たな変異が現れる条件は整っている。
との事です。現在の接種医薬品が新たな変異に効果があるのかという点が気になりますが、そこはおいておきましょう。
接種によって感染を収束させられる可能性はない訳ではないと思いますが、問題は条件です。
①接種速度とカバー率が次の波の発生を押さえ込める程度に迅速である事
②感染予防効果期間中に押さえ込みが完了すること
③押さえ込んだ後は検査体制による監視で次の波を押さえ込むこと
どれも難しいと思います。
①について
現在まで、接種は感染が拡大を始めた後の後追いの対応になっています。しかし接種予防は本来、感染が始まる前(つまり平常時)に完了しておく必要があります。
どのくらい前かと言いますと、感染が始まる2週間前に2回目・3回目接種が完了していないといけません。
これが社会の構成人口の高い率でカバーされないといけないのですが、予防措置により亡くなる人や健康を害する人も出てくる、とか感染と同様に未知の副反応のリスクがありますので3回目以降接種は見送る人もでてきて接種速度が落ちるのではないかと思います。
特にモデルナは警戒されていて高齢者の中にはファイザーを希望する人が多いのですが、これが問題になります。(次で解説)
②について
こちらは技術的なお話になりますが、抗体量の検査のみで言いますと、感染予防に必要な抗体量を維持できる期間はF社は2回目接種後1週間経過して1~3日、M社は2週間経過して2.5ケ月です。
ですのでM社の製剤の利用率を上げないと接種後感染が増える事になります。F社の有効期間内に感染を押さえ込む事は不可能で、日本でもF社の製剤しかなかった時期には押さえ込みはできませんでした。
③について
日本のようにPCR検査に消極的な国があるので難しいと思います。また、PCR検査は万能とは言い難く、特に接触感染(経口感染含む)や臓器感染が見過ごされる可能性が高い検査方法です。
現在ここが感染経路不明とされているものになっています。
自治体の見解
鳥取県平井知事「実は全国の知事がみんな言うのは学校のことなんですね。それで、なかなか政府も、ここはタブーなのかあんまりおっしゃらないんですが、やっぱり学校の対策というのは非常に重要だと思います。それで、今、学校での感染が本県でもクラスターが相次ぎまして報告をされているところです」 https://t.co/jge0mmxAJz pic.twitter.com/vGeanwCi6q
— Takuro⚓️コロナ情報in神奈川県/横浜市/東京都(全国も) (@triangle24) January 23, 2022
(引用ありがとうございました)
現在感染の主体は学校、全国的傾向。学校の対策が重要。
との事です。実は地方新聞は各地でこの問題を取り上げているのですが、全国ニュースではあまり話題になりません。検索してみると明確にそれが分かります。学校の対策をなぜ強化しないのかという問題は残りますがそれは置いておきましょう。
実態として学校での感染が拡大し、そこから家庭へ広がっているのは事実のようです。
様々な要因ありますが、学校という場の特性から考えると
①部活動、それに伴う大会参加での移動や宿泊、共同生活
②中途半端な電子化生活で配布されたタブレット
が大きいと思います。
給食については一応の対策は取られていると思いますので取り上げませんでした。①②については意外とチェックが甘い、つまりある意味意図的に見過ごされている内容です。
①について。バスや宿泊は旅行会社大手地元との慣例化した契約に基づく観光類似事業になっています。都会の大手も関係しています(経済的要素として大きい)。おそらく学校行事という事で価格設定されているのですが、契約継続しないと費用も変わってくる可能性あります。大会は地区ブロック→全国となり文化系も含めて秋季中心に活発化します。これが時間を置いて感染拡大の原因となります。
②については、2021年の3月に九州の医療施設でクラスタ化した原因と言われています。何か物を触る→その指で画面に触る(もしくは他人と表示を共有する際、顔と向き合い使用する画面が直接飛沫を浴びている)→その汚染された画面に使用の度触る わけですので感染を媒介する事になります。
都度消毒が必須なデバイスなのです。が、アルコールではウィルスは消滅しませんので、防水デバイスを石鹸で洗う習慣がないと接触感染経口感染の原因になります。こういった配慮なり習慣化の教育がない訳です。
話は逸れますが、このパンデミックでタッチ端末によるサービスが改善なしで増えていますが、これらを提供する事業者は感染拡大に貢献してしまっています。どういう神経をしているのか疑問ですが、社会にサービスを提供する立場という事を理解していない事業者がほぼ100%だという事でしょう。従業員が感染すると損害が出るので防ぐが、客を汚染するのは構わない、極端に言えばこういう事だと思います。※
政府の見解
実際に会見のもようから拾った内容も含みますが
接種を進めるにはモデルナが必須。交互接種も検討する
との事です。
管政権からのモデルナの接種により一度表向き感染者数値の改善に成功したのは事実で、一部事実ベースを含む政策という点は評価できると思います。特に岸田氏はその恩恵、感染低下の風にのって政権を発足していますので個人的に前向きになる印象もあるのでしょう。
モデルナを使用する事は間違っていないと思います。問題は持続性です。先に書きました通り、感染予防効果は短期間です。また、感染が始まってからでは接種は遅いのですが、問題は次の波です。
副作用の全くない薬剤で、個人が自身のタイミングで使用できる経口薬であればまだ良いのですが(接種会場へ移動し滞在するリスクもあります)、専門のスタッフを使い全体人口で接種率を上げるとなると大変な経済的工数的負担が発生します。加えて副反応のリスクがありますが、これは接種を重ねる度に数学的に上昇します(0.0014%は3回で0.0042%、これを10年続けると0.04%になります)。
こういった予算的にもリスク的にも先のない投薬をいつまで続けるのか?について回答がありません。生涯一度接種すればよい薬剤とは違うからです。
こうしてみると決め手となる、もしくは条件に裏のない感染拡大防止策はない(公的機関からは発信されてない)という事になります。
以上です。
ありがとうございました。
※追記
裏を返せば、現在の社会は接触感染を甘く見ていて全くと言って良いほど対策をしていませんし、企業活動においてはそれが許されています。感染経路は不明のまま、感染機会も残したままです。この状態で完全な収束は無理でしょう。
接種やそれに伴う圧力は物への対応、システマティックな仕組みによる対応ではなく、人への対応です。
物に言葉をぶつけても何も起こりませんが、人には無理を言う事で責任を押しつけられるからです。
精神論の構造そのものです。
サポート頂けると嬉しいです。
