
【考察】ガンダムの中の女たち 〜最初にその人気を支えたのは女性ファン、というのは本当か?
はじめに:なぜ「ガンダムは男性ファンが支えて、後からきたのが女性ファン」になったのか?
近年、SNSなどを中心にネットの世界では、「ヤマトやガンダムは男性ファンが支えてきたのに、人気が出てきたら女性ファンが入ってきた」などという言説がささやかれているようだ。当時を知る男性からはもちろん、それを否定する言葉もたくさん投稿されているが、振り返ってみると、当初は顕在だった女性ファンが潜在化していった時期、というのがあるのかもしれない。
というのは、私はもともと同人活動的なこととは無縁で過ごしてきたが、インターネット普及した2000年頃から自身でホームページを作るようになり、ガンダムファンとして情報発信をするようになったのだが、そのホームページの考察系の文章がよく読まれ好評だった。そして、それが編集者の目に留まり、宝島社から出版された『僕たちが好きなガンダム』『僕たちが好きなΖガンダム』にライターとして参加させてもらったのだ。
その時の1冊『僕たちが好きなガンダムDX』(2005年1月20日発行)の巻末の著者紹介を見ていると、36人いるライター中、女性は私を含めて3人しかおらず、1割にも満たない状態だった。
また、それと同時期に、N H Kで『B Sアニメ夜話』という番組は放映されてたが(私はこういう番組にあまり興味がなくて、一度も見たことはない)、ある日、この番組で「機動戦士ガンダム」を取り上げることになっているが、出演者が男性ばかりになってしまっているので、女性ファンとして出てもらえないか、という依頼のメールをいただいた。
自分としては、そのような依頼に悪い気はしなかったが、その頃には書きたいことはほぼ書き終えてホームページの更新も滞り、気持ちが作品から離れていたということ、何より自分が女性ファンの代表みたいな顔をして番組に出るのは、どう考えても「違う」と思ったということもあり、お断りさせてもらった。
ここで言いたいのは、2000年代のこの当時には、女性ファンとして目立つような存在が、ほとんどいなくなってしまっていたのではないか、ということである。私はたまたまライターの一人として出版物に関わらせてもらったということだけで、こうした依頼を受けることになったのだが、本当は長年のファンであっても、ファンクラブや同人活動をやめてしまい、メディアでのこういう露出がなければ埋もれていってしまう、ということがある。そうした状況の中で、2000年代に入ってから「ガンダム」に触れ始めた人たちにとっては(それとて、もう20年も前の話だ)、もともと男性ファンが人気を支えていた、と思っても何の不思議もないだろう。なにしろ、1990年代前半より前というともはやインターネットもなく、紙媒体の情報はネットではさがすこともできないのだから、ないに等しい。
そこで、往年の男性ファンの方々が言うように、確かにガンダムには女性ファンがたくさんいたし、むしろ女性ファンがその視聴率のふるわなかった番組を支えていた、という事実と、なぜ、それほどまでにガンダムが女性の心を惹きつけたのか、という理由について、ガンダムの中に描かれた女たちの姿を通して、紐解いていきたいと思う。
(1)ヤマトの艦橋、ホワイトベースのブリッジ
「機動戦士ガンダム」を語る上で、触れざるを得ないのが「宇宙戦艦ヤマト」である。言うまでもなく、当時はアニメを卒業する世代だった10代の若者を、主な視聴者として取り込んだからである。そして、そこには多くの女性ファンがいた。戦艦大和を超技術で蘇らせた宇宙戦艦ヤマトの艦橋には、森雪という紅一点の存在があったからだ。特撮モノには定番の存在だが、艦橋に席を持ちレーダー、調査を担当する傍ら、生活班長として、一年を旅するヤマト乗組員の生活全般や医療、保健衛生を担当するというスーパーレディーだった。であるにもかかわらず、親しみのもてる等身大のキャラクターで、女性からの共感を得たのはまちがいない。主人公・古代進に寄せる恋心が成就するのか、というところにも、興味を惹かれるところがあっただろう。
「宇宙戦艦ヤマト」にはしかし、彼女の他には主要キャラクターとして、イスカンダルの女王スターシャぐらいしか女性は登場しない。ヤマト艦内で乗組員の男たちを世話する森雪、放射能に汚染された地球を救うため使者を遣しヤマトを導くスターシャ。女性に割り当てられているのは「ケア」や「癒し」という役割であり、その意味で、特別な存在だった。それゆえ、メインとなる戦いの場面ではその主体となることはほとんどなかった。
そんな「宇宙戦艦ヤマト」がブームを巻き起こす中で、制作されたのが「機動戦士ガンダム」である。本作が、「宇宙戦艦ヤマト」の逆張りのような話になっていることは、全話レビューでも折に触れて書いているが、中でも大きいのは、ヤマトでは最終回、地球への帰還を前に命尽きる艦長が、ガンダムでは地球への旅が始まったばかりの第4話で死んでしまい、艦内に大人といえる人物はほぼいなくなってしまうということだろう。
そんな、若者ばかりで航行することになった戦艦ホワイトベースは、紅一点の船ではなかった。そのブリッジで舵を取るのはミライ・ヤシマ、通信席にはセイラ・マス(のちにフラウ・ボゥ)。艦長席のブライト・ノア、オペレーター担当のマーカー、オスカとあわせても、5人中2人が女性だったのだ。

主人公アムロの部屋に駆け込んで「あきれた、軍の放送聞かなかったの?」とフラウ・ボゥが避難を促し、戦闘で操舵手を失ったホワイトベースで「クルーザー級のスペイスグライダーのライセンスが役立つとは思えませんが」とミライ・ヤシマが手を挙げ、我先にホワイトベースに避難しようとしたカイ・シデンに「それでも男ですか、軟弱者!」と平手打ちを食らわしたとき、きっと見ていた女の子たちは思ったはずだ。これは、私たちの物語だと。男の後ろでヒヤヒヤしながら見守り、傷ついた男をケアするだけの役目でなく、女も主体的に前に出て戦う、私たちの待っていた物語なのだと。
(2)ともに戦う女たち
ガンダムの船、ホワイトベースには主要キャラだけでも3人の女性がいた。それは、宇宙世紀という、今より少し先に進んだ未来には、今よりもずっと、女性も主体的に行動するのが普通になっているはずだ、という想定があってのことだと思う。それは、ヤマトのキャラクターが全員日本人だったのに対して、ガンダムは多国籍「風」になっていたことと同じである。
では、ガンダムの中の女性たちの主体性、自立と成長はどのように描かれてきたのか、キャラクターを紹介しつつ振り返ってみよう。
フラウ・ボゥ
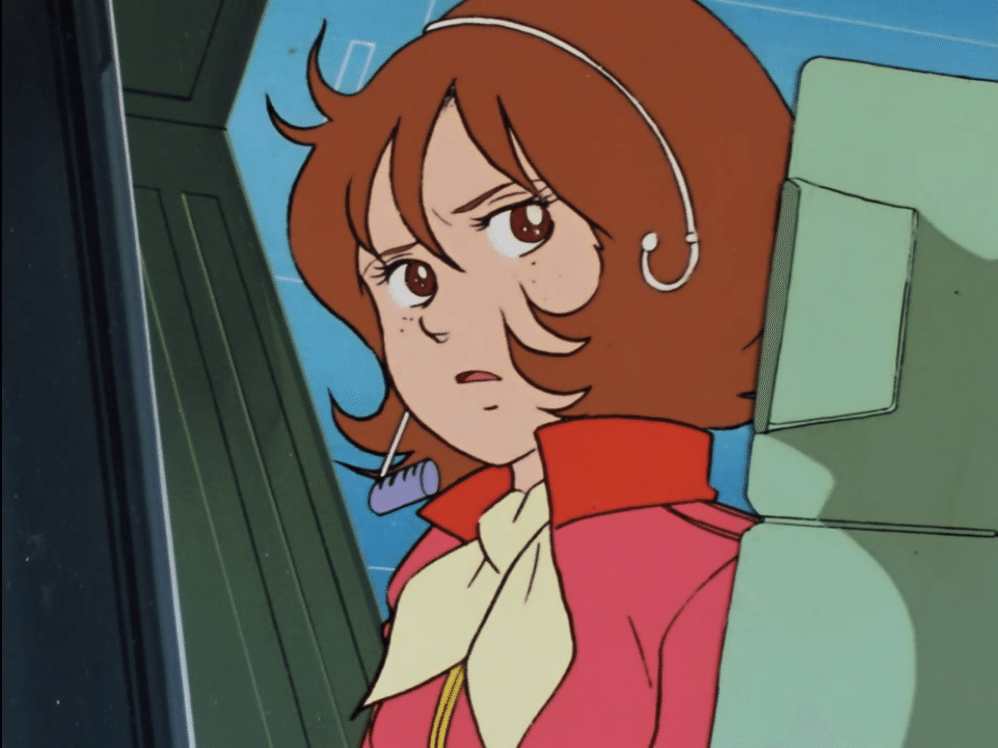
主人公アムロ・レイの隣に住む少女で、何かにつけて母親のいないアムロの世話を焼いている様子から物語は始まる。軍の避難命令をアムロに伝え、一緒に避難するのだが、もし彼女がアムロを呼びに来なかったら、ガンダムは大地に立たなかったかもしれない。しかしアムロがパイロットとなって戦い始めると、彼女と立場が逆転してしまう。アムロが好きな彼女は、何かと世話を焼き面倒を見ることで、彼と対等であり続けようとした。だが結局、アムロがめざましい成長を遂げるにしたがって「離れていってしまった」と感じるようになる。 セイラ・マスがパイロットになってからは、後を継いでブリッジの通信席に座り、ブライトとパイロットたちの間を取りもちながら的確に指示を伝える役目を果たす。アムロの世話を焼くことで自らの存在価値を見出そうとすることを諦め、彼女は本当の自分らしさを見出していったように思う。ホワイトベースに避難した三人の子どもたちを気遣い、最後まで彼らを守って戦い抜いた。強がりではない強さを身につけて、成長していく姿を見せてくれた。
ミライ・ヤシマ

スペースグライダーのライセンスを持っているから、と、操舵手を失ったホワイトベースの操縦を引き受ける少女。名前を名乗ると「あの、ヤシマ家の‥‥」と驚かれるほどのお嬢様なのだが、それは、当時の性差による役割分担の常識を考えるに、家柄によって下駄を履かせることで、男性と対等な立場になれるように演出したのだろうと思う。
艦長のブライト・ノアの補佐役を務め、ホワイトベースのナンバー2として重要な役割を果たしていく。また操舵手としても、敵のモビルスーツを背面飛行で振り落としたり、艦砲戦では巧みな操船で攻撃を回避するなど活躍する。一方で、過労でブライトが倒れ、艦長代理を引き受けた際は、指揮能力の低さとブライトへの依存心の強さが露見し、セイラを呆れさせた。
しかし中途配属されたスレッガー中尉との出会いで、彼女も変わってゆく。親同士が決めた婚約者がいたが、再会したとき、彼の(もともとは彼女自身がそうだったかもしれない)依存心の強さを見せつけられ失望。婚約者を捨てて自らの思いに正直にふるまう強さを身につけてゆく。
セイラ・マス

アムロやフラウ・ボゥと同じく<サイド7>の住民で、負傷した兵士らを助けながらホワイトベースに避難してきた少女。当初はホワイトベースのブリッジで通信兵を務める。実はジオン軍に生き別れた兄がいるのではないかと疑い、その消息を知るため自ら勝手にガンダムに乗って出撃。結局アムロに助けられるが、そのとき捕虜から兄の無事を聞き涙を流した。やがてその能力を買われてGアーマーのパイロットになり、活躍を見せる。実は敵国の創建者ジオン・ダイクンの娘であり、ミライと同様、家柄によって下駄を履かせることで、男性と対等の活躍の場を与えられた存在といえよう。ただ、兄であるシャアと直接対面して言葉を交わしたことをきっかけに、父ジオンを暗殺したザビ家に復讐したいという兄の真意を悟り、それを阻止しようと奮闘しはじめる。兄思いの優しい妹だった彼女もまた、戦いを通して自己のアイデンティティに目覚めてゆくことになる。
イセリナ・エッシェンバッハ

ホワイトベースとは関係ない脇役キャラだが、女性の描かれ方として印象的なこの人についても書いておきたい。ニューヤーク市長の娘でありながら(彼女もまた、家柄という下駄を履いたキャラである)、敵国であるジオン公国軍の貴公子、ガルマ・ザビと恋仲になっている。そのことを父から咎められて「自分で自分の道を選ぶ権利がある」などと反抗するが、ガルマ戦死の報を聞いて泣き崩れた。しかしそれでは終わらず、彼女はガルマの残存部隊に駆けつけて、ともに仇討ちの戦いに挑むのである。まさに父に宣言した通り「自分で自分の道を選び」、彼女は戦場に散ったのだった。
このように、女性キャラクター一人ひとりの背景や心情、そして彼女らが戦いを経てなしとげようとした自己変革について、本作では丁寧に描き出された。すぐれて群像劇的だった本作だが、その群像の中にあって、女性キャラクターもまた人格ある存在として物語の中に生きている、というところに、女性ファンを惹きつける要素があったと私は考えている。
(3)マチルダ中尉の衝撃
その中でも、特に大きな衝撃を与えたのが、ホワイトベースに物資を届ける補給部隊の隊長として登場した、マチルダ・アジャン中尉ではなかっただろうか。

彼女は艦長のブライトと同じ、グレーの士官用の軍服と制帽を着用し、まさにプロフェッショナルとしてホワイトベースの少年少女たちの前に颯爽と現れる。そして、たちどころに少年兵らの憧れの的となり、主人公アムロもまた、恋心を抱くようになる。アムロが彼女に「なぜ補給部隊に入ったのか」と問うたとき、彼女はこう答えた。「、戦争という破壊の中でただひとつ、モノを作っていくことができるからかしらね…戦いは破壊だけでも、人間はそれだけでは生きていられないと私には思えたから」。自分の考えに基づいて、自分の道を選んで生きている女性。そうした存在が描かれることが、とても新しかったからである。
マチルダ役を演じた声優の戸田恵子は、当時のマチルダ人気について、このように述べている。
マチルダは、何しろ初めてのアニメ出演だったので、無我夢中で終えて、今になってこんなに人気が出てきたことに驚いています。
自分ではよく判らないのですが、何といっても主役のアムロが初めて恋心らしきものを抱いた人という設定がよかったのではないでしょうか。(中略)
面白いことに、ファンレターの殆んどが女性なんです。アニメの中で、マチルダみたいなタイプの女性が出てくるのは初めて、という意見が多く、女なんだけれども軍人で厳しい感じがいいとか、多少宝塚的な要素もあって、宝塚が女性にウケルというのと同様の感じだったのではないかとも思います。(後略)
マチルダ中尉は、補給中に敵の攻撃を受けた際、ホワイトベースを守ろうと自ら出撃し、アムロの奮闘も虚しく敵前に散る。その後、連邦軍基地ジャブローで、アムロは彼女に将来を約束した婚約者がいたことを知る。
その悲劇性もまた、彼女の人気を支えた一つの要素であろう。ここで注目したいのは、彼女の死の理由である。恋人のためだったり、子供のために自らを犠牲にするのではなく、彼女は自らの職責を全うするために命を賭けたのだ。これまで男性に振り当てられていた役割を、女性が担った。女性ファンの多さは、そんな彼女の描かれ方に対する衝撃の大きさを物語っている。

(4)きっかけは、シャアとガルマ
このように、女性ファンの心を惹きつける要素として、今までにはなかった女性像が描かれたということをポイントとして示してきたが、おそらく女性ファンが顕在化したのには、別の要素が大きかったと思う。イケメンの敵キャラクター、シャアとガルマが、少女らの心を鷲掴みにしたのである。
敵の美形キャラクターが人気を博するというのは、何も「ガンダム」に始まったことではなく、先行するロボットアニメでも、また「宇宙戦艦ヤマト」でも、主人公の敵であるデスラー総統が多くのファンを獲得した。敵の美形キャラクターとは、そういう先例があって設定されたものであるが、その敵キャラクターである仮面の男、シャア・アズナブルもまたその一人である。その人気に火をつけたのが、同じく美形の友人ガルマ・ザビであった。
ガルマ・ザビはジオン公国を統治するザビ家の三男で、シャアとは士官学校で同級生で親友という間柄である。シャアが謎めいた過去のある男であるのに対し、ガルマは家柄もよく素直な性格で、まさにシャアとは真逆のキャラクターである。
そのガルマについて、脚本家の一人山本優はこのように語っている。
あのキャラクターについては家庭の中で抑圧された人物を描こうとしたんです。ぼっちゃん育ちで、才能はあるんだけどとても繊細で、強烈な個性をもつ自分の家族に対して、常に抑圧と劣等感を感じていた。だから何か突出した行動で自分を表現したいという衝動を内在した人でした。
そうしたキャラクターの内面は、女性という理由で、あるいは男性にくらべて家庭の中や学校、職場で抑圧されてきた人たち、女らしく、良い子を演じることを強いられている女性たちの共感を得るものではなかっただろうか。そのガルマと真逆の性質を持つシャアとが親友であることに、この謎めいた男が抑圧からの解放者となってくれる、という期待を抱いたとすれば、シャアとガルマ、という二人の存在は、まさしく女性の心に刺さるものとなったわけである。
だが、残念ながらシャアはガルマにとっては偽りの友でしかなく、彼の「突出した行動で自分を表現したいという衝動」につけ込んで、彼を死へと追いやってしまう。そのとき、ファンから「カミソリが送られてきた」ことが語種になっているが、それもまた、キャラクターとの自己同一視が進んだ結果といえよう。

デフォルメされたシャアとガルマが繰り広げるコメディ
(5)視聴率の振るわなかった作品を支えたファンたち
日本サンライズから出版された「機動戦士ガンダム 記録全集」の最終巻には、ファン人大特集というページがある。「ガンダム制作の見えない協力にあたって」と題した一文が添えられ、ファンから届けられた同人誌が紹介されている。誌面に取り上げられた52の同人誌のうち、発行者の氏名から女性ファンと推察されるものが、少なくとも25誌はある。


また、1981年2月発行の「月刊OU T 2月号」の中の、「機動戦士ガンダム」を課題とした「アニメ感想文発表」のコーナーでは、応募総数697通(ヤマトの10倍)、原稿用紙にして6000枚分の感想文が寄せられている。入選第一席はなしという厳しい選考だが、最終選考に残った作品は入選9作、佳作5作であった。うち、全文が掲載された入選作9作のうち2作が女性、名前のみ発表された佳作5作のうち4作が女性のものだった。
当時のアニメ雑誌の投稿欄には、アニメのキャラクターを用いたパロディ漫画などが数多く投稿されており、そのごく一部を手に取っても、ガンダムをネタにした女性の作品は数多く、放映中から、本作のファンとなって応援してきた女性は決して少なくなく、男性とほぼ同じくらいいたことが伺い知れる。

このとき同人活動をしていた人たちは、少なくとも私よりは年上で、今では60歳代になっていてもおかしくない。インターネットが普及し始めた1990年代後半から2000年代には30代後半から40代で、その頃には、こうした同人活動からも離れ、もはや可視化できる存在ではなくなっていた人も多いだろう。
ただ、制作当時ガンダムを支えた彼女ら女性ファンが、離れていったのはそれだけが理由ではないようにも思われる。
(6)ガンダムは、家父長制を破壊した
さて、冒頭では「宇宙戦艦ヤマト」の艦橋と「機動戦士ガンダム」の船ホワイトベースのブリッジとを比較し、紅一点だったヤマトに対してガンダムでは複数の、それぞれに異なった素質や背景を持つ女性がいたことを紹介した。その違いは単に女性キャラクターの数や彼女らに与えられた役割だけにあるのではない。もっと大きな違いが「艦長=父親」の存在の有無である。ヤマトの艦橋には、艦長席に乗組員よりはるかに年上の沖田十三という艦長がどっしりと腰を据え、年若い乗組員たちを見守り、時には厳しく接しつつ指揮していた。それはさながら、伝統的な家父長制の組織であった。
しかし、ヤマトの逆張りをゆくガンダムでは、早々に年配の艦長は死んでしまい、若干19歳のブライト・ノアにその重責がのしかかる。しかも乗組員は組織化された兵士ではなく、たまたま乗り合わせ武器を取ることになった民間の少年少女であり、組織の論理などお構いなしである。2、3歳ほどしか年の差のない指揮官に、そうでなくても反抗的な思春期の少年少女たちが、従順になれるはずもなく、出撃拒否、無断出撃、命令違反、脱走などを繰り返し、ブライトにとって敵はジオンだけではなく艦内にもいるといった状況であった。
もちろん、ではヤマトは万事平穏だったのかというと、そんなことは全くない。ヤマトの主人公、古代進は沖田が気に入らないと当初は反発し、何かにつけて楯突いたり自分勝手な行動を起こしたりしていた。だが、最終的には沖田の権威と指揮官としての采配によって秩序を取り戻し、古代は諭される。こうして、家父長制による組織運営は微動だにせず守られ、沖田はその死後も彫像となってヤマトの艦橋で神の如く睥睨していた。
しかし、わずか19歳で指揮官としての経験もないに等しいブライトには、そんな権威を振るうことができるはずもない。逆に言えば、彼の下で戦う者たちにとって、彼は自分をぶつけていきやすい、チャレンジしていきやすい壁だった。こうした、ブライトの有り様は、ただそのままで、年齢順や性別によって負うべき役割や責任を割り振り、その秩序の維持を最優先とする家父長制を「ぶっ壊す」ことにつながったと言っていいだろう。
そんなブライトについて、脚本家4人の座談会で星山博之はこのように述べている。
私はね、ブライトっていうの、最後の二本書くときまでわからなかったのね、正直いって。あそこでやっと、ああこれは乗り越えられていく父親像っていう面をみたとき、なるほどと思ったくらいで。それまで、あんまり意識しなかったしね、キライだったし。
それに対して松崎健一は「ぼくは意識したよ」と述べ、続けて
ブライトは挫折しちゃいけないんですよ、絶対に。あのキャラが挫折したら、ホワイト・ベースはぶっこわれちゃいますよ(笑)でもね、ブライトの弱さを書いたのぼくだけなんですよ。
と言っている。ここで語られている「乗り越えられていく父親像」というのが、日本の家族を長く支えてきた家父長制の中の父親像と対立するキャラクターとなっているのである。
なぜ、ここで家父長制に言及するのかというと、それは男性優位の社会の土台であり、女性を男性より下に置いてコントロールするという社会システムで、みながそれぞれの立場でその影響を受け、この社会の中でそれぞれの生きづらさを作り出しているものだからである。ホワイトベースで、主人公のアムロは、地球に残る母と再会したものの、「あそこには仲間がいるから」と母を捨て旅を続ける選択をした。ミライはヤシマ家の娘で親の決めた婚約者がいた状態から、自分で自分の好きな相手を選ぶ自由を得た。セイラ・マスはシャアが兄であり、その目的がザビ家への復讐であることを悟ったとき、軍を抜けろという兄の忠告を無視して戦場に立ち続ける。それぞれが、家族からのコントロールを受けずに自由に生きる道を選ぶ中で、ホワイトベースは疑似家族的な集団へとなっていくのである。
本作の最後には、ニュータイプというややオカルト的な概念が出てきて、それが議論を呼んだこともあった。だが、今、こうして40数年の時を経て眺めてみると、ニュータイプなるものは、既存の社会システムから自由になって生きることを選んだ者、とみると、腑に落ちるものがあるような気がする。
その意味で「乗り越えられていった父親」としてのブライトもまた、この世界の新しさを象徴するキャラクターだったといえるだろう。
だが、続編の「機動戦士Zガンダム」で、その世界観は一変する。物語第2話に登場したブライト・ノアは、命令なく自己の判断で行動したことを咎められ、上官から暴行をうけてボコボコにされる。こうして世界は、家父長制の中へと引き戻されてしまったのである。
(7)裏切る女、殺される女
ヒルダ・ビダン
主人公カミーユの母で地球連邦軍の技術士官。ティータンズの人質に取られ、カミーユの目の前で殺害される。
ライラ・ミラ・ライラ
地球連邦軍のパイロット。主人公カミーユとの対戦で戦死。
エマ・シーン
特殊部隊ティターンズを裏切り、反地球連邦組織エゥーゴに参加。最終回で戦死。
レコア・ロンド
半地球連邦組織の工作員だったが、裏切ってティターンズに参加。第49話で戦死。
マウアー・ファラオ
ティターンズの士官で主人公カミーユの敵ジェリドと恋仲になる。戦闘中ジェリドを庇って戦死。
フォウ・ムラサメ
記憶を消された強化人間。香港でカミーユと出会い恋に落ちるが互いに敵対する組織にいることがわかり苦悩する。すったもんだの挙句、カミーユを守って戦死。
サラ・ザビアロフ
ティターンズのパイロット。スパイ工作中にカツ・コバヤシと出会い好意を抱き、戦闘中敵であるカツを守って戦死。
ロザミア・バダム
ティターンズの強化人間で、カミーユが兄という偽の記憶を受け付けられている。主人公らをさんざん振り回した挙句に、カミーユにより殺害される。
ここに挙げたのは、「機動戦士ガンダム」の続編「Ζガンダム」に登場する主要な女性キャラクターのうち、殺された者のリストである。最後まで生き残ったのは、主人公のガールフレンドのファ・ユイリィ、アムロの恋人ベルトーチカ・イルマ、そしてアクシズを率いるハマーン・カーンぐらいではないか。
しかも、主人公のカミーユは、このリストのほぼ全員と何らかの関わりがあったり接触したりしているのだ。これでは、主人公は「女」と戦っている、と思われても不思議はない。
しかも、これら女性キャラクターは、軍隊という組織に組み込まれた軍人であり、あるいは特殊な能力を見出され、自らの意志に反して強化人間にされ戦いに駆り出されるという、家父長制的な組織やコントロールに従順にさせられた存在として登場する。精神に異常をきたし、錯乱したりする者もいる。また、この中の幾人かは、個人的に好意を持つ男性を庇って死んでいる。
ここまで書けば、前作「機動戦士ガンダム」ではいきいきとしていた女性キャラクターの描写が、後退してしまっていることがおわかりいただけるのではないだろうか。
前作から5年後に続編として制作された本作だが、その5年の間に、作品をめぐって大きな変化があった。前作の放映終了後に異例のこととして、もともとスポンサーではなかったバンダイから、プラモデルが発売され第ブームを巻き起こしたのである。このブームが下火になってきたことで、「ガンダム」の名を冠した新作が求められるようになった。そして制作されたのが、こうした特色を持つ作品だった。
これは、前作の女性ファンを惹きつけられるドラマだっただろうか。新しくこの世界に入った人の中に、女性ファンはどれだけいただろうか。今となってはわからないが、結局のところ、女性ファンが多かったということも、女性ファンの姿が見えなくなってしまったことも、その作品が何を描いてどう受け止められたか、ということの結果としか、言いようがない。
(8)BLは乗り越えるべきもの
最後に、少しだけ触れておきたいのは、BLについてである。今やファンノベルやファンアートには「女性向け」「腐向け」といった注意書きがつけられるようになって久しい。それらはBL、いわゆる男性キャラクターどうしの恋愛を描いた作品を意味する。女性ファンが、女性キャラクターが排除された独自の世界観で作品を再解釈するのである。
この根っこには、女性自身の中に内面化されたミソジニー(女性蔑視)があると言われている。
ガンダムの世界においても、女性ファンの作り出すファンノベルやファンアートの中心は、BLである。こうなったのには、作品に罪があるとは思わない。女性として、自分の内面にある醜い感情、劣等感などに向き合い、それを克服していかなければいけないと思う。ただ、作品が問いかける価値観を、無条件に自分の中に取り込んではいけないと思う。私自身はBL作品はもともと好まなかったが、そうであっても、自分の書くものの中にも女性蔑視の傾向があったことは確かである。しかし、それを飼い慣らし、自らを慰めるものとしてはいけないと思う。むしろそういうものの縛りに気付き、解放されてもっと自由に考えられるようになる、そういう道を一人ひとりが選べるといいな、と思っている。
最後までお読みくださり、ありがとうございます。 ぜひ、スキやシェアで応援いただければ幸いです。 よろしければ、サポートをお願いします。 いただいたサポートは、noteでの活動のために使わせていただきます。 よろしくお願いいたします。
