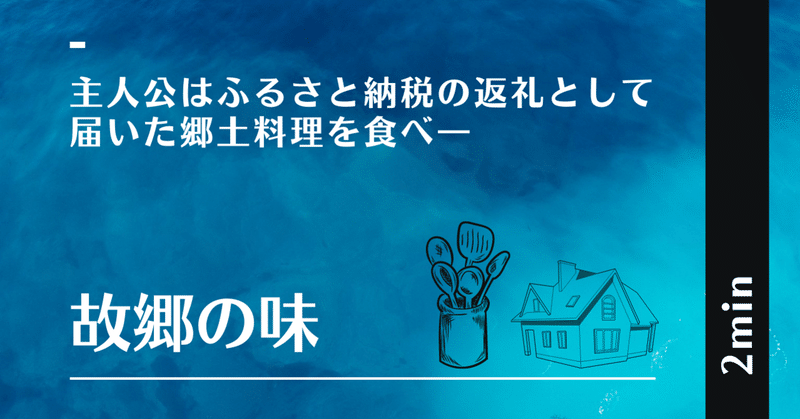
故郷の味|1,053字
彼の元にその郵便物が届いたのは、彼が大きな仕事を片付けて長期休暇に入った初日の朝方のことだった。
自宅に備えてある宅配ボックスを開けると、そこには彼の故郷の名とイラストが印刷されたダンボールが入っており、それは彼が故郷に収めた『ふるさと納税』のお礼の品に違いなかった。
「あぁ、もうそんな時期だったか……」
そうつぶやいてから箱を開けてみると、そこには真空パックされた状態の『のっぺ汁』が数十個入っていた。
*
彼はその味を頭の中で思いだすと、懐かしい感覚が溢れ出してしまったこともあり、早速朝食に食べてみることにした。
「あぁ、懐かしい……この味だ」
そう言って、彼は数年ぶりの郷土料理を心から楽しんだ。
(でも、おふくろの作ったやつとは少し違うかもな……)
そんな考えが頭がよぎり、彼はメールボックスの中身のことを思い出し始めていた。
*
彼の両親からメールが届いたのは1週間前のことだった。
そのメールを要約すると「こっちは元気にしているがお前は元気かい?気が向いたらいつでも顔を見せてくれ」といったいつもの内容だった。
彼は二十歳を過ぎた頃に家出当然のごとく実家を飛び出しており、それからすでに10年近くの時が経過していた。そのあいだ彼は両親に対して一切の連絡をとっておらず、定期的に届く両親からのメールもすべて無視していた。
*
彼は自分の両親のことが嫌いだった。
両親とは縁を切ったつもりでいたし、今回のメールも無視しようと決め込んでいた。
しかし、久しぶりに故郷の料理を味わった彼は、子供の頃にその料理を作ってくれた両親のやさしい記憶がフラッシュバックしていた。
そして次の瞬間には『ふと故郷に帰ってみたい』という気持ちが湧いてきた。おそらく、長い年月が彼の心や考え方を変化させていたに違いない。
「おふくろはもう……80歳になる頃か……」
生きているうちに最後に会ってみるのも悪くない、彼はそんなことを思ったのかもしれない。
*
その日の午後、彼は運転席に乗り込むと、キーを回してエンジンを始動させていた。
彼はその時に至ってもなお心の中で躊躇する気持ちを捨てきれずにいたが、小刻みな振動を体で感じているうちにその抵抗が薄れていくのを感じ、ようやく決意を固めた。
「そうだな……」
彼はリクライニングシートに身を任せ、徐々にスピードが上がっていく慣性を体で感じていた。
*
「故郷か……」
彼はそうつぶやいて、窓ガラス越しのはるか前方の景色を見据えた。
その瞳には飛び立った時と同じ姿をした『青い惑星』が映っており、その目元にはその惑星と同じように水が浮かんでいた。
―了―
役に立った記事などありましたらサポート頂けると嬉しいです。
