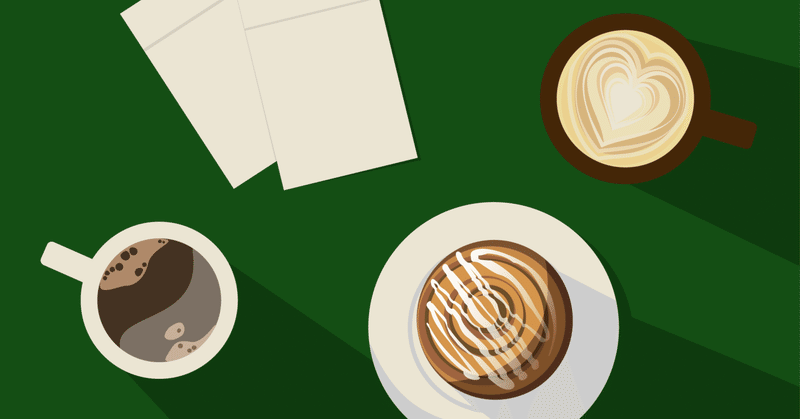
会社経営の基本原則とは?|経営者が理解すべき経営の基本・・・という記事の紹介です。
起業する前に商工会議所主催の創業塾で学んではいたのですが、あらためて基本について再確認しておきたいと思いました。
会社の営みを続けるための基本原則、即ち、会社経営の基本原則は「お金を増やし続ける」ところにある。
なぜなら、会社経営は、お金が無くなると破たんし、お金さえあれば永遠に続くからだ。
会社のお金をキープする、或いは増やすための最低条件は二つあり、一つは「黒字経営」、もう一つは「利益拡大」である。
事業をしている以上、これは本当に当たり前のことなんですけど、介護現場で仕事をしていると、なんだかそうではない違和感を感じたりするのですが、それは介護という人間の尊厳を守るための当たり前に存在するはずの行為を経営という枠にはめてしまった事による違和感なのかもしれないな、なんて考えたりしてますが、介護保険制度が民間の業者が介護サービスを提供する仕組みである以上、そこに上記の基本原則である、黒字にすること、利益拡大すること、が求められる状況になるのは当然です。
事業所が破綻しては、元も子もありません。
黒字経営とは収入よりも支出が少ない状態を表し、モノを売ったら、1円以上儲かるというのが黒字経営の基本原則になる。
収入よりも支出が下回っている以上、資金繰りを見誤らない限り、会社が倒産することはない。
しかし、黒字経営であっても毎年一定の収入と支出では、会社の利益も一定になり、成長投資の規模も経営者や社員の生活レベルも一定ということになる。
ここも重要ですね。
1円でも黒字であれば倒産する事はありませんが、利益がずっと同じであれば職員を含めた生活レベルも同じで賃上げはできない、という事です。
ですので、いろんな意味で”停滞は後退である”と言われていますが、そういう事なんだと思っていて、それは経営競争にさらされている介護事業所にも同じことで、昨日と同じ、去年と同じ、という状況であれば、そこに成長はなく事業所が良くなる事も賃金が上がる事もない、という事になります。
特に介護保険制度の中で単位や定員を国が定められている介護事業は、その制限の中でも利益を増やし続けないと成長も処遇改善もできないという事で、物価高騰や他産業が賃上げをしていく流れの中で、かなり厳しい経営判断が求められている状況と言えるし、現場職員は、限られた人員の中で昨日よりも、去年よりも1円でも多く売り上げを上げる必要がある、という事になります。
そういうのは経営者・経営陣の仕事でしょ、と言われるのですが、それは当然その通りなのですが、現場でサービス提供して売り上げを生み出しているのは現場の職員にほかなりませんので、現場レベルでのサービスの質、提供量、顧客満足度というのが直接売り上げにつながるわけで、その上で今後は人手不足になるわけですから、賃上げもセットで実現するとなるとこれまでと同じでいい、という事にはならず、これまで以上の成果を出さないと何も始まらないという事で、生産性向上のためのシステムやロボットの導入に資金を投入するという事は、その分だけ賃上げに充てられる資金も少なくなるという事なので、経営者にはそういう部分でのバランス感覚が求められているという事でしょう。
介護保険制度の中では処遇改善の仕組みもあるので、もしかしたら成長しなくても処遇は改善できる状況はあるかもしれませんが、経営の原理原則は黒字化と利益拡大ですので、それが出来てない状況であれば事業の継続は厳しいという事に違いはないでしょう。
つまり、経営者が成長志向を放棄すると、会社衰退のリスクが高まるのだ。(ちなみに、ボチボチの黒字経営から一転して会社が衰退した中小企業の実例は沢山ある)
会社が衰退するということは、収入が減少するということだ。万が一、収入よりも支出が上回ると黒字経営が破たんする。
ひとたび黒字経営から赤字経営に転落すると、会社のお金が減りはじめ、事業の衰退スピードは一段と加速する。
ですので、経営していく上で、これでいいや・・・という状況は存在しないはずなんですよね。常に成長を意識する。
ただ、現場レベルにこういう話を理解してほしいという事ではなくて、あくまで経営者やリーダー層は知っておくべき基本中の基本である、という事なんですけど、僕自身は現場職員だった時に、その職場維持を考えた時に、やはり現状維持では破綻すると思っていたので、職場を大切にしたいとか、この仕事を続けたいというマインドがあれば現場職員であっても自然と行き着く到達点なんじゃないかなぁと思います。
未来永劫に亘って経営を続けるには、ただ単に黒字経営を続けるだけでは物足りない。
やはり、黒字経営に満足することなく成長投資の規模拡大のため、或いは、経営者や社員の生活レベル向上のために、利益の拡大を考えなければならない。
それが、中小企業が経営を続けるための基本原則なのだ。
職員の処遇を少しでもアップさせたいのであれば、どうかんがえても利益の拡大はセットになります。
現状ママでの処遇改善というのは基本原則から外れた状態であるという事です。
それは、そもそも他産業よりも低い処遇での経営モデルでやってきた介護業界全体に言える事で、他産業に合わせた処遇改善をするのであれば、それそうおうの経営構造やシステム・組織やチームの変革がセットで行われなければならないのは当然の話になるわけです。
経営の基本原則に続いて、経営者の基本的立場についても解説する。
経営者は自分の判断を他人事にできない唯一の立場にいる。なぜなら、経営者には、副社長以下とは違い、自身の経営判断を委ねる相手がいないからだ。
会社の業績は経営判断の繰り返しで形作られていくので、経営者の業績責任は非常に重い。
経営者の孤独感、時おり背筋を正される重圧の正体は、この辺にあるのではないかと思う。
また、経営者にとって「経営」と「人生」は、一心同体である。
どういうことかというと、会社の経営が発展すれば経営者の人生も発展するが、会社の経営が行き詰れば経営者の人生も行き詰るということだ。
この部分、僕自身も経営者になって痛感というか、ほんとに実感している内容です。
僕の会社の業績の責任は全部僕の責任なんですよね。
なので、僕の人生=会社の経営、というのも本当にその通りです。
やりたい事にチャレンジできる一方で、常に背水の陣であるという緊張感はふとした瞬間に非常に強いストレスになって襲ってきます。
以前雇われていた時にリーダーや管理者は孤独だ、と思ってきたし、そういう事を後輩の管理者やリーダーにも伝えてきたのですが、経営者の孤独というのはそれ以上のプレッシャーですね。
経営の基本原則は、売上・利益・現金、この3つの数字を拡大することです。売上拡大に躍起になっている経営者は多いですが、大切なのは、利益と現金の拡大です。業績が低迷している中小企業ほど、利益と現金の拡大を見落としています。利益と現金なくして、会社経営の成功はあり得ないと思ってください。
基本原則の売上・利益・現金、これは本当に重要と思います。
特に意識してそうしたわけではないのですが、弊社では手元に現金が入った時点で会計処理をしています。
2か月後に入る予定の売上があったとしても、今この瞬間に手元にないお金の事を考えてもあまり意味がないと思ったからなんですけど、会社の口座の残高が増えるようになるまでは本当に厳しかったですが、増えるようになってくるとその数字自体が安心感になってます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
