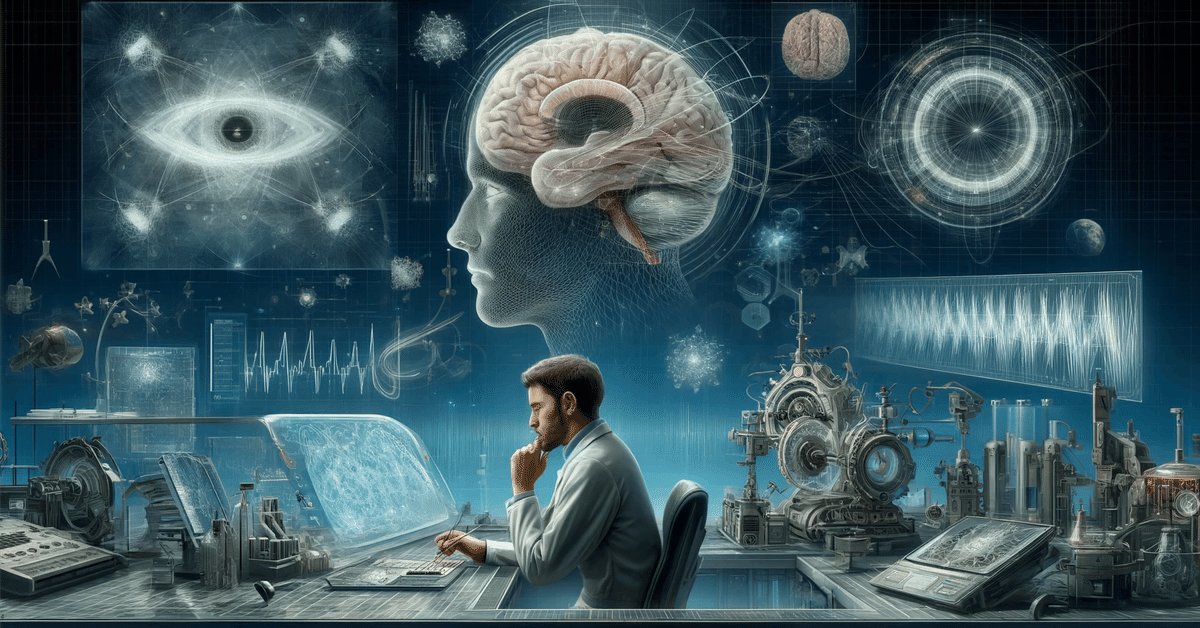
意識を解明しようとする脳科学の限界が気になる
ある時から脳科学という言葉をよく耳にするようになった。今からすれば、かなり昔の話だ。それまでは人の心や意識の領域を扱うのは哲学や心理学、あるいは文学が定番だったが、そこに脳科学が参入してきた形に見えた。
脳科学は脳の機能全般を扱う学問だから心や意識だけにフォーカスしているとは限らないが、いずれにしても哲学や心理学よりも実験的、生化学的、数学的なアプローチを取るイメージがある。
脳科学の中でも、私の関心は意識の問題に集中している。私たちの持つこの意識はどんなメカニズムで生じているものなのかということだ。
私が青い空を見上げる時、その青は脳のどんな作用によって青と感じるのか。私が昨日の空を思い出す時、青い空を背景に風に揺れていた木々の緑はどうやってこうもありありと浮かび上がるのか。
興味は尽きないのだが、一つ大きな疑問がある。それは、意識が生み出した言語や数学といった体系を用いて意識を客観的に記述することなど出来るのか。記述出来たとして、その記述はこの私の意識とどれだけの関連性がありうるのか。
こういうのを上手く表現した言葉があったと思うが何だっただろうか。再帰的や自己参照的といった単語だろうか。
脳の機能の一部が意識という機能を司っているという考え方自体が分析的であるが故に、どうしても死角ができてしまうのではないか。分析するという手法が科学を前進させたのは間違いないとしても、脳の機能を把握することに限っては上手くいかない気がしてならない。
脳の仕組みを模倣しているAIにしても、それはあくまでも模倣であって、神経細胞の機能の一部を抽出してシンプル化したものだ。脳と同じレベルの大きさとエネルギー源で動くようなAIは当分出来そうにもない。脳科学の研究で使えるような、コンパクトで完全な人工脳が出来る見込みは当面ないだろう。
ということは、私が生きている間に意識のことが解明されるという期待は裏切られる可能性の方が高そうだ。
どうせ分からないのであれば意識のことに思いを馳せる時間を費やすのは無駄なことだろうか。逆に、解明されるのだとしたら無駄ではないと言えるのか。
どちらにしても私のような凡人が思いを巡らせたところで何が分かる訳でもない。謎が謎でなくなったら楽しみが無くなってしまうので、しばらくは分からないままの方が良いのだろう。意識の謎が解明されたところで、私が変わらず私であり続ける訳だし。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
