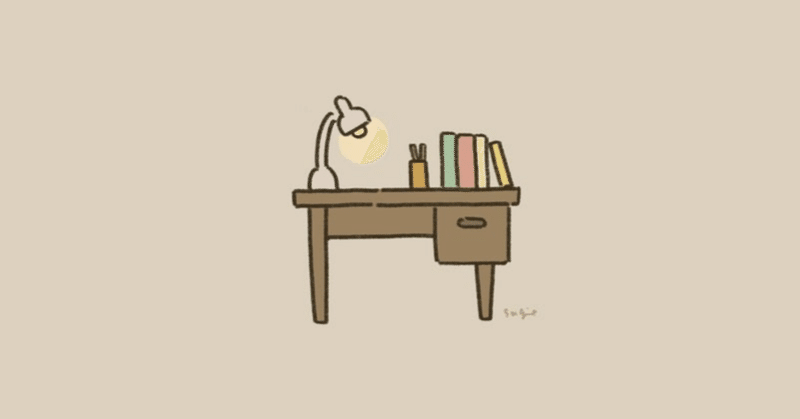
勉強には自分で意味付けをする / 書く習慣1ヶ月チャレンジ Day19
自分があまり賛成できない常識
これは常識なのか分からないが、「学校の勉強はやる意味がない」という意見には賛成できない。
学校の勉強=知識の詰め込みではないと思っている。私が考える「学校の勉強の意味」は3つある。
好き/嫌い、得意/苦手を見つける
学校の勉強ってみんな一律だ。周りとも比べやすい。
それがいいか悪いかはさて置き、一律だからこそ気づける自分の特性もあるのかなと思う。
好きなことや得意なことが見つかれば万々歳だし、嫌いなことや苦手なことがあれば、今後の進路の候補を絞る指標にもなる。
在学中はもちろんしんどい思いをすることも多いけれど、今となっては自分を知るための時間だったんじゃないかと思える。
物事を見るときのフックになる
学校での勉強範囲は、けっこう幅広い。小学校は特に、嫌でも色々な分野に触れることになる。
大事なのはその場の暗記ではなくて、2回目に同じものに触れたときなんじゃないかな。「これ進研ゼミで見たやつだ!」のあの感覚。
あまり興味がなくても、1度触れているものにはなんとなく引っかかる。そのフックは、割と学校の勉強で作られている気がする。
フックが多いと、日常生活がちょっと面白くなる。「知ってる」って、豊かなことだと思うんだ。
タスクへの取り組み方の型を作る
教育は権利であるはずだけど、当事者からしてみればタスクだ。
タスクへの取り組み方にはけっこう個性が出る気がする。自分が1番成果を発揮しやすいやり方を、学校の勉強で見つけられたらラッキーだ。
卒業しても、タスクからは解放されねえんだもん。
ほんとにやりたいことだけやれたら幸せだけど。やりたいことのために、やりたくないことをやらねばいけないこともある。
そういうときに「タスク片付け力」が役に立つんじゃないかな。自分の型があれば、ある程度自分のペースで取り組むことができる。
長々と書いてきたが、それなりの時間を費やしてきた「勉強」というものに対して、意味付けをしたかったのかもしれないな。
知識としては必要なかったり、成果として表れるものではなかったとしても、「意味ない」なんてことはないはずだ。
私は、学び続けられる大人でありたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
