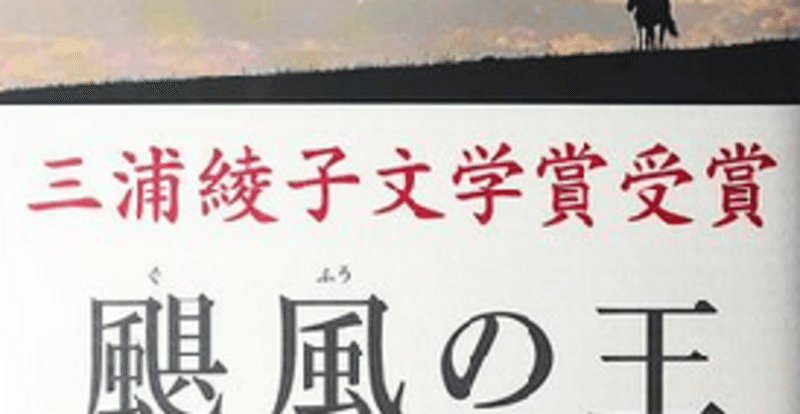
必死に生きてこそその生涯は光を放つ。
動物は自らを殺さない。
生きることに執着する。それは私も、きっと祖母も。
花島の馬も。それは個人の意思を超えたところにある、
不変の事実なのだろう。
(本文より抜粋)
我々人間たちはその昔、山には、海には、
この、自分たちを取り巻く自然や、そこいらで生きる動植物たち、
凡ゆる物事には「及ばぬ」ことがあることを知っていた。
どんなに抗っても、力を尽くしてもダメなことがあることを、
ただ「生きている」だけで知っていた。
しかしそれは限界や諦めではなく、「身の程を知る」という意味に於いて。
それ故に畏怖し、畏敬の念を以てして生きていた。
人間と自然は切り離されたものではない。
むしろかつての我々はその一部であったのだ。
だからこそ、及ばない。
しかし、いつしかそれらを掌握しようなどと驕り高ぶり、
自然から仲間外れにされていく。
私たちは精巧なAIにはなれず、動物として生きることもできず、
ただ、理を破り、土足で踏み荒らし、そして、自分たちでそう仕向けたにもかかわらず、生きる意味とはなんぞやと、
空を見つめる阿呆の如き得体のしれない何かに 成り果ててしまったように思う。
生きる事とは、それ自体が今よりもっとずっと切実で、
それはそのまま生の喜び、自分が「生きている」ことの喜びに素直に直結していたはずなのに。
現代でも冬には文字通り雪に閉ざされる北の大地、東北、北海道。
まだ北海道が開拓される前、
明治の東北に一人、馬と共に生きる青年がいる。
一心同体ではないかと思うほど、馬と心を通わせるその理由は、
かつて馬を喰らって生き長らえた母の血だからだろうか。
本書は、その母から産み落とされた主人公捨造の門出から始まり、
明治・昭和・平成を綴っていく、
とある一族と馬の6代に渡る壮大なクロニクル。
たった244ページながら、その風情、まるで大河ドラマを1本観たような読後感。
特に、読み始めてからほどなくして訪れる捨造の出生秘話。
静寂の中で行われるギリギリの命のやり取りの、凄まじい描写の中にある、
種族を超えての強烈な互いへの迸る愛に涙腺崩壊。
こんなにも自然な涙が出ることに驚いたが、決して悲しいだけの涙ではない。
時が経ち、総ての物事は変わっていく。移ろい往く。
変わらないことなど何もない。しかしそれは必然の理。
誰をも責めることはできないのだ。
この物語もまたそれをまざまざと思わせる。
時代が変わるにつれ、選ばれる言葉も現代に近くなり、
明治から平成の変化と同じくして変わっていく文体の妙にもしばしうっとりした。
及ばぬ。 人の意思が、願いが、及ばぬ。
ひかりの脳裏に強い文言が蘇る。オヨバヌ。
祖母が繰り返していた言葉だ。
地も海も空も、人の計画に沿って動いてはくれない。
祈りなど通じず、時に手酷く裏切ったりもする。
それは人がここで生き、
山海から食物を得るうえで、致し方ないことなのだと。
(本文より抜粋)
しかし、彼らの想いの鎖の末に生れ出ずる平成の孫は、
父が、母が、祖母が祖父が、曾祖父母が命を賭してきたその想いは
例え及ばぬことだらけだった人生であったとしても、
その実「及んできた」のではないかと思うに至る。
懸命に生きた証は其処此処に確かに有るのだ
その生涯の集大成が、彼女の目の前で光り輝いていた。
本書はまた、自分は決して一人で存在しているのではないということ、
脈々と受け継がれてきた血が流れているということを教えてくれる。
そして、上っ面の憐憫や同情、自己満足に満ちた動物愛護とは違う、
共に生きる同士としての動物愛に満ちてもいた。
自分も同じ地球に生きる生物の1個であるということと、
「生きる」ということの本来を改めて知らしめ、
その行為の根源的な問いを投げかけながら、元羊飼いが放つ己の生を見つめる物語。
超おすすめです。
↓ Instagramはこちら
https://www.instagram.com/p/CJrzqbbjcsq/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
