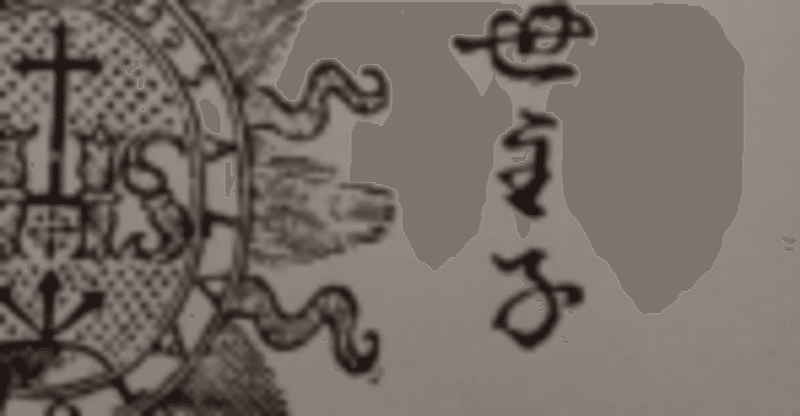
子の刻参上! 一.あけがらす(十二)
「鈴木さま、といやぁ……」
寝転んで箱枕をかい込んだままの次郎吉は、幼いころ中村座でその名を聞いた、と益田に話した。
「“まことは石高、二万一千石。むかしむかしに、抜け荷の帳尻をば合わせんとて、増しにましたる四万二千石との偽りが。一人歩きの。あ。百姓ごろしよ。” ってなあ。
なんとかお年貢高を正しく減らして、乱のあとの百姓を救ってやってくれと。
鈴木代官さまがこう、お芝居だからお武家さんはなさらねえやりようで、訴え書きを上役のお歴々に読んで聞かして、説諭なさる」
「そうだ、その鈴木の親戚筋だ」
益田は狐が持ってきてくれた茶を、とぷとぷと黄瀬戸の湯呑についで、ひとつを次郎吉に盆で押し出し、ひとつを自分の手元にした。
「いただきやす」
「その芝居は、興行できたのか」
「いやぁ、」と次郎吉、手をひらひらと左右に振った。
そうして芝居のせりふ回しを借りて、
「座付き作者はいろいろ練って、役者も所作をさだめてみるが。
受けがいいのは上へ上への義忠孝。
やんやの喝采を下さるお客様方が、総出で捕(とら)まってお仕置きをくらっちゃあ。
一座そろって、や、その日ぐらしの、銭もとまらぁ。
これは興行にはならねえ、あきらめな。ときた。
そんなのが二百も三百もころがっていまさぁ」
「はっはは」益田は興がった。「次郎さん、つくづく、いい声だなあ」
「ひとつのできごとが、芝居の種にできるころってのは、そのできごとが、なんのさしさわりも、なくなってからじゃねえと」次郎吉は茶をひとくちのむために、あぐらに直った。
「そうだな。
ほんの六十年ほど前に地蔵を建ててもらえたそうだが、いまだに、首を打たれた三万七千の、骨がそのままあちこちに埋められて、そっと見張られてもおるのだ。
きりしたんばてれんの術がかかっていると、終わりの日によみがえってくる、といういいつたえがあるのでな」
「術?」
「かの国では、司祭が水で洗って、信徒に生まれ変わらせるのだ。
神の子が三日後に死からのよみがえりを果たしたことを信ずるものは、水と火とでうまれかわる、と、本に書いてあるのでな。
終わりの日によみがえりがある、と信じ切ったばてれんが、ぱぱさまからの手紙を、なんども読んで聞かせる。
伝えるほうも、伝えられるほうも、本国で何度も何度も千年前から迫害を受けては耐えておるので、信じ切って死ぬことについては、年季が入っておるのだ。
村々に回状がまわってな。くりかえし、くりかえし。
本国では、“おみさ”というて、七日に一度、みなで集まって祈るときに教えを聞かせて天使のような童たちが歌をささげて皆で祈るのだ。そのようにして信徒を訓練しておるという。
孫子の兵法で最も恐れられている“死兵” を、文字通りに何代もかけて、作ってしまえるのだ。かの戦の、もっともむごいところはそこだ」
「“死兵” とは、死んでも死んでもよみがえってくる兵のことですかい」
次郎吉はみぶるいをした。
「孫子の教える死兵は、あとがないところへ追い詰められて、死に物狂いになった軍勢のことだ。後へすさったら死ぬばかり、という水の前に陣をしくので、背水といわれる。古来、死兵の作り方は急場の用兵であって、橋を落としたり、水の前に陣をしいたりして、覚悟をさせる。
ところが、その戦の死兵は、ずっとずっと長い間練りに練られてしまっていたところが、強く、むごいのだ。
うその石高を信じ切った年貢の取り立て側が行う蓑踊りや水責めと、迫害されても耐えて神の子の再臨を待てという書物に忠実な教えとが、くりかえしくりかえし、死兵をきたえてしまっていたのだ。
黙示録(もくしろく)という、本の最後に入れられた記録は、迫害の目を盗んで書かれたために、読み解けないほどわかりにくくしてあるのだ。その中に、 “さいごのぐんぜい” が天からおりてくる……と、たいそうきらびやかなことばでかかれておる。
まぼろしをありありと見せられる神のことばのあずかり人を、預言者というのだ。
神の言葉であるから、足してもいかぬ、引いてもいかぬと書かれておるので、書かれたものをそのまま一字一句たがえずに伝える。
訓練に本国で練られたやりようがことごとく入っておるので、七日に一度読んできかされ、歌をささげて皆で祈る、という集まりは、途方もない力を作り出すのだ。
普通のものには持ちこたえられぬところを、こらえて、こらえて、
ある日、だ。
ぱぱさまが二十五年前に予言していた善人が生まれ出た、といって、時節をひたすら待っていた豊臣軍も続々と加わり、ばねがはじけたのだ。
もとい、耐えがたきを耐えた “ばね” を、とうとうはじいた……のだ」
「一向衆の一揆の千倍も万倍も、おそろしいや」次郎吉はぎゅうっとちぢこまった。
衆をつくるものに対しては、どうにも恐怖心があるのだ。次郎吉が一人働きしかしていないのは、その辺にも事情がある。
「それが、ひいおばあさまの兄君、というわけですかい」
「うん」
「よみがえりをこわがられたせいで、三万七千のたてこもり衆は、女子供も骨のまま、土に浅く埋めたままでお留め置きにあってた、と、こういうことですかい」
「赤子もいたろうに、ひとりを除いてみなの首をまちがいなく打ちおとしたのも、恐れられたせい、としか説明のしようがない。籠城を二月(ふたつき)と旬日(とおか)余りもちこたえた強兵なのだ。清水様の高松城も二月より早く城主切腹で明け渡すと決め、成田様の忍城も寄せ手に三百人弱の溺死者を出しひと月。あわれにも、豊臣方の最後の戦場(いくさば)を待っていたものたちが合力(ごうりき)したせいで、赤子もおなごもとしよりも」
「そりゃあ、城を出て降伏したところで、水牢だの蓑踊りだのを喜んで見物する連中が待ち構えているのだもの、城で死にやすよねぇ」
「水と、火とで、彼らをのっぴきならない死兵に生まれ変わらせてしまったのは、領主とその手下(てか)なのだ。
三万七千の犠牲をもってして、領主の打ち首ひとつ。腹を切らせてやらなかったのが、ただひとつのこらしめだ。
鈴木代官の切腹によってしか動かぬ、うその石高も、のこったきり。
なんという、なんという戦のやりようだろうか」
「最大値の2割」ぐらいで構わないから、ご機嫌でいたい。いろいろあって、いろいろ重なって、とてもご機嫌でいられない時の「逃げ場」であってほしい。そういう書き物を書けたら幸せです。ありがとう!
