
マルコ・ローゼの新システム3-D-3解説
はじめに
どうも僕です。
このどうも僕ですの元ネタ思い出しました。
YouTubeで遊戯王開封されてる「みさわ」さんって方が太古の昔に動画始めの挨拶で使ってたんですね〜。
なんて言うとりますけども。
今回は先日のビーレフェルト戦から突如導入された、3-4-3について解説していくゾ!
3-D-3とは
タイトルにもありますこの3-D-3
見た感じ顔文字にも見えなくは無いですが、これは「 Diamond 」の頭文字であるDを使ったフォーメーションの表現です。

3-1-2-1-3の中央ダイヤモンド型を表現する際にめんどくさいので、ドルトムントのアシスタントコーチであるレネ・マリッチが使ってる表現をパクリました。
4バックでも4-3-1-2の中央ダイヤモンドがあるので、めんどくさい人は使ってみてください。
3-D-3のシステム
可変フォーメーションが欧州トップレベルに定着して数年が経ちましたが、その流れはとどまることを知らず、状況に合わせて姿を変えられる良さにフォーカスをあてた、利便性の良いフォーメーションが様々生み出されました。
その中の一つとして紹介していきます。

中盤の選手たちが旋回するように大きく動くこの可変フォーメーション。
シャドーの位置に入る選手がトップ下の様な役割から、IHの様な役割までを担当。
CHに入る選挙がIHの様な役割から、アンカーの様な役割までを担当します。
それでは実際に試合で行われた動きから、システムの機能性を探っていきましょう。

アンカー役を中央に配置する事でプレーエリアが広がったIH役は、CBの間に落ちてCBの前進を促したり、自身がCBの脇に落ちる事で相手守備者のアプローチを惑わせ。相手守備ブロックをズラしていきます。
対5バックのブロック相手はいかに守備者のマークをズラして前進出来るかが鍵となります。
そして、このIHの動きに合わせてトップ下役が相手中盤ブロック裏から顔を出しボールを受け取ったり、アウトナンバーを作り出したボールホルダーに合わせて裏を狙っていきます。WBもその動きに合わせて中、外にポジショニングを動かして、サイド攻撃に安定感と複数のパスコースを作り出します。
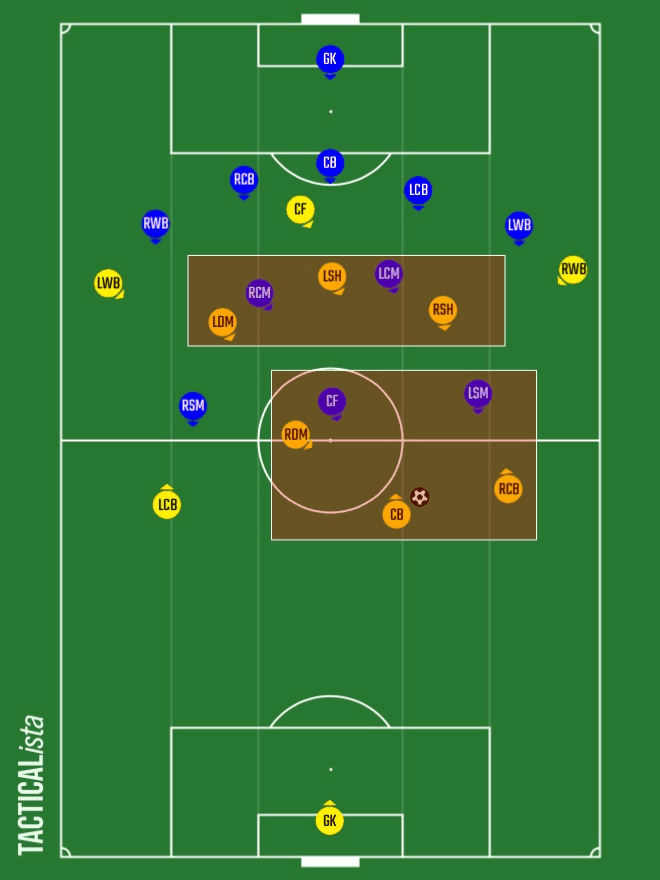
中央での局面も最終ラインの数を活かして、トレンドである2-3の多角形ブロックを交わせる事ができ、IH役の採用により中盤相手CHに基準点を与えつつ、中央を広げさせられます。
これだけではFWの選手が相手CBを背負う構図になるものの、ここで3-D-3の利点であるトップ下役の存在により、レイオフで相手をいなしつつDFラインの前を使えたり、そのままトップ下に配給して前を向いてボールを前進させる事も出来ます。

次にIH役がブロック間に居るパターンです。
相手は5-3-2になりますが、CBを起点にしてボールを運ぶ過程でアンカー役とCBでFWを挟み込み、アンカー役とIH役で相手IHを挟み込む事で、中間ポジションの選手の存在を相手守備者に意識させます。
これによりプレス意識の中にポケットを生み出し、脚が動きにくい短い時間でボールを前進させていきます。
常に相手守備者に二択を迫るポジショナルプレーの基本的な要素ですね。
更にIHが相手大外守備者の動きを規制し、WBに時間的余裕を付与するプレーも存在します。
これも同様、降りてきたWBと中盤+CBで相手中盤守備者を囲い込み、ボールを前進させていきます。
この場合はハーフレーンを使う選手を選ぶ部分から攻撃が始まるので、CBがハーフレーンを持ち上がる場面もありますし、ここに相手守備者が釣られれば、奥の大外に逃げた選手や、ブロック間のトップ下役の選手にボールを付けられる構図になります。
状況や相手フォーメーションに合わせて形を変える上で、中盤に4人とWG役を置ける柔軟性が非常に出ている可変フォーメーションだと言えます。

最後にファイナルサードでの局面での動きです。
左WBにサイドはアタッカーが配置されやすくなり、カットインからの展開や、そのまま中央の選手とのワン・ツーが組み込まれています。
WBと中央ブロック間に陣取る選手を補佐するように、ハーフレーンの低めには選手が配置されており、3人の関係が出来上がることで永続的にポジションを回しながらボールを動かす仕組みもあり、3-4-2-1の良い所を3-D-3でも使える工夫になっていますね。
この左からのプレーで右サイドへの展開が成功すると、WBが相手大外守備者を引き連れてブロックへ飛び込みます。これに入れ替わる様にIH役が大外へ開き、フリースペースとなった大外レーンを使うという動きが主な形となっています。
こうすることによって相手のマーク整理をぐちゃぐちゃにする事ができ、大外から技術力のあるIH役が安全にクロスを供給出来ます。
直近のインゴルシュタット戦ではまさにこの形からのゴールが2つ生まれて勝利しています。
まとめ
機能性としては、トーマス・トゥヘルの3-4-2-1~3-5-2を思い出す様な、緻密に練り込まれた3バックのように見えますが、選手の戦術や戦略への順応、誰が出てきてもこなせるような確かなシステムにまで落とし込まれているかと言うと怪しい。
しかし、顔を見せたのはほんの数節前の試合ですが、4バック時には無かった安定感+コーベルで、守備の脆さをカバー出来そうな雰囲気はある気がしています。
ローゼが本当にやりたいのは3バックなのかは未だに分かりませんが、3バックでも俺はここまでやれるんだぞ?という問い掛けをドイツ中に行う事で、4バックも使いやすくなる効果も期待出来るので、見せてよかった手札だよなと思います。
(ケルン戦で4バックに戻したし戦い方がそもそも3-D-3じゃなかった点から見てもどれ使うか迷ってそう。)
さいごに
監督がローゼになって、再現性という単語が自分の頭の中にチラつく頻度が増えたのは個人的に嬉しい変化です。
根気強く相手の脆い部分を突いていく地味さが、対局を大きく左右する要因となり得る事を、選手たちは持って知っていく必要があると私は思っているので、このまま選手たちの意識が更に変わっていくことで、アヤックス戦の様な不甲斐ない試合を減らす事が出来ると思っています。
あと全然関係無いですが、最近急に寒くなってきたので、皆さん体調管理を怠らずに、残り少ない今年を走っていきましょう。
僕ですか?僕は半袖短パンです!
~完~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
