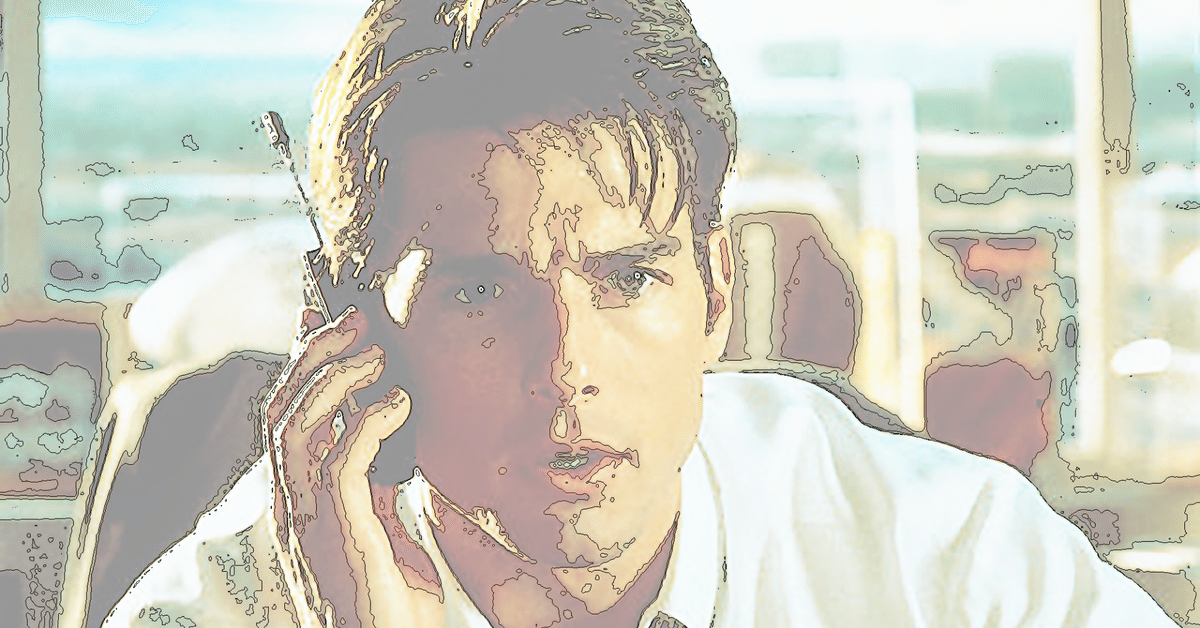
スタートアップのエンジニア採用
どこの職場でも採用は難しい課題となっていますが、とりわけITエンジニアはものすごくハードルが高くなっているようです。
ITエンジニアといっても職能とキャリアのレベルで多岐にわたっており、自分の認識は以下のとおりです。
サーバーサイドエンジニア
フロントエンドエンジニア
インフラ・ネットワークエンジニア
セキュリティエンジニア
フルスタックエンジニア
上級職だとこんな分類になります。
アーキテクト
テックリード
VPoE
CTO
最近は弊社でもエンジニア募集をはじめましたが、少人数スタートアップだとパーツだけを補う採用(ジョブ型採用)というのは難しいと思います。
サッカーに例えるとユーティリティのような選手を取らざるを得ないのが現実になります。
ではいかにそういったエンジニアを取るのか。
採用方法に関して言うと以下のパターンが普通かなと思います。
コーポーレートサイトでの募集広告
人材エージェント
リファラル採用
ダイレクトリクルーティング
ヘッドハンター
ポジショニングマップにするとこんなイメージでしょうか?

コーポレートサイトに掲載するのは最低限やらないといけないことではありますが、よほど有名な企業でなければコーポレートサイト経由というのは応募が多くないと思います。
一番いいのは今いるメンバーからの紹介・いわゆるリファラル採用なのですが、人間関係を気にしたりする手前、意外と難易度が高いです。自社のことをよく知っているメンバーが、会社に合いそうと推薦するからこそマッチ率が高いとは思います。会社側も紹介を促すために入社したらいくらみたいなインセンティブを用意していることも多いですが、なかなかそれだけだと紹介に踏み切れないのが現状です。仮に紹介で人が入っても、この人(紹介元)にお金が入っているのかと紹介された側に思われるのも微妙かもしれません。
ただ、悪いことばかりでなく、そこを乗り越えて入ってくれた人がいると、今いるメンバーの離職防止にも役立つのでうまく機能すればといったところでしょうか。
ダイレクトリクルーティングといえばCMでおなじみのビズリーチかと思います。ちなみに弊社ではWantedlyを利用しています。すなわち、転職意欲のある人に直接スカウトをかけるというものです。これは例えば半年でいくらとか年間でいくらという費用を払って紹介記事を載せさせてもらうというのが一つ。それに付随してスカウトを送れる件数が金額で決まっているので、良さげな候補者を検索して、スカウトメールを送ります。
候補者は色んな情報を出しているのですが、転職意欲とか、過去の経歴とか希望の仕事とか出ていて、狙いを定めてラブレター(スカウトメール)を送ってもなかなか開封や返信につながらないものです。しかし、採用が決まってもそれによる報酬を別途払う必要もないのでうまく活用できて最短で採用できればお安いソリューションとも言えます。
ヘッドハンターはあまりスタートアップ向けじゃないのですが、一応載せてみました。他社の有望な人材を直接引き抜いてくるという方法です。SNS経由、もしくはメールでコンタクトが来ることが多いです。私のところにも極稀に問い合わせが来ることがあります。SNSの中でもLinkedInはわかりやすいくコンタクト多いですが、ネット上でエゴサーチすると名前がいい感じに出てくる人はもう少し直接的に声かけられやすいのではないかと思います。
いい感じというのは有名企業の重役とか新聞、雑誌、大手メディア掲載実績あるようなパターンです。
採用企業側からするとお金はかかるのを覚悟で重要なポジションを埋めるという話になるので、ヘッドハンターの腕と企業側の動きの速さや熱量次第で採用にかかる期間は短縮されます。
DMMの亀山会長がpixivの片桐CEOをヘッドハンティングしてきたのはTOPが直接引き抜きを行った有名な事例になります。
最後に人材エージェントですが、これは登録している人を企業に合わせて紹介するというものになります。採用が決まれば、その人材の年収の30%〜35%を支払うというものです。ただ、実際は大手有名企業はエンジニアの採用に関してはかなり重要視しているので80%とか100%払っているところもあるようなのです。そうすることで優先的に有望な人材を紹介してもらえるという話です。
リクルートエージェント、Findy、Geekly、レバテックなどの大手に登録している人は相当数に登るため、紹介依頼をかけて時間がかかることはまず無いです。企業側の条件が厳しいものでなければ(スーパーエンジニアだけど年収300万でとか)候補はたくさん出してもらえたりします。この点で採用までのリードタイムは上に上げたものの中で一番短いといえます。
採用に関しては雇用形態もかなり重要です。社員採用は制約が非常に多く、慎重にやらざるを得ないのでどうしても時間がかかります。簡単にクビにできないというのとか社会保障払わないといけないとか固定費になってしまうので企業としても失敗は避けたいところです。同様に社員採用を求めるエンジニアも今では売り手市場なので一番条件のいいところにしたいこともあって、内定を出してもOKしてくれるとは限らないのです。
これに対してフリーランスの業務委託はもう少しライトに決まります。エンジニアでフリーランスに転じる人は年々増えています。以下の調査でも大幅に増えていることがわかります。コロナを背景にしているものと考えられます。

もともと社員として働いていて、給料が上がらないのと人事評価に嫌気が差してフリーランスに転じる人が増えているのでしょう。こういったひとたちが技術向上を求めていろんな職場での機会を求めているようです。長期には高くついてしまいますが、早く人を入れたいという現場には合っていると思います。もちろんこれも金額とか条件次第ではあります。
私も色んな人からアドバイスを頂いてはいますが、100の現場があれば100通りの答えが返ってきます。そういう意味で正解はないので参考程度にするようにしています。
業務委託で採用して、お互いの相性が良ければ社員化というのが一番美しいのかもですが、こういう話も今までの既成概念を取り払ってエンジニアにとってやりやすい条件に譲歩して上げる必要が出てくるんじゃないかと思っています(フルリモートOKとか図書費、イベント参加費会社持ちとかPCを好きなものにしていいとか)。
会社にとって欲しいエンジニアというのは、技術の裏付けあって、ビジネスに精通しつつ、会社へのロイヤリティが高い人であり、そういう人材に長期に働いてもらいたいということになると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
