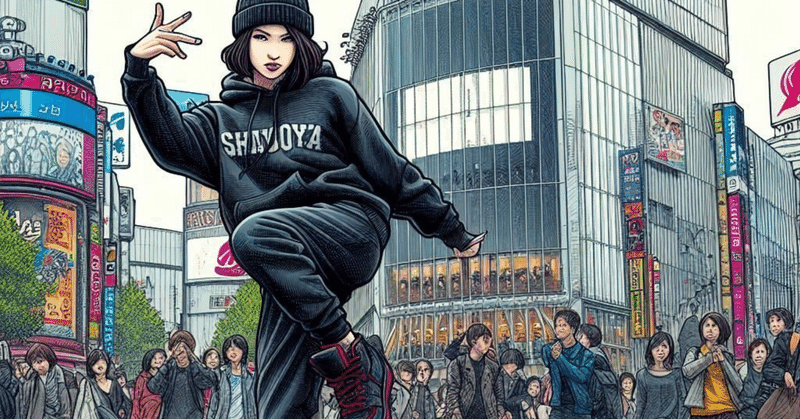
ヒップホップ禁止令からみる学校とメディアの関係性
今回はヒップホップ禁止令という目下、日本を騒がせているテーマをきっかけに、マスメディア、学校、文部科学省、そして大衆という4者の関係性について語っていきたいと思います。学校側からみたメディアの問題ですね。
ヒップホップ禁止令
ヒップホップ禁止令はつい先日(2024年6月時点)、東京都の麹町中学校が体育祭や文化祭でヒップホップダンスの発表を禁止して、代わりに創作ダンスをしなさいと命じたことが話題になったものです。
「なんでこんなのが全国的な話題に」と思われるでしょうが、麹町中学校ってのが特別で、ここは前任の校長が昨今話題の工藤勇一という人物で、彼は学校改革を声高に唱えておりますので、その学校に置いて後任の校長がある種の保守的とも捉えられる制限をかけたことが「生徒の自主性を阻害しているんじゃないかあ!」と非難を浴びたわけです。
つまりショボいニュースでもある種のブランド中学だから取り上げるに値すると判断されたわけですね。最初に大々的に報じたのは朝日新聞だったように記憶しています。それに有名人が次々とリアクションをしたことで話題が話題を呼び、ついには国会で議員が文科相に質問するところまで至ってしまった。
はっきりいってバカげています。こんなので国会の時間使うなよと心底あきれます。
ムカムカしつつも、いくつか確認しておきましょう。
第一に、マスメディアの目的は達成されていること。
マスメディアは広く大衆の関心を呼ぶニュースを伝えることが目的です。話題になる=目的達成。有名人が反応しまくったあたりで、この記事を書いたライターはガッツポーズしたことでしょう。報道の根っこに社会正義があったらいいなとは思いますが、一介の民間企業にそんな倫理的な期待を寄せるのはやめましょう。商売は商売ですので、たくさん閲覧・視聴されることが目的化していることでしょう。その意味で記者は成功しています。
第二に、これが話題になったのは学校の対応に問題があったからではなく「ヒップホップ禁止令」というワードがキャッチーであったから、ただそれだけであること。
「安全面への懸念から文化祭でのお化け屋敷を禁止する」といった学校の対応はよくみられるもので、学校と生徒とで話し合って解決できるならやればいいし、できなければ禁止すればいい。外野がとやかくいうほどの問題じゃありません。
この程度のニュースが話題になったのは、麹町中のブランド力もさることながら、「ヒップホップ禁止令」という文字列にパンチがあり、「ヒップホップ文化を抑圧する学校」みたいな図式が読み手の脳裏によぎるからです。実態はそんなことないですけどね。広告業界の視点でみれば、キャッチコピーが成功した一例です。
ちょっと話それますけど、これっておもしろくないですか?
「東京都中学でヒップホップ禁止令」とか、ニュースサイトに表示される文字列ってだいたい10文字ぐらいじゃないですか。10文字ぐらいがスマートフォンの画面に表示されて、たったそれだけの情報でクリックされるかが決まります。先週ニュースを見た大衆の膨大な選択の積み重ね、その勝者がこのニュースというわけですね。
そうしてみると、やはりキャッチーなタイトルを作った記者こそが勝者と呼ぶにふさわしいですね。そのキャッチーさにまんまと踊らされた大衆、そしてその大衆の関心から人気取りのためにイッチョカミしてきた国会議員という構図です。ズバリ言いましょう、どんな騒動も踊らされている側はおしなべて愚かです。
話を戻して。
第三に、有名人たちの目的も達成されていること。
こうした争論が起きると、有名人たちは自身の支持基盤となる層に向けてメッセージを発する必要があります。私もこのニュースを知ったのは呂布カルマ(※同世代の同郷の人なんで前からシンパシー感じているラッパー)のコメントでした。彼は「ヒップホップというのは学校にお膳立てされてやるものではなく裏でこそこそやるものだ」といった苦言を呈しているのですが、至極真っ当な意見です。
ダースレイダーというラッパーもヒップホップカルチャーの大切な要素についてメディアで語っています。彼の場合はややインテリ路線なので、このニュースをきっかけにヒップホップカルチャーの普及に努めている印象ですかね。
彼らには、ヒップホップ文化がメディアに取り上げられた場合、何らかのコメントを出すことが期待されています。立場上、出さねばならないんです。そうでなくてはヒップホップ界のご意見番という立ち位置を失ってしまいますから。仕事すべきときにしただけ、役割をこなしただけです。
これらを前提として、何が問題か考えてみましょう。
メディアは学校に実害を生む
問題はなんといっても実害があることです。
メディアでの争論に学校現場が巻き込まれると、そこで学ぶ子どもにとって悪影響があります。校門を出るとカメラをもった記者が何人もいて、マイクを向けられてインタビューをお願いされる。生徒の動揺を呼び起こします。
学校には次々電話がかかってきて教職員はその対応でかかりっきりになったり、保護者の不満や不安を抑えるために臨時保護者会を開いて事態の説明をしたりします。普通の教育活動がしづらくなる。どうみてもプラスに働くとは思えない。
こうした騒動は、部外者からみれば「話題の種」でしかないのでしょうが、現場にいる人間には実害があるのです。
渦中の校長にも同情します。こうして話題になってしまうと、今後もいろんな場面で校長がリーダーシップを発揮しなければならないのに、周囲が言うことをきかなくなるかもしれない。学校のマネジメントにも悪影響があるのです。
「いや学校が決断を誤ったから話題になったんだろう、記事にして何が悪い」とおっしゃるかもしれません。
でも本当にそうでしょうか。学校の決断がそこまで間違っていたものかどうかは、悪いけれど、部外者には知りようがないことです。メディアが語るごくわずかな情報だけで一方的に判断できるとは思わない。
特に「がんばってきたダンスができなくなって泣いている子どもがいる」みたいな情に訴える書き方はよくないですね。子どもが悲しい思いをして泣くことなんてたくさんあります。減らした方がいいけれどゼロにはできません。それだけを取り上げて一概に学校を悪者扱いにするのは間違っています。
学校現場には、こうした利害関係の調整事項がたくさんあるので、不利益を被る子どもの数をゼロにはできません。泣いてる子がいるんですよってのは、悪くいえば泣き脅しで、それ言ったら勝ちみたいな最強のカードにすべきじゃない。
だからまあ、学校関係者としては、こうした報道はデメリットの方が大きいと思います。実害を受ける側だからそう思っちゃうんですかね。
文科省はどっちを向いているか?
今回語りたかったのはここからです。こうした学校を巻き込む騒動が起こった際、文部科学省(文科省)っていったい何を考えているんでしょうか。どっちを向いているんでしょうか。
文科省って学校を管理する立場です。公立中ですから、自治体にある教育委員会を間に挟む形で、学校のマネジメントは監督されています。問題があるなら文科省が積極的に是正しなくちゃならない。
ところが文科省って、こういう世論が過熱したケースだとメディアに叩かれないことを第一に考えているんです、たぶん。それ、全然大事じゃないのに。
例えば2019年、大学入試改革の際にあった英語の民間資格試験活用を撤回したときとか。名前は出しませんが、文科省(正確には文科省が管理する大学入試センター)がある企業と結託して進める気満々だったのに、実害に遭いそうな高校生たち声を上げて、それをメディアが取り上げたことをきっかけに一気に見送りを決めました。ときの文科相(文部科学大臣)であった萩生田さんの「身の丈発言」もヒートアップさせた一因となりましたね。
結局、このケースで文科省が方針を変えた原因はなんでしょうか。文科省は現場(=学校や高校生)からの声を拾い上げたのではないです。現場の声をメディアが拾って、大衆が関心を持ち、その過熱化する世論によってやめたんです。つまり文科省は、メディアを通じて世論の矛先が自分たちに向くことを最も恐れています。
現場の声を拾って動くわけではなくて、メディアが取り上げた先にある世論を恐れて動いているのがポイントですね。いじめでも不登校でもブラック校則でも良いんですが、世論の矛先が文部科学省に向かいそうになったらすぐに何らかの通知を発出します。
通知を出すのは結構なことですが、問題は、不純な動機で通知を出したって事態は解決しないことです。めちゃんこ穿った見方をすれば、文科省の動機は、事態を解決することではなく、矛先が自分たちに向かないように何かしたふりをすることにあります。
それじゃあ学校現場にとってプラスに働くことはまれです。事態は一向に改善されず、教員が残業して面倒くさい調査をしなきゃいけなくなった(出来の悪いエクセルシートに入力して送る仕事が増えた)といったオチだけが待っています。
調査や報告という病
ちょっと脱線しますが、調査をして報告する。これは学校と文科省の関係性が生んだ病の一つです。ファクトやエビデンスベースで行政的な決断をしよう(つまり税金の使い道を決めよう)とすれば、どうしようもないことかもしれません。でも「本当にそれ必要か? いくらなんでもリソース注ぎすぎやろ」とよく思います。
そもそも、学校も文科省も記録に残すことが大好きで、授業1つにしても学習指導案という計画表を作りそれを元に授業をするという面倒くさい行為を推奨しています。
ラッパーがライブ計画票というものを作って「何分にどういうことをいって観客を煽るか」とか台本に書くとは思えませんが、まさにそんなようなものを作れというのです。まったく不合理だと思います。
塾・予備校業界から学校業界に舞台を移したときに、すぐに感じた違和感がこれでした。
まあいいや。
なんにせよ調査報告しかしないことの問題点は、問題は解決しないものの労力だけが増えるから、仕事が増えるだけで何も変わらず誰も得をしないことです。
再来週あたりに、文部科学省が全国の学校宛に通知を送り、そこに「ダンスのジャンルに制限を設けるような行事を実施しているか」といった調査をする旨が書いてあるとか、そんな未来が想像できてしまいますね。面倒だなあ。
四者の関係性
今回は学校を取り巻くマスメディア、文科省、大衆の関係性を論じてみました。おそらく外側からは見えないだろう、四者の間に働く力学を語りたかったんです。
今回の件では文科省やメディアを悪者にしちゃいましたが、正直いうとそれほど嫌っているわけではなくて、感謝していることも多いです。そもそもメディアを通じて世論が形成されて、結果的に社会が変わっていく、そのこと自体は悪いことじゃないですし。
今回取り上げたケースでいうなら、ヒップホップ禁止令はバカげていますが英語民間資格試験活用の撤回は英断でした。そのきっかけを生んだ高校生たち、それを取り上げたメディアはまさに社会正義をなしたと思います。
今回お伝えしたかったキモは順番です。
まずはメディアが報じる、次に大衆が関心を持つ(世論形成)、そして文科省が調査や通達をする、最後に学校は疲弊する。この順番がよくない。学校を蝕む負の連鎖の一つがこれですね。順番を変えるべきです。もっとシンプルに、文科省が世論よりも学校現場を気にすればいいだけなのかもしれません。
この四者の関係性ですが、チャート化すればもっとわかりやすく提示できそうです。暇があったらやろうかなと思ったけど、やっぱりめんどうくさいんでやめときます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
