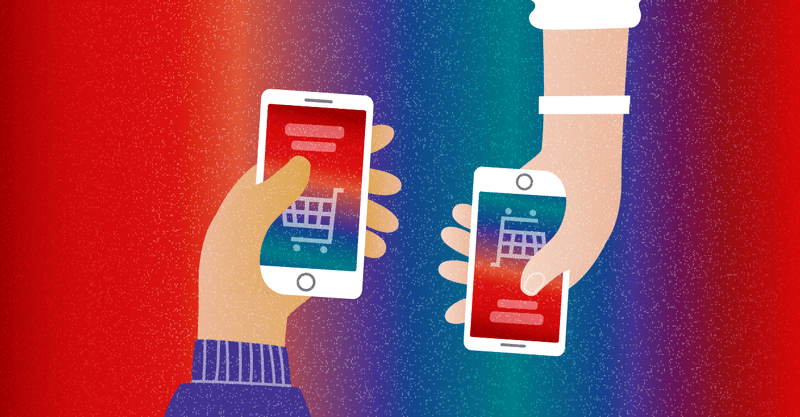
自治体のキャッシュレス化はどう進むか~キャッシュレス決済の基本から現実の課題まで~
数年前、大がかりなポイント還元キャンペーンで話題となったキャッシュレス決済。いまその普及の波が、一足遅れて自治体にも押し寄せつつある。特に、コロナ禍を契機として「デジタルトランスフォーメーション」が一種のブームになるにつれ、にわかに注目度が高まっている。しかし、実際の導入にあたっては、様々なハードル、課題が待ち受けている。
本稿では、そもそもキャッシュレス決済は、消費者・店舗・社会全体にとってどんな意義があり、何をもたらすものなのかを整理し、その上で、その変化に対し、自治体はどう向き合うことになるのかを展望することとしたい。【やや長文注意】
1.はじめに
最近、公共施設や窓口での支払いにキャッシュレス決済を導入する自治体が増えている。自治体のキャッシュレス化については、クレジットカードなどの商取引を所管する経済産業省が、「公共施設・自治体窓口におけるキャッシュレス決済導入手順書」を策定・公表するなど、ここ数年、熱心に取り組んでいる(*1)。また、政府全体の方針としても、閣議決定で「公的分野の効率性向上の観点から電子決済の利用拡大」が掲げられるなど、推進の方向性が明確に示されている(*2)。こうしたなか、近年、徐々に自治体でのキャッシュレス決済への認知も広がりつつあったが、コロナ禍を受けた非接触化へのニーズとデジタルトランスフォーメーションの機運の中で、さらにその流れが加速しようとしている。
ただし、自治体での実際の導入にあたっては、いくつかの日本固有の課題に直面することになる。その結果、キャッシュレス化に対応できる自治体・できない自治体の差が出てくるだろう。また、利用できる決済の手段やサービスも地域によってまちまちの状態が続く。この状況は、事業者間でのサービス向上への競争を促す側面がある一方で、利用者や自治体にとってはわかりづらさ、ときに不便さをもたらす。
本稿では、キャッシュレス決済の光と影を、なるべく公平かつ具体的な形で拾いながら、今後、自治体がキャッシュレス化を進める上で、具体的に何が論点となるのか、どんな姿が予見され、どんな課題に取り組むことになるのかを展望してみたい。
2.日本は現金大国か
日本はしばしば「現金大国」と揶揄される。他の先進国と比べると、タンス預金をはじめとした現金預金の割合が5割を超えており、他国に比べて顕著に高い一方で(*3)、キャッシュレス決済の比率はドイツに次いで顕著に低い(*4)(図1)。最近でこそ、キャッシュレス決済に対応する店も増えてきたが、小規模商店や自動券売機/精算機などは現金払いしか受け付けていないことが多い。クレジットカード対応をしている商店でも、端末が埃をかぶっていたりする。顧客もキャッシュレス決済対応店であるにもかかわらず現金で支払うことが多い。これは日本では現金が非常に使いやすい、すなわちATMが多く、紙幣が非常に清潔で、通貨単位のバランスが良い(100円、500円、1,000円、5,000円、10000円)ことが一因とされるが、国民のデジタルリテラシーも影響している。特に最近のQRコード型決済などは、スマートフォンをある程度使えなければ、ほとんど対応できないからである。どうしても高齢者などにとってハードルは高くなる。
図1 世界主要国におけるキャッシュレス決済状況(2017年)

(出典:キャッシュレス・ロードマップ 2020)
それでも、徐々にキャッシュレス決済は社会に浸透しつつある。博報堂が毎年行っている調査では、これまで「現金」派が過半数を占めていたが、直近の調査では「キャッシュレス社会」賛成派がはじめて過半数を上回った。コロナ禍の影響が大きいと思われるが、ようやく日本人のマインドも変わりつつある。
なお、日本がキャッシュレス化で取り残されている、という見方には様々な疑義があることも指摘しておく。欧州でもキャッシュレス化が進んでいるのは主に北欧諸国であり、ドイツやフランス、南欧諸国ではまだまだ現金が健在である。韓国も人口当たりATMの台数は日本より多いとされる。また、日本で普及している公共料金等の口座振替をキャッシュレス決済とカウントすると、国際的にそれほどそん色はないとの見方もある。日本=遅れているという見方に囚われすぎると本質を見誤る。分野に応じて、現実的なメリット・デメリット、制約条件、具体的な選択肢などを検討していくことが重要である。
3.なぜキャッシュレス決済化なのか
キャッシュレス決済については、書籍やウェブサイトなどで数多くのメリットが挙げられている。実際、消費者にはかなりのメリットがあることは疑いない。他方で、店側のメリットはかなり“盛られている”ことが多い。例えば、キャッシュレス化によって、現金の管理から解放されるかのように書かれるが、現金の取り扱い量が半分になっただけでは、現金処理に関する部分に限ってみても、業務量はとうてい半分にはならない。現金の取扱いがゼロになれば大きく変わってくるのだが、いきなり「現金お断り」に踏み切れるような店は、現状ではほとんどない。現実的な範囲で、利用者側・店側双方のメリット・デメリットを整理してみよう。
【利用者:メリット】
利用者は、キャッシュレス化が進むことで、次のようなメリットが得られる。
・支払いがスムーズになる:支払いの際に財布を探したり、現金を数えたり、皿から拾ったり、といった時間が節約される。最近、駅のコンビニでも普及が進む無人レジを使うと、明らかに決済が速い。時間を惜しむ利用者にとってのメリットは大きい。
・財布をもたずに済む:キャッシュレス化に対応する店舗が増えてきたことで、財布を持たずに、より手軽に出かけられる機会が増えてきた。財布の盗難や紛失によって現金を失うリスクも減る。仮にスマホを落としたとしても、拾ったスマホでモノを買ったり、お金を引き出したりすることは普通はできない。
・感染リスクを減らせる:素手で触れた現金をやりとりしなくて済むようになる。コロナ禍を通じてはじめて認識されるようになった大きなメリットである。
・ポイントが貯まる:キャッシュレス決済を始めた人の多くは、これが大きな後押しになったと思われる。企業によるポイント戦略がなければ、これほど速やかにキャッシュレス化は進展しなかったに違いない。マイナポイント事業もまさにこうした消費者心理を狙って実施された。逆に、仮に現金で支払えば3%引き、という店舗があったとしたら、多くの人は現金を選ぶのではないか。(筆者はおそらくそうする。)
・購買以外のお金のやりとりもスムーズになる:後述する電子マネー型のキャッシュレスサービスでは、送金や割り勘での支払いなどの機能がついているものもある。現金手渡しや銀行送金に比べると利便性は大きく、キャッシュレスならではの新たな付加価値といえる。なお、中国ではご祝儀やお年玉などでのキャッシュレス決済も普及している。
・その他:上記のほか、Paypalなどで提供されている、支払い手段を統合して家計管理に活用する、といったデジタルならではの付加価値を持つサービスも、今後増えていくだろう。
【利用者:デメリット】
現状、利用者はキャッシュレス決済も現金決済も選択的に使えるので、キャッシュレス化によって現実的なデメリットを受けることはない。懸念点として指摘されているのは、キャッシュレス化をすると使いすぎてしまう、セキュリティに不安がある、といったことである(*5)。実際、クレジットカードの普及を政府主導で強力に推進した韓国では、カードの使い過ぎによる自己破産が急増し、社会問題化した。しかし、これは後払い型(=クレジットカード)特有の課題である。他方で、QRコード決済での不正利用も指摘されており、かつての7payは、それが端緒となってサービス廃止にまで追い込まれた。ただし、この点も、事業者側の不正対策と利用者のリテラシー向上が進むにつれて徐々に改善してくだろう。注意すべきは、こうしたリスクは決してゼロにはならないということだ。現金決済であっても不正は行われる。そうした意味で、本当のデメリットとはいえないかもしれない。
本当の意味でのデメリットが顕在化するのは、「現金お断り」の店が増えてきて買い物に困るようになってからだ。そうなると、スマートフォンを使えない≒キャッシュレス決済に対応できない高齢者などは、買い物が困難になる。ただし、日本社会がその段階に至るにはいましばらく時間がかかるだろう。
【店舗:メリット】
前述のとおり、店側にとってキャッシュレス化は、現金受取りを禁止しない限り、劇的な業務改善をもたらすものではない。たしかに現金でのやりとりが減れば、計算ミスも起きにくくなり、締め作業もある程度は楽になる。屋台などでは、支払いのたびにいちいち作業を止めて手を拭く必要もなくなる。店の回転も少し速くなるかもしれない。しかし、店員の作業の部分部分が楽になったとしても、一人何役もこなす小規模店舗では、人を削るわけにもいかず、結局、業務負荷の軽減はコストの低減にまでは繋がりにくい。キャッシュレス決済の機器やサービスを取り扱う手間や負担の増加を考えると、業務負荷軽減のメリットも霞んでしまう。ある程度の売り上げがあれば、利用傾向から売上データをマーケティングに利用できるかもしれないが、キャッシュレス決済が売上の一部にすぎず、しかも複数のキャッシュレス決済サービスを取り扱う店舗では、断片的な情報しか得られない。他方で、対応するサービスの種類を絞れば、顧客を取り逃す確率が高まるというジレンマがある。前節でコロナ禍の感染リスクを下げられるという点も挙げたが、これとて店側に直接的なメリットもたらすものではない。
結局、店舗がキャッシュレス決済を導入する決定的な動機は、お客様を逃したくない、ということに尽きる。しかし、これも同じ商圏内での顧客の奪い合いにとどまってしまえば、結局、商圏全体としての売上は増えないまま、手数料だけを外部に吸い上げられる形になる。店舗側にとってキャッシュレス化は迷惑な変化と受け取られても仕方がない。よほど賢く、戦略的にキャッシュレス化を進めない限り、店側には、次に挙げるデメリットに見合うだけのメリットは得られないだろう。
【店舗:デメリット】
店側にとってキャッシュレス決済の負担は軽くない。よく小売業の営業利益率が2.1%なのに、クレジットカードで2~3%もの手数料を取られては利益が残らないといったことが指摘される。実際には、2.1%というのはあくまで小売業全体の平均であって、規模別にみると中小企業は3.5%なので(*6)、商店には1%程度は利益が残る計算になる。大企業の利益率は1.0%程度だが、キャッシュレス決済の手数料も低くなるので、こちらも利益は残るのだろう。とはいえ、毎回営業利益率に匹敵する手数料を差し引かれることが痛手でないはずがない。しかも、これに機器導入・メンテのためのコストもかかってくる。QRコード型では多くの場合、初期投資も手数料もクレジットカードよりも低くなるが、程度の問題ではある。「メルペイにおける累積の決済金額が少なく、出金手数料が無料になる10万円に売上が達していないため、出金した時点で売上の多くが手数料(200円)と相殺されてしまい利益にならない」といった声もある(*7)。
以上を踏まえると、多くの場合、店舗でのキャッシュレス決済の導入は、生き残るためにやむを得ず取り組んでいる、というのが実情に近いだろう。
【マクロ経済:メリット・デメリット】
現金は、匿名性、即時性、セキュリティを兼ね備えた、優れた価値交換手段であり、人類最古にして最大の発明のひとつである。とりわけ日本では現金が使いやすいと冒頭述べたが、その代償もまた大きい。現金を使いやすい形で流通させ続けるには、膨大なコストがかかる。輸送や警備、保管など現金決済に関する社会コストは年間1兆円にのぼるとされる(*8)。キャッシュレス化は、このコストを削減するのに直接、寄与する。
これに対し、途上国では通貨の維持に十分に手がまわらず、現金は劣化しがちである。筆者は15年ほど前に中国の雲南省を旅したが、そこでやり取りされる現金は汚れてぐしゃぐしゃに丸められており、なぜかしっとりと湿っている。触ることも厭われるほどだった。しかし、そうした現金の劣悪な状態が逆にキャッシュレス化を加速させる要素となっている。不利な状況を梃子とした、リープフロッグ現象の一種といえるだろう。
さて、キャッシュレス化は社会全体のデジタル化にも寄与する。逆に、デジタル化はキャッシュレス化の十分条件でもある。決済手段がデジタル化されれば、オンラインでの取引も行いやすくなる。デジタルとキャッシュレスの間での価値交換のスタイルは、新たなビジネスモデルの創出をももたらす(図2)。
図2:デジタル化とキャッシュレス化の相乗効果

別の側面のメリットとして、キャッシュレス化は資金の流れの透明化を通じた経済社会の健全化にも資するという点もよく指摘される。キャッシュレス化が進めば、取引はすべてデジタルで記録されるので、脱税や非合法のアングラマネーの流通などがしにくくなるからである。(もちろん政府による統制の強化を内心迷惑に感じる人は少なくないだろう。)
また、前述のとおり、非接触化によるコロナ禍に対する公衆衛生の向上も大きくクローズアップされてきている。この一点をとっても社会的には、キャッシュレス化を推進する十分な意義があるのかもしれない。
他方で、マクロ経済面で、キャッシュレス化に伴うデメリットは見当たらない。前述の韓国の例のように、クレジットカードの使い過ぎによる自己破産の急増などが起きればマイナスの影響は小さくないだろうが、現下の日本の状況ではまず起きないだろう。
【自治体:メリット・デメリット】
では、自治体にとってのキャッシュレス化のメリットはどうか。この点は評価の観点によって異なってくる。
・利用者サービスの向上:利用者に決済方法の新たな選択肢を提供できる。行政には売上拡大への志向が存在しないため、取組みの実施理由は、究極的には、こうした利用者に提供する無形の価値に依拠することになる。
・事務効率:残念ながら、キャッシュレス化によって常に事務の効率化を図れるとは限らない。現金を取り扱う頻度が減り、その分の業務負担や職員のストレスは軽減されるが、キャッシュレス決済の対応のための業務も追加される。また、結局のところ、公平性やデジタル格差への配慮の観点から現金をゼロにすることはできないので、二重管理が続くことになる。結局、店舗の場合と同様に、対応しているキャッシュレス決済手段による支払いが一定以上の回数・頻度に達してはじめてメリットが出てく。
・地域振興:自治体による地域のキャッシュレス化の取組みは、まずこの点が動機になっている。ただし、キャッシュレス化そのものは目に見える付加価値を生み出すわけではない。結局、自治体が期待するのは、キャッシュレス決済とセットで付与するポイントによる経済効果である場合がほとんどである。たしかに現金やクーポン券を配るよりもスマートであるが、地域ポイントが本当に経済波及効果をもたらすのかについては、懐疑的な見方も根強い。
■日本の状況のまとめ
以上を総括すれば、日本社会全体が置かれた状況は、次のようなものだろう。まず、キャッシュレス化は不可避の流れであり、これによって、政府と消費者は様々な便益を享受する。これに対し、店舗にとっては、全体として負担が増える。それに見合うほどのメリットは得られない場合が多いが、生き残るためには、対応せざるを得ない。日本全体として経済成長しているわけではないので、結局のところパイの奪い合いとなり、売上の大きな伸びは期待できない。メリットが出てくるとすれば、社会全体としてのキャッシュレス化が大きく進展し、現金の取扱いが相当程度小さくなるとともに、決済手段がある程度、淘汰や統廃合によって絞り込まれたときだ。そこまでくれば、業務効率化の効果が顕在化してくる。店舗としては、あと数年~十数年、我慢のときが続くだろう。自治体については、店舗ほど差し迫ってはいないが、キャッシュレス化対応へのプレッシャーが高まっている。デジタル化に意欲のある自治体、体力のある自治体、住民のキャッシュレス化が進んでいる自治体から徐々に対応が進んでいく。
4.乱立するキャッシュレスサービス
現在、自治体で進められているキャッシュレス決済の手段やサービスの種類・組合せは、クレジットカードのみ対応の場合、QRコード型サービスのみの場合、専用POS端末を設置している場合、マルチ端末のみを設置している場合など様々である。最近では、LINE PAYに絞って対応する例も増えている。自治体の業務はどこも大きく変わらないのに、サービスがこれだけバラバラになっていることには、様々な理由がある。順に紐解きながら、今後、自治体が窓口や公共施設での支払いに導入する際に検討すべき論点を整理してみたい。
4-1. キャッシュレス決済手段の種類
まず、キャッシュレス決済にどのような種類があるのか、なるべくわかりやすく全体像を示してみたい。キャッシュレス決済手段には大きく、
・後払いのクレジットカード
・即時払いのデビットカード
・前払いの電子マネー
の3種類がある。キャッシュレス決済のビジネスモデルの類型としては、基本的にはこの3つだけである。いちおう概要を説明しておくと、クレジットカードでは、利用者はカード会社の信用で買い物をし、後日、カード会社から利用者に請求が行く。デビットカードは買い物を行うと即時に銀行口座から支払代金が引き落とされる。電子マネーでは、予めある程度まとまったお金を入金しておき、その範囲内で買い物をしていく。電子マネーは読取方式によってさらに、
・SuicaやPASMOなどの非接触IC型(カードの場合とスマホの場合がある)
・PayPayやLINE PayなどのQRコード型
に分かれる(図3)。後者は、初期投資の少なさと、事業者による大規模なポイント還元キャンペーンによって、ここ数年、急速に認知を拡げてきた。現在のキャッシュレス決済のムーブメントを作ったのはこのQRコード型であり、単にキャッシュレス決済といった場合、まずこのタイプを想起する方も多いだろう。
図3:決済手段と読取方式のバリエーション

4-2. キャッシュレスサービスの多様性
日本には、こうしたキャッシュレス決済手段の類型ごとに数多くの事業者がひしめいている。日本の大きな特徴は、こうしたサービス、事業者の乱立である。多くの国では、キャッシュレス決済のパターンはある程度、決まっている。
・米国・韓国・シンガポール…クレジットカードが強い
・欧州…キャッシュレス決済といえばデビットカード
・中国・東南アジア…電子マネー
といった具合だ。これに対し、日本では、クレジットカードも、交通系を中心とした電子マネーも、現金もそれなりに強い。
また、それぞれの決済手段の中に多数のサービスが乱立している。例えば中国では、電子マネーはいまやAlipayかWeChat Payにほぼ収れんされている。これに対し日本では、これら中国系のサービスも含め、PayPay、楽天ペイ、d払い、LINE PAY、メルペイなど、多岐にわたっている。ただし、これは過渡期の状況かもしれない。中国も現在の2強に落ち着いたのは、多数の事業者の乱立状態からの淘汰によるものだ。日本でも先駆者だったORIGAMI PAYが既に舞台から去っている。今後、収れんが進んでいく可能性がある。
ほかにも特殊性がある。例えば、日本のクレジットカード利用者の多くは、翌月の引き落としで清算するのが当然と思っており、金利を払うことなど考えていない。1か月前後の時間差があるだけで、使う感覚としては、デビットカードとほとんど変わらない。利用者は、支払いの利便性とポイントを期待してクレジットカードを使う。これに対し、米国では、基本的にリボ払いであり、信用枠まで使おうとする。
4-3. サービスの乱立がもたらすもの
さて、こうした事業者の乱立は、誰にとっても不幸である。利用者にとっては複数のアカウントを作ってアプリをインストールし、利用方法を覚え、支払いを管理しなければならない。店舗にとっても、それ以上に重く、管理や習得の負担がのしかかる。そして、サービスが乱立している状況そのものが、キャッシュレス決済を取っつきにくいものとし、キャッシュレス化の足を引っ張ることになっている。人は選択肢が多すぎると、思考停止に陥るからだ(ジャムの法則)。多くの事業者が参入してビジネスが動き、業界が活性化しているように見えるが、こうしたマイナスの影響は無視できない。
政府はこうした状況に対し、QRコードの業界統一規格JPQRを開発し、導入を推進している。これは、利用者にとっては一定の利便性があるものの、店舗にとっては本質的な解決策にはならない。たしかに店頭に事業者ごとにQRコードが乱立する状況は改善される。しかし、結局、申し込みも出入金の管理も事業者別に行うことに変わりはなく、業務はあまり改善されないからだ。
こうした状況の影響を受けるのは自治体も同様である。これだけ手段が多様化してしまうと、どう整理を進めたらよいのか判断がつきにくくなる。なんとか判断しようとすれば、検討自体に大きな負荷がかかってくる。
5.自治体にとってのキャッシュレスの最適解
自治体がキャッシュレス決済を導入する場合、通常の店舗とは異なり、業務の効率化や住民サービスの向上だけでなく、地域全体のキャッシュレス化への寄与も期待される。自治体がどのサービスを選択するかは、地域の店舗や事業者のふるまいにも影響を及ぼす。地域の商店街がQRコード決済で足並みをそろえている中、役所だけがクレジットカード限定のキャッシュレス決済サービスを採用することは憚られるだろうし、役所の選択は、それ自体がひとつのメッセージとなる。では、どうやってキャッシュレスの決済手段やサービスを選んでゆけば良いのか。いくつか論点がある。
5-1. 決済手段の多様性に関する立場の違い
まずはシンプルに、キャッシュレス決済の手段は多い方がよいのか、少ない方が良いのかを考えてみたい。前章では、キャッシュレス決済の種類が多すぎることがキャッシュレス化を妨げていると述べた。しかし、現場の担当者目線でみると判断もまた変わってくる。現場には、どのような賛成ないし反対の立場があるのかを整理してみよう。
①決済の種類を少なくしてほしいとする立場
まず、店舗側はなるべく決済の種類は絞り込んでほしいと考える。売上がサービス毎に分散すれば、出入金管理も、データ分析も困難になりキャッシュレス化のメリットがしぼんでいく。手数料などのコスト負担にも見合わなくなってくる。自治体内では、入金処理の担当者がこうした立場に立つ。
②決済の種類を多くしてほしいとする立場
これに対し、利用者は様々な方法を用意しておいてほしいと考える。自治体での支払いのためだけに自分のスマホにサービス追加などしたくないからだ。自治体内で住民サービスの向上に取り組む担当者もこうした立場に立つ。せっかくキャッシュレス決済を導入するのだから、少しでも多くの住民に利用してほしい、そのためには、より多くの決済手段に対応することが必要、と考える。
以上の関係性を図式化したのが図4である。
図4:キャッシュレス化の利害関係者と立場の違い

5-2. キャッシュレス決済のベストミックス
ただし、ここで考えなければならないのは、決済の種類の多様化はあくまで手段でしかないということだ。「決済手段・サービスの多様化=住民サービスの向上」と考えるのは、手段と目的をはき違えている。対応できる決済手段・サービスの種類が少なかったとしても、結果としてキャッシュレス化が進み、利便性が向上するならば問題ないはずだ。
そうであるならば、最小限の決済の種類で、最大限のキャッシュレス化を図れるのがベストミックスということになる。そして、そうした状態に近づくために、キャッシュレス化を巡る地域の状況、役所での利用者の状況を踏まえ、もっともふさわしい決済手段を検討することが必要になる。その際、それぞれの決済手段の次のような特性も考慮の対象になるだろう。
・低価格の店舗では、初期導入費用や手数料が安いQRコード型が、高級店ではクレジットカードが受け入れやすい
・公共交通機関が発達している地域では交通系電子マネーが受け入れやすい
・大都市圏ではクレジットカード契約率が高い
・インバウンド需要として、中国人を重視するのであればAlipayとWeChat Payに対応したQRコード型、欧米人を重視するのであればVisa pay WaveやMastercard ContactlessといったNFC非接触型が望まれる
なお、欧米人の多くはQRコード決済の経験はない。また、彼らが使うNFC非接触型は世界標準タイプA/Bという規格であり、日本のFeliCa端末では対応できない。
こうした点を考慮しながら店舗側の事情と自治体窓口のニーズの異同を把握し、折り合いをつけていくことになる。実際の導入にあたっては、地域でのキャッシュレス決済の状況をリサーチしておくことも重要である。
5-3. 庁舎内での端末配置のベストミックス
自治体内で、どの部署に、どのタイプの端末を、何台導入していくかも論点となる。例えば、
・特定の支払に多くの利用者が集中する窓口…専用のPOS端末
・様々な支払手段のニーズに対応する窓口…複数の決済手段に対応できるマルチ端末
といった使い分けをしていくことになる。専用POS端末は価格も高額になるが、処理スピードは速い。マルチ端末は、様々な支払い手段に対応できるが、処理速度が遅い。他方で、遅い処理速度でも足りる程度のニーズしかない窓口では、そもそも導入する意味を問われかねないので、導入の判断は難しいところである。今のところ必ずキャッシュレス決済に対応しなければならないわけでもないし、あらゆる決済手段に対応することも現実的ではないからだ。
このあたりの最適解を見極めることは難しく、実際に導入してみないと分からないところもある。まずは試験的に一部の窓口で導入し、利用状況や利用者の反応、業務処理の状況などをみながら、徐々に導入対象を広げていくのが王道だろう。国もキャッシュレス決済導入にあたっては、まずはスモールスタートを検討するよう勧めている(*9)。これから取組みを開始する自治体にあっては、まずはいかにして最初の一歩を踏み出すかに注力することが必要となろう。
6.キャッシュレス化推進に当たっての留意点
このように、キャッシュレス決済の導入にあたって検討すべきことは多い。他方で、既に導入の立ち上げを終えた自治体にあっては、次にどこを目指すべきかが問われることになる。これはつまるところ、中長期的に地域のキャッシュレス化をどこまで高めるか、という論点に帰結する。この点は、キャッシュレス決済が進んだ国では、ひとしく直面している課題である。
諸外国の中には、北欧諸国のように高度にキャッシュレス化が進んだ結果、現金自体を目にすることが少なくなった国もある。スウェーデンでは、3分の2の銀行では現金を扱っていないし、現金お断りの店舗もみられる。その一方で、日本に限らず高齢者はスマートフォンの操作が苦手な傾向があるので、こうした方々を取り残さない配慮が課題となりつつある。米国の一部の州や中国などでは、店舗による現金の拒否を禁止するルールが施行されたりしている。キャッシュレス化をどこまで進めるべきかは難しい命題であるし、おそらく技術動向や経済環境など時代の変化とともに、最適解は変わっていく。自治体としては、そうした変化を見据えながら、一定間隔、例えば、3年ごとに方針の妥当性を検証することが望ましいだろう。
これとは別に、キャッシュレス化に伴い副次的に発生する論点として、前述した次のような点についても検討が必要となってくる。
・災害時に停電でキャッシュレス決済ができなくなった場合への備え
・クレジットカードの使い過ぎによる自己破産の抑止
・キャッシュレス決済のデータを活用する際の個人情報保護
・不正利用やスキミング等への対策
こうして数多くの論点や懸念点に対し、優先順位をつけながら整理していくことになるが、最終的に優先すべきは目の前の利用者である。行政にできることは高が知れている。仮想の政策的波及効果に頭を悩ますよりは目の前の来庁者に何ができるかを優先すべきだろう。あくまで利用者中心でサービスをデザインしていくことが重要である。
このとき注意すべきは、利用者にとって、決済はサービスの中のいち構成要素でしかないということだ。決済に捉われすぎて、そこだけを変えようとすると本質を見誤る。中国はキャッシュレス化が高度に進んだ社会となっているが、必ずしもキャッシュレス化そのものを目指したわけではない。中国のAlibabaやテンセントが提供しているのは、キャッシュレスサービスではなくて、UX(ユーザーエクスペリエンス)に根差したデジタルサービスなのである。そのなかでキャッシュレスは一構成要素であり、かつ、全体にとって不可欠の要素となっている。さらにいえば、こうしたプロセスの中で行われている決済は、もはやQRコードではなく、アプリ内決済またはオンライン決済である。uberを使った経験がある方は、サービスと支払いがすべてアプリを通じてオンラインで完結する体験をしていると思うが、まさにあのような取引である。ここに至るともはや現金の授受かどうか、といったことは問題の本質ではなくなっているのである(図5)。
図5:デジタル化とキャッシュレス化の融合

どのような決済手段を用意するかは、ビジネスにおいて最重要の要素のひとつである。しかし、顧客は決済手段によって商品やサービスを選ぶわけではない。サービスのデジタル化を進める際に重要となるのは、あくまで利用者の目線に立って全体最適を目指しつつ、デジタル体験をデザインしていくことなのである。
■出典
*1 経済産業省,「キャッシュレス」ページ
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/cashless/index.html
*2 閣議決定,未来投資戦略2017
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017.pdf
*3 資金循環の日米欧比較,日本銀行,2020
https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf
*4 キャッシュレス・ロードマップ 2020,一般社団法人キャッシュレス推進協議会,2020
https://www.paymentsjapan.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/roadmap2020.pdf
*5 博報堂生活総合研究所、 「お金に関する生活者意識調査」結果を発表
https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/78034/
*6 経済産業省,商工業実態基本調査
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syokozi/result-2/h2c6klaj.html#menu0
*7 JPQRは日本のQRコード決済のカオスを解決するか
https://www.watch.impress.co.jp/docs/series/suzukij/1250506.html
*8 平成29年度産業経済研究委託事業(我が国におけるFinTech普及に向けた環境整備に関する調査検討)調査報告書
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000187.pdf
*9 経済産業省,公共施設・自治体窓口におけるキャッシュレス決済導入手順書(第2版)
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210331008/20210331008.html
■参考文献
・キャッシュレス国家,西村友作,文春新書,2019
・キャッシュレス経済,川野祐司,文眞堂,2018
・キャッシュレスで得する!お金の新常識,岩田明男,青春出版社,2018
・キャッシュレス進化論,安留義孝,金融財政金融財政事情研究会,2019
・キャッシュレス・イノベーション,財務省財務総合政策研究所[編],金融財政事情研究会,2019
・キャッシュレス・マーケティング,長谷部智也,二本経済新聞出版、2020
・スマホ決済の選び方と導入がズバリわかる本,小宮紳一,秀和システム,2019
・中小・小規模事業者のためのキャッシュレス決済導入ガイド,監修:TKC全国会システム委員会,TKC出版,2019
・60分でわかる!キャッシュレス決済最前線,キャッシュレス研究会,技術評論社,2019
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
