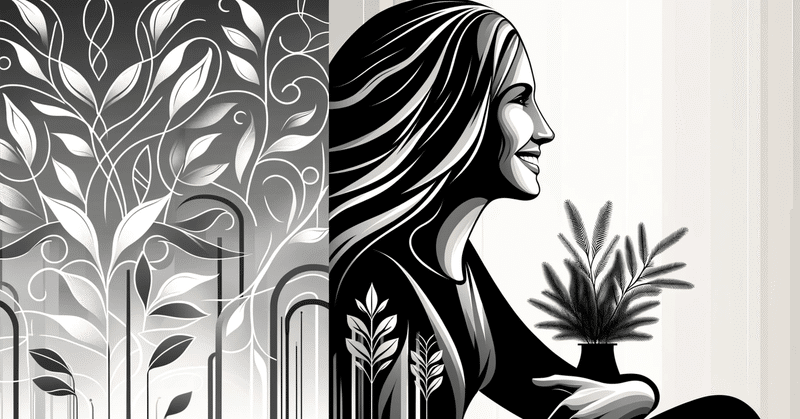
【め #8】期待される後付けでの『しゃべる家電』
水野 千津子さん
水野さんは、第6話及び第7話でご紹介した阿部さんと同様に、遺伝子のキズが原因で光を感じる組織である網膜が少しずつ障害を受ける病気である『網膜色素変性症』を患い、小さい頃から視野が狭くなって見えない部分が出てくる『視野狭窄(しやきょうさく)』もあった。
しかし、阿部さんが暗いところでものが見えにくくなる『夜盲(やもう)』に対して、水野さんは全く逆なのだ。普通の人が眩しいと感じない光を眩しいと感じる『羞明(しゅうめい)』。「自転車に乗れたり何でもできたが、外に出ると眩しくて大変で、いつもサングラスをかけていた」。
水野さんは、”目が見えていた”ので一般校に通った。しかし、”いつか目が見えなくなる”こともわかっていたので、23歳で改めて盲学校に入学して点字や歩行訓練などを学び、『あはき師』の資格も取得した。ちなみに、あん摩の“あ”、鍼師の“は”、灸師の“き”で『あはき師』と呼ばれる。
でも、その頃には「光や白と黒の反対色なら見えたが、ピンクや黄色などの色の区分けはもうできなくなっていた」。いわゆる『色弱』が進んでいた。
その当時にご結婚されたご主人や、その後に生まれたお子さんの顔を当然記憶しているが、今では「光さえ失われた」結果、目鼻立ちなどはっきりわからなくなってしまった。
現在の水野さんの視界では、光が「豆電球みたいになったり、ピカピカしたり、花火みたいになったり」している。そんな光の残像が、昼夜を問わず、例え目をつぶっていても消えずに、「ずっと視界が暗くなることはない」そうだ。
小さい頃から今に至るまでを振り返ってくれた。「本当に少しずつ、“蛇の生殺し”みたいでした。それはそれで大変なんだけど、見えなくなるなら早くなってほしかった。徐々に見えなくなるのも精神的に辛く、怖かった」。
その後全盲になられた水野さんはいま、高齢で豪雪地帯に一人暮らしをされている。
「なるべく周囲と話し合いながら、自分から環境を変えていかないと」と話された。例えば、日々の生活ゴミを出しに行くのに、雪の上で白杖をついて歩くのは大変だ。誰もが積極的には受け入れないであろう区域のゴミ出し場所を自身も出しやすい自宅の前にすることを提案し、一方で、自宅の前の雪を流雪溝に流す区域の決まりは周囲に手伝ってもらう。「ありがたく生活させてもらっています」と感謝を述べられた。
他方で、こうした共助のボランティア精神が、福祉に「サービス」や「ヘルパー」という言葉が生まれて、そこに「お金」が発生し「作業」に線引きができたことで、少なくなってきたように感じるとも寂しそうに話してくれた。
自分では変えられない環境についても教えてくれた。家電製品だ。例えば、最近では「冷房、○○度です」などと『しゃべる家電』も広がっているが、すぐに買い替えることもできない。自宅のエアコンにせよ炊飯器にせよ「どれもピッかピピッという音だけなので、後付けでしゃべってくれる機能とかないものか」と切望されている。
カメラで読み上げる機能も使ってみたことはあるが、かざす場所がわからなかったり、音訓などをちゃんと読み上げてくれず、周囲でもあまり良い話を聞かないので、使わなくなってしまったそう。
障害のある方はご自身のできる範囲で環境を変えて生活しておられる。でも、できない範囲の環境については、もう一段テクノロジーで支えてあげたいものだ。
⭐ コミュニティメンバー大募集 ⭐
Inclusive Hubでは高齢・障害分野の課題を正しく捉え、その課題解決に取り組むための当事者及び研究者や開発者などの支援者、取り組みにご共感いただいた応援者からなるコミュニティを運営しており、ご参加いただける方を募集しています。
Inclusive Hub とは
▷ 公式ライン
▷ X (Twitter)
▷ Inclusive Hub
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
