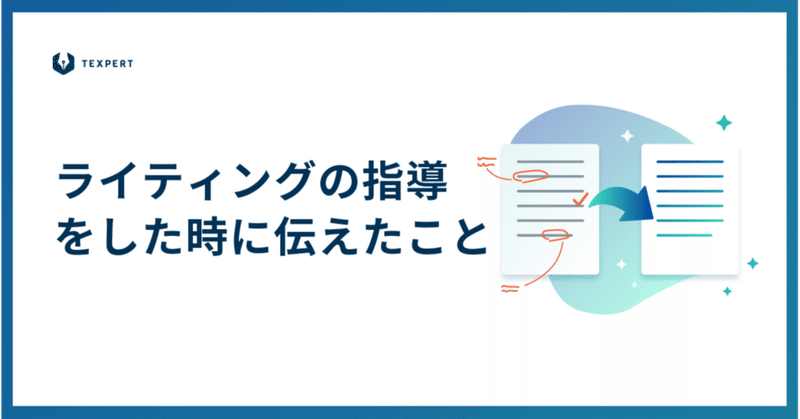
ライティングの指導をした時に伝えたこと
こんにちは!テキスパート編集部の今野です。
テキスパートは文章制作プロダクションとして、コラム記事や取材記事、ホワイトペーパーといった文章コンテンツの”制作”をお任せいただくことが多いのですが、時折「ライティング力向上のための指導」をご依頼いただくことがあります。
要は「自社に記事の制作チームはあるけれど、イマイチクオリティが上がららないから、テキスパートさんにライティングについて指導をしてほしい」
というものです。
ご依頼してくださった企業様には、テキスパートが持つ文章制作の極意を余すことなくお伝えしました。
その結果、ほとんど修正の工数をかけることなく、自社で良質なコンテンツを作れるようになりました。
今回は、これまで指導させていただいた企業様に対し特に重点的にお伝えした内容を4つ厳選してお伝えします。
指導ポイント①:表現はとにかくシンプルに
まずは意識して句点を打つようにお伝えしました。
夢中になって文を書いていると、つい句点を打つのを忘れ一文が長くなってしまう傾向にあるからです。
結果、一文内に主語や目的語が何個も出てきて、結局何が言いたいのか分からない難解な文ができあがってしまいます。
文を書く際は「一文一義」を意識して、最初は意図的に文を細かく区切りましょう。
ただし、あまりに細かく句点を打ちすぎると今度は箇条書きのようになってしまいます。
コツとしては、まずは意識して細かく句点を打ち、一文一文を短くした上で、繋げられる文同士は繋げる。
イメージとしては「息継ぎなしで読んでも苦しくならない程度に一文の長さは留める」です。
■一文が長すぎる例
テーマ:お盆休みの過ごし方
今年のお盆休みは実家がある神奈川県の茅ヶ崎市に帰省し、家族と過ごすことにしたので、お盆休みの混雑を予想し早朝の電車に乗り、駅からは迎えに来てくれた両親の車で家に向かいました。
■一文が短すぎる例
今年はお盆休みは帰省することにしました。家族と過ごすためです。実家は神奈川県の茅ヶ崎市にあります。お盆休みは電車が混んでいると予想しました。よって、早朝の電車に乗りました。駅からは迎えに来てくれた両親の車で家に向かいました。
■一文の長さが適切な例
今年のお盆休みは家族と過ごすため、神奈川県茅ヶ崎市にある実家に帰省することにしました。お盆休み中は電車が混んでいると予測し、早朝の電車でに乗ることにしました。駅からは迎えに来てくれた両親の車で家に向かいました。
指導ポイント②:読者に察することを求めない
自分が詳しいテーマについて書く時、書き手はつい
「これくらいなら説明せずとも読者は理解できるだろう」
と思ってしまう傾向があります。
例えば、
■テーマ:駆け出しWEBライターが月5万を安定的に稼ぐ方法
WEBライターとして安定的に月5万円を稼げるようになるには、SEOは避けては通れません。記事のEATを担保することにより、読者の検索ニーズを満たす有益な記事となるでしょう。最近では従来のEATに加え、新たなE(Experience=経験)という概念が誕生しました。つまり、今後WEBライターとして活躍していくには、自分が書く記事のテーマに関するある程度の経験を持っておいた方が良いわけです。自分が持っている人にはない経験や知識を洗い出し、活躍できる分野を見つけていきましょう。
という文章。
従来のEATという概念に新たなE(Experience=経験)ができたと書いていますが、そもそも「EATとなにか?」という説明が一切ありません。
記事のテーマは「月5万円を安定的に稼ぐ方法」であり、すなわち駆け出しのWEBライターをターゲットにしているにも関わらずです。
これは、書き手がWEBライティングに詳しすぎるあまり、「EATくらい説明しないでも分かるだろう」という考えが無意識のうちにライティングに反映されてしまっているのです。
この記事を読むだけでは、読者はEATについて別途調べるか、「よく分かんないけどEATはSEOにおいて大事なんだな」と何となく察して読み進めなければなりません。
自分が詳しい分野について書くときでも、自分の知識レベルを基準とせず、あくまで記事のターゲットの知識レベルを理解し、寄り添うことを忘れないようにしましょう。
指導ポイント③:主語や目的語を省略しない
これも一つ前の「読者に察することを求める」の典型例です。
書き手の頭の中では主語と動詞の関係がはっきりイメージてきているから、「毎回書かなくても読者も分かってくれるだろう」と思い込んでしまうのです。
例えば、
私は、今年のお盆休みに実家がある神奈川県茅ヶ崎市に帰省しました。お盆休みの電車は混雑することを見越して、比較的空いている早朝の電車に乗り、茅ヶ崎駅からは車で迎えに来てもらいました。
「帰省する」「電車に乗る」の主語は間違いなく書き手である「私」ですが、「茅ヶ崎駅に車で迎えに来てくれたのは」誰かは書かれていません。
書き手にしてみれば、「実家に帰ったと書いているのだから、迎えに来るのは当然両親だろう。わざわざそこまで書かなくても読者は分かるはずだ。」と思うかもしれません。
確かに、「実家のある街に帰省しているのだから、迎えに来るのは書き手の両親だろうな。」と読者は察することはできます。
しかし、書かれていないことを読者が察しなければならないということは、大げさに言えばそれだけ読者の脳に負荷をかけていることになります。
もう一つ、例えば以下のような文章。
株式会社ABCは、売り手と買い手がオンライン上で取引できるフリマサービス「フリマABC」をローンチしました。
同プラットフォーム上の画期的な機能として、売り手が出品した商品に対しての価格交渉だけでなく、同価値のアイテムとのトレードも提案できる「物々交換機能」というものがあります。
この文章の問題点は、二文目です。
「価格交渉」と「物々交換」機能を使えるのが売り手と買い手のどちらであるかが明記されていません。
サービス運営者は当然サービス内容を熟知しているので、「価格交渉」や「物々交換」機能を使えるのはどちらかを把握しています。
しかし、このサービスに初めて触れる人は、誰がどんな機能を使えるのか、まだ具体的に理解していません。
『えーっと。この「物々交換」機能は特に画期的だし使ってみたいけど、これは買い手の方から売り手に対して物々交換を申し出ることができる機能って理解で良いのかな・・・?』
と読者に「思考することを強いる」のです。
書き手の「暗黙知」は読者に通用しないと考え、読者がストレスなく書かれている内容を理解できるよう、漏れなく情報は書くよう最初は意識しましょう。
指導ポイント④:誰かに対して意図せず失礼でないか意識する
相手の顔が目に見える対面のコミュニケーションや、宛先の顔が浮かぶお手紙などとは異なり、相手の顔が見えず不特定多数の人に向けたライティングにおいてやりがちなのが「無意識失礼」です。
昔の実例を交えて紹介します。
とあるライターさんに「ペット火葬」に関して一記事書いていただくよう依頼しました。
その記事の冒頭の一文がこうです。
飼っているペットが死んだら、誰でも悲しいはずです。
安心してペットを送り出せるよう、効率的且つコストを抑えられる火葬方法を紹介します。
これが例えば、自分の知人がペットを亡くした場合であれば、言葉をかけるときにこのような言い回しにはならないはずです。
「死んだ」ではなく、「亡くなったら」。
火葬に対しても「効率的」のような、まるでそれが手間のかかる面倒な作業であるかのような表現は使うべきではないでしょう。
「コストを抑える」も、「飼い主様のご予算に合わせた」など、もう少し飼い主の感情に寄り添った言い方があるはずです。
このように、読者の顔が見えていないと、つい丁寧で配慮のある言葉遣いを疎かにしてしまうことがあります。
その表現が誰かを傷つけたり、イラッとさせたりしないかを常に意識しましょう。
読者の顔を思い浮かべてライティングできると自ずと文章力はアップする
今回挙げた3つに共通しているのは「読者への思いやり」です。
読者のことを思いやれていれば、回りくどい表現は避け、読者に察することを求める表現もなくなり、失礼な言葉遣いもなくなるはずです。
文章力が上がらなくて悩んでいる方は、語彙力や表現力を高めるよりも、まずは「徹底して読者のことを考える」意識を持つことが第一歩ではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
