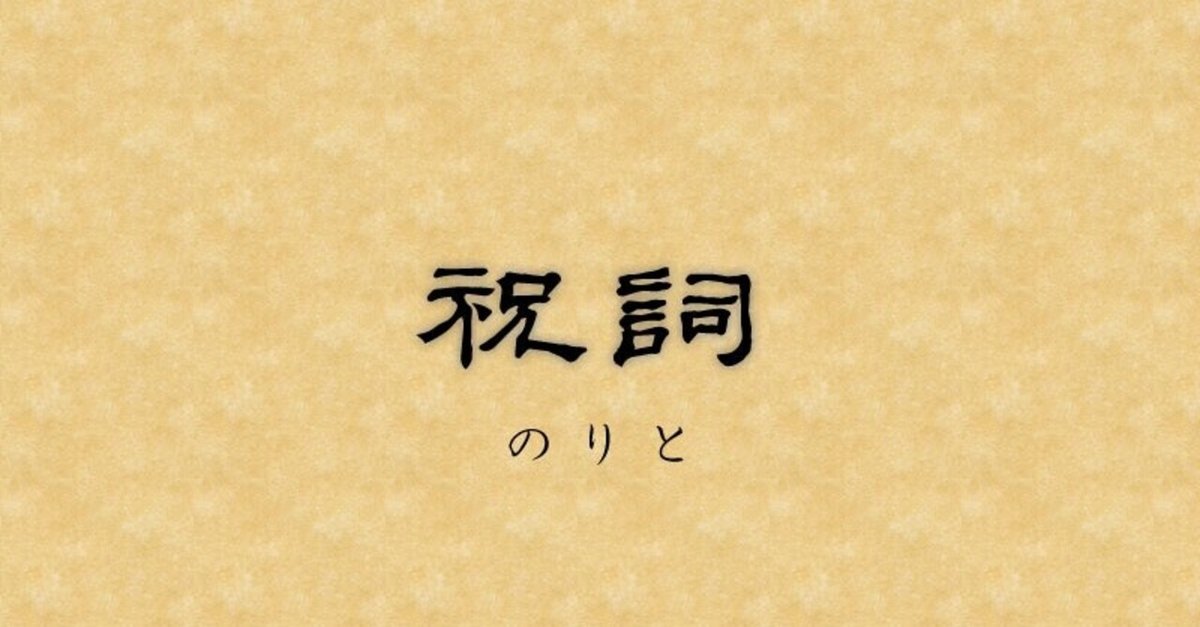
祝詞とは何なのか
色々なところで耳にする祝詞ですが、実際のところよく知らないという人が多いのではないでしょうか。
祝詞というのはそもそも宣説言のことで、神に申し上げる言葉だと本居宣長さまは述べています。

また、折口信夫さまによれば、のりとごとだと述べています。
つまり、神を祀る場である宣り処で発する言葉ということですね。
要するに、天皇が神の資格で発する言葉を祝詞としたわけです。

祝詞が出てきたのは天の磐戸神話において、フトノリトゴト、ハラヘノフトノリトというのが初です。
内容までキチンとした文献は、平安時代に入ってからできたもので、醍醐天皇の残した延喜式祝詞ですね。

新嘗祭のような恒例のお祭りに使われる祝詞。
地鎮祭や結婚式などの個人に関わる儀式で使う祝詞。
祭りの相手が違えば祝詞も別のものを使います。
しかしながら、よく使われる祝詞は延喜式ですね。
祝詞を唱えたりする人も、周りでは結構いるようですが、折角唱えているので、あまりそれについて詳しい方は多くないとも感じています。
見えない世界というものを考えていく上で、祝詞は古来から続く大切な叡智です。
そういうものについてもキチンと学んでいきたいと思う方は、ぜひ一緒に学んでいきましょう。
これからも良い記事を書いていきます。
