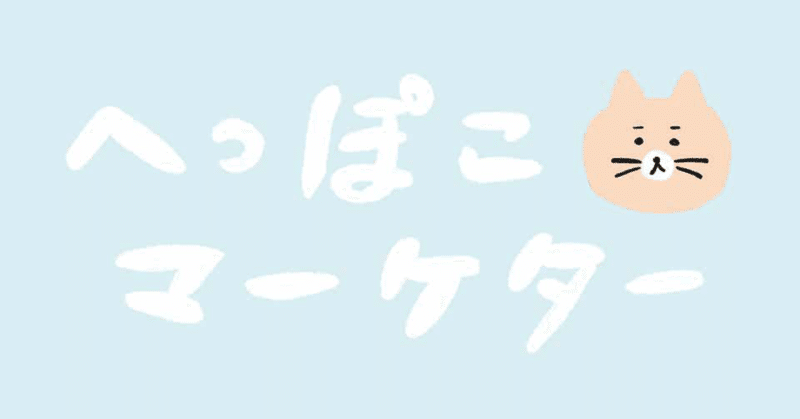
事例研究どうしよう、という話
「へっぽこマーケターの日々」第40回(前回は3/13更新)。
今週もファンマーケティングの定例があったので、先週の「作品が爆発的に広がるために必要な2つの軸、という話」の続きを書こうと思う。
前回のおさらい
●議題
物語を作り、届けることにおいて、「濃いファンとの繋がり」と「爆発的な広がり(ムーブメント性)」の両立を探る
●仮説
「コンテンツ(思想)」と「コミュニケーション」の両方がバランスよく備わっている物語は、物語について読者によって語られるムーブメント、すなわち同時多発的に語られることが起きる。
●補足
「」で囲われている言葉の定義は、前回の定例のnoteを見られたし。
今回の定例のアジェンダ
前述の仮説に当てはまりそうな事例の研究をすることにした。
始めたばかりのため、方向転換が発生することを考慮して、具体的にどの事例かは敢えて触れないでおく。作家や作品が事例になってる想定で読み進めてほしい。
●議題
・研究について目線をそろえる
・事例研究の切り口について
・学びをどう実践していくか
以下にプロセスを記していく。
研究について目線をそろえる
前提の確認である。下記のようなディスカッションをおこなった。
●研究のゴール
仮説を検証するにあたり、「コンテンツ」を作る部分はコントロール不能なのでは、という意見が出た。なぜならエージェントであるコルクは、作家が作りたいものをサポートする役割なので、作ることには「介入」ができない。関わり方としては、真っ先に作品の感想を作家に伝えることだ。
※「介入」のニュアンスを伝えるのが難しいと個人的に思っている。
よって自分たちは、「コミュニケーション」によって、受け手を取り巻く空気を読み(時代性)、作品を通じてファンと繋がるという、「広める」「届ける」ためのノウハウの抽出に今回は注力したらよいのでは、という話になった。
そしてその際に必要なのが、「作品の魅力」と「なぜその作品を作ったのか」という、作品理解だというところまで言語化できた。
●研究対象について
メンバーが研究事例について、各々どんな興味を抱いているかの共有。事例となるコンテンツについて、受け手として感じていることや、強みだと思うことを各々話した。
●研究方法
質の高いコンテンツと受け手との繋がり方を分析して型化するにはどうしたらよいか。
ひとつの案として「トレース」を提案した。webデザイナーが勉強のために行う、素晴らしいデザインを完コピすることと似たものをイメージした。写しとることで先人の細かな工夫を学ぶ、絵の模写のような練習である。
しかし今回その手の「トレース」を行うのは適さないのではないか?という議論になった。たとえるなら、大物歌手を研究しようとしたら、歌い方や曲調に影響を受けすぎてしまうようなものだということだった。型を参考にするはずが劣化コピーになりかねない、という懸念だ。
今回取り扱う事例も、まさに大物歌手の楽曲のような、正に強いコンテンツであるため、それはもっともな意見だろう。これを踏まえ、本家に飲み込まれない一歩引いたアプローチとして、事例の「コンテンツ」と「コミュニケーション」について分解する
事例研究の切り口について
前述の研究方法で議論したことを踏まえ、事例について「どんな切り口で分析するか」という分解の仕方について話し合った。
ブレスト的に話して出てきたのは、
・コンテンツの広がり方(事象の観測)
・「コミュニケーション」のハードル=シェアおよびリアクションしにくさが生まれる背景
・シェアされるに至るまでに、発信側と受け手側でどんなアクションをお互い積み重ねているのか
の3点であった。まだまだありそうではある。
学びをどう実践していくか
まさにこれから「ムーブメント」を起こす必要がある作品として、コルク所属の新人作家・やじまけんじさんのLINEでの新連載マンガ『コッペくん』について、4月の前半あたりを目処に学びを活かして、試しにアクションを起こすことにした。
※実は『コッペくん』は単行本を去年刊行してあるが、キャラも含めた新しい物語としてスタートする。
今回の定例参加者がいつもの半数の4人だったので、不在だったメンバーの意見を踏まえて多少変更が発生するかもしれない。
次回定例に向けて
宿題として『コッペくん』の作品理解を各々やってくることになった。
次回の定例は宿題を持ち寄りつつ、引き続き研究する際の分解方法について議論する。
わたしをサポートしたつもりになって、自分を甘やかしてください。
