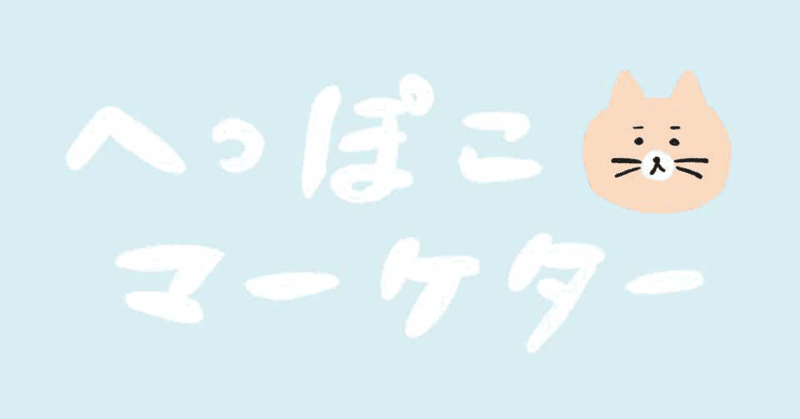
施策の改善サイクルに影響を与える、“よい受け身”と“悪い受け身”、という話
「へっぽこマーケターの日々」第38回(前回は3/10更新)。
仕事において「受け身」というとあまりいい印象を受けないと思うが、実は「受け身」にも2つのタイプがあるのではないだろうか。
言われたとおりにやったことを、また次回以降さらに改善して質を上げられるか否かはどんなことによって左右されているのか、考えてみた。
(ちょうど今日同僚と話したことがベースとなっている)
***
ダメな「受け身」とは何か
世に言うネガティブな「受け身」とはつまり、「他責」タイプの「受け身」なのではないだろうか。
それはいわゆる「言われたとおりにやる」ことであり、そこには「自分のやりたいこと」が介在していない。そうすると自分の軸がないので言いなりでしかない。
そんなスタンスで取り組んで、結果が出ればまだいいかもしれない。しかし、芳しくないときはどうか。果たしてその失敗を自分ごととしてふりかえることはできるのだろうか。
仮にもし、言いなりになったことで他人が言ったことをやったという意識が強ければ、「あの人の言っていたことは間違ってた」と結論づけてしまいかねないのではないか。そんな捉え方で、果たして次回どんな改善ができるというのだろう。
よい「受け身」とは何か
しかし一方で、言われたことを黙ってやりきることは、社会人には一定必要なスキルでありマインドだろう。四の五言わずにタスクを完遂する人材が重宝されているのは、ご存知のとおりだ。
これは、本人にとってもメリットのある姿勢だ。なんせ行動することで結果的にモチベーションも上がるのである。
というのも、人間には「ホメオスタシス(恒常性)」という性質が元来備わっている。これは本能的なもので「なるべく現状のままでいよう」と作用する。そのため、思考すればするほど、先延ばしにしてしまう訳だ。
しかし逆に行動を先にすると、思考は容易く変化する。「作業興奮の原理」の「行動するとやる気が出てくる」というのがわかりやすい例だろう。つまりそれまで躊躇していた気持ちが、行動するだけで変わるのだ。
これでわかるように、思考を変えるよりも行動を変える方が簡単なのだ。
そういう意味では、このスタイルは新卒の新入社員なんかには打ってつけの方法だ。とにかくやる・やりきることでしか信頼を獲得できない時期なのだから。この時期に、意味もわからず納得もできず、でも必要だと言われたから愚直にやる。やるうちにモチベーションが湧いてくる。そして言われたとおりにやって結果が出て初めて、それをやることに納得を見出せる。これらが合わさることで「次はうまくやってやろう」という気持ちが芽生える。
そもそも、四の五言わずにやる人が重宝されるのは、裏を返せば「文句を言わずにやる状態」ひいては「やる気を持って取り組む状態」に人間を変えるのがいかに大変かということだ。
とにかく行動したことで結果的にやる気を獲得した人は、モチベーション高く改善にとりくむことが期待できる。
***
受け身にもよいタイプがいる、という一方で「結局最後に粘れるのは、受け身ではなく、やりたいこととして取り組んでいるメンバーなのではないか」という仮説もある。
これに関しては人間の根源欲求に関わる部分なので、引き続き議論を重ねたいと思う。もしうまくいったら日ごろの仕事がプロセスレベルから楽しくなるかもしれない。
わたしをサポートしたつもりになって、自分を甘やかしてください。
