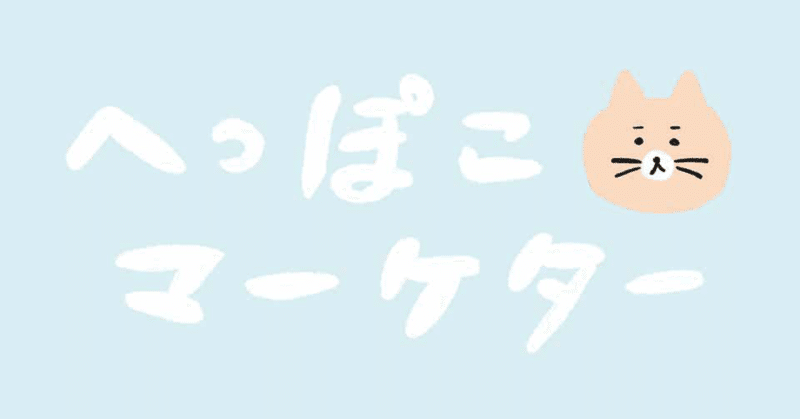
売上に直結しない活動をKPI化する意味、という話
「へっぽこマーケターの日々」第32回(前回は3/2更新)。
今回は、KPI設定についての理解がまだぼんやりしている人向けに、イメージを掴めるようにと思って書いた。
***
データを闇雲にとっていないだろうか。
世の中、実はやろうと思えば自社データは結構いろいろ見れる。そしてデータ分析をアテにする人は皆、“気づき”を求めている。
しかし多くあるデータの内、意味のあるデータ、つまり次のアクションに繋がるようなデータはどれくらいあるのだろう。
意味のないデータをみて一喜一憂してる暇はない。
***
コルクでは、ファンと直接繋がることを掲げている。そのため、作家担当の日々の業務というのは、売り上げに直結しないファンとコミュニケーションが多く存在する。
公式サイトの運用や、週刊メルマガの執筆、そして毎日のTwitterなどのSNS更新だ。
いかにも定性評価の領域になりそうな活動だが、収益という切り口で見るとデータで評価できる面も出てくる。
(定性or定量評価のみではなく、両方のバランスを探るべきだ)
要するに収益化、いわゆるマネタイズという視点で日々の活動を評価しようということだ。
日々の活動を評価する切り口としての“マネタイズ”
エンタメコンテンツの収益化というと、思い浮かぶのは有料コンテンツだろう。確かにコルクもそうなる。
しかしただの課金ではない。コルクにおける有料コンテンツは、「より深く作品を楽しむ手段」という位置づけなのだ。
たとえば、
SNSで無料でマンガを何話か読む
↓
電子書籍でフルバージョンを読む
や
SNSでのスタッフによる裏話に触れる
↓
世界観をこめたグッズを楽しむ
と言った具合だ。
そんな有料コンテンツをより多くのファンに届けるための活動も、日々の活動には含まれている。
企業としての規模や価値を向上させるための“可視化”
幸いなことに、コルクは徐々に所属/管理する作家や作品が増えてきている。それぞれがファンと繋がれるようにするには、以前から各作家担当が行なっていたことで「うまくいった」ものを、他の作品でも再現する必要がある。
よい施策を再現することができれば、より多くの人に作品が届き、作家の価値が世間に理解されるはずである。そこから最終的にはコルクという会社の価値の向上にも繋がる。
何を“可視化”すればよいのか
昨日のnoteにも書いたように、「うまくいった」かどうかを個人の肌感覚に委ねてはいけない。なんとなくの評価は最適解を生まないのだ。
では、やったことが、うまくいった/いってないを正しく認識するためにはどうしたらよいか?そこでデータによる定量評価の出番となる。
データによる定量評価で「正しく」ふりかえることができるようになってはじめて、次回何をしたらよいかアイデアがストックできるようになる。これにより、ヤマカンに頼らなくて済むし、声が大きい人の意見ばかりが通ることもなくなる。
そして前述のように、有料コンテンツをより多くのファンに届けるための活動も、日々の活動には含まれている。このことをデータで表す必要があるが、そのひとつが、KGIとKPIという指標の分解アプローチだ。
KGIとKPI
KGIは、「今期は売上10%アップ」のような最終目標の達成度合いを可視化した指標。KPIは、最終目標を達成するために必要なプロセスの達成度合いを測る指標だ。
日ごろの活動が最終的にどんなふうに有料コンテンツに繋がっているか分解していくことで、最終的にどんなデータ(KPI)を伸ばせばいいのかわかるようになる。
このように、活動と収益化の関係性を理解した上で、定量的に可視化できるようにすれば、以前よりさらにいろいろな知見が社内に共有されることを見込んでいる。
そうすることで、コルクに関わる作家・作品がよりよい体験を届けることができると思う。
わたしをサポートしたつもりになって、自分を甘やかしてください。
