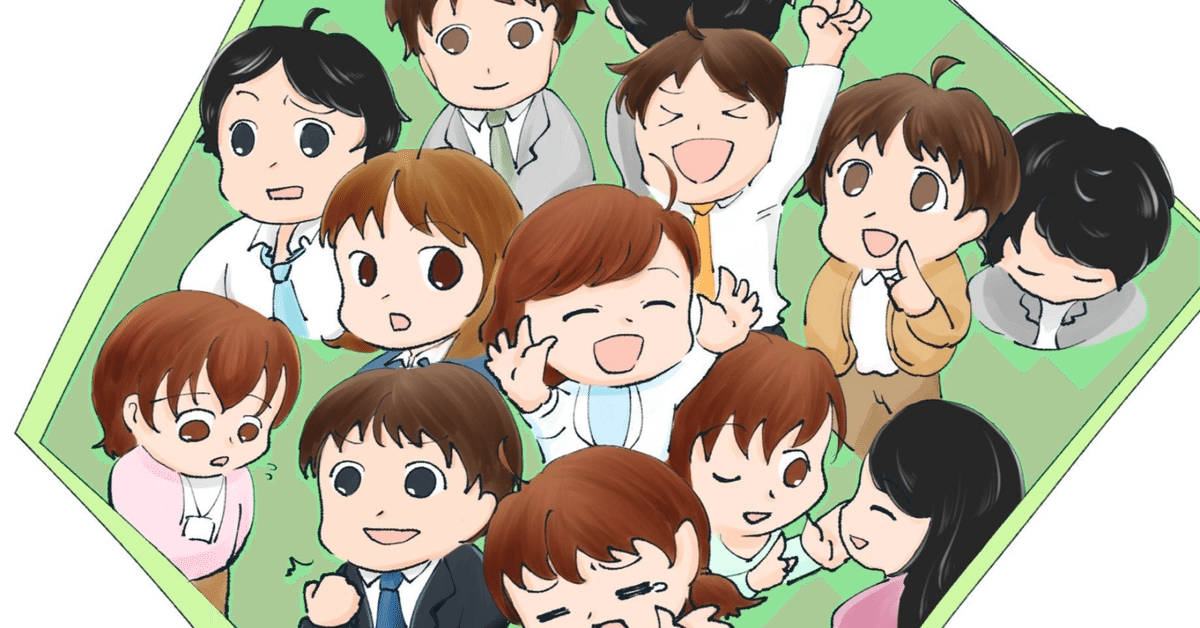
#1158 人間のための教育
上田薫の著書『人間のための教育』を読んだ。
ここには、「教師」という人間が、「子ども」という「人間」に対して、どのような姿勢で教育に臨めばよいかが記されている。
今回は、この著書から学んだことを整理していきたい。
教育の「結果」よりも「過程」を重視する
教育はとかく「結果」が重視されやすい。
「〇時間、指導した」「テストで〇点取らせてやった」のように、結果至上主義に陥っている。
しかし本来、教育というものは、そんな甘いものではない。
教師が指導したからと言って、全ての子どもを画一的に変容させることは不可能である。
大切なのは、「結果」ではなく、「過程」なのである。
そのためには、教師にも、子どもにも「ゆとり」を生み出す必要がある。
知識の「量」よりも「質」を重視し、思考の余地を残す
ということは、「いかに多くの知識を身につけさせるか」ではなく、「いかに質のよい知識の習得過程を設定できるか」が問題となる。
そして、知識が習得されるには、子どもの「思考」が必要不可欠である。
そのような思考のできる余地、すなわち「ゆとり」がなければ、「質」も「過程」も重視することはできないのだ。
なので、「どのくらい多くの時間、学習したか?」という時間の「量」よりも、「その時間内でどのくらいの努力をしたか?」という「質」の方が重要なのである。
授業は子どもに「学習のきっかけ」を与えるもの
授業は、あくまで子どもに「きっかけ」を与えるに過ぎない。
子どもはその「きっかけ」により、自主学習を始める。
授業で子どもを「A地点からB地点へ変容させる」などという単純な構図はあり得ないのである。
やはり、子どもが「学習のきっかけ」を感じ取るような「ゆとり」が必要なのである。
子どもだけを変化させようとせず、教師自身が変わる
「子ども」という人間を直接変化させることはできない。
教師はあくまで、子どもに「影響を与える」ことしかできない。
そのように子どもを「人間」として尊重するのであれば、無理やり子どもを変えようとする姿勢はなくなる。
そして、子どもを変えようとせず、教師である自分自身を変えようとするようになる。
それができれば、子どもに影響を与えることのできる幅が広がっていく。
子ども中心の授業をしていくのであれば、子どもの「自主的学習」が増え、教師にとって不都合な面をもたざるを得なくなる。
しかし、それが自然なのである。
いつでも、教師にとって都合のよい学習ばかりしている授業の方が不自然極まりないのだ。
なので、教師が狙うところに、子どもを無理やり収めようとしないことが必要となる。
子どもと教師の「自主性」を共に生かす。
両者の「自主性」が激突することで、理想的な授業が実現するのだ。
知的肥満児
系統学習を展開すると、「知的肥満児」と「なりそこなった栄養失調児」ができあがる。
なぜなら、系統学習には「問題解決過程」が存在せず、その過程で獲得できる「瞬発力」が育たないからである。
柔軟で瞬発力があり、ペーパーテストのみならず、生きてはたらく知識を活用することのできる子どもは、問題解決学習の積み重ねにより、育成されるのである。
競争は評価を局所的にしてしまう
「競争」はある一定の「ルール」に基づき、勝敗が決まる。
したがって、評価が局所的になってしまう。
大切なのは「勝敗」よりも「プロセス」である。
競争していく中の「努力」から得られるものを重視する必要がある。
また、「賞罰」も競争と同じで、「教師の判断基準」という局所性をもっている。
子どもを「局所性」という狭い枠にはめ込んではいけないのである。
評価は「終末」ではなく、「途中」を意味する
評価は「あなたはA」「あなたは80点」だとと「決めつけて終わり」のものではない。
評価は「指導の始まり」「指導の途中」を意味する。
どのような評価も「形成的評価」なのであり、いつまでも子どもに寄り添い、支えていくための評価をする必要があるのだ。
多面的・全体的・立体的評価を重視する
子どもを一元的目標で評価しないことが求められる。
子どもは一人ひとり「実態」が異なる。
その異なる「実態」をもっている子どもに、「画一的で一元的な目標」を与えることはナンセンスである。
子ども一人ひとりに応じた最適な目標を与える必要がある。
それに伴い、子ども一人ひとりを、多面的・全体的・立体的に評価するのである。
また、動的で個性に応じた、その学級担任だけがつくれるカリキュラム編成を重視する。
「目の前の子ども」不在のカリキュラム立案、目標設定、評価計画をしてはいけないのだ。
無論、子ども不在の教材研究もあってはならない。
子ども一人ひとりを思い浮かべ、子どもに合う教材研究を重視していく。
全体的な深い変化
子どもに「~を見に付けさせる」「~ができるようにする」というのは、部分的な変化である。
そのようなレベルで、「ある子は変わった」とは言えない。
子どもの「部分的な浅い変化」ではなく、「全体的な深い変化」を可能にするのがプロの教師である。
そのためには、教師も全体でぶつかる必要がある。
自分自身を常に変化させる。
個々の子どもたちと正対していく中で、自然と「自己変革の力」が生じる。
子ども理解が更新されていく。
知識が更新されていく。
そのような「柔軟な人間性」をもつことで、教師は自分を自然と変化させていける。
つまり、教師は「不完全者」なのである。
不完全者としての教師が、不完全者としての子どもにかかわることで教育が成り立つのだ。
指導は「画一的に完全に」ではなく、「非画一的に不完全に」が原理である。
子ども一人ひとりに応じた不完全な指導を積み重ねていくことで、子どもの「全体的な深い変化」を可能にするのである。
一人ひとりの子どもの人間理解を極める
ここまでの話は全て「人間理解」という理念に落ち着く。
「教育」が「人間」と「人間」の間のダイナミックな営みである限り、教師は子ども一人ひとりの人間理解をしなければならない。
それを可能にするのが、上田薫の提唱した「カルテ」の実践である。
カルテを用い、時間的・空間的な人間理解をしていく。
一人ひとり子どもの人間理解が土台としてない限り、その教育は無力と化す。
子ども不在、子ども理解不在の教育は「無」に等しいのである。
だからこそ、子どもを知っていくためには、自己変革が必要となる。
「俺様」「王様」のような専制型教師は、子ども理解などしない。
自分の信じた教育をやり通す。
しかし、それは真の「教育」ではない。
命令・強制・宗教である。
教師が自己変革をし、子どもを知っていくことで、授業の質が上がり、結果的に子どもの学びも増幅していくのである。
子どもを徹底的に知ること、自己を変革していくこと。
この2つを上田薫の著書から学ぶことができる。
常に意識するようにしていきたい。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
