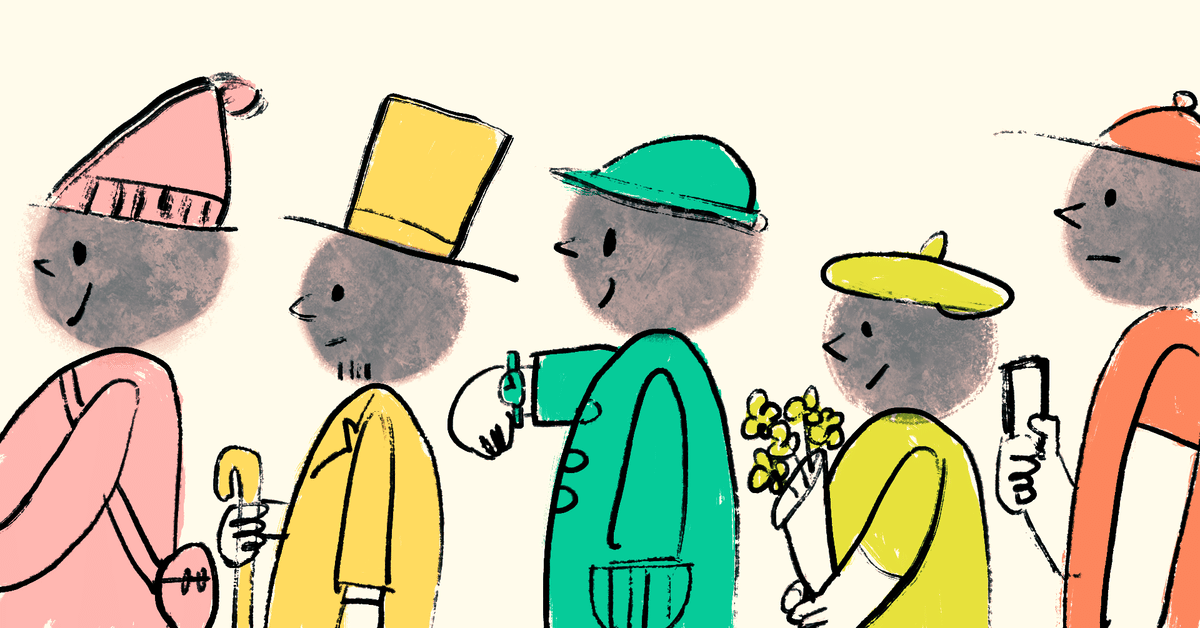
Photo by
noouchi
#625 多様性とは「何でもあり」ではない
多様性を「何でもあり」と勘違いすると、学級経営が望ましくない方向に進む。
「一人で黙々と勉強する」「みんなでワイワイ話す」「学習せずに寝る」「男子だけで固まる」「女子だけで固まる」など。
これらを全て「多様性だから何でもあり」としてしまう。
すると、いつまでたっても望ましい学級集団にはならない。
「何でもあり」ではダメなのだ。
人と人は「折り合い」をつけなければならない。
互いの個性を尊重し合い、折り合いをつけて「つながり」を実現することで協同することができる。
そうやって人類は進化し続けてきたのだ。
だから「何でもあり」ではなく、多様性を認めつつ、折り合いをつけていくのだ。
折り合いをつけることで、「つながり」が生まれるのである。
だから学級の中で「何でもあり」が重視され、「つながり」が意識させていないときは、教師が評価しなければならない。
「折り合いをつけることができていない」または「折り合いをつけることができた」と評価する。
「つながりが意識できていない」または「つながりが意識できている」と評価するのだ。
そのような教師からの評価・フィードバックにより、子どもたちは「折り合いをつけること」「つながること」の重要性を認識することができる。
そして、「つながり」の多い望ましい学級集団になっていく。
多様性の在り方を勘違いしないようにしていきたい。
そして、折り合いをつけることができるよう、適切に評価していきたい。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
