
新しいグループ監査がぴたりとはまる会社とは?【監査ガチ勢向け】
改正監基報600が適用されますが、新しいグループ監査は米国企業の子会社管理と親和性が高いんです。米国企業がどうやっているのかを知ると理解が深まります。
監査法人で30年強、うち17年をパートナーとして勤めた「てりたま」です。
このnoteを開いていただき、ありがとうございます。
改正監基報600「グループ監査における特別な考慮事項」の導入準備はできていますか?
すでに各監査法人で方針が出され、特にクライアントに影響がある点から優先して対応されていることと思います。
改正600の最大の変更点
何が変わったんだったっけ?という方は、直ちにJICPAの17分のビデオを見て思い出してください。企業向けですが、コンパクトにまとまっています。
(改正600が発行されてすぐ私のnoteでもまとめたのですが、おもしろおかしく書こうしているところが空回りしていて、鼻につきます。お読みになる方は「お前、スベってるぞ!」と突っ込みながら読んでください)
忘れてしまった方も、こんな図を覚えていませんか?

「重要な構成単位」という概念がなくなることは記憶にあると思いますが、それに増して重大な変更は「タテ」が「ヨコ」になること。
つまり、構成単位ありきで考えていたものが、勘定科目単位で考えるように切り口が変わることです。
この結果、これまで「重要な構成単位」としていた子会社の一部の勘定科目が対象外になったり、連結監査の対象としていなかった子会社の一部の勘定科目をどうしても対象にしないといけないようになったりします。
日本の多くの会社の場合、子会社ごとにシステムもプロセスもぶつ切りになっていることが多く、「タテ」に(構成単位を軸に)見ることで違和感がなかったと言えます。
それを「ヨコ」に(勘定科目を軸に)見るなんて、理屈は理解できても実務がどう回るのか、イメージが難しくないですか?
そこで、これまでも「ヨコ」の連結監査を受けてきた米国企業のことをお話しすると参考になると思います。
米国企業の子会社管理
最初にお断りをしないといけませんが、日本企業にもいろいろあるように、「米国企業」でくくってしまうのは主語が大きすぎます。
私がこれまでに監査で関与した米国企業10社ほどでの経験から、平均的なところを抽出して書こうと思います。
ポイントは業務の「標準化」と「集約」の2つです。
業務の標準化
典型的な米国企業では、親会社が大量のマニュアルを作り、子会社に「この通りやれ」と言ってきます。
また、システムも共通化が進められています。
どこかの子会社をパイロットとして導入したシステムをほかの子会社に横展開することが多いようです。
同じマニュアルやシステムを使うことで、業務が標準化されます。
これには、次のようなメリットがあると考えられます。
子会社ごとにゼロベースで業務をデザインするのと比べて、効率的
子会社に任せる部分を小さくすることで、業務のアウトプットの品質をそろえる
ある子会社で生まれたベストプラクティスをほかの子会社に横展開しやすくなる
もちろんデメリットはあり、現地の商慣行に合わないためにマニュアルやシステムがそのままでは使いづらいことがあります。
かつては、受取手形や支払手形の処理がよく問題になっていました。
業務の集約
日本でも、シェアード・サービス・センター(SSC)を設ける企業が増えてきました。SSCはグループ会社の管理業務などを集約する拠点です。
米国企業はもっと大胆で、国境を超えたSSCが珍しくありません。
例えば、アジアの子会社の業務の一部を、フィリピンやシンガポールにあるSSCに移管しているのです。
日本の会社法に基づく計算書類を、シンガポールで作っている、といったことが起こります。
この最大のメリットは効率化です。
各子会社で少人数で多能工的に処理していたものを、SSCで一括して処理することで、より習熟したチームで実施することができ、トータルの人数も減らすことができます。
この前提には、もともと業務が標準化されていたことも大きいと思います。
米国企業のグループ監査
このように業務の標準化と集約が進んだ米国企業を、あなたならどうやって監査しますか?
全国に支店のある日本企業で考えてみると…
その前に、同じ機能を持つ支店を全国に配置しているドメスティックな日本企業の監査を考えてみましょう。
業務プロセスを識別し、内部統制を識別して、運用評価手続のために25件サンプル抽出して……といった手続を各支店について実施するようなことはしないと思うんです。
全支店を一つの単位として(親会社内に同じ機能を持つ部署がある場合は、それも含めて)手続を実施します。
改めて考えてみるとこれは、全支店(+親会社)の業務プロセスが標準化されているからできることです。
さらに、業務が親会社などに集約されていると、親会社に往査すればほとんどの手続が実施できるということも多いでしょう。
グループ監査に置き換える
全国に支店のある会社で考えたことを、グローバルに拡大して考えましょう。
米国企業のグループ監査では、米州、欧州、アジアパシフィックなどの地域単位で手続を実施することになります。
あるいは、全世界を一つの単位として実施することもあります。
これにより、子会社ごとにフルにウォークスルーし、内部統制を識別する工数を大幅に減らすことができます。
運用評価手続のサンプル数も減らすこともできるでしょう。
さらに業務がSSCに集約されていれば、SSCを往査することで多くの手続を実施することができます。
むしろどうしても現地でしか実施できない手続、例えば実地棚卸の立会や固定資産の現物チェックだけを子会社の監査チームに指示すればよいことになります。
日本企業への改正600の適用
アメリカの上場企業の監査には国際監査基準ではなくPCAOB基準が適用されますので、600の改正は関係ありません。
しかし、これまでお話ししてきたことで、「ヨコ」の監査がやりやすいことはお分かりいただけたと思います。
グローバルベースでは業務の標準化も集約も行われていない日本企業の監査への適用は、とても難しいと言わざるをえません。
各監査法人で工夫されていると思いますが、まともにやるとこれまで対象にしてこなかった子会社が対象になり、新たに内部統制の手続や実証手続を実施することになって、工数は相当増えると思います。
また、何らかの手続を実施する子会社が増えることでコミュニケーションの工数が増え、それに伴うストレスも大きくなるでしょう。
おわりに
私が監査をはじめた35年前には、米国企業では業務の標準化はすでに行われていました。国境をまたいだSSCも、30年近く前からはじまりました。
一方、多くの日本企業では、このような米国企業の動きを聞いたことはあっても、情報収集して自社での導入を検討したケースは少なかったように思います。
米国企業のやり方がすべて正しいわけではないですし、業務の標準化や集約のデメリットもあります。
しかし、検討する日本企業が多くなっていれば、その結果導入する企業も増え、よりグローバルに活躍しやすい体制を整えられたのではないか、とも思います。
そして、その背中を押すことができたのは、日米どちらのパターンの企業にも関与する監査人くらいではなかったか、とも思うのです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
この投稿へのご意見を下のコメント欄またはX/Twitter(@teritamadozo)でいただけると幸いです。
これからもおつきあいのほど、よろしくお願いいたします。
てりたま
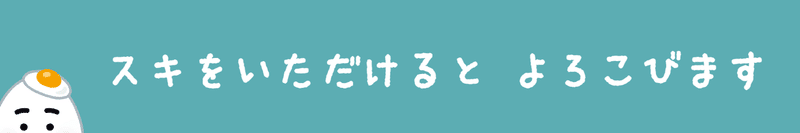
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
