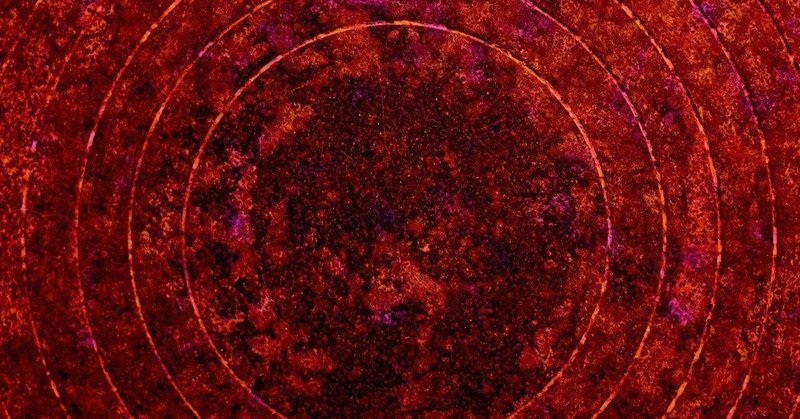
東京大空襲 (後編)
翌朝、私は目覚めました。
否、眠ってはおりませんでした。
眠られるはずなど、ございませんでした。
気の遠くなるような、一晩でした。
プロペラの音が遠くに聞こえるだけで、飛び起きました。
人の叫び声と泣き声と断末魔が、絶えず続いておりました。
私は自分が生きていることを、はじめは信じられませんでした。
四肢が残っていることが、信じられませんでした。
昨晩見た、腕と脚が散らばる光景が、目に焼き付いていました。
何度も何度も、確認しました。
自分の腕と脚を、何度も触りました。
確りと、存在しておりました。
ゆっくりと、立ち上がりました。
立ち上がれるという事実に、感謝しました。
涙が、頬をつたいました。
辺りを見回して、愕然としました。
私がいた河川敷は、全て燃え尽きておりました。
草一本、残っておりませんでした。
私が恐怖に震える間にも、火の手は目の前に迫っていたのです。
私が乗っていた小舟が燃えなかったのは、奇跡でした。
小舟から降り、私は歩き始めました。
向かうところなど、ありませんでした。
全てが、焼け落ちていたのですから。
しかし、何もせずには居られませんでした。
自分が息をしている、歩いている、動くことができる。
それを感じることが、その時の私には必要でした。
しかし、すぐに歩くのを止めました。
一歩踏み出す度に、恐怖が襲うのです。
死体が、無残に散らばっておりました。
否、散らばっていた、どころではありませんでした。
所々、足の踏み場も無いほどでした。
私は、咄嗟に目を閉じてしまいました。
しかし、何時までもそうしているわけには参りません。
覚悟を決めて目を開き、また歩き始めました。
死体を見るのに段々と慣れていく自分にも、恐怖しました。
できることなら、上を見ながら歩きたい。
しかし亡くなった方々を踏んでしまうことは、許されない。
黒く焦げた死体ばかりでは、ありませんでした。
当時の日本には、「ピンク色」という概念がございませんでした。
しかし、表現するのなら「ピンク色の死体」でございました。
煙の影響で、窒息死された方々でした。
辛うじて炎を逃れても、辺りに充満する煙から逃れられなかった方々です。
薄いピンク色の塊となり、横たわっておりました。
その方々は、少なくとも四肢は残っておりました。
しかし、私には想像してしまいました。
呼吸ができない苦しみを、全身で感じる辛さを。
爆弾が直撃し、一瞬のうちに迎える死。
火炎に巻き込まれ、水を探す間もなく迎える死。
肺が煙で充満し、苦しみに悶えながら迎える死。
私には、全て想像できてしまいました。
昨晩、断末魔を聞き続けたことが、それを可能にしていました。
あれらの叫び声の一つ一つが、私の耳に蘇っておりました。
しばらく歩いていると、死体が山積みにされている場所がありました。
生存者の方々が、それを燃やす準備をしておりました。
死体は、次々と運び込まれていました。
生存者の方々が、死体を貨車で運んでおりました。
一台の貨車に、複数の死体を乗せて、運んでおりました。
何度も何度も、行き来しておりました。
積まれた死体の山に、新たな死体が次々と投げ込まれておりました。
まるで、何か大きなゴミが投げ込まれるように。
あれほど残酷な光景は、忘れることができません。
私には、出来ないことでした。
亡くなられた方々に、触れることすらできませんでした。
その作業をしている方々を、軽蔑すらしてしまいました。
しかし、私は気づいたのです。
周辺に、吐しゃ物が散乱していることに。
作業をしている方々のものでした。
彼らだって、本当はやりたくない。
しかし、亡くなった方々の遺体を腐らせるわけにはいかない。
これ以上、惨めな姿を晒させることは許されない。
そういうお気持ちで、作業に取り組まれていたのだと思います。
私は、激しい自己嫌悪を感じました。
口にはしませんでしたが、彼らに謝罪を送りました。
作業を手伝えない申し訳なさからか、私は足早にその場を離れました。
近くに、小高い丘が見えました。
他に目指す場所も無い私は、目的も無くその丘に向かいました。
丘を登り始めた私は、多少の安堵を覚えました。
転がる死体の数が、明らかに減ったからです。
思えば、当然のことだったと思います。
爆撃機から見えやすい丘の上に、わざわざ逃げる者などおりません。
人は皆、防空壕や川を目指して走ったはずでした。
その丘は一晩経って、私にとって安寧の場所と成りました。
丘の中腹あたりに、一人でしゃがみこんでいる少女が見えました。
私は、声を掛けずにいられませんでした。
彼女を心配する心と、生きている人間と話すことへの強い欲がありました。
近づくにつれて、彼女が泣いていることに気付きました。
理由を尋ねると、母親とはぐれたとのことでした。
私は彼女の手を引いて、丘の頂上を目指しました。
彼女の手の温もりが、私をどれほど安心させたか今でも覚えています。
丘の頂上を目指して歩くにつれて、私は絶望を覚えました。
あちらこちらに、死体の山ができ始めていたのです。
幼い少女には分からないことかもしれませんが、見せるわけにはいかない。
私は彼女にその場で待つように言い、私が頂上から確認すると伝えました。
彼女も疲れ果てていたのか、途端に座り込んで眠り始めました。
私は勇気を振り絞って、頂上に向かいました。
頂上に立った私は改めて、深い絶望を心から感じました。
一つ、二つ、などではございませんでした。
数えられるだけでも、十ほどの死体の山が見受けられました。
私は成す術もなく、その場に崩れこみました。
涙が、止まりませんでした。
嗚咽が、止まりませんでした。
いつまで、そうしていたでしょうか。
とても長い間、蹲っておりました。
顔を上げるのが、怖かったのだと思います。
なんとか正気に戻った私は、自らを落ち着かせました。
そしてもう一度、その残酷な現実を自分に突きつけました。
もう、涙は枯れておりました。
誰を責めるべきなのか、分かりませんでした。
敵を責めるのも、間違っていると思いました。
誰にも向けようのない怒りが、私を満たしました。
その怒りを抑えるのは、不可能でした。
しかし、何かをしていなければ、自分を抑えられませんでした。
私は、いつの間にか土下座をしていました。
深く、土下座をしました。
頭を地面に押し付けても、まだ足りない思いがございました。
自分が生きていることに対する、謝罪なのか。
彼らを追って自刃する覚悟も無いことに対する、謝罪なのか。
昨晩一人も救うことができなかったことに対する、謝罪なのか。
私には、分かりませんでした。
私には、土下座しかできませんでした。
自分の情けなさに、ただただ、怒りが湧きました。
その後のことは、微かにしか覚えておりません。
気を失ったのかも、しれません。
あの少女がその後、何処に行ったかも、分かりません。
大変、申し訳ございません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
