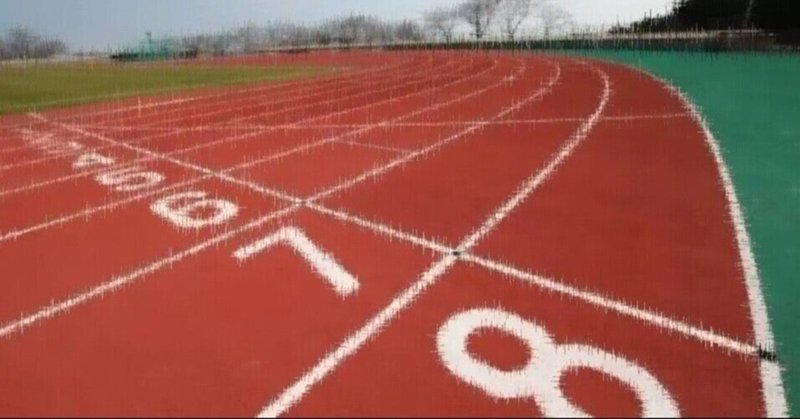
徐々にタイムが落ちていくシーズン初戦
まずは結果から
春のシーズンは久しぶりに4戦全線に出場することができた。競技役員で周回記録員を行うことがほとんどの僕は5000mに出場するとなると、そこそこ周りに迷惑をかけることになるので、少し控えながらの出場も考えるのだが、1500mと5000mの出場を使い分けつつ、なんとか出場することができた。ときにはウォーミングアップを早めに済ませ、中学生の3000mの周回記録員をしてから、ほぼそのままスタートに直行することもあったが。。
とりあえず結果の方から先に紹介すると、、、
シーズンインのタイムは徐々に低下
①4/17 5000m 16'13"04(全体11位、十勝管内2位)
②5/1 1500m 4'23"40(全体3位)
③5/8 5000m 16'07"43(全体2位)
④5/15 1500m 4'17"96(全体4位)
細かな話はこれから書いていこうと思うのだが、シーズンインのタイムは緩やかながら、確実に右肩下がりになっている。なんとかこの低下を抑えなければと思うのだが。。
2016年 16'57"47
2017年 16’06”61 ※トラック初レースは10月
2018年 15'42"94
2019年 15'56"72
2020年 16’09”27 ※トラック初レースは7月
2021年 16'13"04
初戦は前々回の投稿で書いたように1000m×5本(間200mjog)の総合タイムとぴったりの結果となってしまった。自分の考えが的を得ているという嬉しさの半面、もう少しは良いタイムで走れると思っていただけにかなり残念であった。
これも投稿で書いたのであるが、練習のタイムというものは「どの環境」ということも差し引いて考えるべきだとは思う。これは市民ランナーの方でもそうであるし、指導に当たる方にもあてはまることだと思う。最近では実業団や大学あたりでは「どのシューズで走ったのか」ということも差し引きつつ、設定ペースを考えているようである。
例えば、
・ひとりで走ったのか、集団で走ったのか
・オールウェザートラックで走ったのか、土で走ったのか
・400mトラックで走ったのか、300mトラックで走ったのか
・朝練で走ったのか、日中の練習で走ったのか
・比較的疲労がない中で走ったのか、疲労が残っている状況で走ったのか
・シーズンへの移行段階なのか、シーズン中なのか
というように、少し上げただけでも、練習の条件というものは様々であるということがわかる。
同じ1000m×5本といっても、練習の環境によって設定タイムを上下させる必要があるし、その結果についても単純には試合のタイムとつなげてはいけないと思っている。
そんな風な考えを持っているので、試合1週間前に行った1000m×5本の練習はというと、
・ひとりで走った
・朝練で走った
・ほぼシーズン最初のスピード練習
という条件であったので、もう少し条件が整えば、3分10秒で5本は揃えられただろうと思う。そんなことから15分50秒あたりをイメージしていたのだったのだが。
シーズン初戦(5000m 16分13秒04)を振り返って
管外の駅伝強豪校が出場していたこともあって、速い流れになることは想定していた。練習の状況を考えると、最初の1000mを速く入っていくことは非常に危険だと思っていたので、抑えて落ち着いて入っていくことを心掛けた。同じ社会人ランナーで力的についていけそうなメンバーがいたので、3000mまではとりあえず粘ってついていこうという考えで走っていく。
こう書きながらも5000mのレースの考え方は難しいなとつくづく思う。「3000mまではとりあえず粘っていこう」と書いたように、誰しも何かしらそういう気持ちや考えをもってレースに臨むと思うのであるが、割と僕は3000m+2000mという考え方で5000mをとらえることが多く「まずは3000mまで」という感じ走る。
何年やってもこの考えを変えるのが難しいのだけれども、正直この考え方は良くないのではないかと最近思う。「まずは3000mまで」の考えで走っていくと、3000mでいったん気持ちが切れてしまうことがとても多いと感じる。特に近年のように5000mを走るのに満足したスピードと持久力の練習ができていないと、基本的には3000mを余裕をもって通過できる状態には正直なっていないのだ。その状態で「あと2000m」というのはかなり精神的に厳しい。ある程度の練習が積めていない選手であれば、これは高校生にも言えるのだが、4000m+1000mという方が気持ちが楽なのではないかなと思う。そうは思うのであるが、3000mという距離は試合にもある距離なのと、割とトレーニングでも多く用いられる距離なので、どうしても気づけば3000mでいったん気持ちが切れてしまうのが、いまの大きな課題かもしれない。
今回のレースは、3'09"1-3'11"2-3'16"4と1000mラップを刻み、9'36"7で3000mを通過した。15分50秒の目標タイムからすると、やや厳し状況となっている。2400mまでは時折離されそうになりながらも、必死にストライドを伸ばして差を離されないようにするような厳しい状況であったが、3000m手前でややペースが鈍ったこともあり、幾分かの余裕をもって3000mの通過をした。
このままでは15分台も厳しくなってしまうのと、少し脚に余裕があったので一か八かで、集団から抜け、もうひとつ前を追うために切り替えたのであるが、それもたった1周で力尽き、3000m-4000mは3’14”0と少しだけペースを上げたのにとどまり、ラスト1000mは3'21”6となんと最も遅いラップを刻むという、なんとも情けないレースとなってしまった。
いかに後半の2000mをしっかり走り切るか
これについては個人的に明確な答えを持っている。
簡単なことで、2000mのインターバルだとか、練習の中に2000mという距離を入れていくことだと思っている。
わかっているのだが、2000mという距離はトレーニングとしてはかなり難易度の高いメニューだと思っていて(ちなみに300mという距離も競技場の性質上、基本的にインターバルが100mになるので難易度が高い距離と思っている)、特にひとりで行うにはハードルが高くて敬遠してしまう。
ここら辺については、おそらく専門家であっても同じ意見を持っていて、東海大学の西出コーチも自身のトレーニング論の中で「1000mだと楽に行ける。2000mだと追い込めない。なので1600mという距離が良い」というようなことをおっしゃっている。
例えば2000m×3-4本(r=400mjog)のようなメニューを5000mのレースペースでしっかりとこなせる選手は強いと思うのだが、なかなか自分のメニューに落とし込んでいくには勇気がいるメニューだ。課題が明確であったとしても取り組めない。ここらへんが自分でメニューを立てて、ひとりで練習する限界なのかとも思うこともある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
