
夏夜の一声|秀歌を紐解く(1)
夏の短夜と言いますが、このところ暑すぎて、寝苦しさのあまり早く目が覚めてしまうのです。
まだ明けやらぬ中、遠くで聞こえる「テッペンカケタカ」の声。都会から山の近くに引っ越して来て、初めてホトトギスの鳴き声を聞いたときは感慨深かったです。
古典の世界では、死出の山の使いだとか、吐血して鳴くとか、とかくおぞましい印象ですが、実際に聞いてみると、変拍子の感じも相俟って、むしろどこか愛嬌のあるようにも思われる声です。ウグイスのような、悠然と長く引いて歌う声ではなく、立て続けに鼓を打つような慌ただしさ。明けやすい夏夜と取り合わされるのにぴったりです。
本記事では、そんなホトトギスを詠んだ和歌を一首ご紹介します。
「一声」の夜明け
夏の夜の臥すかとすればほととぎす鳴く一声に
明くるしののめ
『古今和歌集』巻三〈夏歌〉156番、紀貫之の一首です。そろそろ寝るか…、と床につく刹那、気忙しい《鼓》のリズムと共に、ぽん!と夜空が白むという面白さ。マンガ的というか、虚構に走り過ぎるきらいはあるものの、当時の人々にとっては好まれる趣向だったようです。というのも、この「一声」という語、平安人にとっての最推しである漢詩人・白居易(白楽天)がよく使ってるんですね。
早くは毘沙門堂本『古今集註』という注釈書に、
此歌ノ心ハ、楽天ノ詩ニ「早夜欲曙一声ノ間」ト云心也。
と指摘されています(ただし、惜しいかな、この詩句は現在発見されていないようです。『古今集註』の著者の覚え違いか、今後新しく白居易作の詩句が見つかるかはわかりません)。この他にも、
九江三月杜鵑来る、一声催得して一枝開く。
別れを念ひて時節に感じ、早蛩一声を聞く。
※「蛩」はコオロギのこと。
微月初三夜、新蝉第一声。
という具合。特に一例目は杜鵑(=ホトトギス)で、鳴き声と同時にぽん、とサツキの花が開く、という仕立てが、貫之の歌とそっくりです。このあたりに、貫之の発想の源があったことは容易に想像できます。
だからといって、「白居易のパクリやん!」と、貫之を責めるのは、あまりに現代人的な考えに偏った誹謗に過ぎません。そう、これは「換骨奪胎」というもので、昔の人々の創造力は、むしろ前作に倣うことから強く生じるものだったんですね。先人の遺した名作は、当然後世の人が知っていて然るべきで、それをどう今風に、自分たち風に料理するかこそが、腕の見せ所だったのでしょう。
夏の夜「の」はどこにかかるか?
では、貫之の料理の腕前や如何に、ということになりますが、彼、結構仕込んでます。きっと、もやしの根はきっちり取る、かぼちゃの煮物は面取りをする、こんにゃくには飾り包丁を入れていくタイプですね(?)。一首の冒頭から、その細工の片鱗が垣間見られます。初句「夏の夜の」の「の」です。
夏の夜の臥すかとすればほととぎす鳴く一声に
明くるしののめ
これを、
▲夏の夜に臥すかとすればほととぎす鳴く一声に
明くるしののめ
と改変すると、その点がよく分かります。「の」の後には通常体言が接続するので、「臥す」という動詞が来るのは不自然です。このミステリーについて、注釈書では主に二つの説が唱えられています。
「(明くる)しののめ」にかかる説
半澤幹一・津田潔『対釈新撰万葉集』(勉誠出版2015)
新撰万葉集研究会編『新撰万葉集注釈』巻上(一)(和泉書院2005)など
初句で切れる(夏の夜の短さ、等の省略)説
西下経一『古今和歌集新解』(明治書院1957)
片桐洋一『古今和歌集全評釈』(講談社1998)など
片桐全評釈には、次のようにも述べられています。
「の」は体言に続くことを要求するので、「郭公」に続こうとして続き切れず、また「一声」に続こうとして続き切れずに、最後の「明くるしののめ」に至って、やっと受け止められるという「竹岡全評釈」の説は説得的だが、声を出してその調べを味わうと、「夏の夜の〜」で小休止する趣があることも否定できない。
(すみません、例により竹岡全評釈当たれてません…古今集研究をやる上であるまじき行為ですね、お恥ずかしい。)
私個人の考えとしては、竹岡氏の指摘が一番すとんと腹落ちする気がします。というか、これ、
▲夏の夜の闇にまどへるほととぎす鳴く一声に
明くるしののめ
みたいに、第二句さえ「ほととぎす」に修飾する形なら、何ら問題は無いんですよね。特に古今集時代もてはやされた「中実」(第三句にメインテーマの景物の名を入れる技法)のことも考えると、一首の重心は真ん中にあってもおかしくはなく、そうなるとむしろ、第二句の「臥すかとすれば」は挿入句で、一首に力技で捩じ込まれていると考えた方が妥当なのでは?
本当の飾り包丁は、どうやら第二句の方に隠されているようなのです。
「臥すかとすれば」の新しさ
このほととぎすの一首を詠んだ時、貫之は二十歳代前半だったと考えられています(もっと若かった可能性もある。目崎徳衛『紀貫之』巻末年表他)。古今集の撰者に栄えて選ばれるのはまだ十年以上後の話、新進気鋭の若手歌人として名を上げていく頃の意欲作です。力が入らないわけがない。
先ほど、「換骨奪胎」の話をしました。先例の表現に依拠することが、彼ら平安歌人の創造力なのでした。むしろ、あまりにオリジナリティを求めすぎると、「みんなが知っている和歌」の枠から外れてしまう。貫之から300年後、革新的な新風和歌を起ち上げた藤原定家が、同時代歌人たちから「新儀非拠達磨歌」(=目新しさを追いかけるあまり、先例に典拠がなく、わけのわからん意味不明歌)と謗られてしまったように、です。
だけど、もちろん時には冒険も必要です。定家ほどとは言わないまでも、ここでの貫之も、先例にある穏当な表現から抜け出して、伝統から逸脱する危険を冒しているのです。というのも、この「臥すかとすれば」の句、意外と先例が見当たらないのです。
「臥すかとすれば」という、まるまんま同表現の句は、先例に全くありません。それどころか、「〜とすれば」という言い回し自体、ほぼ無い。
試しに、国際日本文化研究センター(日文研)が公開している「和歌データベース」で検索してみましょう。このデータベースは、勅撰二十一代集に加え、『万葉集』や主要な私家集、『夫木和歌集』など私撰集の和歌を収録していて、私のような趣味の在野研究者にとっては大変な宝です(新編国歌大観は…なにせお高いですから…)。こちらで「とすれは(濁音は清音で表記)」を検索すると、103件ヒットしました。多いように見えますが、実はこのうち、当該の貫之歌より前か、同時代と見なされる用例は以下の3件しかありません。
花と見て折らむとすれば女郎花うたたあるさまの名にこそありけれ
(ただの花だと思って、折り取ろうとすると、「女」なんて名がついていて、どうも嫌なさまの名であったよ。)
そゑにとてとすればかかりかくすればあな言ひ知らずあふさきるさに
(だからといって、ああすればこうなる、こうすればああなる。嗚呼、何と言っていいかわからない。こちらがよければあちらで差し支えるといった行き違いが起きるので。)
日し暮ればいざとく寝なん夏衣脱ぐかとすれば
明けぬといふ夜に
(日が暮れたなら、さあ、すぐに共寝をしましょう。夏の薄衣を脱ぐか…とすれば、次の瞬間には明けてしまう、というこの短夜だから。)
上掲の三首は、貫之歌との先後関係が不明です。二首目の「そゑにとて」は、何となく古い感じがするんですが、「とすれば(ああすれば)」の用例で、「〜とすれば(=この場合の「と」は代名詞ではなく格助詞)」の用例ではありません。一首目と三首目は貫之歌と同じく「〜とすれば」の用例で、なおかつ《〜しようとすると、…という事態が発生する(ので、〜することが中止されてしまう)》という仕立ても共通しているので、もしこれら二首が貫之歌に先行するならば、貫之はこうした先蹤表現に倣ったとも言えるでしょう。ところが、この場合の「換骨奪胎」には、例よりも幾分冒険的、逸脱的な要素が含まれています。次の二首を見比べてみます。
花と見て折らむとすれば女郎花うたたあるさまの
名にこそありけれ
夏の夜の臥すかとすればほととぎす鳴く一声に
明くるしののめ
それぞれ、「女郎花」「ほととぎす」を第三句に配した「中実」の歌です。すなわちこの二首は、オミナエシやホトトギスといった自然の景物を詠むのに際し、「折らむとすれば」「臥すかとすれば」といった人間側の行動を共に描写しているのです。そこまでは共通していますが、前者の「折る」は花に直接作用する行動なので、オミナエシをテーマに詠む場合でも描写の必然性が高いのに対し、後者の「臥すかとすれば」は、ホトトギスをテーマに詠む場合、描写の必然性はそこまで高くはないといえます。これは、例えばホトトギスではなく「夏の短夜」がテーマであっても同じです。だって、
▲夏の夜はまだ宵ながらほととぎす鳴く一声に
明くるしののめ
のような、自然物に沿った描写でも良いわけですから。貫之は、敢えて「臥すかとすれば」という句を挿入することで、わざわざホトトギス以外の登場人物(それはもちろん、歌の作者自身=貫之かもしれないし、それ以外の架空の人物かもしれない)を一首の世界に喚び出しているのです。
自然賞愛表現
この、「自然物がテーマの歌に、その自然物を愛でる人物の行為を詠み込む手法」を、私は仮に《自然賞愛表現》とでも名付けたいと思います。賞愛の行為としては、「折る」「見る」が一般的ですが、今回のように、「臥す」という動作の妨害、という形で、結果的にほととぎすの鳴き声を賞愛することになった人物を示唆する、という複雑なやり方もあるのです。そもそも、自然物を「歌に詠む」ということ自体が賞愛行為なのですから、全ての和歌は例外なく賞愛表現ではあるのです。ただ、その明示の度合い、メタ表現としての複雑さに差が現れてくる。そしておそらく、そういった複雑さをより強く求めたのは、万葉歌人たちに比すれば、古今時代の歌人の方ではなかったか、と感じるのです。現代人には看取されにくいものの、こうした表現は、結構「新しい」取り組みだったのではないか、ということです。
事実、この貫之の斬新な取り組みに敏感に反応した同時代人がいました。
当該歌は、「寛平御時后宮歌合」に詠出され、『新撰万葉集』に採録、その後『古今和歌集』等にも再録されています。このうち、『新撰万葉集』は、主に「寛平御時后宮歌合」に取材した和歌を、万葉仮名風の表記で記載し、そのすぐ後に、その翻案内容を漢詩で表現する、という独特の構成を持っています。当該歌の翻案である漢詩は次のようなものです。
日長く夜短くして晨に興くるに懶し、夏漏遅明に郭公を聴く。嘯取きて詞人の偸かに筆を走らすに、文章の気味春と同じ。
この漢詩を作った某歌人が、貫之にとっての「良き理解者」であることについて、小島憲之氏は次のように語られています。
この歌の作者紀貫之は、夏の明けやすさを郭公の「一声」によって強調しようとし、唐代の詩語、特に白詩に多くみえる「一声」を「ひとこゑ」に改装する。これを受けて、詩人は一首四句の中にあまたの白詩語を利用して、白詩的雰囲気を描く。これは平安歌人貫之の歌に対する平安某詩人の詩による一つの解釈でもある。歌が詩に先行し、不動のものである限り、詩もなるべくそれに添うことを要求される。そこに無理をすれば、時には和臭(和習)的な詩ともなり、その果ては「拙し」の評を受けることになる。しかし歌意が満たされると、少なくともその残りの詩句は、詩人にとって、表現の自由な天地でもある。そこに詩人は自由の詩界を開く。しかもなおそこは広いかのように見えながら、実は一定の唐詩というワクがあった。それは平安人の心を魅了した「白詩語」という枠内である。
第三章の三「『新撰万葉集』の詩と歌」
詳細は同書に譲りますが、詩中の「筆を走らす」という表現も、白居易が好んで用いた「白詩語」であることが明らかにされています。ほととぎすの声を賞愛し、それを和歌の形で写し取ろうと「筆を走らす」歌人の姿を、漢詩はしっかりと明示しています。貫之の仕組んだ、暗示的な《自然賞愛表現》を、漢詩の方もしっかりと理解して、阿吽の呼吸で詩に興している。当時の文学の最先端が、これらの詩歌の何気ない表現に顕在化しているのです。
まとめ∶夏の夜もいいよね
以上、饒舌になりましたが、貫之のほととぎす詠について紐解いてみました。
まとめは、次のとおりです。
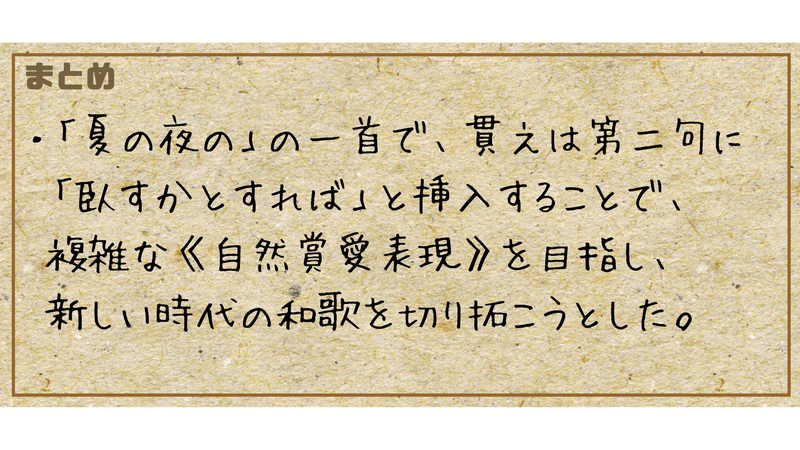
哀しき現代人の身にはエアコン(おやすみモード)無しには過ごせない夏夜ですが、1100年前の貫之の試行錯誤に思いを馳せながら、ホトトギスの鳴き声鑑賞を追体験してみるのも風流かも。とは言いつつ本音は、はよもう少し涼しくなってくれんかなあ…、ってところなんですが。テッペンカケタカよりも、晩夏のカナカナが待ち遠しい。
朝霧の薄闇に鳴くかなかなを児は寝惚けつつ
「あ、はぶらしだ…」
※長男4歳の夏の未明の実話より
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
