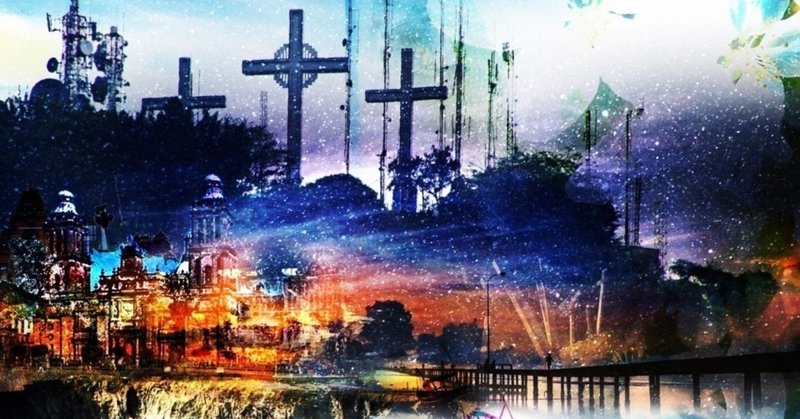
死と政治(安全・安心の政治が忘れていること)
「死と政治」というのは自分が長いこと論文にしようとしていたテーマである。数年前に手を付けたのだが、大学に巣食う「学問の敵」どもからとんでもない邪魔が入って、そのままになってしまった。もう自分にはこれを完成する力は残されていないが、このまま墓に持って行くのは何としてもくやしい。輪郭だけでも書きつけておこうと思う。ちょっと専門的な話になるが、その意義はむしろ学者の好事家的関心ではなく市民的関心の対象であると思う。
古典時代の死と政治
今日では政治と死を結びつける人は少ないが、思想史においては二つは深く関わり合っている。いつぞやも書いたが、「政治 politics 」の語源となったギリシアの都市国家(polis)においては、それは今日とは全く違うものとして理解されていた。この世の存在ははかない。時の流れはすべてを呑み込む。万物は生じては消滅していく。人の一生も短い。しかし、人間は共同体をつくる。そして、共同体の生命は個人の死を超えて永続する。
政治共同体というのは単なる経済共同体ではない。ギリシア人の理解では、経済においては自由はない。それは必要を満たすために必要なことをするという、必要の領域である。これに対して、政治の領域には自由がある。そこは自由人が言論を通じて互いを説得し合い、決定を行い、共に行動する場である。
今日の我々には、せっかくの余暇をそんなことに費やすなんて馬鹿げているように見える。そんな暇があるなら、なぜゲームを遊んだり、買い物したり、カラオケに行ったりしないのか。ギリシア人の理解では、政治こそが人間性を完成させる場であった。ここで偉大な行いをした者は伝説となり、共同体が続くかぎりその記憶が再生産される。こうして個人は死を乗り越え、永遠の生命を得る。つまり、政治は死=はかない生を乗り越える手段であり、そのためにこそ政治共同体がある。
近代政治における死と政治
我々が住む近代国家は、もはやこうした意味での政治の場としては考えられていない。しかし、政治と死との腐れ縁は切れてない。近代国家理論の祖ホッブズは、当時内戦によって挑戦を受けていた政治権力の正統性を、過去の政治理論とは異なる確固とした地盤の上に築こうとする。その際に、万人がもつ死への恐怖にその基礎を置いた。
人間ならば誰でも死を恐れる。天命を全うできるならまだしも、他人の手に殺められるようなことになっては浮かばれない。しかし、他人の暴力から自分を守るためには、個々人に暴力を任しておいてはおぼつかない。主権者にすべての暴力手段を委ね、その代わりに主権者は丸腰の個々人の生命を守る義務を負う。個人は主権者に絶対的服従を誓うが、その代わりに命の保証はされる。そればかりか、主権者が明示的に禁じないところでは、個人は自らの自己保存に必要だと思われることを何でもできる自由を得る。つまり、近代人は暴力への権利を国家に委譲する代わりに、安全と自由への権利を得た。
この理論においては、国家は人がどのように死ぬべきかに関する支配権を得る。誰かが死ねば国家のエージェントが現われて自殺か他殺かを判定する。他殺の疑いがあれば、それは刑法上の犯罪、つまり国家に対する犯罪として、犯人を捜しだし罰する義務を負う。つまり、何が「適法」の死に方であるかは国家により決定されるのである。その代わり、個人の生に関しては、死に関係のないかぎりは、個人の私的な問題として国家の管轄から外れる。そして、古典的な意味での「政治」は失われ、人民が管理の対象となる「行政」に取って代わられる。
このホッブズの理論にはいくつか問題が指摘されている。一つには兵役、もう一つは死刑の問題である。もし国家の義務が生命の保護であるならば、国家は人民が戦争で死ぬことを強制できない。また、国家は死刑も課することができなくなる。そうなると国家の存続が危うくなるではないか。これに対するホッブズの答えはちと苦しい。主権者は徴兵を行う権利を持つが、個人が兵役忌避をすることは不当とは言えない。また、死刑判決を受けた囚人は、あらゆる手段をもってこれに抵抗する権利を留保する。逃げられるのであれば逃げても不当であるとは言えない。
また、先にあげた自死や安楽死についても、ホッブズの理論は明確な答えを与えられない。当然ながら他人の命を左右する自由は国家では失われるが、自分自身の命についてはどうか。自死は法律では禁止され得ないが、自殺ほう助は犯罪とされている。しかし、国家が自死を許さないのは、どうも理論的根拠のある話ではなく慣習上のことである。たとえ自分の生命に対するものでも、暴力の独占に対する挑戦を国家は許すことはできないのかもしれない。
死と国家のいたちごっこ
人々が国家に服従するのは自らの命を他人の暴力による死から守るためである。しかし、たとえ他人の暴力から守られても不慮の死からは逃れられない。病気、事故、災害でも人は死ぬ。貧困や過労によっても人は死ぬ。実際に、餓死したり過労死したりするには十年かかるからといって、それが暴力死でないと言えるかどうかは怪しい。
そうなると、国家は医療、衛生、事故防止、災害対策、貧困緩和策、労働条件規制など幅広い分野での介入を求められるようになる。自由であるべき生においても、だんだんと国家権力により統制される領域が増えてくる。行政の対象としての我々の自由もその分削減される。
要するに、国家の役割を個人を暴力死から保護することに限ったことにより、我々は最大限の自由を得たかのように思えるのだが、実際には国家の役割は思いもかけない領域まで拡大する可能性を有している。しかも、それは個人の自己保存の欲求を満足させるためという一つの目的に偏った形でである。そうして、その欲求を完全に満足させることはいかなる国家にもできないのである。
死すべきものの宿命
なぜそんな逆説が起きるのかと言えば、ホッブズ(と今日のわれわれ)が人間にとっての死の意味の豊かさをとらえきれなかったことが一因となっていると思う。ホッブズは、死への恐れというのは自己保存の本能から生じる情念であり、すべての動物に普遍的なものであると見た。しかし、人間の死に対する恐怖は必ずしも本能的なものには限られない。
死ぬのはつらくはない
死ぬのはつらくはない
死ぬのはつらくはない
ジーザスが私に臨終の床を準備してくれるから
これはあるゴスペル・ブルースの歌詞の一節である。ブラインド・ウィリー・ジョンソンの作とされるが、どうもその起源はさらに古そうで、いろいろなバージョンがあり、教会などで歌われている。ちなみにレッド・ツェッペリンのカバー("In my time of dying")が有名であるが、ジョンソンではなくボブ・ディランのバージョンが底曲になってるようだ。
キリスト教で自殺は禁じられているから、ジーザスによる自殺ほう助の詩ではない。死への恐怖を和らげようとする歌なのである。実際に、ゴスペルにおいては、死に対する恐怖というのはもっともありふれたテーマの一つである。しかし、これらの歌が歌われるのは、必ずしも棺桶に片足を突っ込んだ老人や病人のためではない。そうなると、まだ生物学的にはまだぴんぴんして死にかけてもいないのに、死について恐れを抱く人々が存在したことになる。
トルストイの『イワン・イリッチの死』や滝田洋二郎の映画『おくりびと』で扱われている死も単なる生物学的な意味での死ではない。死とはまた生の終わりでもある。生に終わりがあるという事実を意識することは、死をもたらすものを忌避するだけの無意識の本能とは違って、生自体に関心を向ける。死に際して生の総決算を迫られることを予期して生きることを迫られる。
人間にとっての死への恐怖というのは、無意味な生に対する恐怖なのでもある。意味のない生というのは確実な死への過渡期にしかすぎない。文字どおり生きることはだんだんと死ぬこと以外の意味をもたなくなる。人生に何の意味も見いだせない者にとって、現在の生を来るべき死から隔てる主観的時間の長さは限りなくゼロに近づくのである。
そうすると、死への本能的な恐怖を抑えてでも、意味のある生を生きようとする者が出てきてもおかしくない。「自由を与えよ、然らずんば死を」というのは米国独立戦争の指導者パトリック・ヘンリーの言葉であるが、すでにルソーの思想において自由は自己保存よりも高い価値を占めている。フランス革命も自由のために命を賭す者が増えなければおそらく起らなかった。そして、それはいかなる革命にも言えることである。ガンディーの非暴力主義の抵抗が成功を収めたのも、多くの人が自己保存よりも自由(民族的独立)を高い価値としたためである。
死への本能的恐怖を克服した人という脅威
自己保存の本能からその正当性を引き出す近代国家にとって、死を恐れない人間というのは異星人ともいえる存在である。死を恐れない人間は刑罰という脅しだけでは統御できないから、あとは物理的に除去するしかない。革命家や徹底した平和主義者だけじゃなくて、単独犯のテロリストや通り魔でも十分に厄介な相手だ。自死を望む者も国家の権威にとっては危険な意味を帯びかねない。
たとえば、米国みたいに銃が普及している社会では、死を覚悟したテロや通り魔を予防するのはほぼ不可能だ。これをやろうとすれば、プライバシーの権利をほとんど持たない監視社会を作り上げなければならないし、ちょっとでも怪しい奴は病院か留置所に拘束しなければならない。今日の米国では、ニーチェやハイデッガー、ドストエフスキーどころかトルストイでも病院送りにされると思う。そうして、社会は暴力団同士の抗争みたいな仁義なき戦いを死を恐れない人々と繰りひろげないとならなくなる。すでに、米国では掟なき戦いを補助するようなものが一大産業となって栄えておる。ホッブズの自己保存のための政治は自由主義社会への道を開いたのであるが、けっきょくは全体主義国家に近いものに行きつくことになりかねない。
実は、この書かれなかった論文自体がそれが批判しようとした対象によって迫害を受けるという笑えん話になっている。理性的な人間であれば忌避すべきものという以上の意味を死に与えようとするような思索自体が、精神病理の徴候として危険視される。銃の乱射事件なんかが多発するアメリカの大学では、こんな研究でさえ許容されなくなっている。本人たちがそれを理解していたかどうかは怪しいが、実質的には学問の自由を治安・安全保障のために犠牲にしたのである。どうやら、われらはすでに近未来のディストピア社会に生きている。
政治から疎外された政治
古代の都市国家や他の自治団体が解体して、政治が人生の意味を与えてくれなくなると、広い意味での宗教(○○教という名を持つ特定の宗教や宗派だけでなく、個人の経験を超出するようなものの存在を問うたり表現したりする哲学や芸術も含めて)の意味はますます重要になる。だから、今日でも宗教的なものはなくならない。なくならないだけじゃなくて、政治発展の偏りに対する重大な挑戦を突きつける存在としての重みを増す。言ってみれば、近代宗教は近代政治のアンチテーゼである。政治から疎外された政治自身である。これはイスラム過激派に始まったわけではない。むしろ、近代史を通じて、国家は常にそのアンチテーゼの挑戦を受けてきたのである。
元来、死は政治とは切り離しがたいものであった。それを無理に切り離したのは、生命を育み富を生産する俗なる領域を宗教的情熱が生み出す過剰から保護しようという意図からであった。だが、死と政治の関係が忘れられてしまうと、政治は多くの人にとってどうでもよいものになった。また政治に対する不満が高まれば、宗教や芸術の分野で醸成された情熱が政教分離の垣根をあふれ出し、行政としての政治に慣れた人々を驚かすことになる。政治と死のあいだに健全な距離を保つためには、今いちどそれらのあいだの関係を考えなおしてみる必要がありそうだ。
(自分が「死と政治」というテーマに関心をもったのは、柳田国男の『遠野物語』に関する三島由紀夫の「死と共同体」と題する評論を読んだときである。だが、自分の研究分野への関心に引っ張られて、ぜんぜんちがう方面に研究が進んでしまった。そうして最近、ドイツ思想には別の形で死が政治と関わって来たことに気づいた。ハイデガーの「死への先駆」が有名であるが、同様の考えは同じくヘーゲルの奴隷主と奴隷の対決に見られ、ドイツ的な「歴史」の観念には死や病がはじめからつきまとっている。柳田国男の歴史観、政治観に内在している死も、このドイツ的流れと切り離しては理解できそうもない。また大きな宿題を抱え込んだ。山頂に運んだ岩はまた転がり落ちる。一度始めた旅は旅人本人も思いがけぬところへ導いていく。なかなか終着点にたどり着かぬ。)
*抽象的な話になってわかりにかったかもしれんが、「死と政治」の具体的な応用例の一つが、いま話題の新型コロナウィルスへの対応に伴う危険である。合わせて読んでもらえれば、自分の言わんとすることにもう少し実感をもってもらえるかもしれない。
ここから先は
¥ 100
コーヒー一杯ごちそうしてくれれば、生きていく糧になりそうな話をしてくれる。そういう人間にわたしはなりたい。とくにコーヒー飲みたくなったときには。
