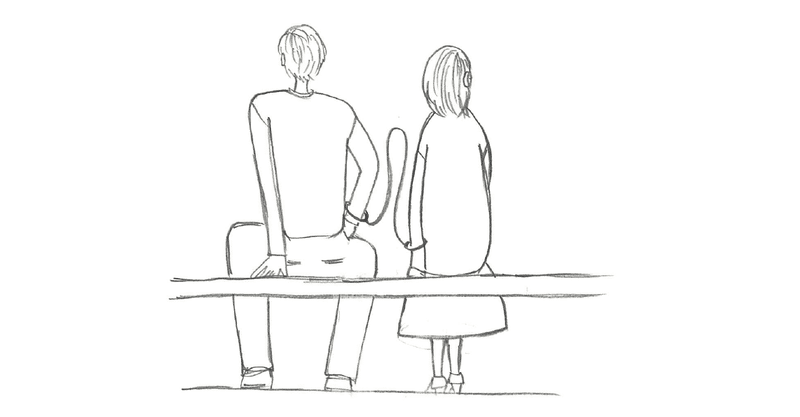
重ならない世界を重ね合わせていくということ
前回からの続き。美術館でケンカ別れをしたあの二人は、いまどこかのカフェでお茶を飲んでる。どうやら、ケンカの後も交際は続いたらしい。
二人ともちょっと変わり者だが、知的で率直な人物のようであるから、もう少し彼らの会話に耳を傾けてみよう。読者諸氏にとっては、私のつなたい講義調の文章よりは学ぶところが多いかもしれない。
その前に、もうしばらくつき合うことになるかもしれない二人なので、名をつけておいた方がよさそうだ。女のほうは愛美(まなみ)さん、男のほうは哲(あきら)くんとでもしておこう。
*****
「今日は来てくれてありがとう。あんなふうに別れたから、正直なところ、誘っても断られるんじゃないかって思ってた」
「わたしも少し反省したの」
「反省?」
「あのね。実をいうとね。わたし、前にも何人かあの絵の前に連れて行って、同じテストをしたことがあるのよ。哲くんにしたのと同じのをね。みんながみんな褒めてくれたわ。いい絵だって。だけど、あの人たちの目には、絵じゃなくてわたししか映ってない、ってすぐわかったわ。少なくとも、哲くんは嘘はつかなった」
「なんだ。じゃあ、ぼくが最初の犠牲者ってわけじゃないんだね。愛美ちゃんも人が悪いや。だけど、その落第した先輩がたには少し同情がなくもないな。連中が嘘をついたって言うのは、少し気の毒だよ。彼らも彼らなりにきみが傷つかないように配慮したんじゃないかな」
「気の毒な女の趣味をけなさないために嘘をついてくれたってわけね。やさしいわね、哲くんは。同じ女を口説き落とそうとした宿敵も、落伍してしまえば戦友ってところね。でも、わたしにはやさしくしてくれなかったのね」
「きついなあ、愛美ちゃんも。でも、ぼくもそいつらの仲間入りするかもしれなかった。ぼくも迷ったんだ。きみを気持ちを害するんじゃないかってね。だけど、後でボロがでるよりも、最初から正直なところを言った方がいいと思ったんだ。それで試験に合格したわけだから、けがの功名だよ」
「そうじゃないわ。合格したわけじゃないの。まだわたしたちは同じ世界には住んでないわ。でも、わたしを傷つけないためにしてもなんにしても、哲くんは自分で本当だと思わないことは軽々しくは口にしない、世界を大事にする人だってことがわかった。だから、対話ができる。もっと話をすれば、ひょっとするとわたしたちの世界が重なっていくかもしれない。そう思ったの」
「その世界を大事にするっていうのはよくわからないけど、じゃあ、仮免取得ってところだね。だけど、その期待に応えられるかどうか、ぼくは不安だよ。だって、趣味っていうのは、理屈じゃないからね。いくら話をしても、趣味は変えられない。ぼくはあの絵をみても、本当に何も感じなかった。美しいともなんとも思わなかった。あの絵だけじゃない。どんな絵でもそうなんだよ。ぼくには美術の価値がわからない。愛美ちゃんが好きなものなら、ぼくも好きになりたいさ。でも、こればかりは自分の意志でどうにもならないよ」
「ちがうのよ。わたしの趣味を押しつけたいんじゃないの。だって、あの絵がいい絵っていうわたしの判断がまちがってるかもしれない。わたしはあの絵が好きだし、きっとほかの人も無心にあの絵を見れば好きになるはずだって、そう思ってるんだけど、もしかするとわたしの趣味に問題があるかもしれない。それは、自分ひとりでは決められない。でも、それならそれで、誰かがわたしにそれを知らせてくれないとならないわ。その可能性も含めて話をしたいのよ」
「うーん。それもむつかしいな。ぼくには美術の知識がぜんぜんないから、愛美ちゃんの趣味判断を云々することもできないよ。でも、きみがあの絵が好きなら、きっといい絵なんだよ。ただ、ぼくにはそれがわからないだけさ。それじゃダメなのかい」
「ダメなの。あの絵にかぎったことじゃないのよ。わたしが大事だと思うものを大事にしてくれる人と、わたしはいっしょに生きたいの」
「もちろん、大事にするさ。愛美ちゃんの大事なものなら」
「そうじゃないの。わたしのために大事にするなら、テストにパスしなかった人たちと同じじゃない。そうじゃなくて、哲くんが自分でそれを大事だと思ってくれないとダメなの。それが世界を大事にするってことよ」
「ふーん。ややこしいんだね」
「・・・・・」
「なんだい?」
「いま、わたしのことを面倒な女だなって思ったでしょ」
「いや・・・・・」
「いいの。正直に言って」
「面倒だなんて思ってないよ。いや、ちょっとは思ったかもしれない。ごめん。だけど、愛美ちゃんは、あの絵が好きな人とでないといっしょに生きていけないって、本気で思ってるのかい? それどころか、その理屈だと、あらゆる趣味が一致しない人とは、世界が共有できないなんてことになりはしないかな。紅茶の銘柄からお気に入りの歌手まで好みが同じじゃないと、いっしょに生きていけないなんて、ちょっと厳しすぎないかな。そんな人に出会うには、一生かかっても時間が足りない。そもそも、そんな人が一人でもいるのかだって怪しい。ぼくら人間は多様なんだから、そんなこと言ったら、みんな孤独に暮らすか、自分を捨てて完全に他人と同じになるか、二つに一つしかない」
「そうね。そういうことになるわね。でも、いくらわたしでも、すべての趣味が一致する人なんて求めていないわ。それは理想よ。完全にその目的は達成できないし、してしまったら幻滅するだろうって知りつつも努力する、そういう理想」
「またややこしい理想だね。でも、なぜあの絵なんだい?」
「理由がないのよ。わたしの心の奥の闇から出てきた選択。だから不安なの。だから誰かの意見を求めるの。たかが絵だけど、あの絵をみて何も感じないなら、きっとその人もわたしを決して理解することができないだろうって、一方では思うんだけど、本当にそうなのかどうかは、わたしにもわからないの。けれども、わたしにとってどうしても譲れない線を引いておかないと、不安になるの。他の面では赦せても、これだけはどうしてもっていう何かを決めておきたいの。そうでないと、なしくずしに自分を失っちゃうような気がして」
「自分らしさってことかい?」
「んー、そうかもしれないけど、それ以上のものだと思う。自分の存在価値だけじゃなくて、この世界とそこにいっしょに住む人々が関わってるのよ。いいわ。話してあげる。わたしの両親はね、仲が悪かったの。毎日、毎日、いがみ合ってたわ。さすがにわたしの目の前で怒鳴り合うことはあまりなかったけど、夜中によく怒声が聞こえて、わたしはベッドで震えてた。ケンカしてないときでも、ひとりが黒と言えば、もうひとりは白、高いといえば、低い。いちいち相手を否定してみせないと気が済まなかった。ビートルズに『ハロー・グッバイ』っていう歌があったでしょ。知ってる? You say yes, I say no. You say stop, and I say go, go, go っていう歌。あんな調子ね。
「父も母もそれぞれにわたしを愛していたわ。だけど、二人は憎み合っていたの。なのにというのか、だからというのか、直接には話をしないの。我慢できなくなって怒鳴り合うとき以外はね。そうじゃなくて、わたしに言うのよ。お互いの悪口を。でも、わたしに仲裁を期待してるわけでもないの。どっちも自分の陣地から一歩も出るつもりがないのよ。まるでわたしに裁判官になって、判決を下してもらおうとしてるみたいだった。自分に有利な判決をね。わたしは引き裂かれたわ。父も母も失いたくなかったけど、どちらかを選ばずにはいられないんだって。そうしないと、どちらからも憎まれるかもしれないって、それが怖かった。
「この陰険な駆け引きが、幼いわたしの心に毒を吹き込んだの。この世界は一つじゃなくて、バラバラなんだって。人それぞれが自分の世界に閉じこもっていて、その世界は重なるところがない。そのそれぞれの世界から、人々は他の世界に住む人々とその世界を憎み続けるんだって。それで、わたしもどれか一つを選ばなないとならない、それはいっしょに生きる人を選ぶことでもあるんだって」
「そうだったのか。それは知らなかった。ごめん。ひどいこと言って」
「哲くんが謝ることないわ。それに同情してもらいたくて、こんな話をしてるわけじゃないのよ。で、ある日、なんでこの人たちはいっしょになったのかなあ、って不思議になったの。父と母の言うことに気を付けて、比較するようになったの。そのうちにわかったのよ。あの人たちは物理的には同じ世界に住んでるけど、主観的にはぜんぜんちがう世界に住んでるんだって。同じものにぜんぜんちがう意味を見出してるんだなって。それで、わたしは決心したのよ。じぶんはこんな風に生きていくのは嫌だって。残りの人生を過ごす人とは、なるべく同じ世界を共有していたいってね」
「その気持は分かるよう気がする。だけど、同じ世界観を共有するのも大事だけど、相手とのちがいを尊重することも大事なんじゃないかな。思いやりとか寛容とか」
「わたしの両親もね、最初から仲が悪かったわけじゃないの。古い写真なんか見ると、二人とも幸せそうに笑っているもの。最初は互いに思いやって、赦し合ってたんだと思うわ。ときどき母はそういう話もしてくれた。相手を傷つけないように世界観のちがいを見て見ないふりしてたのね、きっと。わたしの絵を褒めてくれた人たちのように。でも、人の思いやりとか寛容には限度があるのよ。
「ねえ、知ってる? 人間って嘘つきなんだけど、嘘に対する忍耐は無限じゃないの。嘘をつかれる方だけじゃなくて、嘘をつく方も耐えられなくなるの。嘘を憎む心が誰にでもあって、それが思いやりだったものを最後には裏切りに換えてしまう。相手だけじゃなくて自分自身に対するね。だから、我慢のひとつひとつが怨みになって積み重なっていって、しまいにははじめっから何もかもが嘘っぱちだったって信じたくなるのよ、きっと」
「・・・・・」
「ごめんね。嫌な話を聞かせて。もううんざりした?」
「いや。そうじゃないよ。ちょっと考えさせられたんだ。何て言ったらいいのかな。夫婦とか恋人ってのは、最小単位の社会なんじゃないかなって。二人以上の人間が集まれば社会ができる。まったく同じ人間はいないから、二人とはいえ、その間にはちがいがある。異なる趣味をもっている。趣味であるから、その根拠を相手に説明できない。だから、互いに尊重して、赦せるところは赦し合わないとならない。だけど、それだけじゃ、この小さな社会でさえもたない。人はいつかは嘘にうんざりする。たとえ思いやりのための嘘であっても。とすると、何百万人、何千万人からなる社会はいったいどうやって可能なんだろうって。あ、いや、ごめんよ。愛美ちゃんの話をしてたんだな」
「ううん。やっぱり話をしてよかったわ。そんなふうに考えることができるのね、哲くんは」
「いや、ふとそんな考えが浮かんだだけさ。あれ、もうこんな時間だよ。どうかな、愛美ちゃん。今日はご飯に誘っても断られたりしないよね。もちろん、愛美ちゃんともっといっしょにいたいからなんだけど、ぼくも少しこの話題に興味が湧いてきた。まだぼくは愛美ちゃんの言うことに納得がいかない点がたくさんあるんだけど、でも、もっと話を聞かせてもらいたいんだ。ひょっとしたら、きみとあの絵のことも、もっと理解できるようになるかもしれない」
「ずるい誘い方ね。そう言われたら、断るわけにもいかないわね。いいわ。特例でつきあってあげるわ。少なくとも一つ、わたしたちの世界に重なり合う部分ができたんですもの」
ここから先は
¥ 100
コーヒー一杯ごちそうしてくれれば、生きていく糧になりそうな話をしてくれる。そういう人間にわたしはなりたい。とくにコーヒー飲みたくなったときには。
