
国際政治経済学講義ノート 4(自由主義-リベラリズム)
さて、三つのイズム(自由主義、現実主義、マルクス主義)のうち、いちばん古いものは自由主義です。他の理論的伝統にも前史があるのですが、今ある形で現われるのは自由主義に対する批判としてです。なので、自由主義から始めるのが他の理論的アプローチを理解するにも都合がよいです。
もう一つ自由主義を最初に学ぶ理由があります。現在わたしたちが住んでいる世界における経済秩序というのはだいたいリベラルなものです。もちろん自由主義者が理想とするようなものからは程遠いですし、ここ数年は反自由主義的な動きが広がっています。それでも自由主義を理解することなしにはわれわれの生きる世界も理解することができないと言えると思います。
第一部でお話したように、これは英国と米国というふたつのリベラルな覇権国によって19世紀以来築かれてきた秩序です。何度も危機に瀕して崩壊しかけたんですが(一度は実際に崩壊しました)、まだその生命を保っていると言えます。
戦後に日本の生活水準が飛躍的に向上したのも日本人が働き者であったからかもしれませんが、このリベラルな国際経済秩序がなかったら不可能であったと思われます。日本には真の自由主義者といえるような人は少ないのですが、実は最大の被益者の一人であるとも言えます。ですから、日本人が自分たちを理解するために、改めて学ぶ必要が余計にあるんではないかと思います。
自由主義の基本信念
さて自由主義です。ひとことで言ってしまえば自由を重んじる主義です。この自由というのは個人の自由ですから、個人主義とも深い関係があります。しかし、ただ個人は自由であるべきだ、ひとそれぞれでいいじゃないか、というだけでは「主義」と呼べるような思想になりません。思想としての自由主義の要諦は、個人の自由と公共善が対立しない、いやそれどころか個人に自由を許すことが公の利益を実現する最善の手段である、という主張にあります。
この主張は自明ではありませんね。直観的には真理でないように思えます。特に個人を尊重する価値観が希薄な日本のような国では、みんなが好きなように振る舞うことは公の利益に反するとしか思えない人が多いはずです。では自由主義者はいかにしてこの一見矛盾するような主張を成し得たんでしょう。それを考えてみましょう。
リベラルの基本的信念はだいたい次のようにまとめられます。
1.個人は合理性を有する
リベラルの人間観の根幹をなすのはその合理性です。個々人は一人一人に合理性が生まれつき備わっている。だから潜在的にはすべての人間が合理的たりうる。この信念が、個人は自由であるべきであるし、また個人間に道徳的な序列はないとする平等観の根拠にもなります。
ではこの合理性とはどういうものであるかという問いが浮かんできます。これには諸説があるのですが、ここでは与えられた目的を達成するために最良の手段を選択する能力と考えておいてもらえればよいです。例えば同じものを手に入れるのであれば、より少ない労力とかより少ない費用で手に入れる手段を選択する。もちろん知識とか情報の差で認識できる選択肢の幅が変わってきますが、同じ選択肢を与えられればすべての人間が同じ選択をするはずである。それが合理性という言葉の含意するところです。
2.市民社会(市場経済)は自生的・自立的である
そうした合理的な個人からなる社会のことを市民社会と呼びます。この市民社会にはもとは市場経済も含まれていました。市民社会という概念は、第一部で説明した国家という権力機構に対抗する概念として出てきたものです。つまり強制力を行使する権力機関がない社会にも秩序が備わっていて、だいたいにおいて人々は自ら定めたルールに従って、平和に暮らすことができる。そういう意味が含まれています。
要するに、社会(市場)が存在するのに国家は必ずしも必要でない。社会(市場)は勝手に生じて、また国家の手を介さずに勝手に機能しうる。そうリベラルは信じます。
経済学の父と呼ばれるアダム・スミスという人は、この市場の自律的な自己調整機能を「見えざる手」と呼びました。まるで「神の見えざる手」が働いているように、誰も指令を出さないのに、必要なものが必要なだけ生産され、それをもっとも有効に使用する人のところに届く。その不思議な性質をこういう比喩で言い表わしたわけです。
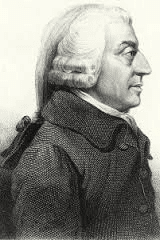
Adam Smith
市場の自動調整機能を説明する際に「均衡(equilibrium)」という力学の用語が経済学にも導入されています。各種の力がちょうど釣り合って静止しているような状態です。静止といっても死んでるのではなくて、多様な力がうまいこと釣り合っていて、外から見ると何ごとも起きてないかのように見えるわけです。ブランコや振子、モビールなどを思い浮かべてみてください。外から力を加えると揺れはじめますが、最後には同じ状態に戻る。そのような機能が市場に具わっていると考えるのがリベラルの考えです。

CC 表示-継承 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1168979
3.国家は必要悪である
社会や市場が自生的で自律的であると考えるリベラルにとって、国家という権力組織は社会には基本的に外生的なものです。役に立てば使うし、そうでなければ使わない。
そして、リベラルは国家の役割を認める人たちです。つまり、社会や市場だけではうまく処理できない問題があることを認めている。第一部でお話しした「市場の失敗」です。それに私的所有権の保護や経済的取引のための統一されたルールの制定や執行も国家にやらせた方が効率がよい。
だからリベラルは国家を肯定しますが、あくまでも必要悪としてです。権力による強制は原則として自由の侵害であるから、少なければ少ないほどよい。ここから出てくるのが「限られた政府(limited government)」という考えです。政府の権力の使用目的には厳しい制限が課せられるべきであるという考えですね。
特に個人の自由を守るために国家を利用するわけですから、絶対に侵害されてはいけない個人の権利というものがある。これがリベラリズムにおける今日の立憲主義および人権の位置づけです。だから、たとえ弱者のためであってもある人の人権のために別の人の権利は侵害しても合憲であるなどと唱え始めると、もうそれは「人権」や「憲法」とは別のものになりますね。少なくとも自由主義的なものではなくなります。
4.市場は放置されたとき最善の働きをする
これは2.と3.から必然的に帰結しますね。市場が自生的・自律的であり、国家が必要悪である以上、国家による市場への介入は必要最小限に抑えるべきである。つまり、財・サービスの生産や分配に関することは自由な個人の選択に任せておく。暴力を背景とした強制力を使った介入は、それがなければ最善の結果が出ないことがはっきりしているような場合だけに許される。
このような原則はレッセフェール(laissez-faire)と呼ばれたりします。フランス語で「好きなようにやらせておく」「放っておく」という意味です。
このため、リベラルは政治と経済を厳密に区別する傾向があります。第一部でお話ししたような政治学と経済学の分断も、実はこの自由主義思想の影響があります。自由主義の功績は暴力や強制力がものを言う国家生活と自由な個人による合意に基づく社会生活を区別したことなんですが、勢い余って国家と市場の相互作用を見失ってしまったと言えるわけです。
ただし、今日では、市場自体が大組織化し官僚制化してしまいました。自由で平等である個人ではなく官僚的大組織(大企業や半官半民の政府機関)が市場の主要なアクターになっているということです。だから市場が個人の自由を制限し、また不平等を生み出すものになってしまいました。それで思想においても市民社会という概念から市場が分離しています。そのために、以前の国家対社会という二元的対立構図が、今日では国家、市場、社会の三つ巴になっています。
これに対応してリベラル陣営も分裂し、市場に軸足を置く経済的リベラル、市民社会に軸足を置く政治的リベラル、というように多様なリベラリズムが存在するようになっています。
政治的リベラルは市場の行き過ぎを抑えるために国家に頼ろうとする人が増えたので、今日「リベラル」というときは、普通は福祉国家のようなものを支持する人々のことを指しますね。しかし、それでもリベラルである以上は、市場というものを完全には否定していません。問題はあるけれども公共善を達成するためには欠かせない制度であるという意識がある。少なくとも個人の自由を侵害せずには市場を放棄することができないと信じています。だから集団農場とか計画経済みたいなものはやはり否定するんです。
近年はこの信念が怪しい「リベラル」も増えています。特に日本の場合は個人の自由を重んじる伝統がもとから弱かったので、「リベラル」を自認する人たちのなかには本当にリベラルなのかどうか怪しい人たちの方が多いです。これも言葉の定義以上の問題なのですが、弱者を守るためなら国家は個人の自由や権利を躊躇なく制限すべきであるとする主張は、もはやリベラルの範疇からはみ出ていると考えた方がよいのではないかと自分などは思っています。
自由貿易理論
さて、自由主義者は国内においても市場の擁護者ですが、国際経済においてもやはり自由な移動を支持します。モノでも人でも金でも情報でも国境を越えてなるべく自由に動けることが望ましい。もちろん、必要であれば国境管理も認めますが、原則自由がよいという考えです。
個人の自由を守る立場から当然なんですが、自由貿易論者の論拠はその点ではなく、自由貿易こそが経済的に最適な結果をもたらすという理論に基づいています。つまり自由貿易は道徳的な観点からも功利主義的な観点からも管理貿易よりも優れていると考えるわけです。
自由貿易理論を考えたのはデイヴィッド・リカルドゥという英国人です。簡単に説明すると、彼の理論はアダム・スミスが説いた分業の利益を国家間の分業に適用したものといえます。それぞれの国がもっとも得意なものの生産に特化することにより、生産量が増加する。そして国内で消費されない部分を互いに交換することによって、世界経済全体の効用が最大になる。そういう理論です。

David Ricardo
この主張が真であれば、そこからいくつかの帰結が導かれます。第一に、一つの国が何でも自分で生産しようとする自給自足の追求は非合理的ということになります。そんなことをすると、質の悪い商品に高い値段を支払うことになり、国民が損をする。この「国民」というのは消費者のことです。管理貿易というのは、特定の集団の特殊利益のために他の国民=消費者が犠牲にされるものであるというのが自由貿易論者の主張の一つです。
第二に、自由貿易はそれに携るすべての国に恩恵を与えるものであり、利害の対立はあり得ないというものです。リベラルにとって経済はゼロサムゲームではなくプラスサムゲームです。ある国にとっての得が他の国にとっての損にはなりません。特定の集団は損をするかもしれないけれども、国全体(つまり消費者全体)としては得する。だから、国同士の利害対立は最終的には調整可能である。むしろ国家が特殊権益を守ろうとして下手に介入するから、この調整機能の働きが阻害されて、国際間の対立が生じる。このようにリベラルは考えます。
第三に、そうであるなら国家間に自由貿易を推進すれば、世界はますます平和になるはずである。貧困には別の原因もあるから消滅はしませんが、少なくとも今よりは減少するはずである。特に、国家自体が民主化して、全体の利益のためにより合理的な意思決定をするようになれば、自由貿易も推進される。最終的には民主的な国家が自由貿易によってつながった平和な世界が訪れる。
自由主義者の理想的世界秩序
もうお気づきでしょうが、この自由主義というのはコスモポリタニズムやグローバリズムとも親和性が高いです。世界のどこのおいても人間は合理的な存在であり、自由で平等であるべきである。特に消費者としては誰でも質のよい財をできるだけ安く入手することを喜ぶわけだから、国民性のちがいなど問題にならないほど同質的である。普遍的な世界市民というのはまずは普遍的な消費者として想像されたんですね。
そして、国家の介入を排除してモノやヒトの動きを自由化して行けば、最後に行きつくところは国境を越えてグローバルなレベルで統一された一つの市場ですね。個人はどこで何を生産し、どこで誰にそれをいくらで売り、またどこで誰によって造られた商品を購入し、またどこで消費するかを自由に選べる。
市場が自生的なものであったように、リベラルは国際市場やグローバル市場もまた自生的なものと考えます。誰が強制したものでもない。自由な個人が自由に交流しているうちに自然にでき上がってくる。ただ国家権力が邪魔をしなければよいわけです。
一部のリベラルは、この市場のグローバル化に伴って、国家というものもまた進化していくと考えました。つまり世界政府です。そうなればもう国民も国家もない。あるのは世界市民だけです。さすがにこれは現実的には無理だろうと考えたリベラルも多いのですが、理論上はそれが理想のリベラル世界秩序であることは否定できません。
リベラリズムが生まれた世界というのは、まだそうした考えが机上の空論にしか過ぎない時代でした。だからリベラルはまた理想主義者という側面をもっていました。しかし、19世紀以来、この理想の一部が実現していきましたから、今日ではむしろ現実がリベラルの理想に近づいてきた。
だけども、他方で理想の常なんですが、実現したユートピアというのは思ったよりよいところではないということにもわれわれは気づきはじめた。今日のリベラルが世界的に傷ついたブランドになったのも、一つはそうした認識が広まったからかと思います。しかし、リベラル・ユートピアに代わる理想像を提示できる人はそうは多くありません。それがリベラリズムがいまだに強い生命力を保っている一つの理由かと思います。
コーヒー一杯ごちそうしてくれれば、生きていく糧になりそうな話をしてくれる。そういう人間にわたしはなりたい。とくにコーヒー飲みたくなったときには。
