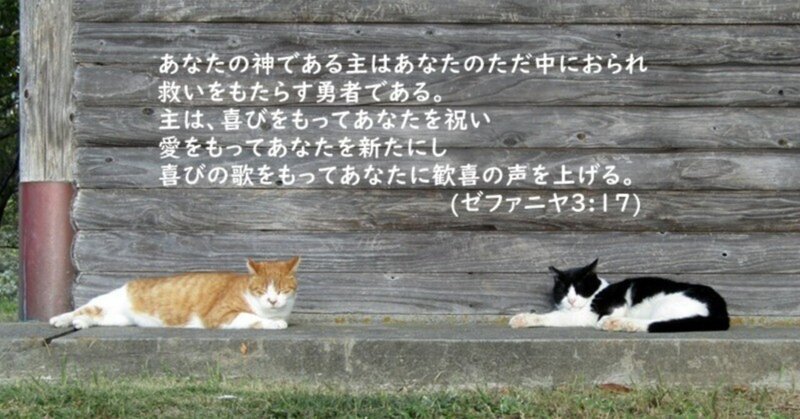
愛はどこから (エフェソ3:14-21, ゼファニヤ3:14-17)
◆教会が祈る
エフェソ書を開きます。パウロが書いたとされている書簡ですが、ほかの書簡を書いたパウロとは別人ではないか、という研究者がたくさんいます。専門的な議論をお伝えするのが目的ではありません。パウロという特定の人であれ、その信仰を受け継いだ人であれ、神からの言葉として受け止める上では、根本的には問題ではない、という態度で、聖書から大切なものを受けてみようと考えています。
ここは美しい祈りです。こうなると、誰が祈ろうが、共に祈ればよいと思うのです。この祈りは、よく見ると、教会の存在が見え隠れするような気がしませんか。もちろんエフェソの教会への手紙ですから、受け手は教会です。「教会」という言葉が出てくるのはようやく最後に来てからですが、教会のために祈り、また教会があなたのために祈っているよ、というメッセージを、私は感じるのです。
あなたのために、あなたの教会は、祈っているでしょうか。教会の規模がどうとかいう問題ではなく、特定の人の名が週報に挙がるほかには、祈る気持ちを失っている教会も、残念ながらあるようです。もしそのように、教会の人が自分のためには祈っているようにはとても思えない、というような人がいたとします。寂しいことではあります。けれども、絶望はしないでください。聖書の中でパウロか誰かが、このように祈ってくれています。イエスが祈ってくれています。これが神の言葉であるのなら、神はあなたの味方です。
まさか、そんなことあるものか、と嗤う人がいても、心配はいりません。あなたが、それを信じていればよいのです。あなたが信じているかどうか、それがあなたと神との関係なのです。そのくらい能天気でいられるのが、神を信仰する、ということなのです。
この書かれた祈りが、具体的にどういう場面で祈られたか、何をイメージしているか、それは研究する人がいても構いませんが、それを説き明かしたとしても、私にはあまり意味がありません。私が、この祈りを自分と結びつけることができるのであれば、それで十分です。あなたも、そう思いませんか。
この祈りの中から、二つの点に注目しましょう。そして、私たちもそれに重ねて祈りましょう。
◆内に働く神
まず「内」という言葉で表すものに注目します。
16:どうか、御父が、その豊かな栄光に従い、その霊により、力をもってあなたがたの内なる人を強めてくださいますように。
17:あなたがたの信仰によって、キリストがあなたがたの心の内に住んでくださいますように。あなたがたが愛に根ざし、愛に基づく者となることによって、
20:私たちの内に働く力によって、私たちが願い、考えることすべてをはるかに超えてかなえることのできる方に、
ここに、「内なる人」「心の内に」「私たちの内に働く力」と、三つの「内」に言及されます。短い祈りの中に三度も現れるからには、決して軽いものではないと思わせるものがあります。
私たちの「内なる人」とは、見かける肉体的な自分ではなく、何か魂のようなものを感じさせます。聖書は、霊肉の二元論で人間をかたづけることはしないので、気をつけなければなりません。でも私たちは、外の見た目での人間の一面では捉えきれない、内部というものを漠然と感じています。気力とか心とか呼ぶこともあります。さしあたりそのようなものとして捉えておきましょう。
これが「弱い」のだという前提があるからこそ、「強めてくださいますように」と祈っているに違いありません。弱いからこそ、強めてください、と祈るわけです。だって私たちは、すぐに心が折れるではありませんか。
だとすれば、キリストが「心の内に」住むように、との祈りは、元々キリストはそこには住んでいなかったからに違いありません。ひとの心には空洞があり、それは神でなければ埋められない、という言い方が、時々説教でもなされます。これを神の側から見ることを想像すると、神はキリストという形をとって、あるいは聖霊という形をとって、私たちの心の穴を埋めに、私たちの外から、私たちの内へとやってくるのでしょう。
そうして、私たちの内に来たら、内側から私たちを立たせてくださることでしょう。神の力が、「私たちの内に働く」のです。
◆神は超えたところから
すると、私たちは神と出会うために、私たちの内を探ることが必要になるように思われるかもしれません。確かに、私たちはが自分の内へと深く魂を探ることにより、そこで神に出会うというような体験をする場合もあるでしょう。しかし、神の力は、私たちの外から、私たちの内へと働くという段階を、ひとつ心得ておきたいと思います。自分で悟りを開くとか、自分に正直であればよいとか、そうした原理に迷い込むことがないようにしたいのです。
たとえば、私たちはキリストの愛を覚えますが、それは、確実に私たちの外から、私たちを超越したところからもたらされます。
19:人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができ、神の満ち溢れるものすべてに向かって満たされますように。
私はここで立ち止まってしまいました。後半が何を言っているか、分からなかったのです。調べてみると、どうやらこの後半は、多くの聖書が訳すのに苦労しているようです。ルターも苦し紛れに訳したようで、以後西洋の訳ではそれが踏襲されているのですが、確かに元の言葉は、不思議な表現がとられているのだそうです。
田川健三氏は、こうしたところに非常に熱意をもって挑む方で、およそこのように考えているようです。キリスト者として成長していくならば、「神の満ちるもの」の中へといつか達することができるであろう、と。宗教的に成長していくことを願っているよ、というような気持ちで読むとよい、そのようにアドバイスしてくれています。これならばスッと胸に入ってきます。私もそのように受け取ることにしようと思いました。――あなたがたが、キリストの愛を、自分の知恵で片付けようとしないで、自分の思いを遙かに超えた次元から来るものとして受け止めることによって、どうか霊的に成長し、素晴らしい神の世界へと導かれることを祈ります。
神は、私たちの外から、私たちの内に働くお方です。そして私たちの心の内に、キリストが住んでくださるのです。人にはその謎が解明できたり説明できたりするものではありません。私たちの願いも想像も、すべてを遙かにめちゃくちゃ超えた神が、私たちの内側から力をもたらしてくださいます。
元々神の思いが人のはかることを超えているのは、当然のことでしょう。私たちの理解や想像を超えたところから、しかも私たちの内側に、神が臨んでくださいます。私を超えたところから、神は力を注ぐ、そのことを覚えておきましょう。神は私を遙かに超えたところから、私の内に働くのです。本日お伝えしたかったことの要点は、これに尽きます。
◆キリストの愛
けれども、もう少し味わい深く聖書に触れていきましょう。今「キリストの愛」というものが突然登場しました。クリスチャンの皆さまは、いまさら「キリストの愛」だなんて、分かりきっているではないか、とお思いになるかもしれません。私も、改めて「キリストの愛」とは何かをここで蕩々と述べることは致しかねます。
ただ、それは十字架の愛と呼んでもよろしいでしょうか。キリストの愛は、癒やしや祈りや、放つその言葉の一つひとつにもこめられていることは承知の上で、それでもあの十字架に架かった主の姿の中に、最高度の「愛」というものを見出すことは、咎められることではないと思うのです。
キリストの愛を思えば、もう涙が出て止まらない、という人がいます。自分が罪を犯したため、自分こそ十字架に架けられて当然の者であるのに、キリストが十字架に架かったことでそれが赦され、自分はいまこうして生きているのだ、という思いが消えることがない、というのです。私のためにキリストが代わりに死んだ、という事実を弁えて、涙するのです。
他方、十字架刑に処せられたということだけを見るならば、それはただの極悪犯罪人である、としか思えないという人もいるでしょう。そんな人間にだけはなりたくない、と忌避するわけです。いや、中には同情する人もいるはずです。自分が罪を犯したのではなく、美しい愛だ、と認めることだって、きっとあるでしょう。心ある人は、それはどんなにか痛かっただろう、という気持ちも懐くでしょう。
けれども、それが自分とどう関係があるのか、という点においては、何も思うものがない、と考える人がいるのです。それは至極当然の感覚なのだろうと思います。二千年前の出来事が、いまの自分と深い関わりがある、というようなことを、教会では話しているが、それについては全く感じるところがない、というのです。これもまた、それはそうだろう、というふうにしか思えません。実際、素直に考えると、そうに決まっていると思うのです。
いやいや、聖書のことは勉強した、だから自分は十字架の愛が分かっていますよ、と口にする人がいても、やはり自分とキリストとの関係が、頭で考えたという程度の人は、十字架について冷たく論評したり、全くリアリティのないままに、ただの教義として十字架を説明するケースがあることには、注意しなければなりません。ある意味で、これが一番質が悪いのです。自分は分かっている、という顔をしておきながら、実はキリストとの関係が結ばれていないとなると、聖書を的確に語ることがてきません。京都に住んだことがなくて、本をいくらか読んだだけで、俺は京都通だ、と豪語するようなもので、それが京都について教えてやるよ、と身を乗り出しきても、それは聞くだけよけいに間違ったことを吹き込まれるだけではないでしょうか。
キリストの十字架とその死が、自分とどう関係があるのか。信仰においては、そこが一番大切な本質である、と言ってもよいでしょう。その愛が、どんなに広いか・長いか・高いか・深いか。それが人知を超えた愛であり、さらに超えたところから愛がこの私に迫ってきたのだ、と驚くのが信仰だと思います。しかも、そのキリストの愛に根ざして、その愛に基づいて、そういう者たちがつながって教会という形になっていくように、手紙は祈っています。この祈りが、愛による教会を形成していくことでしょう。そのような祈りを、改めて祈りたいと思います。
17:あなたがたの信仰によって、キリストがあなたがたの心の内に住んでくださいますように。あなたがたが愛に根ざし、愛に基づく者となることによって、
18:すべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものかを悟り、
19:人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができ、神の満ち溢れるものすべてに向かって満たされますように。
◆愛と命
日野原重明さん。もしかすると、もう過去の人になってしまったでしょうか。2017年に亡くなったとき、105歳でした。生まれたときは中国の「辛亥革命」直前であり、まだ元号は「明治」でした。聖路加国際病院に1941年に入ってから、亡くなるまで現役医師を務めました。牧師の父親をもち、信仰の心で医療にあたり、予防医学や終末医療の面で、日本の医療をリードしてきました。1970年のよど号ハイジャック事件に遭遇し、人生観が変わったとも言っていました。地下鉄サリン事件の時の医療リーダーを執ったことでも知られていますし、「成人病」という言葉を「生活習慣病」という名称に変更したことでも知られていますが、いちばん知られているのは、その著書でしょう。ベストセラーを含め、300冊以上もの本を著しています。晩年は、睡眠時間を削って執筆に追われていたといいます。
その著書の中で、最近『生きることの質』を手にしました。講演集ですが、その中には、自ら仰るのですが、他ではめったに語っていないという、「愛」をテーマにした講演が収められています。
人は死を避けられない。だから、死を前にして医学は結局は負けてしまうこと。しかし自分の命を愛することが必要であり、医療従事者としては、目の前のその人の命を愛することが求められること。だが、報いを望むものではないということ。その愛は、天性のものに頼らず、学ばねばならないこと。その人が、自分の人生には意味があったと思えることを求め、病む人の心がどこに向いているかを気遣う医学でありたいこと。そんなことを語っていました。
しかし、幾つかの講演で度々強調することも、そこにありました。愛とは、互いに相手の顔を眺め合っていることなのではなく、同じ方向に二人で一緒に眼を向けることだ、というのです。これは、サン=テグジュペリの作品から、アン・リンドバーグが引用した言葉である、と日野原重明さんは紹介します。そしてこのことを随所で強調しています。
愛し合う二人というのは、二人が同じ方向を見て歩むこと。それは、一つの人間の知恵に過ぎないかもしれません。けれども、若いときに私もこの言葉をどこかで知って、いたく感動した記憶があります。これは、人と人とが愛し合うときに、きっと励みになる言葉だと思うのです。
キリストの愛は、私に注がれます。私はキリストの方を向いていますし、キリストも私を見ていてくださいます。しかしこれは、人間同士の営みではないからです。キリストは私を超えたところから愛を注ぎます。私の内に、働いてくださいます。だから、しっかりと向き合うことが必要だと思います。けれども、キリストの愛の下にあって、「互いに愛し合いなさい」と命じられたキリスト者たち、そして教会共同体に結ばれた者たちは、向き合うことよりも、共に同じ方向を見つめて歩むのだ、というのは本当だろうと思うのです。
そのようにして共に歩む者たち、つまりキリストの名の下につながる者たちは、互いに神の国を目指して励まし合います。前に、日野原重明さんはホスピス医療の普及に努めたとご紹介しました。限られた命である点は誰しも同じではありますが、現実に限られた命の時を突きつけられた人の切実さは、他人がどう想像しても共有できないものを有していると思います。そういう方のSNSに、私は「いいね!」を押すことがなかなかできないでいます。「悲しい」とか「大事にしたい」とかいう意味のボタンもありますが、そんなパターン化したメッセージで済ませられないと考えるのです(反応したこともありますが)。黙って毎日見ては、祈る、その繰り返しです。その気持ちは、伝わらないかもしれません。けれども、祈りは、イエス・キリストを通してつながっていることを信じています。反応がない、とがっかりしていたら、申し訳なく思います。が、神はがっかりなさらない、というところを信じて、ボタンやありきたりの言葉では表現できない呻きを、祈りに乗せているのが実情です。
父が、遺言のように、後のことを、と私に言います。これこれをよろしく、と。けれども、私は応えるのです。「分かりませんよ。こちらが先になるのかもしれないのですから」と。その言葉に嘘はないが、それを聞いて父は笑います。まぁ、笑ってもらえてよかった、とは思います。
命の行方は、しかし誰にも計算できないものです。明日のことは、否5分後のことさえ、誰にも分かりません。自分で左右できないことが、人生にはあります。ただ、神がそれを握っておられるという点だけは、揺るぎなく信頼しておこうという気持ちです。できることは、せめて命の行方を思うとき、その思いの中核に「愛」という言葉とその意味とを置いておきたい、と願うことです。実にその「愛」こそ永遠であるのですし、聖書がいう「永遠の命」というものも、そこにあるのだ、といつも思うからです。聖書から、神はそのように語りかけ、教えてくれたのだ、と信じるからです。
私個人の、どうしようもない罪。しかしその罪を赦す方がいる。十字架の上にキリストがいて、その言葉と行動が、私の暗い道の続きを照らす光となっている。私の外から、私の知りえない、私を超えたところから、キリストが愛を以て臨んでいる。キリストは私の内に来てくださり、住んでくださる。ちっぽけな私の心が、限りなく広く・長く・高く・深いものに満たされる。私は内側から強められ、変えられて、新しい命に生かされる。この瞬間、それは永遠と結びつき、神のものとされる。それを説くのが「キリスト教」なのだ、と私は叫びたいばかりです。
◆ゼファニヤ書の祝福
旧約聖書に、ゼファニヤ書という小さな預言書があります。南ユダ王国への神の裁きを語りますが、やがて救いへの道が拓かれることを告げます。バビロン捕囚を背景としているであろうことは容易に想像がつきますが、この書のことが、ふと思い出されたので、ご紹介します。
14:娘シオンよ、喜び歌え。/イスラエルよ、喜びの声を上げよ。/娘エルサレムよ、心の底から喜び祝え。
15:主は、あなたに対する裁きを取り去り/敵を追い払われた。/イスラエルの王なる主はあなたのただ中におられる。/もはや、災いを恐れることはない。
16:その日、人々はエルサレムに向かって言う。/「シオンよ、恐れるな/力を落としてはならない。
17:あなたの神である主はあなたのただ中におられ/救いをもたらす勇者である。/主は、喜びをもってあなたを祝い/愛をもってあなたを新たにし/喜びの歌をもってあなたに歓喜の声を上げる。
「娘シオン」とは、エルサレムの町一帯を指していると見てよいでしょう。そこには主のための神殿がありました。旧約聖書の時代では、神殿は、神がそこにいるということを象徴しています。新約聖書では、世の終わりに、このエルサレムがすっかり新しい神の都として現れ、永遠に輝くのだ、というストーリーが立てられていくことになります。
そのエルサレムに「心の底から喜び祝え」と預言者は言葉を向けます。そして「主はあなたのただ中におられる」という宣言が二度繰り返されます。
今日、私は新約聖書から、神は私を遙かに超えたところから、私の心の内へと来て働いてくださる、という良い知らせを申し伝えました。ところがいまゼファニヤ書という旧約聖書においても、神はいずれ人々の「ただ中」にいるとのメッセージが送られていました。その結果、主は「喜びをもってあなたを祝」うこと、「愛をもってあなたを新たに」すること、「喜びの歌をもってあなたに歓喜の声を上げる」こと、こうしたうれしい知らせが次々と届きました。これを受けて、素直に喜ぼうではありませんか。
心の底から、喜ぶのです。人前で恰好つけるのではありません。建前で喜ぶのではありません。心の底からです。なぜなら、そこにキリストがいてくださるから。神が外から、私の内に来てくださるから。「あなたのただ中に」というのは、預言者はイスラエル民族のことを思い浮かべていることでしょうが、文字通りに「あなたのただ中に」でよいではありませんか。教会の中、それでも構いませんが、もっとあなた個人の中で、よいではありませんか。それが、信仰というものなのです。
主は喜んで、あなたを祝福します。愛を以て、あなたを新しくします。今日、いまここで、あなたは新しくなれるのです。
◆あなたは新しくされる
聖書の中の物語や教えは、空想上のお伽噺ではありません。ただの作り話ではありません。人類の半分近くは、旧約聖書を大切な書物だと扱っています。世界の四人に一人くらいでしょうか、そのくらいの人々は、新約聖書をも信仰の書と理解しています。教会に属さない人もいます。教会がない国や地域の人もいます。また、教会組織が信仰の点で崩れたとしても、個人的に信仰の火を燃やし続けている人もいます。このような人たちは、組織的な教会のメンバーではないにしても、神は、聖書の中から語りかけてくださいます。聖書の言葉として、パウロが祈り、イエスが祈ります。名もなき祈り手が、私のために、あなたのために、祈っています。そこに聖書がある限り、聖書の中の文字が、それを保証しています。私たちに、信じる心さえあれば、神の支えが、そこから与えられます。
キリストの、広く・長く・高く・深い愛が、私たちを遙かに超えたところから、私の内に臨みます。私たちは、その愛に根ざして、そこから養分をもらいます。すると心の内にキリストが来てくださり、私は強くなります。折れず、凹まない心を与えられます。そして自分の罪にさえ気づいて、イエス・キリストの十字架が救いであると信じたならば、私は新しくされます。新しい命に生かされて、ここから歩み始めることができます。私の目には、それまでとは違った景色が見え始めます。
昔、その「それまでとは違った景色」を見た方がたくさんいらっしゃるだろうと思います。もしかして、しばらくあのときの激変した景色のことを、忘れかけていませんでしたか。もしもそうであるなら、今日、新しい風に晒されましょう。植物にも活力剤のようなものがあります。鉢に挿せば、枯れかけた葉や根が、たちまち元気になります。ただ水を与えるだけで、茎がシャキッとなる花もあります。
ここに「活ける水」があります。キリストが与えた水があります。礼拝の説教は、神の言葉を語ります。命の水を通す管となって、あなたに神の言葉が注がれることを願います。私を遙かに超えたところから、神は私の内に働きます。いまこの瞬間に、永遠に輝く命をもたらします。もう今までも幾度となく耳にしたその良い知らせを、今日改めてお届けすることができたら、と願いつつ、言葉を紡ぎ出してきました。主は喜んで、あなたを祝福します。愛を以て、あなたを新しくします。今日、いまここで、あなたは新しくなれるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
