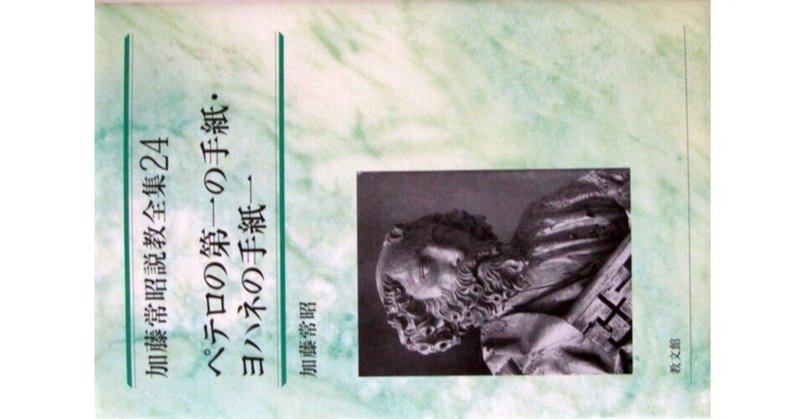
『加藤常昭説教全集24 ペテロの第一の手紙・ヨハネの手紙一』(加藤常昭・教文館)
加藤常昭先生の本は、振り返ってみると、ずいぶん読んでいる。代表作はもちろんのこと、聖書講話シリーズや、道シリーズなどもある。翻訳ものを含めると、個人別にして一番多く持っているだろう。だが、「説教全集」は、一冊も持っていなかった。なにしろ高いのだ。そして、きりがないからだ。
しかし、D教会で一年間説教を続けた2003年度のものが入った巻があるという。D教会のH牧師から聞いたので、「これは」と思った。急に値が下がったタイミングで、別にもっていたポイントを重ねて、ずいぶんと安く買えた。そうでもしないと、なかなか手に入れられない私なのだ。
本巻は、鎌倉雪ノ下教会で1976年後半に多く語られた、ペテロの第一の手紙の講解説教と、D教会で、H牧師の留学の期間に語られた、ヨハネの手紙一が収められている。分量は、ほぼ同じである。
礼拝説教を忠実に収めてあるため、どの説教も、長さは大きく変わらない。よほど早口で喋っても40分ほどはかかったであろうから、あの加藤先生の話し方からすると、少なくとも60分、あるいはそれ以上の時間を要したのではないだろうか。そういう、語るのにかかった時間という情報は、いまのところどの説教集でもお目にかかったことがない。そういうデータがあれば、話す速さが推測できて、面白いかもしれない。
さて、前置きが長すぎる。この本の良さはどうなのだ。そんなことはどうでもいい。私はたっぷり、毎日ひとつずつ、恵みに浸る時間を30分ほど、ほぼ一か月間与えられ続けていた、という事実だけで十分だ。
私は、こうした書には、黄色の蛍光ボールペンでラインを引くことにしている。だが、この本には、どうしても引けないと思った。しかし、後から見返す必要はある。何か足跡は遺したい。そこで、フィルム附箋を貼ることにした。これなら、厚みが伴わないので、何枚貼ってもかさばらない。ラインよりも頻度を落として、それなりに「ここだ」と思うところに貼ることにした。600頁ある本書に、数えてはいないが、2,3頁にひとつ程度に抑えた。それでも、上から見れば、まるで歯ブラシの毛のような本になった。
惜しむらくは、D教会におけるヨハネの手紙の講解説教の、最終回がない、ということだ。録音テープを紛失してしまったのだという。これは「あとがき」に書いてある。具体的な箇所は、5:13-21である。「永遠の命を得ていること」「死に至らない罪」「真実な方を知る力」など、わくわくするような言葉が溢れている。そして、最後の謎の言葉「子たちよ、偶像を避けなさい」の意味を、加藤先生がどう語っているのか、知りたかった。これはもう、永久に知ることができないのだろうか。掲載できないとなると、益々それが知りたいではないか。
D教会のH牧師は、加藤先生の一番弟子の一人である。先生が薦めるような形で、アメリカ留学をすることとなった。その責任をとって、というのはどこまで信じてよいのか分からないが、牧師留守の間の教会を守るという形で、説教を担うこととなったのだ。そのD教会の方々が、録音テープから書き起こした原稿が、本書の後半である。それは、自分の教会を牧会している中で語る説教とは、意味が異なることを、「あとがき」が告げている。
ところで、私の目は節穴であるが、職業上、誤字脱字には比較的目が留る性質がある。もちろん、常にそういう目で探しているのでもないし、全く気がつかないということも多々あるはずである。だが、ヨハネの手紙一2:7-17の説教の中に、ミスを見た。ひとつは明らかな変換ミス、ひとつは同じ流れの中で漢字表記とひらがな表記が意味なく並んでいること、もうひとつはたぶん同音異義語で普通その場面でそちらは使わない、というもの。同じ説教の中で重なっていることから、恐らく同じ人かグループによるものであろう。逆に言えば、その他では特に引っかかることはなかったわけだから、精度は見事である。とやかく言うべきものではあるまい。
その教会では、いくつかの書籍を発行しており、腕の立つ編集者がいた。2024年、加藤常昭先生が亡くなり、その編集者も亡くなった。大きな時代の変革期を迎えたことになる。その年に私は、本書に触れた。これからの時代を担うバトンを渡されたはずなのに、私個人は何の役にも立っていない。歯痒いものだが、鎌倉でもDでも、いまは勢いのある説教が、毎週命を注いでいる。その命を受けて、次の世代が育たなければならないのだが、育っていない。否、私たちの世代が、育てることができていないのだ。
説教集は、昔取った杵柄のような記念として発行されるものではないはずである。実際に語られた声の言葉とは、また違うと言えば違うのであるが、それでも、書かれたものは、再現性が高い。現に二千年やそれ以上昔の「聖書」が、こうして私たちの許へも届き、そこから命を受けることができるようになっている。命を与える説教を集めたこのような本は、ただ「よかったらお読みください」であってはならない。昔の百科事典のように、ステイタスとしての飾りであってはならない。積極的に、共に読む機会を、無理にでもつくっていく必要があると思うのだ。またいつかやろう、ではなく、そうだ、すぐにでも始めよう、という勢いを、いまの時代の霊は与えてくれないだろうか。その霊を、私たちは受けることができないのだろうか。自戒を込めて、呟かせて戴きたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
