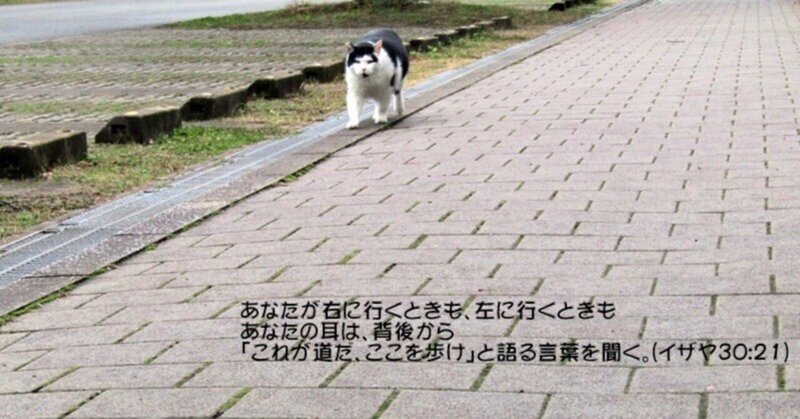
インターネット・ラジオ
ここしばらくの、インターネット・サービスの展開には、ほんとうに感謝している。テレビやラジオが、いつでも見られるようになった。もちろん、ある程度の制限はあるが、かなり自由に、番組を視聴することができるのだ。
仕事中の番組は、それまで、なかなか視聴できなかった。録画予約、あるいは録音予約をしておけばなんとかできたが、放送に気づかなかったら、もう諦めるしかなかった。それが、放送後も視聴できるようになったのは、画期的である。何か作業をしながら、パソコンのディスプレイの片隅にそれを流しておくことができるので、軽いものはそうやって片手間にでも視聴できるのだ。
ラジオの方に話を限定していこう。聞けない時間帯のラジオについては、それまでは録音していた。昔はテープに予約録音も可能だった。そう、「エア・チェック」である。もはや死語なのだろう。ラジオ放送を録音することを、英語の表現でそのように呼んでいた。
ラジオに目覚めたのは、小学校の上級だったと思う。親にねだって買ってもらったのが、当時最高級とも言えた、「スカイセンサー」。この名前にビビッとくる人もいることだろう。世界中の短波を受信できる。BCLにまでは踏み込めなかったが、あちこち探るのは楽しかった。ラジオ日経を知ったのも、その時だった。大橋照子さんが、いまも現役で話し方を教えていると聞くと、驚いてしまう。
やがて、ラジカセにしても、音質のいいものを買ってもらった。お年玉を含めたかどうか、記憶はない。「FM fan」を買って先々でかかる曲をチェックして、その時間に予約録音、ということも苦労してやっていた。クラシックの良さには、そうやって触れた。バッハやバロックの番組はよく録音した。ブルックナーは友だちから教えてもらった。モーツァルトやベートーベンも、代表的なものは漏らさず録音して聴いた。カセットテープのケースには、その雑誌の番組表のところを切り抜いて挟んでおけば、万全な情報となった。
自分で情報を得て、その時を待ち構えて捕まえる。そういう方法は、それなりにかなりの技術をマスターすることとなったが、それがいまや、聞き逃しても聞ける。なんともありがたいものだ。
しかし、語学番組は、もう少し後から聞きたい、と思うこともある。聞き逃しは基本的に一週間と限られているからだ。NHKなら「らじるらじる」、民放なら「radiko」というありがたいシステムがあるが、私は夏休みの講習中などでは一週間以内に聞けそうにないこともあるのだ。また、気持ちの問題だが、保存したい番組もある。貴重な音源や、めったに聞けない演奏やインタビューなどは、保存したい。
ところがこのラジオを録音するアプリケーションが、実はある。予約しておけば、ちゃんと録れる。最初に使っていたものは、インターネット特有の「遅れ」を自分で調整しなければならなかったが、それでも録音できるメリットは嬉しかった。ただ、これも予約してなんぼである。そしてそのうち、このアプリケーションの開発が終わってしまった。放送の提供者側の都合でシステムが変わるなどしたら、もう使えなくなるわけだ。
そこで探すと、凄いものに出会った。「聞き逃し」を録音できるというのだ。本当だろうか。試してみたが、ちゃんとできる。これは真に画期的だ。放送が一週間以内に気づけば、後から録音ができる。しかもタイムラグもなく、正確に開始から終了まで録音できる。音質もいい。
私のラジオ生活は、このアプリケーションで一変した。
そこで、radikoプレミアムに申し込むことにした。日本全国のラジオ放送が聴ける。もちろん、アプリケーションのほうも、それに対応して、日本全国のラジオ放送について、聞き逃しからもキャッチできる。一日あたり約10円で、地方局でしか放送されていないようなものも、全部手に入る。東京や京都には、福岡では聴けない番組がやまほどあるのだ。沖縄や北海道も楽しい。それに、地震や洪水などの災害が起こったときには、その被災地のラジオ番組の声を直接知ることができた。
ラジオは、別の作業をしながらでも聞くことができる。現にいまこれを書きながらも、バックに音楽を流すことができている。お喋りは少し気持ちを奪われることがあるが、ニュース程度ならば上手に両立できることが多い。
残念ながら、ろう者は、この経験が難しい。そういう生活感というものについて、いくら想像してみても、やはりその当事者にはなれない。気持ちが分かる、などと安易に言うことはできない。何か代弁できたら、とも思うが、無責任なことを言うと迷惑をかける。また、ろう者に不快な思いをさせるだけだろう。
せめて、当事者から発される声に敏感になっていられたら、と願う。映画やテレビ番組に、字幕をつけてほしい、という声はずっと叫ばれているが、なかなか進展しない。まずはそこのところから、声を発し続けてみようか、とも考えている。
せっかくの技術である。いろいろな可能性を開く道をつくることができるのなら、もっとできたらいいのに、と思うのだ。
聴者として私は、様々な技術に感謝する。ただ、私たちは「ながら族」をあたりまえだとしておくと、大事な声がかかったときに、それを聞き逃すかもしれないことを危惧する。静かな声、か細い声が、響いているに違いないからだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
