「教育」から「学習」へ。社員が自ら学ぶ仕組みを目指す【RUUUN導入事例③株式会社日本経営様・後編】
RUUUN(ラーン)はTATEITO株式会社が提供する、成長し続ける組織づくりを目指す企業のための動画配信プラットフォーム。
働き方の多様化、組織課題の複雑化が進むなかで、企業はどのような意図や世界観をもってRUUUNを活用しているのでしょうか。
今回は、会計・税理業務から経営・組織戦略まで、医療・介護業界を対象として幅広いコンサルティングを提供する日本経営グループ様にお話を伺いました(前編はこちら)。
日本経営グループ 株式会社日本経営
組織人事コンサルティング部 NKアカデミーチーム 主任 田中梨央様
聞き手:TATEITO株式会社 代表取締役CEO 平野 考宏
eラーニングできちんと言葉にして伝える
平野
今、「言わなきゃわかんないよ」というケースが増えているような気がしています。これまでは、一緒にタクシー乗ったときだとか、お昼ご飯を食べに行ったときにちょっと話す機会があって、自然と伝わっていたものが、コロナ禍で伝わりづらい環境になっていると思います。
田中
まさにそうだと思います。特に危機感を感じているのは、「気軽に話す時間がない」ことと、「観察学習」ができないことですね。上司の背中を見て真似するというようなことが、完全にできなくなるので。
平野
ある企業の方も、まさしく観察学習のことをお話しされていました。
例えば、これまですごく優しい人たちと仕事していたのに、いきなり強烈な先輩と仕事をしたら衝撃が大きすぎてメンタルをやられてしまう……とか。
リアルの場だったら、直接仕事をする前に「あの人と仕事やるときはこういうことに注意したほうがいいぞ」みたいな情報が事前に入ってくる、つまり「外から観察」することができたと思うんですけど、今はそういったことがまったく見えない世界になってしまった。
田中
そういうケースは、これから増えてくると思います。
あと、「その時々に合わせて、考えて発言する」訓練が機会として少なくなっていく気がしています。特にWebでの会議だと言葉にしないと何も伝わりません。対面だったら、ちょっと考え込んでいる状況を見た上司や先輩から「どうしたの?」と話しかけてもらえるようなこともあると思うんですが、Webの場合は自分から言葉にしなければ伝わらない。意見として固まる前の、ちょっとした発言をする機会が減っているように思うんです。
ですから「eラーニングできちんと言葉にして伝えることが、新人の表現の豊かさにもつながる」と思っています。さらに、その言葉を現場に持って帰って、考えてもらうところまで導線が引けるといいなと。まだそこまでやりきれてはいないので、今後の課題ですね。

インプットした知識を使うための思考を磨く
平野
新人研修では、動画の視聴以外にアウトプットする課題はあったんですか?
田中
はい。弊社の『日本経営フィロソフィ』『50周年社史』などの小冊子を読んで感想文を書くような課題がありました。
平野
「言語化していく」という点で、アウトプットは、インプットとセットで必要ですよね。
田中
ここは、私個人の意見なのですが……感想文というより、さらにもう一歩踏み込んだ形で何かできないかと考えているんです。
今、観察学習ではなく経験学習だとよく言われると思うんですが、経験学習サイクルに則って、体験を内省し、次のために具体化し、それをまた体験して……と、サイクルを回していくのが本当に大事だろうなと思っています。
したがって、コンテンツ受講やその後の業務などの体験をもとに内省し、学びを仮説化するところまで行う機会を作れると良いんですよね。例えば、コンテンツ内で問いを投げかけたり、感想文じゃなく「考察」レポートを書いていただいたりとか。
平野
e ラーニングにおいて「アウトプットが大事」と言うけれども、それをどのように実施するかというところをより深く考えていかないといけないということですね。
テストで知識の確認をするだけではなく、知識を次の「行動」に活かせるような、そのためのアウトプットとはどのようなものかというところでしょうか。
田中
そうなんです。e ラーニングを使って知識のインプットはできるのですが、本当に提供したい体験は、自分で考えてもらうことです。つまり、その知識を使う当事者として思考を磨いてもらうことです。
思考を磨くというのは、思考を掘り下げて「深化させていく」と同時に「視野を広める」「視座を高める」という側面が必要なのだと思います。
「深化」の部分はレポートなどを通じて一人でもできるかもしれませんが、多角的な目線で広く考えるということは、人との対話なしにできないと思います。リアルで集まれるような場では、ワークショップなどの実施によって、他者の意見を知って自分の視野を広げ、視座を高めるようなことをしていきたいですね。
eラーニングだけでもダメですし、リアル研修だけでもこれまでと同じになってしまうので、上手く使い分けをしていきたいと思っています。
平野
TATEITOでも、そういう場所を作らないといけませんね。
田中
ぜひ、お願いしたいです。

必要なことを自分で学んでいくのが本当の学習
平野
つまり、「対話ができる空間」ですよね。反転学習の本筋はそこだと思うんですよ。
教科書を読んで、「自分はどう思ったか?」「他の人はどう思ったか?」「じゃあ、どうしていけばいい?」というようなことをぶつける場が本来の「反転学習」なのですが、企業内研修だと、そういう場がほとんどありません。そういった場ができてくると、育ってくる人たちも変わっていくような気がします。
現状、研修でよくある相談は「テストをどう実施するか」などが多いんですが、テストは結局「正解がある中で、ちゃんとわかっているかどうか」しかわからない。確かにそれも大事なんですが、その先が必要なのではないかと思いますね。
田中
本当にそう思います。
仕事をするうえで知っておきたい知識についてはテストをすればいいと思うんです。でも学んでほしいことはそこだけじゃないんですよね。
「報告・連絡・相談」の意味を説明できることよりも、報告・連絡・相談を実践できることの方が大事です。テストで理解度を測ればよいというものばかりじゃないと強く思います。
平野
テストで回答できても報連相できない人ばっかりだったらほんとに意味ないですもんね。
田中
はい。また、本当に求められるのは人事部や管理者側がどこまで“管理しないことを選択できるか”だと思います。
テストにしても感想文にしても、「話を聞いていたか」という確認でしかありません。でも本当に大事なのは姿勢を正して動画を見ることじゃなくて、実践につなげることですよね。実践できていれば、何回見ようが何倍速で見ようが関係ない、というところに管理者側が立てるかどうかだと思います。
平野
貴社で開催された研究開発テーマ発表大会で、RUUUNの取り組みが金賞を取られた際の発表動画も拝見しました。その動画の中でも、田中さんがおっしゃっていたのは「教育じゃなくて学習」でしたね。
教育コンテンツを視聴したかどうかを管理するのではなく、本当に必要なことを自分たちで学んでいける環境整備を進めていくのが大事なんじゃないかと。
この「管理しない」という考え方は、このインタビューの中でぜひともお伝えしたかった部分です。ちなみに、新人の方にはどのようにしたんですか?
田中
実は、それは管理しました(笑)。未視聴者にはリマインドメールが送られて、期限までの視聴を指示していました。
平野
ただ、新人は何を学んでいいかわからないわけですから「ある程度の管理は必要」という結論もありえますよね。
田中
そうですね。難しいところですが、あの動画は全社のメンバーに見ていただけたので、私たちの言いたいことは伝わったかなと思っています。
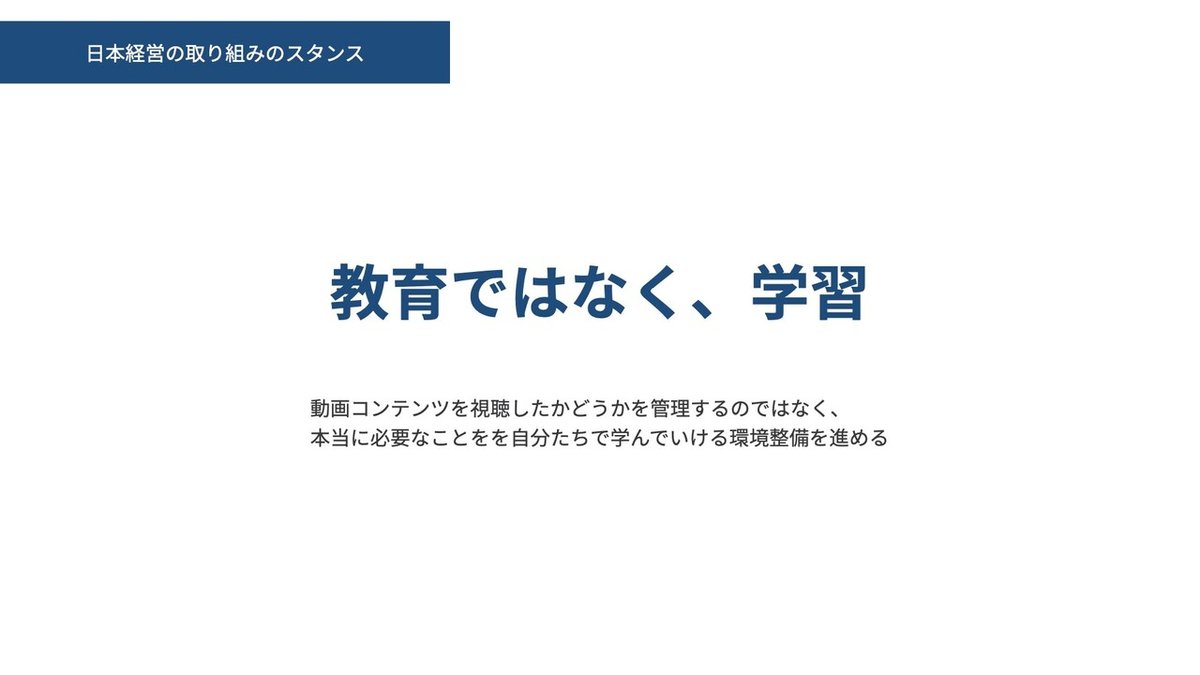
RUUUNをインプットし、コミュニケーションできる場に
平野
まだまだお伺いしたいところですが……、最後に、今後どのようなことに取り組んでいきたいか、TATEITOあるいはRUUUNに期待することなどをお聞かせください。
田中
わかりました。まず、全拠点の社員を対象にRUUUNで階層別研修の配信をしていくこと、今後も活用を広げていくことは着々と進めていきたいと思っています。
となると、次に課題になるのは全社員にRUUUNへアクセスしてもらうところになります。RUUUNのデザインはシンプルでかっこいいので社員にも馴染みやすいと思いますし、是非これからも活用していきたいと思っています。
また、レポート提出機能も本当に欲しいですね。
レポートは思考を深めるアウトプットの場になるだけではなく、上司とのコミュニケーションツールにもなると思っているんです。直属の上司でさえ話す時間がない現状なので、自分で考えたものを言語化して上司に送り、上司からフィードバックが来るしくみは貴重になると思います。価値観を共有し意識をそろえるという意味でも、非常に良い機会になると感じています。
さらに、これは私の願望なんですが、今後RUUUNを全社の情報プラットフォームとして位置づけて、研修動画だけではなく有志の勉強会や営業プレゼンの動画を共有しあい、何かあったらすぐRUUUNにアクセスして検索するような使い方ができたらいいなと思っています。レポート機能もあれば、学習としてのインプットもしつつ、コミュニケーションも取れるプラットフォームになりますね。RUUUNを中心として、社内の連携を深められれば嬉しいです。
※このインタビューは2020年9月24日に実施したものです
TATEITOでは、動画を使った学び続ける組織づくりをサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。
