
顧客と自社の教育課題解決に向けたeラーニング活用【RUUUN導入事例③日本経営グループ様・前編】
RUUUN(ラーン)はTATEITO株式会社が提供する、成長し続ける組織づくりを目指す企業のための動画配信プラットフォーム。
働き方の多様化、組織課題の複雑化が進むなかで、企業はどのような意図や世界観をもってRUUUNを活用しているのでしょうか。
今回は、会計・税理業務から経営・組織戦略まで、医療・介護業界を対象として幅広いコンサルティングを提供する日本経営グループ様にお話を伺いました。
日本経営グループ 株式会社日本経営
組織人事コンサルティング部 NKアカデミーチーム 主任 田中梨央様
聞き手:TATEITO株式会社 代表取締役CEO 平野 考宏
日本経営様 RUUUNプロフィール
・導入年:2020年1月
・ご登録ユーザー数:4,985人
・ご登録動画数:288本
※データは2020年11月27日現在
全国の新入社員研修でRUUUNを活用
平野
まずは、簡単に御社の自己紹介をお願いします。
田中
私たち日本経営グループは、医療・介護福祉業界に特化した経営コンサルティングを行っています。
日本経営グループは、1967年に大阪府の豊中市で立ち上げた会計事務所を母体としています。日本経営ウィル税理士法人と株式会社日本経営を両軸としていますが、他にもさまざまな会社があります。ホームページ等の制作会社である「メディキャスト株式会社」や、行政書士法人、社会保険労務士法人、そして組織開発系の「株式会社ミライバ」などです。
グループ一体となって、医療・介護福祉業界を対象とした会計業務や税務業務、コンサルティング業務など、さまざまなサービスを提供させていただいており、医療・介護福祉分野に関しては総合的に対応できる体制を整えています。
平野
新卒採用はどのような形で行われていますか?
田中
例年、合計25~30名程度の新卒が入社します。日本経営ウィル税理士法人と株式会社日本経営の採用フローは基本的には分かれていますが、内定者研修や新人研修は一緒に行っています。
平野
ちなみに、田中さんはどのような経緯で入社されたんですか?
田中
私は2017年に入社しました。日本経営なら組織人事領域にどっぷり浸かれると思ったのと、先ほどお話した組織開発系のミライバが立ち上がる直前だったこともあり、新しい領域の組織づくりもできることに魅力を感じて入社を決めました。
eラーニング導入。ビジョンに共感してRUUUN導入へ
平野
田中さんは、これまで組織・人材系に特化してこられているんですか?
田中
はい。入社後に組織人事コンサルティング部に配属され、人事評価制度の構築や運用、研修講師などをやっていました。
あるとき、大規模法人様の教育体系を作る仕事を担当させていただきました。非常に難しかったんですが、これをきっかけにそのお客様にはeラーニングを導入していただくことになりました。
平野
なぜ、教育体系を作る中でe ラーニングを導入することになったのでしょうか。
田中
実は、この件の責任者であり、上司でもある濱中(洋平様)の構想が発端なんです。
濱中には、いつか「VRやARなどの映像技術を使って、入院患者さんにエンターテイメントを提供したい」という夢があって。当社で新規事業を立ち上げるにあたり、その濱中のビジョンと当社のリソース、将来的な展開を考え、映像という技術を使って医療・介護福祉のお客様に教育環境を提供し、役立てていただきたいという想いがありました。
先ほどの大規模法人様は東北地方で複数の病院を経営されているのですが、広い地域内に病院が点在しており、場所によっては公共交通機関も十分にない環境でした。濱中の構想とそういった状況がうまくマッチして「これからはeラーニングだ」と比較的スムーズに受け入れていただいたように思います。

平野
濱中さんの構想は最初にお会いしたときから伺っていましたので、そこがスタートだと聞いて、改めて納得しました。
ちなみに、RUUUNを導入した理由を伺ったら「正直言って、機能だけで決めたわけじゃないんだよね」と話をされていたんですが、そのあたりのお話を伺ってもいいでしょうか?
田中
機能に満足したというより、濱中は「平野社長はビジョンの人だから、いい」とよく言ってました。お二人、タイプが似ているんですね。
似ていると言った手前、言いづらくもありますが……話が抽象的すぎるところがあるんですよね。具体論を描くのが私たちの仕事だったりするんですけど(笑)。
同じ一事業の主であり、ビジョンを一緒に語れる相手として、平野さんを頼りにしているんだろうなと思います。
平野
そうなんですね、ありがとうございます。インタビューに同席している社員が苦笑いしております(笑)。
極論を言ってしまうと、機能の追加はやろうと思えば何でもできると思っています。ただ機能を足すことはできても「引く」のが意外と難しいんです。
濱中さんとは早い段階からビジョンを共有していたためか、「こういうことをしたいから、我々はこんな機能をつけています。でも、こういうことはやりません」という説明もすんなり受け入れてくださって、非常に話が早かったですね。
田中
そういうやり方っておもしろいですよね。現実的な計画や目標はもちろん大事ですけど、そこばかりを描いていても新規事業はできないという感覚もあります。
なので、大きなビジョンと、具体的に今できることのバランスをとっていくことが新規事業の面白さだと感じています。
突然のリモートワークでeラーニング研修も急速に進む
平野
では、実際にRUUUNを導入されてから、苦労されたことや、逆に良かったことなどがあれば教えてください。
田中
苦労している点は二つあります。
まず、社内でまだ利用が拡大できていないという状況です。
毎週月曜日に社長からの講話を10分間程度配信しているのですが、それも全員見てくれているわけではないんですよね。
もうひとつは、社内のシステムとどう整合性をとるかです。
例えば、今社内で使っているシステムでは、研修参加予定者に対して研修日時のリマインドや、研修後に書くレポートフォームの案内を自動送信しています。
「受講実績がRUUUNで取れるなら、レポート収集もできないのか」という声もあったんですけど、現状それはできないんですよね。
今は上手く組み合わさってはいるものの、システムを併用しないといけないところは今後の課題だと思っています。

平野
我々も、今後のテーマは「連携」だと思っています。例えばRUUUNからの受講データを簡単に共有できるようにするなど、他社のシステムと合わせて活用していただけるような改良が必要だと考えています。
ところで、日本経営さんでRUUUNを最も活用していただいたところは、新人研修だと思います。新人研修でe ラーニングを使っていくことになったのはいつだったんですか?
田中
結構ギリギリだったと思います。3月でした。4月に東京に緊急事態宣言が出て、完全に出社禁止となりました。それが見えてきたときに、「ちょうどコンテンツがあるし使いましょう」と話が上がって、東京・福岡・大阪の3拠点の新入社員全員を対象としたeラーニング研修が急に進んでいった感じですね。
もともとはお客様向けに作ったコンテンツだったので、私たちも正直「これを使って良いのか」という迷いがありましたが、迷うまもなく全国に緊急事態宣言が発令されて……という感じでした。
学習コンテンツの在り方に対する葛藤
平野
「迷い」とは、具体的にどのようなものだったのでしょうか。
田中
私たちが作ったものが全社の共通コンテクストになる、という点でしょうか。
弊社で大切にしている価値観の一つに「基準行動」というものがあります。「氣づきと挨拶」「早起きと認識即行動」「報告・連絡・相談」等があり、内定者や新入社員に対する講話でもよく話されるものです。ただ、それは日々の業務を遂行する上での心がけなので、各拠点に配属されたあと、OJTや上司先輩との関わりの中で紐解かれていくケースが多いんですよ。

私たちの作った動画では、「基準行動」を一つひとつ解釈して、丁寧に説明してしまっているのですが、それが正しいのかどうかというのは大きな問いでした。私たちとしては「この解釈で捉えたら良い社会人人生をスタートできる」と思って作りましたが、全社員が同じように考えているかはわからなかったので……
平野
今のお話には、2つポイントがあるように思います。
一つは、どんな講義であっても、いったん定義してしまうと「それって本当?」という疑問が挟まるものだという点。例えばマーケティングだったら「マーケティングとは~です」と説明すると、「え、ちょっと違わない?」と思う人が出てくるようなことがあるんですよね。
もう一つは、説明し過ぎることで、本人が自分で考える余白がない点。例えば上司から「お前ちょっと頭冷やして考えてこい」って言われて、その理由を自分の頭で考えるところに気づきが生まれたりするものですが、それが全部整然と並べられると「本当にそれでいいんだっけ」という。
田中
そうなんです。例えば、基準行動には「早起きと認識即行動」という項目があります。「気づいたらすぐに行動に起こす」「その訓練として、朝早くすぐに起きる」という心構えですが、これが変に伝わると「今の時代そこまで会社が言う?」という話になってしまいます。
また、上司から新人へのお話の中では「皆さんはまだ仕事の能力や経験が少ないですが、まずは基準行動を徹底すれば信頼される人になります」と、基準行動が「能力や経験を補うもの」として語られがちです。 それはそれで、能力や経験が身につくにつれて基準行動をないがしろにしやすくなってしまうような教えだとは思っているのですが。
多様な解釈がある中で、「この動画を全社の共通文脈にしていいのか」という迷いがありました。その一方で、こういうふうに基準行動を新人にとらえてもらえれば、おそらく悪い作用は起こさないだろうし、一見古臭く見える教えもフラットに捉えてもらえるだろうという期待もあったんです。
平野
「伝えすぎること」への葛藤もあったようですが、逆に、きちんと説明しないと、残すべきものが残せないということも感じますね。
田中
まさにそうだと思います。弊社には、基準行動以外にも「自責」という考え方があるんですが、それを“自責の念”“抱え込む”などのイメージで捉えられると、時代に合わないと思われてしまいます。
でも、自責とは本来「自分でコントロールできる範囲を自ら広げていく」ことだと思います。他者に依存したり、振り回されたりせずに、「自分はどうするか」という目線をもって前向きに生きられるように物事をとらえるための考え方なんですよ。
だから、「不足を補うためのスキル」や「新人だからやらねばならないこと」ではなく、本当に生き生きと働けるように、「自分の自由意思で働けるような捉え方」をしてみませんかというスタンスで、コンテンツを制作しています。
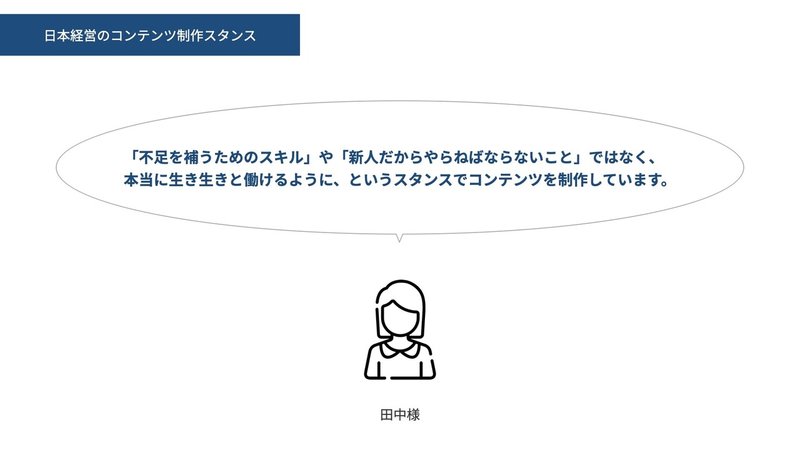
コンテンツ制作のスタンスをしっかり持たれている日本経営様。さらにそのコンテンツのインプットをどうそのあとにつなげていくのか、後編に続きます。
※このインタビューは2020年9月24日に実施したものです
TATEITOでは、動画を使った学び続ける組織づくりをサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。
