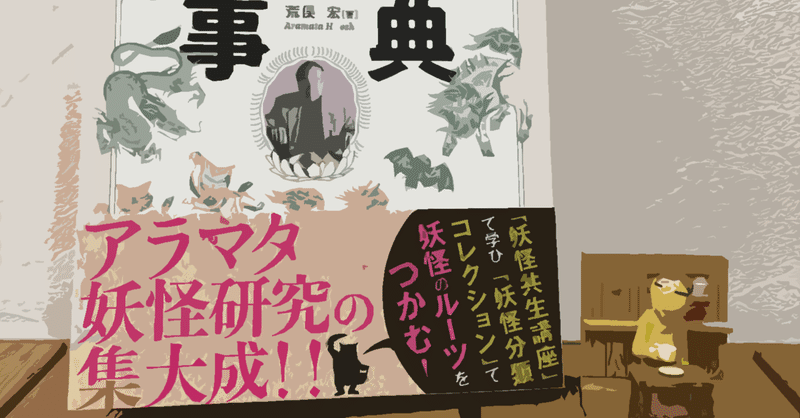
- 7days book cover challenge, DAY3 -
「7日間ブックカバーチャレンジ」企画のルールからは逸脱したやり方ですが、7冊の本を紹介します。
(前置きについてはDAY0をご参照のこと)
昨日紹介した『考現学』今和次郎の師匠は柳田國男。やはり妖怪の本も紹介しなければ。2003年に始めたお寺の音楽会のタイトル「誰そ彼 (たそがれ)」とは『妖怪談義』を捲りながら決めたものだが、それだとちょっと捻りがない。今一番オススメしたい妖怪本は、、、と考えてみると、昨年の夏に出た荒俣宏先生のこの本しかない。
『アラマタヒロシの妖怪にされちゃったモノ事典』荒俣宏 / 秀和システム

この本が画期的なことは、まず書名にあらわれている。アラマタヒロシの『妖怪事典』なのではなく『妖怪にされちゃったモノ事典』である点だ。タイトルだけで「これは多分一番わかりやすい本だな」と確信した。
なぜかというと妖怪は「目に見えない」。絵と解説を並べたとしても「こんな感じらしい」でしかなく「で、結局何なの?」には答えてもらえない。妖怪の楽しみ方はそれでも充分なのだけど、「で、結局何なの?」を知ろうとすると膨大な分野の知を尋ねる旅が始まる。京極夏彦先生は以前、その探求を「玉ねぎの皮むき」と喩えていらしたが、玉ねぎの正体を知りたくて皮を一枚づつ剥がしていくと、中心部には結局「何もない」。なぜかというと妖怪は「目に見えない」からだ。そこが妖怪の難しくて面白いところなのだけど、なかなか味わいにくい。
京極先生の喩えでいうところの「玉ねぎ」を並べたものが『妖怪事典』だとしたら、こちらは「玉ねぎの皮」を種類別に見事なまでに美しく分類して種明かししている。つまり『妖怪にされちゃったモノ事典』なのだ。これは食べやすくて、美味しい。
もう一つ、白眉はまえがきにある。僕はここまで簡潔且つ納得感を以て「バケモノとは何か?」をあらわした文章を知らない。
「バケモノとは何か?」...この本のまえがきで荒俣宏先生はこう書いている。
バケモノは未来を知らせる「予兆」だった
そう聞いて、昨今のアマビエの狂騒的ブームを連想される方は少なくないと思う。
(アマビエについては、兵庫県立歴史博物館学芸員の香川雅信さんの解説がわかりやすい)
膨大な種類の「玉ねぎ」=妖怪が世界中に存在しているけど、「なぜ玉ねぎが生じたの?」という素朴な起源を遡ると、恐らく古代の人々の「これから起きること」に対する「畏れ」にたどり着く。その兆しを捉え、対策をせずにはいられない思いが、色んなモノを妖怪にしちゃったというわけ。
ほら、今も同じでしょう?
----勝手にCM----
僕のチャレンジの目標は、薦めた本を誰かが本屋さんで買ってくれること。(個人店の通販であれば尚良し。だけどなかなかな見つからない…)
というわけで、この本が買えるページを紹介します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
