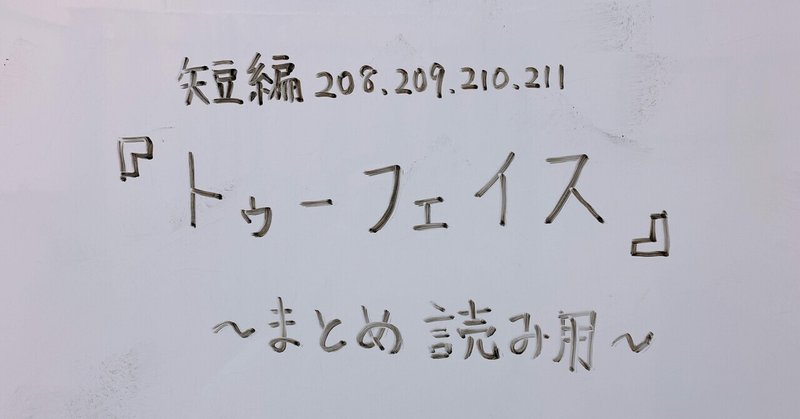
短編208.209.210. 211『トゥーフェイス』(まとめ読み用)
1
男はアメ車のような体格をしていた。つまり、無駄に大きく燃費が悪い。アメリカ製”負の遺産”を拡大再生産したような身体つきだった。
カメラは、首に巻かれた金チェーン、開襟されたシャツから覗く入れ墨、指の太さをはみ出す指輪と順次映していく。
暴力がそのまま形を取ったような姿だ。
でも、その粗暴な”なり”からは想像がつかないほど、箸の上げ下ろしが綺麗だった。それ自体が生を持った生き物のように華麗に舞い、掴み、男の大きな口元へと運ばれた。
*
テーブルには刺し盛りからデザートに至るまで、居酒屋メニューの一ページ目からドリンク類までをくまなく網羅する料理が並んでいた。三人なのに通された八人掛けのテーブルは端々まで、そうして皿で埋まった。載せきれないものは私の膝の上に置かれた。左手にウーロン茶のグラスを持ちながら、仕方なく右手でカメラを構えた。
アウトロー系YouTuberのカメラマンとしてここにいる。何故だろう。普段はカフェや地下アイドルのプロモーション映像を手伝っているのに。目の前にいる二人、全然可愛くない。私が『アメ車』と名付けた男は前述のようないでたち、そしてもう一人、そのYouTubeのアカウント主は日に焼けた太い首をタトゥーで包んでいる。どちらも典型的な法の外の番人だ。
これはクラウドソーシングのサイトで見つけた仕事だった。撮影と編集まで行い、占めて六千二百円。他よりは遥かに安かったが、ハートを多用した語尾と貼り付けられた写真から下心をくすぐられた。
ーーーまぁ、パソコン編集に慣れない素人女子のYouTube撮影だろう。大食いかなんかの。
そうタカを括っていた。打ち合わせのメールのやり取りは素っ気なく終わった。日時の指定のみ。報酬が先払いなのか後払いなのかの記載も無かった。
ーーーこういうことに慣れていないのだろう。可愛いねぇ。
とすら思った。世間というものを教えてやらねばなるまい。その手を取って、じっくりと。
*
待ち合わせ当日、私めがけて二人の男が近づいてきた。「斎藤さん?」と一人が言った。私が頷くと「今日はよろしくな」と肩を組まれた。そしてワンボックスに半ば拉致されるような形で今ここ、居酒屋にいる。テーブルは料理で溢れている。大食いを撮影していることには違いなかった。
「今日は仲間の出所祝いを撮影して、コンテンツにするから」とアカウント主は言った。アウトロー系YouTuber独特のコンテンツだ。アイドルや芸能人には作れないオリジナリティ溢れるコンテンツ。「納期は明日の朝までな」
私は店の時計を見た。十八時だった。撮影して帰って徹夜で仕上げろ、ということだろうか。無茶が過ぎる。文句を言おうにも、目の前の二人を見ると自然、唇を噛み締めるしかなかった。
2
『三年の刑期を終えた今の感想は?』そういうテロップを入れようとして質問したがアカウント主に睨まれた。「なに、勝手に回してんの?司会者気取りかよ」舌打ちと共に割り箸が飛んでくる。私はカメラそのものになろうと努めた。無機物として無事この場を乗り切るのだ。
録画時間が増えていく。その分、編集の手間も増えていく。そして、編集する為の時間は削られる。
十九時。カメラを回し始めてから一時間が経った。先程からアカウント主(首タトゥー男)は饒舌だが、出所した男(アメ車)は終始無言だった。話を振られても首を振るだけで済ませている。
ーーーこれ、どういう”絵”にすれば良いのだろう。
仕上げた絵が思い浮かばなかった。テロップを付けるにも例えば、
「ムショんなかは快適だったか?」
「…」(無言)
「昔、〇〇って奴が下手こいてさぁ」
「…」(無言)
駄目だ。ギャグにしかならない。こんなものを納品した日には、私の身体の一部が飛ばされそうだ。幸いにして住所は教えてないが、調べようと思えば、赤子の手をひねるくらい簡単なことだろう。法の外に生きる彼らにしてみれば、そんなこと朝飯前だ。それに目の前の二人は、実際の赤子を床に叩きつけても笑っていそうだ。
*
そんな時だった。アメ車の箸の持ち方に気が付いたのは。
もし『箸の教科書』みたいなものが存在するとしたら、その表紙に使われていてもおかしくはないほど、見ていて美しさと気品を感じる”持ち方”だった。勿論、手の甲にまで侵食された入れ墨は加工で消さなければならないだろうけど。
アカウント主との対比がまたそれを強調しているのかもしれない。アカウント主は箸をまるでフォークのように扱っている。それをフォークと呼ぶには些かフォークに失礼かもしれない。それよりは単なる木の棒か。唐揚げに箸を突き刺すようにして口に運ぶ。その横でアメ車は、二本を適切な間隔で開き、最短距離で唐揚げへと近づき、最低限の力でそれを摘む。決して首を唐揚げに近づけようとはせず、箸の方から口元へと運んでいく。端正だった。池波正太郎が褒めそやしそうな食事の仕方だ。
箸の扱い方だけを見ていれば、この男がアウトローだということを忘れてしまう。例えば、良家のお坊ちゃんといっても過言ではないだろう。でも指先以外は完全なる反社会的人物。一人の人間の中に相反する性質が詰め込まれているように感じられる。今はただ”悪の力”が優っているだけで、心根は指先の方にこそあるのではないか、と。そんな妄想すら抱いてしまう。
その不可思議さを通して、何故こんなにも箸を綺麗に使えるこの男がアウトローとして三年も刑務所に入っていたのか、俄然興味が湧いてきた。
3
撮影自体は二十三時に終わった。この六時間分のテープを朝までに編集しなければならないことを思うと絶望感に尻を掴まれる。アカウント主とアメ車の二人はこの後、別の店に飲みに行くらしい。私は御免被りたかったし、実際誘われることもなかった。
私にはまだやることがあった。動画編集ではない。少なくとも。
*
支払いはアカウント主と私の割り勘だった。何故?そして端数の細かい小銭は私が出した。何故?財布から飛んでいった金額は動画編集によって得られるはずの報酬、その軽く三倍はあった。何故?
「ちょっと車、取ってくるわ」アカウント主は駐車場の方へと歩き出した。【飲酒運転】【危険運転致死傷罪】【そもそもの倫理】。その背中にはどの漢字も浮かんでいなかった。
私とアメ車(出所男)は店の前に二人残された。普段なら走り去るだろうが、今はこれで好都合だった。恐怖を押し殺して話しかける。
「あの…箸の…持ち方、綺麗ですよね」
「…」とアメ車は言った。
こうして見上げると、頭ひとつ分は大きい。私も小さい方ではないという自負はあるのだが。『蛇に睨まれた蛙』という表現を考え出した古人の心持ちを追体験した。これからは蛙に親近感を抱けそうだった。
「いやその、箸の持ち方があまりにも綺麗で見惚れちゃうほどでしたよ」自分でも笑えるほどの震える声。
「…」とアメ車は言った。言った?
「なんというか…無駄がないというか、型通りの動きというか」実際、アメ車の箸の動かし方は日本舞踊を彷彿とさせるものだった。
「…」とアメ車は言った。言った、という小説表現の限界だった。
風が吹いた。その風には秋がしっかりと姿を隠していた。風の端に腰を降ろし、せっせと自分の居場所を刻印しようとする夏の終わりの風だった。
「親父がな」という声がした。私は声の出所を探った。間違いなくアメ車の喉仏が動いていた。「五歳の頃一緒に暮らした、何人目かの親父が躾に厳しくてな」アメ車は煙草を口に咥えた。「そのあとも何人か親父は変わったけど、本当の意味で親父と呼べるのはアイツだけだな」
ジッポの炎がアメ車の顔半分を明るく照らす。その陰影は間違いなく、正と負とに二分割された人間のそれだった。
4
「ハメられたんだよ、アイツに」とアメ車は言った。
先程アメ車が口を利いてくれたことに気を良くした私の「なんで三年も刑務所に入ることになったんですか?」という質問に対する答えだ。”アイツ”というのはアカウント主のことだろう。それ以外に私の知るアメ車の仲間はいない。
「特殊詐欺ってやつな」
ちょっとした野良仕事だよ、とでも言うようにアメ車は言った。
「アイツに誘われて、軽く小遣い稼ぎでもしようと思ってな」アメ車は半分ほど吸った煙草を地面に捨てた。「でも気付いた時には、俺の名前が一番上になってた」踏み消されたそれは原型を留めぬ姿でそこにあった。「アイツは俺を盾にして上手くガラ躱したんだよ」遠目には内臓を晒した虫の死骸のように見えた。
「じゃあなんでわざわざ今日は撮影なんかに協力したんですか?」
「気にしてない、ってフリしとかなきゃアイツも警戒するだろ」
「フリ?」
「出所祝いを餌にこれからアイツをバラそうと思ってな」
バラす、というワードが”殺す”ということを意味しているのは素人の私でも分かった。しかしそれがアウトロー流のジョークなのかどうかは判別がつかなかった。
「でもそんなことしたらまた刑務所に」
敢えて間に受けたように装った。
「朝一の飛行機で海外に飛ぶさ。もう戻ってくることもないだろうね」
…信じるに足る、言葉の重みだった。
「だからまぁこの撮影の報酬は諦めてくれよ。でも多分アイツは元々、払う気も無かったと思うけどな」
そんな気はしていた。報酬を貰ったところでもう赤字は確定している。どちらでも良かった。
アメ車は彼の大きな尻ポケットから財布を取り出した。そこから壱万円札を三枚引き抜き、私に手渡した。首を切り落とせそうなほどのピン札だった。
「箸の持ち方について何か言われたのは初めてだったけど嬉しいもんだな」とアメ車は言った。
「あの…ホントにこの後、”ヤる”んですか?」
アカウント主のベンツGクラスが排気音を轟かせながら、我々の前に止まった。
「チンコロ、すんなよ」
アメ車は笑いながら、私の背中を軽く打った。それは野球のグローブを投げつけられた時のような衝撃だった。車に乗り込んだ後は二度とこちらを見ることはなかった。私はその真剣な横顔を見つめた。
ベンツは私など居ないかのように、走り去った。テールランプの赤がいつまでも網膜に残った。
*
机の上には編集の手をつけることのなかったカメラと三万円が置いてある。
あれから数日経ったが催促の連絡は無い。かといって、ニュース等で今や懐かしいあの顔々を見ることもなかった。
私は箸を宙で二、三度動かしてみた。でもそれは不恰好で情けなくなるほどの動線しか描けなかった。
#アウトロー #YouTuber #箸 #トゥーフェイス #小説 #短編小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
