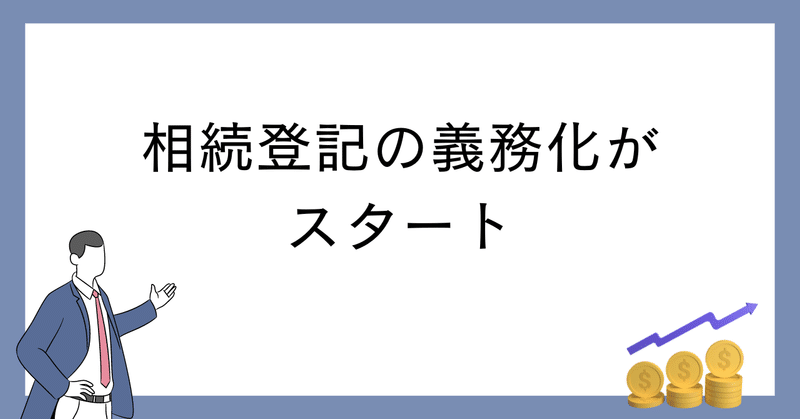
相続登記の義務化がスタート
【相続登記の義務化が4月からスタートします。】
土地や建物を相続をしたが、代々その土地を守っていくということが当たり前なので、相続登記をしていないということがありました。
また、最近では空き家が増加しており、その不動産登記の名義自体が何世代も前のまま変更がされておらず、その権利の所在がわからないというケースも多くなってきたそうです。
そのことから、相続により、土地建物を引き継いだ人が、その登記名義をご自身に変更し、その権利の所在を明確にするために、登記を確実に行っていこうということで、今回相続登記の義務化がされました。
不動産の相続登記義務は、2024年4月からスタートします。
相続などで不動産を取得した日から、原則として3年以内に登記をする必要があります。
不動産の相続登記をしなかった場合には10万円の過料(罰則としてお金を払うことです)が課される場合がありますのでご注意ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私のクライアントのAさんは、父親をだいぶ前に亡くされています。
その際、父親の相続財産がなく、相続税も発生しなかったそうです。ただ実家についての登記名義が曽祖父から名義変更がされていなかったため、相続登記がすぐにできず、そのままにされていました。
土地や建物の不動産を所有していると、固定資産税という税金がかかります。固定資産税はその不動産がある市区町村に納める税金になります。
通常は不動産を所有している人が、その不動産の登記名義人になっているため、固定資産税はその登記名義人が納税することになります。
ただし、今回のAさんのケースのように、登記名義人がすでに亡くなっている曾祖父になっている場合には、市区町村の役所が固定資産税を納税してもらおうと思っても、亡くなっている方に納税を求めることはできません。その場合には相続人に固定資産税を納税する義務があるのですが、曾祖父の名義になっているこの不動産は相続人となる人がたくさんいました。
この場合には、相続人の代表者に固定資産税の納税義務があるのですが、では誰が代表者になるのか?
これは、市区町村の役所が決定するとのことで、よくわかりません。
ただ、その土地、建物に住んでいたり利用していたりしていた人がその相続人の中にいたら、その人に納税の通知がされることになるのだと思います。
今回のケースではAさんに納税通知が届いたそうです。
Aさんは自分では利用していないその土地建物について、固定資産税を支払っていたようです。しかしAさんは、この先、この不動産を利用することもほとんどないので、売却したいと思った。でも、不動産の登記名義人が自分ではなく曾祖父になっているため、その不動産を売却することができませんでした。
その不動産を売却するには、まず、その登記名義人をAさんに変更することが必要でした。Aさんは何か月かかけて、相続人となる人の住所を調べたそうです。
Aさんの祖父のご兄弟は10人、すでに亡くなっている方もいらっしゃって、その場合には代襲相続といい、その亡くなった方のお子さんが相続人となります。(相続の権利が子どもに移っていくイメージです。)
その代襲相続が複数件あり、相続する権利がある相続人が合計で30人くらいになっていました。この不動産をAさんの名義にするためには、この30人に相続について遺産分割協議書という契約書を作成し、1人1人、契約書に実印を押印してもらい、印鑑証明書の原本を提供してもらわないといけません。
Aさんはなんとか、遺産分割協議書をとりまとめ、その不動産の登記名義人を自分に変更して、不動産の売却をすることができました。
なかなか連絡がつかなかったり、連絡がついてもなかなか遺産分割協議書に押印いただくことをご承諾いただけなかったりとすごく大変だったそうです。それでも、Aさんは運よくすべての相続人と連絡を取ることができ、遺産分割協議書を取りまとめることができました。
ただ、相続人とまったく連絡が取れずどうしようもないということもあり得ます。(裁判所で相続手続を進める方法などありますが、そちらはそちらで大変面倒です。)
相続が発生したときは、相続財産があまりないから自分たちには関係ない、登記もお金がかかるし面倒だとして、相続登記の名義変更などの手続をしていない場合、自分はよくても、その次の世代が、すごく大変な思いをすることになるかもしれません。
将来、自分の次の世代が、相続財産について面倒なことにならないため、自分の世代でできることはしっかりやっておくことが大切だと思わされました。
不動産を相続される機会がありましたら、相続登記手続きはしっかりと行ってまいりましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
