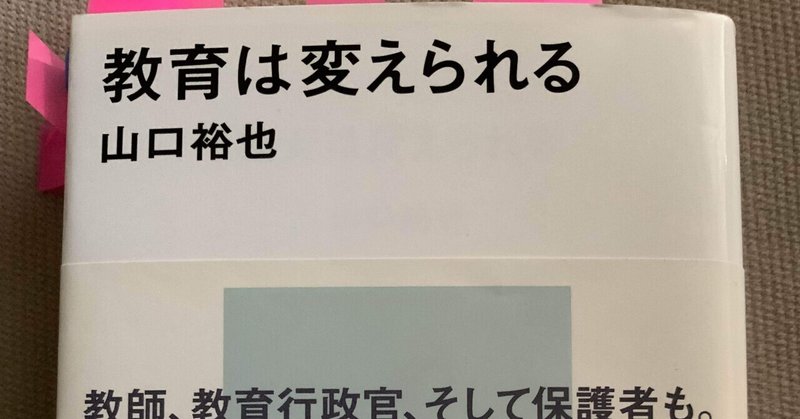
自分の実践に影響を与えた本紹介②
前回は「質問づくり」の本を紹介しました。この本を読んで以来、授業を構成する際には、教室の発問以上に、子どもたちの「問い」を大切にするようになりました。
今日は山口裕也氏の『教育は変えられる』です!以前読書会で読み合った作品で、noteにも紹介していました。
https://note.com/tarou800/n/n2f5dd31d88c8
前回の『たった一つを変えるだけ』と少し繋がる部分もあると思いますので、読んでいただけると幸いです!
学びは「わたし」の営み
前回、教師の発問ではなく、子どもたちの問いを基点に授業を進めていくことを述べました。
他人の物語に自分を重ねるのではなく、自分自身の物語を生きる。人生は、他の誰でもない、自らの道を拓くもの。だからよりよい成長のための学びは、「自分で選ぶ」ことから始めなければなりません。このような文章から始まります。子どもたちの「自己選択」「自己決定」が学びを進めていくために大切になるということです。
筆者は、子どもの「選択」と「決定」の先に、自分で自分の道を切り拓くことができるようになっていくと言っています。
学びの構造転換
筆者は、授業者の学びに対する構造を転換する必要があると述べています。
「教員がどう授業をつくり、どう学習者に教え授けるか」
ではなく、
「学習者が自分で選び決めながら進める学びに、教員としてどう関わるか」に
変えていく。
教師主体ではなく子ども主体の学習スタイルに変えていくことが大切だと述べられていました。前回の本とも繋がってくる部分だと思います。
子どもは教師が教えないと学べないのか
教師の子どもに対する考え方を変えていく必要があると思います。この本でも書かれていましたが、教師が教えないと何もできないという見方から、自分で選び決定することができる存在だと認識する必要があります。
子どもたちを信じることが、これからの教育に必要なのではないでしょうか。
教育は変えられる
子どもを信じ、子どもの選択や決定に委ねる授業づくりが求められているのかもしれません。令和の日本教育に向けて、個別最適化や協働的な学びに向けて、子どもたちを中心とした授業を進めていく必要があると感じました。
それでは、また次回。新しい本を紹介します!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
