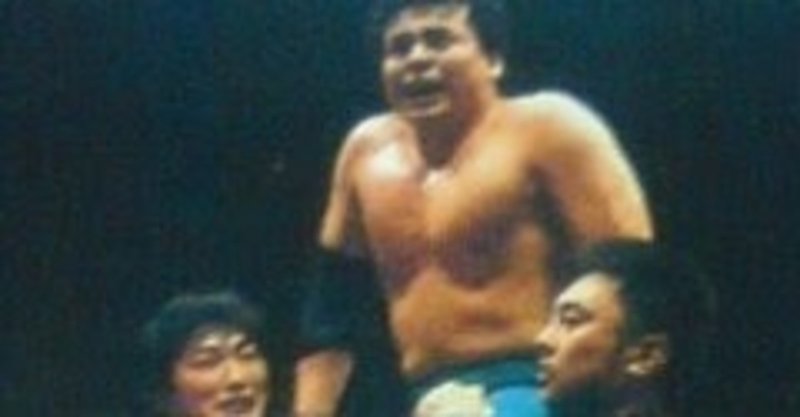
ぼくたちの失敗
三沢光晴を殺したのは私だ。
いきなりこんなことを切り出されても読者は困惑するだろう。順を追って話そう。
私が小学校3年生の頃、昭和57年のある金曜日午後8時、たまたま点いていたTVの画面に映し出されていたある試合によって、私はプロレスの虜になった。ブラウン管の向こう、プロレス中継の画面上で華麗に飛んだり跳ねたりしていた、タイガーマスクというプロレスラーの一挙手一投足に私の視線は釘付けになり、心を踊らせていた。
毎週毎週、世界各国からやってくる刺客たちを迎え撃ってやっつけるタイガーマスク。その姿に自己を同一化させ、子どもながらに心の奥底に蓄積されていた日々のモヤモヤを解消させていた。自分も大きくなったらタイガーマスクみたいなプロレスラーになって、悪い奴らをやっつけたいと心から思っていた。
しかし、小学校も高学年になってくるとプロレスの仕組みに疑問を抱くようになった。なんでロープに振られて素直に戻ってくるのか? なんで絶妙のタイミングでレフェリーが失神するのか? なんで馬場は(以下略
そんな中、我らがヒーローであるタイガーマスクは大人の事情で新日本プロレスを離れ、UWFという団体にスーパータイガーとして現れた。UWFは、格闘技志向が強いプロレスをリング上で展開していた。ロープに振られても戻ってこず、コーナーポスト最上段からの攻撃は交わし、場外乱闘などもってのほかであった。しまいには3カウントルールもやめてしまい、KOかギブアップのみという現在の総合格闘技的な路線に舵を切りつつあった。
この路線を提唱していたのはかつてタイガーマスクの中の人だった佐山聡。しかしこの路線がプロレスファンたちに支持されるには時代が早すぎた。会場の客入りは悪く団体の存続も危ぶまれ、佐山選手は団体を追われるように去っていった。そして佐山選手は、後に修斗という名の総合格闘技を立ち上げた。
私も佐山選手とともにプロレスファンから足を洗った。
--
高校時代からまたプロレスを見るようになった。子供の頃よりも少しは世界の仕組みがわかるようになり、プロレスが持っている虚実入り乱れる世界観、今で言うところの『フェイクドキュメンタリー』的な魅力を感じるようになったからである。
当時のヒーローはUWFを再興させ、そのリアリティあふれるファイトスタイルで社会現象化させていた前田日明。そしてもう一人、巨大資本をバックにした新興団体による選手引き抜きにより、存亡が危ぶまれた老舗団体『全日本プロレス』の若きヒーロー三沢光晴であった。
奇しくも彼らは、私が小学生の頃に愛読していた『プロレス大百科』によると、それぞれ猪木と馬場の後継者候補筆頭の若手選手として紹介されていた二人だった。
三沢選手は全日本プロレスのリング上で、二代目タイガーマスクとして活躍していた。とはいえいくら才能に満ちあふれている選手でも二番煎じ感は否めず、初代ほどの人気は獲得できなかった。また高身長のため、初代のようにJrヘビー級で戦い続けるには無理があり、ヘビー級に転向した。さらに膝の大ケガも重なり、二代目はますます中途半端な立ち位置に追いやられてしまった。
そんな三沢選手が一世一代の大きな賭けに出る。
平成2年5月14日、東京体育館大会。主力選手の多くは新興団体に移籍してしまった。そして館外には雨が降りしきる、興行としては最悪の状況。客入りも悪い。そんな大会の中でも特に注目されてるわけではない試合。その試合で、二代目タイガーマスクは自らマスクを脱ぎ捨て、三沢光晴に戻ったのである。
三沢選手は団体存続の危機を救うため、そして自分自身の再生のために虎の仮面を投げ捨たのだ。
その後の三沢選手の活躍は改めて説明するまでもないだろう。若手選手を集めて『超世代軍』を結成し、当時の絶対エースであったジャンボ鶴田に戦いを挑んでいった。自分たちよりもひと回り大きく、身体能力が抜群でどんな技でもこなせる、さらに無尽蔵のスタミナを誇る、怪物と称された高い壁。その壁に向かって果敢にも戦いを挑んでいく若者たち、という構図は当時高校生だった私の心を捉えて離さなかった。
さらにその熱は普段プロレスを見ないクラスメイトの間にも拡散していき、毎週日曜深夜に放映される全日本プロレス中継の学級内視聴率は50%を超えた。月曜日の休み時間は私の周りにプロレス初心者たちが集い、昨晩放映された試合についての私の説法をありがたく聴いているという、一種異様な光景が繰り広げられた。
しかしそんな幸せな時代は長くは続かなかった。
--
平成4年11月、無敵の王者だったジャンボ鶴田は肝炎により一線を退くことになった。
対立概念を失った超世代軍は、超世代軍と聖鬼軍に内部分裂を起こし、両者の抗争が中心となった。あっけなく世代交代を果たしてしまった彼らはまるで共食いのような抗争に明け暮れることになる。一年中同じ相手との戦いである事情も相まって、マンネリを防ぐために技のインフレ化・カウント2.9の攻防をひたすら繰り返す悲壮感あふれる戦いが繰り広げられた。
時を同じくして海外から『バーリトゥード』という、ほぼなんでもありのリアルファイト(総合格闘技と呼ぶには、ルールをはじめとして未整備のものが多すぎた)が勢力を拡大してきた。時代の流れはリアルファイトを標榜していたUWF系(当時3派に分裂していた)に傾いていたのだ。その焦りもあってか三沢選手たちの攻防はエスカレートの一途を辿る。
リング上、エプロンサイドから場外のコンクリート床に向かって相手を脳天から真っ逆さまに落とすような、もはや技と呼ぶのも憚られる行為が当たり前のように行われるようになった。私は観戦を続けながらも心理的にはかなり引いていたが、表だって懸念を表明することはなかった。その頃、全日本プロレスの興行収益は過去最高を記録した。
私はそのまま会場から徐々に足が遠のき、平成10年にTV中継で三沢選手が『エメラルドフロージョン』という名称の新必殺技を披露したのを目の当たりにしてから、試合を観ることすらやめてしまった。
相手を脳天から真っ逆さまに1m以上の高さから落とします、以上。あれを技と呼ぶのは、私のプロレスファンとしての美学に反するからだ。そしてなにより、人一倍技や攻防に対して高い美意識を持っていた三沢選手が、こんなにも醜い技を繰り出すようになった現実を直視したくなかったのだ。
その後、プロレス界の流れはより一層格闘技路線に流れた。佐山選手や前田選手の後継者である、UWFでデビューした若者たちがバーリトゥードのリングに上がった。彼らは当時隆盛を誇っていたグレイシー柔術に立ち向かい、そして倒した。
全日本プロレスは総帥ジャイアント馬場の逝去をきっかけとし、ほとんどすべての所属選手が『NOAH』という三沢選手が立ち上げた新団体に移籍した。
私はプロレス自体をほとんど見なくなった。しかし平成2年6月8日、日本武道館で行われたジャンボ鶴田vs三沢光晴の試合だけは、事あるごとに見返していた。特に仕事で嫌な思いをした夜には、酒を飲みながらこの試合を繰り返し観ていた。そして三沢選手が鶴田選手からまぐれのような3カウントを取ったシーンで決まって涙腺が緩んだ。
--
平成21年6月13日土曜日。仕事を終えて帰宅したばかりの私は、三沢選手が試合中の事故で病院に緊急搬送されたとのニュース速報を見た。当時私はニコ生で『昭和のプロレスをまったりと鑑賞する会』という放送をほぼ毎日流していた。紆余曲折はあったが、子供の頃に見ていたプロレスは大好きなのだ。
さっそく三沢選手の応援放送を開始する。回復を祈って。視聴者がいつも以上のペースで増えていく。普段プロレスを見ない人も三沢選手の安否が気になっているようだ。
放送を続けている最中に、三沢選手の訃報が入った。三沢選手の応援放送は追悼放送にそのタイトルを変えて朝まで続けた。泣きながら続けた。
プロレスとは鍛え上げられた互いの身体をぶつけ合い、鍛え上げられた部位を攻撃し、全力で相手の技を受けるものだと思っている。それによって攻防の迫力と技の美しさが担保されるのだ。
しかし三沢選手を始めとした彼らの戦い方は一線を超えてしまっていたのだ。ある意味バーリトゥードよりも生命に危険が及ぶレベルまで至ってしまっていた。
そして彼らの戦いぶりにNOを突きつけるどころか、拳を振り上げ声の限り叫び足を踏み鳴らした。
より高く、より遠くへ、より急角度で、と選手たちを煽るように。
結果、プロレスは壊れた。プロレスラーは壊れた。プロレスを壊したのは私だ。
三沢光晴を殺したのは私だ。
--
この事件から10年経った頃、私は女子プロレスに起こっている国際化と世代交代に興味を持つことになった。
20世紀にこの世の春を謳歌していた全日本女子プロレスは倒産し、現在業界トップに君臨しているのは『スターダム』なる団体。日本中に数十の女子プロレス団体あれど、良くも悪くもスターダムを中心にこの業界は回っている。
現在の女子プロレス界最大のトピックは、この業界最大手である団体のトップレスラーであったカイリやイオが世界最大手のプロレス団体(女子プロレスだけではない)WWEに引き抜かれ、そのトップグループで試合をしていること。WWEでは女子に力を入れており、この団体の年間最大イベントである『レッスルマニア』で、2019年に初めて女子プロレスの試合がメインイベントを張ったところである。その流れの中で彼女たちは世界的に注目されているのだ。
そしてもう一つのトピック、それは『世代交代』だ。国内でトップを張っていた選手が海外に流出している。すると彼女たちの代わりにメインイベントを張る選手が必要になってくる。この状況は若手には大チャンス。団体側としても一気に世代交代進めるよい機会だ。スターダムは他団体の有望な若手を引き抜きに掛かった。その中の一人が木村花である。
日本とインドネシアのハーフ。母はプロレスラーにしてシングルマザー。子どもの頃から試合会場が遊び場という環境で育った。母のたっての願いで家業を継ぐことにする。新設されたプロレススクールの一期生となり、卒業後すぐにデビューした。
境遇が似ていることもあり、アジャコングに可愛がられる。いや、アジャだけではなくて、プロレス界に関わる多くの方々に愛されていた。なぜなら、その出自からナチュラルボーン・プロレスラーであるだけではなく、身体能力や技術を超越した『花』が備わっていたからである。
木村花は母の引退試合のタッグパートナーを務めたりしながら順調にキャリアを重ね、スターダムに引き抜かれた。スターダムでは『TOKYO CYBER SQUAD』というユニットのリーダーに納まり、団体が描くストーリーラインの中核に据えられた。その頃スターダムは、日本最大にして、世界第2位のプロレス団体である新日本プロレスの傘下に入った。
木村花はスターダムの広報的な役割を担うこととなった。そんな多忙な日々を送る中で、ひとりの選手がスターダムに移籍してきたのである。
その名はジュリア。日英ハーフであり、元キャバ嬢。お客様との同伴で女子プロレスを観戦しその魅力に取り憑かれ、プロレスラーになってしまったという変わり種。ジュリアにしろ木村花にしろ、こういった異邦人を受け入れて活躍の場を与えることこそが、プロレスの(特に女子プロレスの)持つ懐の深さである。
ジュリアも木村花も役割としてはヒール(悪役)ではあったが、現代のプロレスは20世紀とは違い、リアルファイト幻想は消滅している。あくまでもストーリーラインに乗った格闘芸術であると定義される。なので少なくとも彼女たちはダンプ松本のようにアンチから物理的に石を投げられるようなことはない。時代は変わって、プロレスラーにとってはある意味過ごしやすい時代ではある。
ジュリアと木村花はさっそくリング上でぶつかり合った。団体の要請があってのことであろうが、ヒールのポジションでトップに立てるのはひとりである。ふたりは対抗心剥き出しでぶつかり合った。令和元年12月、さっそく二人のシングルマッチがお膳立てされた。
ふたりは技らしい技はあまり出さずに、感情を露わにしてひたすら互いの肉体をぶつけ合った。結果は時間切れ引き分け。不器用で噛み合っていない試合ではあるが、見るものを惹きつける名勝負だった。実際、ファンの評価がとても高い試合となった。
こういう試合は男子ではあまり見ることがないので、女子プロレスが男子に対してアドバンテージを持つ機会点を見つけられたのではないか?と、私は興奮していた。
この闘いが何回か繰り返されれば、とてつもなく質の高い新時代のプロレスを観ることができるのだと確信していた。しかし、その期待は幻に終わった。
新型コロナウィルスの蔓延により、プロレスの興行が行えなくなってしまった。選手たちもファンもストレスがたまる状況が続く。そんな状況下で、木村花が団体の広報のために出演していた番組の演出によって炎上を生んでしまった。
SNSに無数に貼り付けられる悪意やら正義感やら。ヒールを職業にしているからといって、耐えることは容易ではない。そんな状況に対して、傍観者ではいられず、木村花に向けられた攻撃的なリプライに「もう、貴方みたいな書き込み見たくないからやめて!」と噛み付いた選手がいた。

その選手は、ジュリアだった。
ヒールでありリング上では敵対していても、それはあくまでもストーリーラインでしかない。リングを離れたら敵味方の役割など関係なく、一人の人間として動く。昔ながらのプロレスが好きな人から見れば言語道断、プロ意識のかけらもない行動にしか見えないのかもしれない。
しかし、今のプロレスは昔とは違う。紆余曲折を経て現代化したのである。
プロレスラーは進化した。しかし、観客は進化しなかったのだ。
「プロレスに筋書きはあるのですか?」「プロレスはヤラセですか?八百長ですか?」「プロレスはリアリティショーですか?」「リアリティショーはプロレスですか」「リアリティショーに筋書きは… 」
そして木村花は亡くなった。
私は彼女に対してなにもできなかった。いや、なにもしなかったのだ。
木村花は精一杯戦った。ジュリアも精一杯戦った。私はかつてと同じ過ちを繰り返してしまったのか?
木村花を殺したのは私だ。消えてしまいたい。

いただいたサポートは旅先で散財する資金にします👟 私の血になり肉になり記事にも反映されることでしょう😃
