
田山花袋「東京の30年」読書感想文
田山花袋は、ほとんど知らない。
名前は知ってる程度。
たしか大正だか明治あたりの、小説家の1人。
物置の本棚で見つけた。
題名で手を取る。
昔の東京が30年の間にどう変ったのか、ただ単に興味があって、田山花袋でなくても読んでみたい。
表紙の紹介文には「藤村、独歩、国男ら若い文学者の群像を描く」という一文がある。
国男とは、あの国男か。
柳田国男先生か。
半年ほどまえに、初、柳田国男を「木綿以前の事」で終えていて「おもしろかった」という状態。
初、島崎藤村を「破戒」で終えてもいて「以外に読めたもんだな」という状態でもある。
もう、これは読むしかない。
田山花袋について
本名、田山録弥。
1871年(明治4年)今の群馬県の館林生まれ。
田山家は代々館林藩士。
明治維新後に父親は上京して警視庁巡査となる。
1876年(明治9年)に、父親は妻子を東京に呼び寄せる。
ところが父親は、西南戦争で警視庁別働隊として戦死。
残された一家は帰郷する。
1881年(明治14年)に、11歳の田山は丁稚奉公に出されて上京して京橋の本屋で働く。
「東京の30年」は、ここからの30年が描かれる。
が、この本屋での東京生活は短い。
なにがあったのか、不都合があって親元に帰される。
1886年(明治19年)兄が都内の役所に勤めることになり、一家は市ヶ谷に住むことになって、15歳の田山は3回目の上京をする。
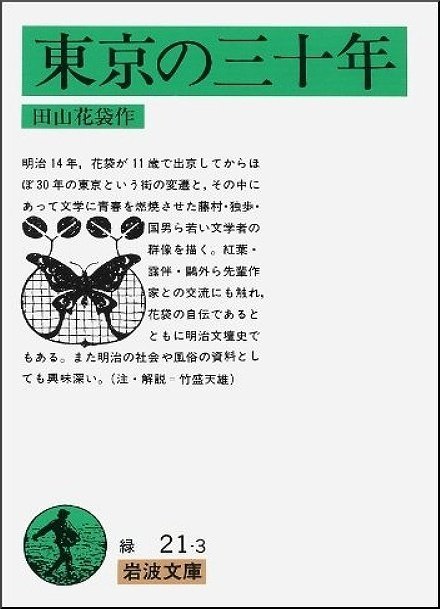
読感
読み終えた直後の感想
おもしろかった。
田山花袋をもっと読みたくなった。
新しく知ることばかり、想像することばかり。
いい読書をした。
全体の3分の1弱ほどは、東京の変遷の様子。
3分の1は田山自伝。
3分の1強ほどが明治の文壇史の解説となっている。
バランスがよく飽きない。
文壇史については、全く知らないことばかり。
自然主義派だとか、ロマン派などさっぱりわからない。
作家もうじゃうじゃと登場するが、聞いたことある程度か、まったく知らない人ばかり。
いかに勉強してないのがわかった。
でも、知らなくても、読んでいて苦ではない。
名前だけでも知っていると「あ!この人、知ってる!」と楽しい気分になった。
江戸から東京への変遷
期待とおりに、明治の東京の30年が描かれている。
すさまじいほどに、変遷していったのがわかった。
江戸時代の名残が全てなくなっている。
以前に、佐賀純一の「霞ヶ浦風土記」を読んだとき、当時は子供だった語り手の年寄りの1人が、明治の終わりにまだ祖父はちょんまげをしていたとあった。
土浦の街には、まだまだ江戸の名残が、そこかしこにあったと読んだ。
たとえば、道路にクランクがあるのは合戦に備えてだったし、堀川にある浅瀬も合戦のときに渡れるためだったり。
年号が変わっても人の暮らしは急には変らない、と柳田国男も「木綿以前の事」でも書いている。
それなものだから、江戸から明治にかけての街や暮しというのは、ゆるやかに変遷していったと想像していたけど、それは地方だけのことかもしれない。
東京に限っては、この30年の間に、江戸が跡形もなく消滅したのがよくわかった。
ちょいちょいと柳田国男が登場する
「東京の30年」はアルフォンス・ドーデの「パリの30年」が手本となっていると田山は明かしている。
そのように書くのを奨めたのは、柳田国男とも。
さすが、国男先生!
登場する柳田国男は、まだ若い。
養子になる前なので「松岡君」となっている。
若い柳田国男は、文学には進まずに官僚となる。
しかし、作家の集まりには顔を出して交流をする。
短命の人が多い
多数の人物が登場する。
第一に感じたことは、いかに短命の人が多かったのか、だ。
たしか、明治の平均寿命は40代前半だったと記憶している。
現在の半分だ。
幼児の死亡率が多かったのが平均寿命を下げている、という解説もあるが、若い人だって普通に死亡している。
この本に登場する、尾崎紅葉だって、国木田独歩だって、30代で病死している。
川上眉山だって、ゴシップに悩まされて30代で自殺してる。
ついでといってはなんだけど、登場した人を調べてみた。
二葉亭四迷は、45歳で病死している。
高山樗牛は、31歳で病死。
樋口一葉などは、24歳で病死。
この本には登場しないが、夏目漱石だって49歳で病死。
正岡子規は34歳で病死。
まだまた「人生50年」の世界だ。
昭和まで、80代や70代まで生きた柳田国男や島崎藤村が、あとは幸田露伴などは、いかに長生きしたことか。
ちなみに田山花袋は、58歳で昭和5年に病死してる。
田山から見た明治の作家の序列
明治4年生まれの田山から見ると、まず、井原西鶴の存在がある。
大御所といったところか。
そして、尾崎紅葉、幸田露伴。
彼らは、先生といったところ。
田山が20代になると、森鴎外が注目されはじめてくる。
森鴎外は、慕っている大先輩という立ち位置か。
島崎藤村と柳田国男とは同世代。
仲もよく、旅行もするし、集まって語り合いもする。
そうこうしてるうちに、国木田独歩、川上眉山、樋口一葉も現れる。
彼らがライバルといったところか。
二葉亭四迷が後輩格といったところか。
「彼が完成させる」といわすほどの才能を見せる。
不思議なのが夏目漱石。
これほど有名人なのに、ただの1度も名前が登場しない。
夏目漱石は1867年生まれだから、田山とは4歳違い。
同世代といっていいのに、30年を通して1度も書かれない。
あえて無視している、とも感じるほど。
交流がなかったからか?
まったく影響を受けなかったのか?
たしか、夏目漱石は東大の教授だったから、学者扱いだったのか?
もしかしたら。
夏目漱石の才能を妬んでいて、無視することで鬱憤を晴らしていたかも・・・と邪推する自分がいる。
ちなみに、正岡子規も1度も名前が出てこない。
彼は俳句だから、ジャンル違いなのか?
でも、田山も正岡子規も、日露戦争の際には従軍記者となっている共通点がある。
とにかく、超有名人の2人には、まったく触れてない。
自伝の部分はちょっと暗い
「自伝という性質上、誇張がある」とあとがきにはある。
「国木田独歩の死は各新聞が大見出しで伝えた」とあるが、実際には一紙だけだったという指摘も。
そうかもしれないが、そうも誇張は感じられない。
前半の田山には焦りがある。
「40代半ばの文章談をきいても、私たち青年にはなんの共鳴もない」と若い田山は気概に溢れているが、文は売れず注目もされない。
海外の本がたくさん入ってきて、なおかつ翻訳が進んで、影響を受けた斬新な作家も登場して、早くも田山も古い世代になりかけていく。
「これしかできなかったからしがみついてきた」と非凡さを書いてもいる。
この悲壮感と焦燥感が交じった自伝って好き。
多少の誇張があっても、ちょうどいいではないか!
小川の水車群の謎がとけた
明治10年に来日した「イザベラ・バードの日本紀行」を読んだときに「小川には水車ばかりある」と不思議さを持って書いてあった。
ひとつやふたつではない。
手に乗るような小さな水車が、手作りの水車が、どのような意味があるのか、あちこちの小川で大量に回っていると、イザベラさんは不思議がっている。
なんのためだろう・・・と自分も疑問が残ったが、おそらく、魔よけとか風習の類だろうと結論づけていた。
田山は、この水車群について2行ばかり書いている。
なんてことはない。
子供達のおもちゃだったのだ。
子供達がおもしろがって、いくつも手作りしては、あちこちに仕掛けていただけだったのだ。
しかし、驚きがある。
田山が書いているのは、明治30年頃の水車。
とすると、イザベラさんが不思議がっていたころからすると、少なくとも20年間は子供の遊びとして続いているのだ。
驚きではないか?
ただの水車のおもちゃが、なんてことはない水車のおもちゃが、飽きることなく世代を超えて手作りされて、大した意味もないままあちこちで大量にくるくる回っているなんて!
驚きでいえば、そこがいちばんに驚いた。
イザベラさんにも教えてあげたい。
あれは、ただの子供のおもちゃだったんですって。
あの不思議がりようからすると、たぶん「オウ!オモチャ!」なんていって驚くかもしれない。
あらすじ
1887年(明治20年)ころの東京
山の手は、まださびしい。
竹やぶ、梅の林、畑が続く。
狐が鳴く。
昔の御家人が、昔のまま住んでいるさびしい一画もある。
そのときの田山は、牛込の自宅から神田にある英語学校に通っていた。
文学に進もうと思ってはいた。
東京市中に古本屋がたくさんあったので、歩いて回るのが楽しみだった。
漢詩、漢文、文集、詩集といった本があった。
明治憲法が発布されたという。
役所は日本家屋に机を並べて、本棚を置いて、書類を作成していた。
まだ、鉄道などない。
表通りには馬車鉄道があり、馬車も走り、人力車も走る。
たいがいの人は、どこに行くのも歩いていく。
人通りは多かった。
いたるところに団子や寿司を置いた茶屋があったが、後に電車が普及するとなくなってしまう。
上野公園の桜はまだ小さい。
九段の靖国神社は、まだ招魂社とも呼ばれていて、鉄製の鳥居が立てられているところだった。
早稲田の学校は小さく、畑や田んぼの中に、ふたつみっつぽつんとあった。
一面の茗荷畑で、早稲田の茗荷といえばよく知られていた。
1892年(明治25年)ころ
都下は変遷する。
道路のあちこちは水道工事で泥まみれになっている。
新大橋が最後まで木橋だったが、近代的なものに架け替えられた。
火消し地がなくなり、通りが広くもなる。
外国人作家に影響を受ける。
トルストイ、モウパッサン、バルザック、ドストエフスキー、ツルゲネフ、イブセン、ニイチェ、ゾラ、ハイゼ、ドオデエ。
まだ翻訳ができてなくて、すべての本が英語版だった。
注文して届くまで2ヶ月かかった。
それらの本を英語で読み漁った。
日清戦争がおきたときの様子
日清戦争がおきた。
外国との最初の戦争だ。
清はアジアの大勢力なので、東京の騒ぎは非常だった。
日章旗で埋められている。
いろいろな軍歌も出てきた。
絶えず、号外の鈴の音が街頭に響き渡る。
人々は熱心な熱情と好奇心に駆られて、そわそわと落ち着かず、何者かに奪われた形になっていた。
成熟した人ですらそうである。
青山の練兵場から機関車で出発する軍隊を見に行く。
青山の原は、柵で囲われて内部はわからない。
しかし、喧騒は伝わってくる。
歩く音、話す声、馬がいななく響き、機関車の黒い白い煙。
軍歌の声が遠くで聞こえてきた。
悲壮な声だった。
やがて機関車が動く音がして「万歳!」という声も聞こえてきた。
これに限らず、都会も田舎もすべて興奮と感激と壮烈で満たされていた。
万歳の声は、あちこちから聞こえてきた。
その年の秋、徒歩で旅行をする。
水戸街道を仙台の方へと歩いた。
どんな田舎でも、山の中であっても、日章旗が風にたなびいていた。
維新の変置、階級の打破、士族の零落。
どうにもこうにも出来ない沈滞した空気が長く続いた。
そこから湧き出したように、漲り上がった日清の役の排外的気分は見事だった。
戦争罪悪論などは、また萌芽も示さなかった。
1895年(明治28年)ころの文学界
ドイツ、フランスといった大陸の思潮が押し寄せてきた。
いろいろな方面から新しい運動みたいなのが起こった。
森鴎外も文壇にデビューした。
彼の学識と読書は、10年も20年も先に進んでいた。
大きく影響を受けた。
森鴎外と二葉亭四迷が、若い人たちに気分を起こさせる動機をつくった。
泉鏡花、川上眉山、高山樗牛、徳田秋声、といった名前も出てきた。
が、新しい時代は圧迫された。
尾崎紅葉を中心にした文芸に、だ。
旧時代の大家とされた尾崎紅葉は、新機軸を打ち出そうと苦心していたが、陰に陽に常に新しい運動と戦ってもいた。
1897年(明治30年)ころ
文学をやる、というと低く見られた頃だった。
傑作を、傑作を書かずに道がない。
心の中で叫びながら、日々、創作に没頭する。
3年間に渡って書き続けた文章が、半分ほど売れた。
25円だ。
3年かかって25円ではな・・・と悲観した。
25歳になっていた。
3月には大火事がある。
神田一帯は灰燼となっている。
すさまじい大火事だ。
混雑と喧騒と恐怖で、街はざわ立っている。
火事は、日本橋、浅草に及ぼうとしている。
鳶のものは火事装束になって、ポンプをかけたり、家屋に上がり火の手を探したりと懸命に働いている。
九段の坂には、火事を見る群衆があった。
「もう、消防しても、どうすることもできないようだ」
「十軒店もあぶない」
「夜だったら見ものだろうな」
「きのうの夜は、なんともいえないくらいきれいだった」
それから数週間は、新聞は火事の記事ですべて埋められた。実は、書いた小説が新聞に載せられていた。
が、火事の話ばかりで誰もなにも言わなかった。
火事よりも、そっちが悲しかった。
国木田独歩も、よく訪ねもした。
自宅は駒場にあった。
渋谷の向こうは、野川に、田んぼが広がる。
茶畑に、大根畑も広がっている。
地平線には、武蔵野独特な林を持った低い丘が眺められた。
尾崎紅葉の死去
ゴッドフリード、パウプトマン、ズウデルマン、ピエル、ブレッド。
ダアウィン、ヘッケル、アルツィバセフ、クウプリン、アンドレーツ。
近松と西鶴しかなかった日本文学に、烈しく凄まじく大陸からの思潮が入ってきていた。
三千年来の島国根性、武士道と儒学、仏教と迷信、義理に人情、屈辱的犠牲と忍耐、妥協と社交の小世界、そういう中にニイチェの咆哮、イブセンの反抗、トルストイの自我、ゾラの解剖が入ってきたさまは偉観だった。
大陸からの思潮が、大きな運動となっていくときの尾崎紅葉の死だった。
高名で、門下生も多く、その葬式には馬車や献花で一杯で歩くこともできなかった。
大名か華族のような葬式をする文学者は、尾崎紅葉を以って終わりとするだろう。
友人の情、門下生の義理、そういったものに我々はあまりにも長く捉えられてきた。
これからは、個人に生きなければならない。
泣けてきた。
尾崎紅葉は、古いものとなったのだ。
1904年(明治37年)の日露戦争で
日露戦争が起きた。
その頃は出版社に就職していた。
従軍記者に志願して、戦地に向かうため軍艦に乗り込んだ。
そこで知ったのだが、その軍艦には、軍医となっていた森鴎外が乗り合わせていたのだった。
お互いに名前は知っている。
面識を得る機会でもある。
が、森鴎外のほうがずっと年上だし、すべてにおいて格上。
しかし、森鴎外は室内に迎え入れて、気さくに話してくれたのだった。
森鴎外に好意以上のものを抱いた。
文壇には、次々と新人が登場していた。
樋口一葉、与謝野晶子、土田敏。
土田敏については、森鴎外に続く才のある人だと感じる。
明治末期のころ
東京の発展は、目覚しいものがあった。
電車が通るために、繁華の場所も次第に変わっていった。
郊外に住む人も、買い物をするには近所でなく、電車で市街の中心に出て行くようになった。
三越、白木屋、松屋、という呉服店が大きな構えとなった。
電車が交差する、銀座、神田、上野の街は一変した。
大通りは、江戸時代の面影を失ってしまう。
破壊と建設の縮図は、東京にあった。
明治天皇崩御
「聖上危篤!」という号外の声が、街路を走っていく。
崩御の発表があったのは7月下旬だった。
大正となったのだ。
40歳を過ぎていた。
「布団」「生」「田舎教師」などの作品が評価も得た。
が、書いても書いても、おもしろいものは出来なかった。
倦怠と単調を感じる年齢となったのだ。
なにを見ても、なにを聞いても、つまらぬ色彩のないもののように思われ出してきた。
作家の第一の条件である「フレッシュに感じる」「驚異する」という心が希薄になっているのを見た。
同世代で交流もあった国木田独歩は、36歳で病死していた。
同じく交流もあった、川上眉山は自殺している。
若くして人気作家になった川上眉山だったが、批判にさらされていて、ゴシップに悩まされていて、39歳で自殺したのだった。
才があると感じた二葉亭四迷は、すでに45歳で病死。
そんなある日、島崎藤村と会う。
すでに作家として名が知られていた。
もう1度、修業に出るという。
フランスで生活をするという。
夫人に死なれて、今の生活から脱去しなければと思っているらしかった。
ラストの1ページほど
東京の上空には、飛行機が飛ぶようになった。
人々は皆、家から飛び出て、空を仰いだ。
木の上、二階の欄干、あちこちに飛行機を見上げる人の姿が見えた。
外国人の飛行家が宙返りを見せている。
人々は驚嘆の声を上げている。
こうした飛行機を、空の上に見ることになるとは。
30年前の東京にとっては夢想もしなかった。
ときどき飛行機は墜落して、その度に号外が出た。
犠牲者が出るたびに、航空術は進歩して、妙となっていく。
電話や電車ですら昔の人たちを驚かすに足りるのに、不思議だと思わせるのに、飛行機など魔法じゃないか。
文明は果たして、いかなる点まで進歩していくのか。
飛行機のうなり声が書斎の窓を震わせた。
ときには、飛行機が低く、裏庭の木立の梢の上に鳴って動いていくのなどが見えた。
