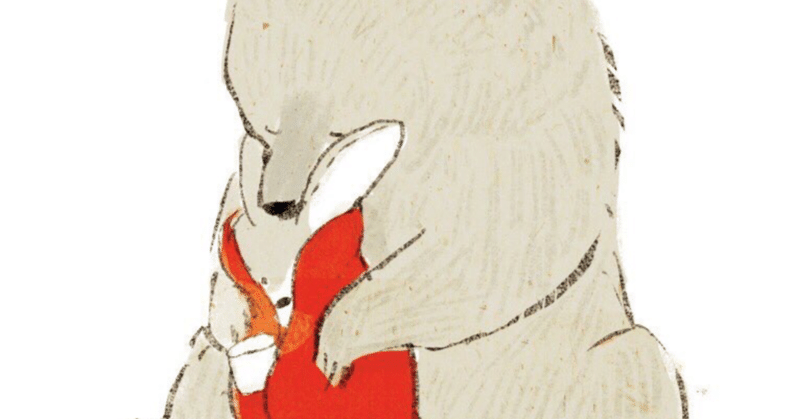
【子育て】社会に出たら、意外に必須能力かも「こじつけ力」~ただの遊びに”教育的価値”をこじつけろ!~#401
おはようございます、tamamioです(^^)子育て中の皆さん、今後、変化の激し社会を生きていくうえで、お子さんがつけておくべき能力は何だと思いますか?
基礎学力は必須、英語も、以前発信した「四つのC」も必要ですね。
今回は、絶対にこういった「まじめな話」では出てこないけど、意外に必要かも?と思う力について発信します。
1 「教育的価値をこじつけろ」
本日の参考文献はこちらです。
私は小学校教師です。本書はじめ、TOSS最高顧問・向山洋一氏の書籍は、年度初めだけでなく、折に触れ、何度も繰り返し読みます。
その中の一節に、とても印象的なものがありました。
班ごとに「卒業単元」の時間割をまず考えさせるのである。条件はただ一つ。「教育的価値をこじつけろ」である。「遊び」の時間ではないのである。
2 子どもが構想する「卒業単元」
小学校6年生の3学期は、実は比較的自由で時間に余裕のある時期です。確かに、卒業アルバム制作とか、卒業式の練習とかもあります。
が、授業に関しては、1月で「ほぼ終わり」になります。残りの期間は「まとめの時期」で、これまでの復習をしたり、ひたすらプリントをしたりするのですが、それだけではつまらない。
私は小学校時代最後の、そしてたった一回のこの時期の授業を、子ども達に構想させることにしている。それが「卒業単元」である。
3 tamamioも追試した「一日授業デー」
これは、私も実践したことがあります。と言っても、TOSSを始めてから6年生担任は今年が初めて。
なので「卒業単元」はありませんが、一日の時間割を子どもが考える「一日授業デー」は、何度も実践しました。
全て授業が終わった3学期末。班ごとに「一日の授業案」を考えさせて、各班にプレゼンさせて、多数決を取ったり「いいとこどり」をしたりして、学級の「一日の時間割」を作ります。
その後、全員が、何かの授業の担当者になり、その担当チームが45分を組み立て、準備、運営、後片付までするのです。
印象に残っているのは、2年生で「習字の授業」をしたことです。
本来、習字をするのは3年生から。まだ習字道具をもってないので、絵の具と絵筆と私が百均で購入した半紙を使って、子ども達は、思い思いにカラフルな書道作品を作り上げていました。
習字を習っている子達が「担当チーム」だったので、その子たちが「ミニ先生」になって、丸をつけたり添削したりする姿も可愛らしかったです。
4 ただの遊び→意味のある教育活動に!?
さて、向山氏の実践に戻ります。向山学級では、次のような案が出ました。
単元
A 百人一首(平安時代の勉強)
B 多摩川へ行く(社会科見学)
C マンガを読む(図画の勉強)
(中略)
G お店屋さんごっこ(社会・金銭感覚を身に付ける)
H のど自慢(音楽)
(中略)
J 昼寝(保健体育・身体を休める)
もう、見事ですよね。「ただの遊び」に、しっかり「教育的価値」がこじつけてあります。そして、保護者の皆さん、ご安心ください。この案が、そのまま「可決」とはなりません。
私の案も半分割り込ませた。例えば、一年からの各教材の授業である。(中略)NHKのクイズ面白ゼミナールの教科書問題作成に私が関係していたことから、教科書クイズも取り上げた。
こうして、「教科書にはない勉強」をさせてもらって、その合間に「教育的価値をこじつけた遊び」があるのですね。
5 実はすごい。この意見が出る学級(しかも6年)
もう一つ。「お店屋さんごっこ」や「のど自慢」が堂々と出てくる学級のすごさです。6年生と言えば、思春期の初期。まだ幼い子もいますが、斜に構えたり、陰湿な雰囲気を漂わせるグループもあったりします。
それが何の屈託もなく、子どもらしさ全開で「お店屋さんごっこ!」とか「のど自慢!」とか、無防備に言えてしまう。そこに向山学級のすごさが伺えます。
今回の発信はここで終わりにしますが、「なぜ、こじつけ力が必要なのか」にまで踏み込んで述べることができませんでした。
次回、こじつけ力が必要な理由とその実例をご紹介します!
では、今日も素敵な一日を!ありがとうございました!
6年生なんて、こんなものです。だからこそ、素晴らしく、可愛らしいのです。
私の創作活動の糧は「読書」です。より多くの書籍を読み、より有益な発信ができるよう、サポートいただけると嬉しいです。
