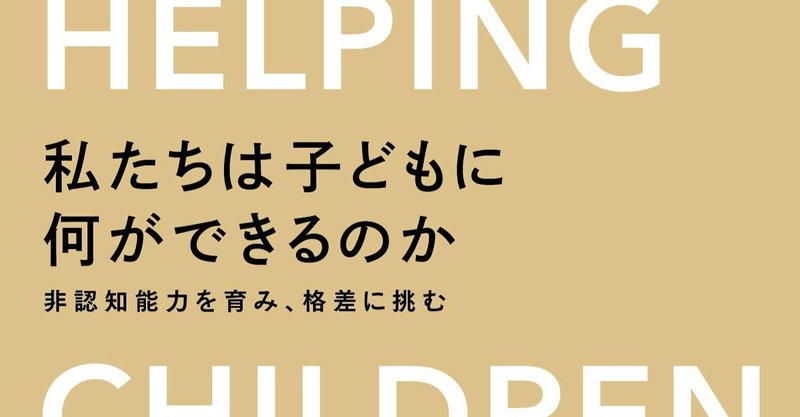
【育児】私たちは子どもに何ができるのか
非認知能力、これは教育格差を考える現場で議論されている言葉ですが、どんな状況でも通用する概念です。
教えない、指示しない、叱らない、ということを徹底します。子どもが自分で考える場を提供し、自由な発想が育まれると、教えられ、指示され、叱られて育った子どもたちより、成果を上げ、自主的に困難に立ち向かえる能力を身に着けます。
貧富の格差が激しい地域でも、この能力さえあれば、貧困から脱することができるものと注目されます。さらに一般家庭の人であっても、やり抜く力が身につけば、成功するチャンスも広がります。
そんなこと言われても、親としてはもどかしいし、つい教えちゃうし、つい指示しちゃうし、つい叱っちゃいません???言い過ぎを反省しながら、「子どもにはちゃんとしてほしいのよ。。」なんてつぶやいてません?
私なんて毎日です。
虫のノミ、あれ飛びますよね。実は自然界では2mくらい飛べるんです。でもコップにいれてフタをしておいて、しばらくしてからフタをはずしてみると、コップの高さ程度しから飛べなくなります。
すなわち、、、子どものため、自分の思う成長を遂げてほしいというその気持ちで行っている日々の小言、これ自体は日本のいたるところで見えるのですが、この教育やこの考え方自体が、自分の子どものキャップ(ふた)になってしまっているんです。
子どもにはのびのびいてほしいのよ、、、(毎日習い事で忙しいけど)
自分でいろいろ考える子になってほしいのよ、、、(毎日あれこれ注意しているけど)
自由な発想を磨いてほしいの、、、(いつも答えを探させてるけど)
子どもの好きにやらせてるわ、、、(自分の思った通りにならないと気分悪いけど)
どれをとっても矛盾だらけです。知ってますし、気づいてます。私だって暇なわけじゃないんです。でも気になるからつい、、、
非認知能力を養うためには、自分で考え行動するためには、「否定されてはだめ」なんです。ひたすら、「いいね」「で、どう?」を繰り返し、自分から考え動けるようになると、貧困からも脱する力を得るくらい大きな能力が宿るわけです。
今後の社会を考えるためにも、自分のわが子に生き抜く力、やり抜く心を育てるためには、まず、親は自らのメンタルトレーニング、コーチングを見直すことになり、まさに修行の日々だと気づくわけです。。。
明日は、何を選んでいても、どう決めても口を出すのはやめておこう。。
できるかな、私。
さ、明日に備えて寝よう。。。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
