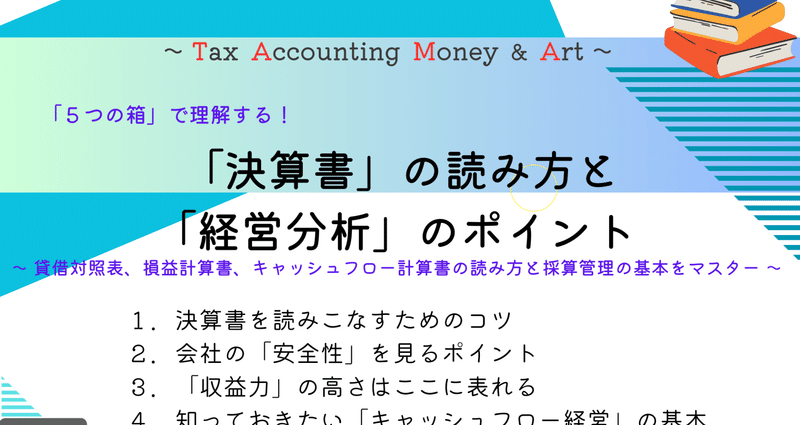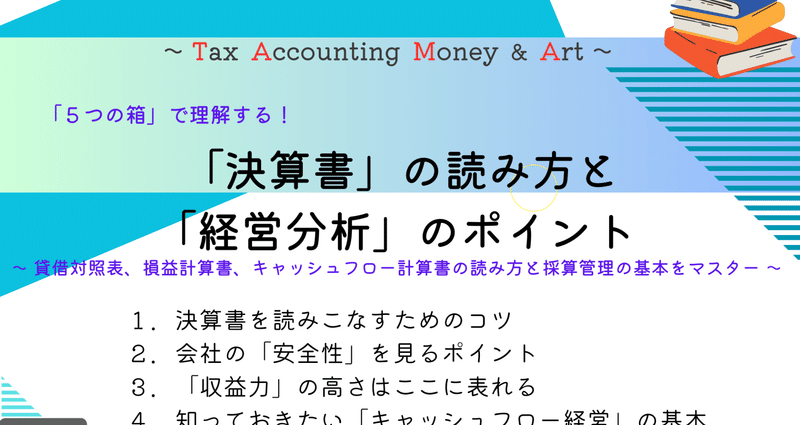第2章 会社の「安全性」を見るポイント
7.「運転資金」の管理で企業価値を向上!
会社を運転するために必要不可欠である資金
会社の資金繰りの管理と計画では、「資金」を次の3つに区分します。
1.日々の決済に充てる「現金資金」
2.本業を継続するうえで必要となる「運転資金」
3.設備投資を行うときに調達と運用のバランスを考えるべき「固定資金」
このうち、運転資金は信用取引(ツケ)と在庫(売れ残り)に関する回収と支払いの時間差から生じる資金であり、商売を維持(=会社を運転)していくうえで必要不可欠なお金をいい