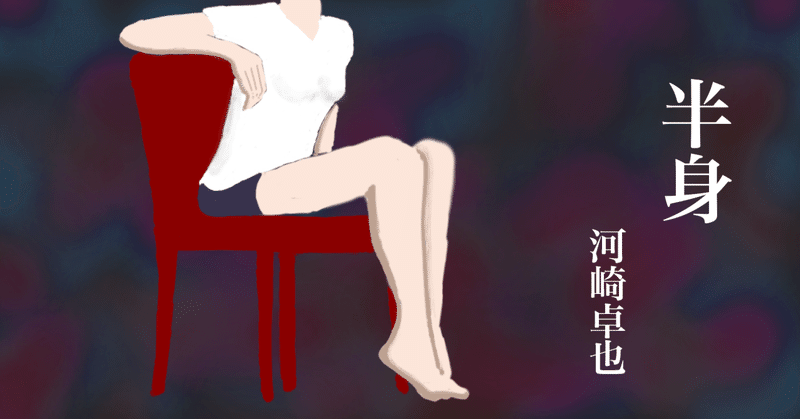
短編小説「半身」
「下半身を一晩お貸ししてもいいわ」と娘は言った。小さな声が夜更たマンションの一室に響いた。私はゴクリと唾を飲んだ。飲み込む音が聞こえなかったろうか、喉仏の動くのが見えなかったろうかと気にかけながら、私は落ち着きを演じた。
「いいのかい」
「ええ、そのために来たのでしょう」
彼女は微笑って言った。ネクタイを緩めながら私ははじめて娘を直視した。椅子に座った女は、二十歳過ぎ、あるいは十代、二十歳前。私にとっては小さな違いだが、何れにしても娘と呼ぶに相応しい歳のようであった。短く切り揃えられた艶やかな黒髪。白いブラウスのほど良い盛り上がり。ショートパンツから露わになった太腿は眩しいくらいに白かった。
「ちょっと待ってて。おつくりしますわ」
おつくりしますの意味を私は分かりかねた。彼女は椅子から立ち上がり、壁の方へ二三歩歩いた。腰付きにやや幼さを残したその女の歩き方は音楽的であった。彼女が演奏するとしたら何の楽器であろう。ヴァイオリンか、ピアノか、クラリネットか、あるいはティンパニだろうか。
クローゼットの扉をあけて彼女が取り出したのは両手引きの鋸だった。ノコギリ――。思いもよらぬ物があたり前のように出てきた驚きを私は隠せなかった。鋸を手にした彼女は何ごともない様子でスッと椅子に戻った。その一連の動きは、冷蔵庫からいつものアイスクリームを持ってくるように自然で滑らかだった。それから彼女は鋸を両手に持って腹に当て、わずかに上体を反らした。鋸の表面に映るブラウスの白が眩しい。そのブラウスが真っ赤に染まる画を想像して私は咄嗟に止めようとした。いけない、それはいけない。が、それよりも速くスッと横に引かれた鋸に私は声も出ず、ただ顔を顰めただけだった。
――何も起きなかった。シュコシュコと音を立てて当たり前に彼女の胴体が削れていく。血が飛散しているかに見えたのは削りカスで、それはキラキラと舞い上がり床に落ちて消えた。
柔らかい音とともに鋸の歯が動く。それに引かれて腰がわずかに揺れる。握った拳を左右に振りながら楽しく踊っているようにも見えた。彼女は微笑っていた。シュコシュコ。シュコシュコ。音もいっしょに笑っている。
やがて彼女の身体は上下ふたつに分かれ、鋸は重みで動かなくなった。彼女が鋸を勢いよく引き抜くと、弾みで上半身はゴトリと床に落ちた。切り口は凹凸のない平面で光沢さえあった。それは馴染みの中華料理店の叉焼のようでもあった。
「お貸しするのは下半身だけですの」
と、両手で身体を起こしながら上半身の彼女は言った。
「心と唇は愛する人のものなの」
私は愛する人ではないのか。そうには違いないのだけれど、それはわかってはいるのだけれど、私は何とも言われぬ寂しさを覚えた。今だけでも愛してはくれぬものか。私のものになってはくれまいか。いや、そんな勝手なことはない。そう思いながらも私は寂しかった。
ゴトリ。と、不意に下半身が椅子から落ちた。膝から崩れるように落ちたので自然と正座の格好になった。切り口はやはり叉焼のようであった。入れ替わるように上半身が椅子に這い上がって座り、上下が正しい位置関係になった。しかし、だからと言って違和感が私から消えたわけではない。
「どうぞよろしく」と、椅子の上の彼女は言った。正座した下半身を代弁しているようであった。私はやはり戸惑いを隠せずにいた。
「どうしたの?」と、彼女は微笑って言った。
「いや、初めてなもので……」
初めてという言葉を使ったが、それはこういう状況のことを指しているのであって、そういう意味ではないことは彼女にもわかっているはずだが、誤解されはしなかったかと私は少し後悔した。
「ふふふ」と、彼女は微笑った。
これも正座の彼女を代弁しているのだろうか。椅子の上の彼女と正座の彼女。それらは姉妹のようであり、上半身が姉で下半身が妹のようであった。私は姉の目の前で妹と戯れようとしているのだろうか。そう思いながら、もの言わぬ妹をベッドに運んだ。さほど重くはなく、乱暴に置いたわけではなかったが、彼女はベッドの上で小さく弾んだ。それは私好みの程よい弾み具合だった。私はベッドの端に腰掛け、眩しく光る腿に触れてみた。若く血の巡りのいい腿はやはり暖かい。
「私の手は冷たくはないか」
「じきに温かくなりますわ」
応えたのは椅子の上の姉だった。彼女は微笑っていた。その目は、どうぞお気になさらずにと言っているようでもあった。こんなことなさっておもしろいのと言っているようでもあった。犯せるものなら犯してごらんなさいと言っているようでもあった。犯すとはなんだ。彼女が望んだことではないのか。彼女が許したのではないか。私は今までいかなる女とも許し合っていたのではないのか。過ぎ去った関係を今さら問い詰められている気がした。いや、やましいことなど何もなかったはずだ。たとえ一時であっても愛し愛されていた。そう確信できる相手としか交わってこなかった。私を愛さない身体になど興味がないし、下半身だけを愛したことは一度もなかった。身体を求めたと同時に心を求めた。唇で互いを確かめ合った。唇こそ心と心の接点ではないのか。
だが、上半身が――その唇がないのだとしたら、どうやって心を通じ合えばいいのか、どうやって愛し合えばいいのか。私は今、心のない下劣な行為をしようとしているのではないか。
いや、彼女がいうように本当に心は上半身にしかないのだろうか。だとすれば、それはどこにあるのか。やはり胸だろうか。本当にそこにあるのだろうか。思い返してみると乳房に心を感じたことはない。むしろ私の愛に応えてくれたのは――。
背後で「ふふふ」と冷たい声がした。椅子の上の彼女は嘲笑っているようでもあり、私の心の呟きを聞いていたかのようであった。
ふと壁を見ると、そこに掛かった鏡に、シャツの裾がはみ出てだらしのない身体をした中年の男が映っている。戸惑い、情けない顔をした男が映っている。――何をしている。私は何をしている。
私は最早彼女を抱くことに無力であった。私は敗北した。何に敗けたのかもわからない。ただ私を締めつけるもの。おそらくは虚しさと孤独。今まで味わったことのない虚しさ。空っぽのくせに重い何かが私の胸を締めつけていた。こんな中年男を前にしてこの娘はどう思っているのだろう。姉のように嘲笑いはしないものの、私を憐れんでいるのだろうか。この部屋に来たときは確かに私の方が上に立っていた。若い娘を前にしてそれは当然のことだった。それが今はどうだ。この情けない私を彼女はどう見ているのだろうか。けれども敗北を認めた私にはどう思われようと構わなかった。むしろ私は娘に抱きしめられたいとまで思った。だが、抱き締める腕はどこにある。受け止める胸はどこにある。見下ろすとそこには腰から下のもの言わぬ娘がいる。彼女は私を受け止めることができないのだろうか。そんなことはない、ないはずだ。私はとにかく何にでも縋りたかった。
私は上体を沈め、彼女の白い両腿を抱くようにしてゆっくりと頭を預けた。頬に感じる温もり。柔らかい腿が脈打っている。私の頬は脈動とともに静かに沈み込んでいく。頭だけでなく全身が溶けてゆく。ああ、これだ。これだったのだ。受け止めてほしかったのは、縋りたかったのは。だが、彼女の腿は私の硬い頬骨を受け入れてくれているだろうか。微かに触れている顎髭はどうだろうか。そして、私の心は――。
いつしか私は眠りに落ちていた。
私は野球場にいた。フィールドには霧が立ち込め、スタンドには観客はひとりもいない。私はバッターボックスに立っている。マウンドには縦縞のユニホームを着た無精髭の投手がキャッチャーのサインに首を振っている。振り返って見ると上下くっ付いた彼の娘が正座してミットを構えている。彼女は微笑っている。
「下半身をお貸ししてもいいわ」
空虚な言葉が霧の中に融けていった
私は向き直って投球を待ち構えた。投手の腕が柔らかく振り出される。投げ込まれた球はキュルキュルと回転したまま、私の目の前でぴたりと止まった。
「お貸ししてもいいわ、お貸ししてもいいわ、お貸ししてもいいわ……」
針の飛んだレコードのように繰り返しながら回り続ける球を、私は狙いをつけて打ち込んだ。カキーン、ヒュー。打球は大きな弧を描いてバックスクリーンを直撃し、ポトリと芝の上に落ちた。振り返ってそれを見届けた投手は膝から崩れてマウンドに座り込んだ。遠くでファンファーレが鳴る。それを合図にブルペンから二人の小人が鋸を持って走ってくる。水平にした鋸の歯に冷たく月が映っている。気が付くと私はマウンドで正座していた。いつの間にか投手になっている。ザッザッ、ザッザッ。足音が誰もいない球場に響く。小人が足音とともに背後まで来る。ひんやりと腰に感じる器物の接触、皮膚を押す圧力、それが水平に移動する。ああ、二人でノコを引いているのだな。シュコシュコ、シュコシュコ。感触は段々前へ移ってゆく。叉焼の気持ちが少しわかった気がした。やがて、深い納得とともに私の上半身はゴロリと目の前に落ちた。
私は夢から覚めた。目の前には彼女の下腹部がそのままにあった。私の頬は彼女の腿に預けたまま、その柔らかさと温もりを感じている。ああ、これだ、やっぱりこれだ。だが、ふと、眠りに落ちる前とは異る感触を私は覚えた。腿が重い。ズシリと重い。私は手を伸ばして自分の腿のあたりを探った。しかし、そこにあるはずの腿はなく、空振りした私の手は平らな何かの表面に触れた。切り口?
背後で「ふふふ」と声がした。私は上体をくるりと回して声のする方を見た。その先には彼女が――姉であった上半身の娘が私とおなじ体勢で横になっていた。その頭の下には正座の格好の下半身が――筋肉質の、男の下半身があった。
「あっ」
私はふたたび腿のあたりをまさぐった。ない、ない。ないはずである。私の下半身は彼女の――姉の頭の下にあるのだから。なんということだ。私は膝枕をして貰っていると同時に膝枕をしてあげている。そして彼女も同じように――ふた組に分かれて。
私は対面する彼女の顔を見つめた。彼女は微笑っていた。それは嘲笑ではなく、感情の読みとれない不気味な笑いでもなかった。彼女は柔らかな眼差しをこちらへ向け、幸せそうに微笑っている。
私はそっと手を伸ばした。指先が彼女の手に触れた。彼女の指先が動いて私の指先と重なった。私は女と、はじめて繋がった気がした。
――了――
あとがき
この作品は、言わずと知れた川端康成の「片腕」からヒントを得たものである。冒頭の娘の台詞をはじめ、あちこちに「片腕」を思わせる記述が紛れ込んでいる。
もうひとつ、ヒントを得た作品がある。今井雅子の書いた「膝枕」だ。癒しを目的とした商品の膝枕が登場する奇妙な物語だ。もともとは「片腕」に着想を得た作品だそうで、Clubhouseで多くの方が朗読し、派生作品も多く生まれている。本作にも膝枕が出てくるが、これは膝枕という行為であり、商品は登場しない。つまり、今井雅子の「膝枕」からヒントを得たとはいえ、物語世界のつながりは全くない。
さて、物語の内容についても少し書こう。若い女が中年男に下半身を貸すというなんともゲスな設定である。「下半身を貸す/借りる」とは一般的にはそういう行為を想定すると思うが、本作でもやはりそのとおりの解釈である。ところが男は想定外の状況に陥る。ただのゲスでは終わらない。「片腕」同様の幻想小説を目指して書いたわけで、官能小説ではないのだ。言うなれば、ゲス・エロ・官能風味の幻想もどきか。ともあれ、私なりに楽しみも苦しみも今まで以上の作品となった。もしお楽しみ頂けたのなら幸いだ。
本作の朗読について
当面、本作の公共の場(インターネット上の空間を含む)での朗読は許可しておりません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
