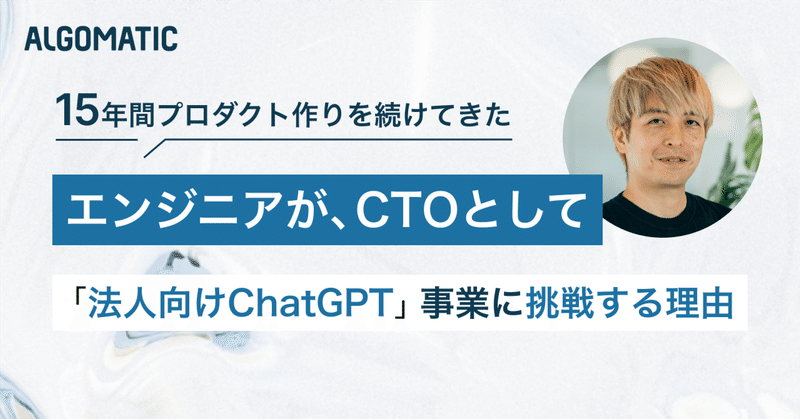
15年間プロダクト作りを続けてきたエンジニアが、CTOとして「法人向けChatGPT」事業に挑戦する理由
こんにちは、菊池です!2023年10月より株式会社AlgomaticにカンパニーCTOとして入社しました。実は入社の少し前から手伝ってきましたが、ようやく正式JOINとなりました。
Algomaticは生成AI領域に取り組むスタートアップで、今年の4月に創業しました。Algomaticではマルチプロダクト戦略を掲げて複数事業を立ち上げており、わたしはその中の1事業におけるカンパニーCTOを務めています。
各カンパニーは独立した権限を持っています。わたしは横断CTOをはじめとしたCxOとコンテキストを同期しつつ、カンパニーCEOとともに最大限の裁量とともに事業運営を任されています。

このnoteでは、わたしがAlgomaticで取り組んでいる法人向けChatGPT事業についてご紹介しつつ、入社理由やこれまで取り組んできたことを書いていきます。いわゆる入社エントリです。
「生成AIの活用」という、まだ誰も答えを知らない領域への挑戦
そんな経緯でAlgomaticに参画し、「シゴラクAI」というプロダクトにCTOとして携わっています。
シゴラクAIは、いわゆる「法人向けChatGPT」というジャンルの製品です。
ともすると「それって、ただのChatGPTの再実装ってこと?何がおもしろいの?」と思われるかもしれませんが、そんなことはなくめちゃくちゃ面白いんです。
突然ですが、シゴラクAIを使って、AIにこんな質問をしてみました。

現状のChatGPTは、この手の質問に正しく答えることをできないということは、生成AIについて知識をお持ちである方ならご存知なのではないかと思います。そういった知識に加えて「プロンプトエンジニアリング」という言葉も今では当たり前に使われるようになりました。
しかし、日頃から最新の情報や技術に触れることの少ない方々にとって、それらはまだまだ遠い世界の話です。チャットインターフェースを目の前にして、「AIに何を聞けばいいのかわからない」「自分の業務にどう活用できるのかがわからない」といった声も多いです。
ところで、GitHub Copilotは本当に良くできていますよね。私もコーディングでは手放せなくなっています。そんなGitHub Copilotがどう作られたのかが以下の記事で語られており、大変示唆に富んでいました。
書いてある内容全て有益だと思っているのですが、特に好きなポイントを抜粋すると、
生成AIのような新しい技術を使った製品開発は、未知の部分が多く、直線的な道ではなく、曲がりくねった道をたどることが多い。開発プロセスに迅速な反復サイクルを組み込むことで、チームは素早く失敗し、学ぶことができる
ここです。未知の部分が多いので、素早く失敗することが大事。プロダクト作りの原則ですよね。
他にも、サジェストしたコードの受け入れ率、コード保持率(開発者によって元のコード案がどれだけ保持または編集されたかを測定する)を指標として定義してウォッチするなど、愚直にやるべきことをやって作り上げたのがあの素晴らしい体験なのだな…と改めて認識したのでした。
ですが、プログラミング以外の業務にどう生成AIを活かせるのか?というのはまだまだ見えていません。シゴラクAIでは、そこを手助けすることで生成AIの価値を感じてもらうことにフォーカスしています。
それにしても、こんな王道かつ根本的な課題について、シゴラクAIだけでなく世界中のプレイヤーみんなが目下試行錯誤をしている段階です。誰もまだ答えを見つけていない問いなのです。そこに自分たちも横並びで立ち向かうと考えると、なんだかワクワクしてきませんか。
法人向けChatGPTづくり、楽しいです。
Algomaticとの出会いと4つの入社理由
そんなAlgomaticを知ったのは今年の5月、横断CTOの南里からのオファーでした。当時はAlgomaticでどんなカンパニーが立ち上がるかも見えておらず、ただ「これからどんどん生成AI領域の事業が立ち上がるから、そこでCTOをやってくれないか」とのオファーでした。
結果的にオファー承諾に至るのですが、どんなプロダクトに関わるかも知らない環境で、ただただ、Algomaticの環境に惚れこんでのオファー承諾です。今振り返っても、なかなかぶっ飛んだ意思決定だったなと思うのですが、決め手は以下の4つのポイントでした。
1. CTOとして、技術に関わる全てを自分自身の責任において取り組める
後述しますが、わたしはこれまで「与えられた制約条件の中で最大の成果を出す」ことを常に意識してきました。しかし、Algomaticではその制約条件すらも自分の責任のもとで決定し、ひたすら「最大の成果を出す」ことができますし、それが求められます。一切の言い訳がきかないチャレンジであり、自分の実力を試す最高のチャンスだなと感じました。
2. 会社の創業タイミングであること
プロダクトやシステムをゼロから開発してきた経験は多くありますが、「会社組織を真にゼロから立ち上げる経験」はありません。会社の創業に携わる経験は、今後の自分のキャリアを考えた時に絶対に外せない経験だと考えていました。さらにそれを、南里や大野のような最高のメンバーと取り組める環境は非常に魅力的でした。
3. 生成AIという、世の中を変えていく技術にフルコミットできること
弊社メンバーの多くが語るポイントですが、これは外せません。わたしがソフトウェアエンジニアとして15年近くキャリアを積み、やれることも増えてきたこのタイミングで世の中を一変させる技術の波がやってきました。ここまで積み上げてきた経験を、そんなチャレンジングな領域に注ぎ込めるチャンスは人生でもう2度とないだろうと考えました。
4. ソフトウェアエンジニアとしてプロダクト作りをしてきた経験が活かせると確信したこと
生成AIの非常に面白いポイントの1つとして、自然言語処理、機械学習に対する特別な知識がなくともアイデアやプロダクトの作り込み次第で世の中に大きなインパクトを与えられる、という点があると考えています。これだけ大きな技術の変革期に、自分の経験や能力が十二分に活かせるチャンスがあるわけで、これに乗らない選択はできませんでした。
自己紹介:15年間プロダクト作りを続けてきたキャリア
このあたりでそろそろ自己紹介をさせてください。
ざっくりいうと、大学院出てからずっとソフトウェアエンジニアをやっている人間です。プログラミングの原体験はRPGツクール2000で無理やりサイドビューバトルを作ろうとしたことで、趣味はドット絵と生クリームを飲むことです。
機械系学科からプログラマーへ
そもそも高専時代は情報系ですらなく毎日CADで図面を引いていた私ですが、大学進学のタイミングでCS系の学科に属することとなりました。そこで学業の足しになればとプログラマーのインターンを始めることになります。
インターン先は、Windows向けのセキュリティソリューションやアンチマルウェア製品を手がけるスタートアップで、APIフックやカーネルドライバによるファイルシステムフックなどを駆使してOSをハックするような、かなりニッチな開発に日々取り組んでいました。何より、とにかくめちゃくちゃ忙しいスタートアップでしたが…「常に文化祭の前日」みたいな雰囲気が楽しかったのを覚えています。
インターンとして頑張っていたところに入社の誘いをもらい、大学院修了のタイミングでそのまま新卒入社することになりました。
余談ですが、その頃の経験からわたしが書いた記事がこちらです。もはや今の業務領域とは一ミリも関係ないのですが、わたしがQiitaに書いた記事で一番ウケた記事になります。
「お金を稼がないと会社は続かない」と知る
その後、いくつかのスタートアップやメガベンチャーでソフトウェアエンジニアを続けていくのですが、この頃に「お金を稼がないと会社は続かない」という、至極当たり前な事実に気づきます。
とあるスタートアップでは、事業上の判断によって開発中のプロダクトがリリースされることなく凍結される、ということがありました。他にも、メガベンチャーの新規事業部門に所属している時には「事業としてやりたいこと」と「部門としての収支を健全化する」という両軸の活動が必要となり、それぞれにフルコミットできないジレンマに苦しみました。
中でも事業を存続させていく難しさや悔しさを痛感したのは、2018年からVPoEとして参画していたVALU社での経験です。VALUは何かと話題に事欠かず、ローンチ直後からほどなくユーザー数10万人を突破、会社としても5億円を調達するなど順調なスタートを切ってプロダクト開発を続けてきました。
VALUの初期コンセプトを活かしつつも持続可能なサービスとするため、カスタマージャーニーと向き合いながらプロダクトの磨き込みを続けましたが、2020年3月にサービスクローズとなりました。
これは単純なキャッシュアウトではなく、法改正などその他さまざまな要因があってのクローズではありますが、ソフトウェアエンジニア、そしてVPoEという立場においてもっとやるべきだったこと、やれたことがあるのではないかと今でも考えます。
VPoTとして「経営と技術をつなげる」ことに尽力
直近で所属していたShowcase Gigは、モバイルオーダープラットフォームを手がけるスタートアップです。累計60億円の資金調達を実施し、数千店舗規模の大型チェーンなどの導入実績を持つテクノロジー企業です。
ここでは、これまで以上に「やれることをなんでもやろう」と考えてきました。たとえば他チームの担当プロダクトで障害が発生した際、対応できるメンバーが不足していれば応援に向かい、初見のソースコードを読んで復旧にあたるなど、とにかく自分の責任範囲を制限しないようにしてきました。
そんなことをしていると、周囲から「システム全体を幅広く知ってそうな人」という認識となります。その結果、のちのプラットフォーム再構築プロジェクトではアーキテクトを担当することとなり、最終的にはVP of Technologyという役職に就き社内全体の技術を管掌する立場となりました。
VPoTとして私がミッションとしていたことは「経営と技術をつなげる」ということでした。Showcase Gigは創業10年を超え、エンジニア組織で40名ほどの規模になっており、経営の意思決定の背景や意図などがメンバーに伝わりにくかったり、ワクワクする未来をイメージしにくい、今後のプロダクトがどう成長していくかのイメージが難しい…などの課題がありました。
それらを払拭し、みんなが同じ方向を向いて、未来に希望を持って熱量高くプロダクトを育てていける組織を作りたいと考え、経営課題や事業の方向性などを透明性高く伝えるエンジニア全体会の開催や、プラットフォームアーキテクチャの未来像やそこに込めた意図などを社内にアウトプットしていきました。
わたしの取り組みは、一見するとテクノロジー感が薄い取り組みにはみえるかもしれませんが、良いプロダクト設計は深い事業理解から生まれます。ですので、上記の取り組みは技術的に最もレバレッジが効く取り組みだったと信じています。
また同時に、VPoEや人事メンバーと協力し採用活動にも尽力したことで、素晴らしいメンバーの入社も続きました。本当に熱量が高く素晴らしい開発組織ができつつありました。
そして、AlgomaticにシゴラクAIのカンパニーCTOとしてJOIN
そんな折、先述のとおり南里からオファーをもらい、Showcase Gigにおいて強い組織が出来てきたタイミングでもあり悩みに悩みましたが、AlgomaticにJOINすることを決めました。
そしてAlgomaticでは、法人向けChatGPT製品であるシゴラクAI事業にカンパニーCTOとしてコミットしていくことなります。
わたしはもともと大学で自然言語処理を専攻していましたが、当時から自然言語処理などの要素技術をアプリケーションとして実装することに関心が強くありました。なので、法人向けChatGPTという「いかにして生成AIを人々に使ってもらうか」という問いを続けるプロダクトは最高のテーマだと感じています。
「次世代の当たり前」をつくるチーム
そんなシゴラクAI事業では「非エンジニアが生成AIを活用するならこのスタイルだよね」という「次世代の当たり前」をつくり、すべてのデスクワーカーに生成AIの価値を届けていきます。

そこに最速で向かうために、プロダクトチームとして以下のような取り組みを続けていきます。
1. 「つくるべきもの」を作り続ける
シゴラクAIでも、「ここをこうしたい」「こういう機能を追加したら便利だろう」という「作りたいもの」はたくさんあります。リソースが無限にあれば全てを作る選択肢も出てきますが、そうはいきません。「なぜそれを作るのか」をチームで常に問い続けています。
その答えは、定量的なデータから得られるかもしれませんし、顧客の声かもしれません。あるいは個人の熱量かもしれません。いずれにせよ、「なぜ作るのか」を常に問いながら、「これを作るべきだ」というものを作り続けていくことが大切だと考えています。
2. 小さく試行し続ける
シゴラクAIが取り組む課題は、練りに練った機能をドカンと出して「どうだ!」と市場に問うよりも、1つ1つを小さく検証し、小さな失敗を繰り返していくことが大事だと考えています。ソフトウェアエンジニアだけでなく、プロダクトマネージャー、CS、セールスマーケ、みんなで協力し、常に試行を続けています。
3. 試行速度を高め続ける
開発生産性を高め続けるチャレンジは常に続けていきます。自己組織化された開発チームによって、毎週少しずつ「何かが良くなっている」状態を作り続けていきます。
また、「早く作る」ことは「雑に作る」こととは違います。洗練された設計を追い求めることこそが試行速度を高めていくとわたしは信じており、シゴラクAIでも設計の改善を常に重ねながら開発を進めています。つい先日もチャットやLLM呼び出し周りの設計をチームで見直しました。本当にああいうディスカッションは楽しいですし、そういった提案が自発的に生まれてくるチームは本当に最高だなと思います。
4. 楽しみ続ける
このnoteを書いている間も、生成AI界隈は新たなニュースが飛び交っています。生成AIのインターフェースという点では、ちょうどGPT-4VやChatGPTの音声対話などが使えるようになりました。純粋にWebアプリ、モバイルアプリとして観察してるだけでも、随所に工夫や思想が見え隠れしていて本当に面白いし刺激になります。
Algomaticでも、職種関係なく日々新技術に対して驚き、楽しみ、考察し、そして「じゃあ自分たちのプロダクトはどうする?」と考えを巡らせています。

ソフトウェアエンジニアだけでなく、セールス、マーケ、デザイナー、プロダクトマネージャーみんながプロダクトチームとして協力しあい、プロダクト開発を進めています。楽しすぎる。
わたしたちと一緒に未来を変えるチャレンジをしませんか
そんなAlgomaticでは、一緒に働く仲間を募集中です。
テックジャイアントもスタートアップも、みんなで生成AIという領域で高速で試行錯誤をしているお祭りのような状況、控えめにいってマジで面白いです。
「自分たち一人一人が、今この瞬間にどれだけやれるか」で半年先、1年先の未来が変わっていきます。それは自分たちの事業に閉じた話ではなく、生成AIを活用していく未来の姿が変わっていきます。
もちろん、他カンパニーのCEO、CTOなどなど、あらゆるポジションを積極採用中です。
最高に優秀なメンバーたちが「今しかない」と入社してくるAlgomaticに少しでも興味お持ちいただけたなら、ぜひカジュアル面談させてください!
「時代を代表する企業」を本気で目指すAlgomaticの創業期をぜひ一緒に楽しみましょう。
また、生成AI高専人会も発足しましたので、生成AIに興味がある高専人の方はぜひお気軽にご参加ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
