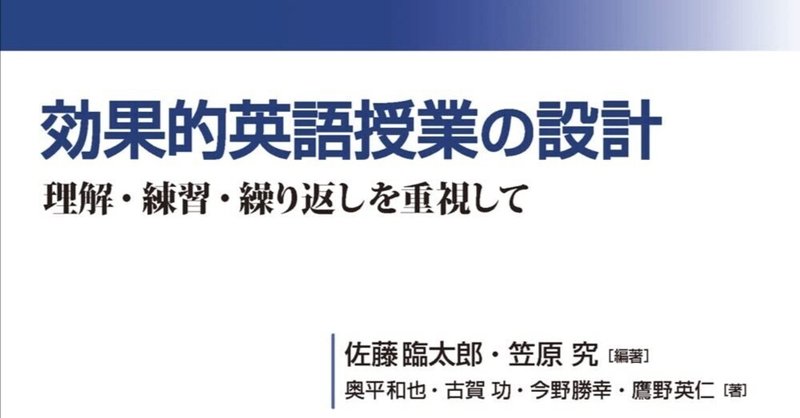
佐藤・笠原(2022)『効果的英語授業の設計 ―理解・練習・繰り返しを重視して―』
はじめに
前回、青木(1987)『いい授業の条件』について「期待していたよりずっと中身が軽い」と書いた記事を読んだ知人から、「めっちゃ昔の本だし大丈夫だと思うけど、こんなこと書いて怒られたりしないの?」と連絡をもらった。
私のnoteを読んだ上で、心配までしてくれる人がいるとは思わなかったので、ありがたい。
だが、(もしかしたら怒られることはあるかもしれないけど)怒られるようなことはしていないはずだ。
単に出版物に対する「受け止め」を書いたまでで、それは著者の人格への攻撃では決してない。
何故わざわざこんなことを書くかと言うと、今回の記事の方がよっぽど心配されそうだからである。
バリバリ大活躍中の先生方の出した新刊。twitterでも「英語科教育法の教科書に採択すべき!」みたいな投稿も見た。でも、それも書籍に対する評価であって筆者らの人格に対する評価ではないという点では私の記事と同じだ。
今回の記事には私の感情がいつも以上に頻繁に出てくるが、それは筆者ら自身に対する感情(好き/嫌い)ではなく、筆者らの「考え方」や「書き振り」に対する私の個人的な「受け止め」であったり、学術的な「批判」に過ぎない。
長々と書いてきたが、要するに筆者らご本人やそのファン・指導学生の皆さんの目に本記事が仮に止まっても、私個人を怒ったり吊し上げたりしないでほしいです、とお願いしておこうと(知人の心配を受けて)思った次第である。この記事に書かれていること自体に対する批判はいくらでも発信してもらって構わない。(むしろどれだけ記事を書いても引用RTもコメントもないので寂しいし、自分の実力不足を憂いている)
でも「どこの誰かと思ったら、全然研究歴もないクソ若造が吠えてるだけじゃん。先生が本気出したら潰せるっしょ」みたいな風には考えないでほしい。(過去にそういうことになりそうだった人も見たので、普通に想像したら怖くなった。)
なお、「その書き方は完全に人格の否定・攻撃です」という指摘も、あれば頂けるとありがたいです。
タイトルからしてあまり個人的に好きなテイストではないことは明らかだったが、英語科教育法の教科書としても使われることが想定されそうだったので、使命感で購入。感想としては「好きではないけど、概ね分かる」という感じ。
以下、冷静かつ公平にこの本のことを論じて紹介しようと思っていたのだが、今週ずっと科研費の申請書を書いていた反動とこの本を読んで生まれたモヤモヤがあまりに大きいのでかなりの乱文となっている。
なので、予めこの本について簡潔にまとめておくと、「生徒に英語を身につけさせるために、できるだけ無駄なことをせずに、力のつくトレーニングをさせてやりたいが、その方法がまるで分からない」という先生にはオススメだ。
逆に「英語の授業をもっと深く、楽しく、面白くしたい」「知識・技能を付ける授業はもうできてるから、思考力・判断力・表現力に繋がる授業をしたい」みたいな人は読まなくて大丈夫そうだ。
また、英語科教育法のテキストとして使用するのであれば、(仮に8単位あるとすれば)残りの6単位でどんなことを扱うのかも含めて検討が必要だ(まぁどんな本でもそうか)。
本書では基本的に英語の基礎的な力として文法・語彙、そして(それらを駆使して)話す力に特に主眼が置かれている。それ以外の部分についてはかなり手薄なので、これ一冊でバランスの取れた教育法のカリキュラムにはならない。(バランスとか、どの口が言う?という感じではあるが)
ちゃんと「理解・練習・繰り返し」を
この本の基本的な理念は副題にある「理解・練習・繰り返し」というフレーズに表されている。筆者らの問題意識は「コミュニケーション重視」やら「思考・判断・表現」やら「自律的学習」やらで、英語の基礎的な知識・技能が蔑ろにされている現状にある。(読んでる途中、結構「耳が痛いな…」と思うことも)
"Study hard, and practice a lot."(略してSHAPL)の考え方を改めて英語教育者に浸透させたいという思いがこの本には込められているようだ。(SHAPLの発音を誰か教えてください)
改訂型PPPの提案
TBLTだCLILだと盛り上がる英語教育界に対して、「もう一度PPPの価値を見直そう」と言い、そして従来の(クソつまらなかった)PPPよりマシな「改訂型PPP」というものを提案している。
筆者らの指摘する伝統的PPPの問題点は(1)インプット量の不足、(2)機械的練習への過度な依存、(3)言語の機能を学ぶ場の欠如だ。改訂型ではこれらの課題を乗り越えることを目指している。
改訂型PPPの最初のP、Presentation(提示)について、かなり長いが引用する。
(前略)文法の説明から入るのではなく、teacher talk / small talkによる英語での導入から始める。これにより、PPPの深刻な欠陥であるインプット量の不足という問題を解決し、言語習得の大前提条件である、潤沢で質の高いインプットを与えることになる。Talkの内容については、もちろん、先生方の自由な発想で決めてもらうことになるが、本時の内容と関連付け、さらに言語学習に寄与するものでありたい。具体的に以下の条件を提案する。
ア 潤沢な質の高い英語であること
イ 生徒が興味を持って聞ける面白い内容であること
ウ 内容が本時と(教科書)と関連があること
エ 前回扱った文法事項が含まれていること
オ 今回扱う文法事項が含まれていること
カ 生徒とのインタラクションがあること
small talkの後は文法事項の導入になるが、生徒の興味を引く例文を示しながらの演繹的指導を中心に、時より生徒に例文から推測させる帰納的指導を補完的に行うことを推奨している。この辺りの考え方にも「理解・練習・繰り返し」の「理解」を確実に行うことへの意識の高さが出ている。
続いてPractice(練習)では、パターン・プラクティスやオーディオリンガルメソッドの系譜に乗りつつも、単に習った文を繰り返すだけでなく同じ構造の中で少しずつ語彙を変えて練習させたり、自分にとって意味のある英文を書いたり言ったりすることを重視する。
そして最後のP、Production(使用)。
ここでの特徴は目標文法の使用の要求の強さで活動を2段階に分けている点だ。まずはある程度明示的に目標文法の使用を求めるような活動を行う。比較的、Practiceに近い活動だ。
第1段階の活動ができたら、次はもう少し目標文法の使用の有無を学習者に任せるような活動を行う。勿論、ここでも目標文法の使用が活動に役に立つようなものを用意するのが教師の仕事だ。自由度を持たせて活動をしてみた上で、目標文法を使うと便利であることを示して、もう一度やらせてみるというのも十分想定できる構造だ。
2つのPと3つ目のPに明確な線引きをせず、前者から後者への移行をよりグラデーショナルなものにするという点で、PPPに対する思い込み・呪縛みたいなものを少しほぐす役割を果たしている点が評価できる。
繰り返しへの意識
私が本書に見出す価値として最も大きなものが筆者らの「繰り返し」に対する意識の高さだ。生徒の英語力の定着にために繰り返しが重要なことを強調するばかりではない。(筆者らによると)コミュニカティブ活動は往々にして準備に時間がかかるため教師がつい敬遠してしまいがちだが、本書では改訂型PPPのPracticeやProductionの活動としてレベルを変えながら再利用可能なものを多く提示している。
特に第3章「分散スパイラル学習・帯学習」はかなり気合が入っている。英語科教育法的な本でも「繰り返し」について50ページ近く割いて理論や活動を紹介しているのは珍しい。
英語教育の教科書としては大きすぎる問題点
上に述べたような良さも大いにある本だが、どうしても指摘せずにはいられない問題もある。以下に3点に分けて論じる。
「明示的知識・暗示的知識」論法
本書、特に第1章に顕著なのが英語の知識を明示的知識から暗示的知識に移行していく的な発想だ。
明示的知識・暗示的知識については、筆者らの説明を引用しておくのがフェアだろう。
文法知識は2つの違った性質の「暗示的知識」と「明示的知識」に区別できるという考え方がある。前者の暗示的知識とは、文法の規則を説明できなくても、直感的にその文法が正しいかどうか判断できる知識、実際にある文法を使用できる知識である。
続いて、外国語として英語を学ぶ時、知識を明示的知識から暗示的知識にしていくことを目指すべきであるという主張について、仮定法過去を例に説明している箇所を引用する。
最初に仮定法過去とは「現在の事実と違う事柄を表し、If + 主語 + 動詞の過去形. . .。」のように規則を明示的に理解する。次に英文を覚えたり、表現を置き換えたり、さらにコミュニケーション活動で使用し、頭で理解した知識を実際に使える知識にしていく。練習や使用において、正しい表現を表出するのに最初は時間がかかるが、それは何度も繰り返すうちにスムーズに使用できるようになっていき、最終的ゴールである「自動化された知識」の習得ということになる。
筆者らの主張は【暗示的知識にしていくために、沢山喋らなきゃいけないんだ!ネイティブを見習え!】とかでは決してない。むしろ、【暗示的知識にしていくためにはまず明示的知識にするための明示的指導と、その後の練習が大事でしょ】というある種当たり前のことを改めて強く主張しているのだ。それ自体は悪くないと思う。SDGsについて空虚なディスカッションを拙い英語でやらされるよりずっと良さそうだ。
しかし、この明示的・暗示的知識の二分法、そして暗示的知識こそが最終的に目指すべきものという考え方を、少なくとも私は支持しない。それ自体が理論的に間違っているとか、そんなものは存在しないとかいう問題というよりは、学校英語教育の現実を考えたときに有意義に機能する考え方ではないということを言いたい。
まず、暗示的知識こそ良いものとする姿勢は、ネイティブ至上主義あるいは高すぎる目標につながる。不思議なのは、筆者らはEFL環境下での英語の教授・学習の難しさという問題意識から本書の議論を始めている(ように見える)にもかかわらず、暗示的知識を良きものとして扱いがちになっているということだ。別の箇所ではネイティブを目指す必要はないし、それは非現実的だという趣旨のことを言ってはいるのだが、だとすればここまで序盤で明示・暗示にこだわる意味が私には分からなかった。
加えて、こういう言説は明示的知識の価値を不必要に貶めてしまう可能性もある。学校で英語を学んだ先には別の言語の学びが待っているかもしれない。大学に進むと多くの場合第二外国語を学ぶし、私の勤務する北陸大学国際コミュニケーション学科では2年次で英語専攻と中国語専攻に分かれ、主として学ぶ外国語が中国語になる学生も一定数いる。他の大学にも沢山そういう類の学生はいるだろう。
義務教育課程及び高校での英語学習はあらゆる外国を学ぶ上での「言語」「言語学習」についての基礎的な学びとしての機能を持つ。その際、明示的知識を持っていることは必ず役に立つはずだ。だから「文法は説明できるようになるのではなく、使いこなせるようになれ」というのは、私はあまり積極的に支持できない。
特に小学校外国語(活動)に関して、簡単には説明できない母語(多くの場合日本語)についても(外国語、主に英語との比較も交えながら)その構造について認識・説明できるようになること、つまり「ことばへの気づき」を目指すべきとする大津の主張も重要だ。
大津のこの主張については、色々なところで書かれているが、最新版で言えば『どうする、小学校英語?:狂騒曲のあとさき』の「まえがき」にもまとめられている。
佐藤・笠原がネイティブ至上主義でもなければ、小学校英語を意識した本でもないことは承知の上で、それでも、日本の学校における外国語教育全体を見据えたとき、やはり私は本書に通底する「明示的知識から暗示的知識へ」という考え方に同意できない。
ルーブリックの杜撰さ
とは言え、「明示的知識から暗示的知識へ」という思考を常に持って英語教育実践に取り組む英語教師がどれぐらいいるかと考えると、そこまで多くはない気がする。なぜなら、生徒の知識が明示的か暗示的かなど確かめる術もないからだ。(確かめられるというSLA研究者もいるかもしれないが、学校英語教員がテストして確かめるというのは非現実的だ)
それよりもっと英語教育界に問題を持ち込んでしまいそうなのが、「コミュニケーションのための文法能力を測定する」(p. 35)ためのパフォーマンス評価で用いるべきとするルーブリックだ。改訂型PPPの最後のP、Productionにおける仮定法過去のパフォーマンス評価としてのインタビュー活動のルーブリックを以下に示す。

評価基準(評価項目と得点の交わる欄)の記述に複数の要素が入っている
評価項目ごとに得点が差別化されていない
主観的な表現が目立つ
ざっと上の3点が問題点として指摘できるだろう。尚、この「3点」について「まぁ、完璧なルーブリックはないから、いくつかの欠点は仕方ないね」という見方はできない。なぜなら、この3点が揃ってしまったのでは、ルーブリックとしてまるで何の役割も果たさないに等しいからだ。
まず「1.評価基準(評価項目と得点の交わる欄)の記述に複数の要素が入っている」ことについて。評価基準を見るまでもなく評価項目①の発話のところを見ればもう分かる。「発話」の中に「声量・発音・イントネーション」がまとめられている。これらの組み合わせが細かく示されているなら「不明瞭な発音ではあるが、めちゃめちゃ聞こえやすい声量で言ってる。」みたいな生徒も評価できるかもしれないが、評価基準を読んでもそのような生徒に何点あげれば良いのか分からない。そもそも複雑に入り組んだ要素をある程度細分化して示すのがルーブリックの役割のはずだ(ルーブリックは「細目表」という意味だと最近勉強した)。
続いて「2.評価項目ごとに得点が差別化されていない」ことについて。このルーブリックでは「発話」「表現」「文法」のそれぞれに1~3点が与えられている。仮定法過去を用いたコミュニケーションの達成度合いを判断するとき、「発話」「表現」「文法(の正確さ)」は全て同様に重要なのだろうか。
友人から貰うプレゼントを評価するとき(そんなことをするのは野暮なのだが、その嬉しさを分析的に捉えたいとき)、仮に「値段」「入手困難さ」「実用性」「インスタ映え度」の4つの指標を用いるとしよう。これらに25点ずつ割り振って100点満点として良いだろうか。「自分じゃなかなか買えないものをもらうと嬉しいから『値段』とか『入手困難さ』って結構大事なポイントかも」「パートナーからの誕生日プレゼントだとしたら、私は『インスタ映え度』より『実用性』が大事かな。そんでむしろ『値段』は低い方が嬉しいし」と、いろいろな考え方があり得るだろう。
(お笑いコンビNONSTYLEの石田さんがM-1グランプリの審査をするときの審査項目と得点の割り振りをネタや芸人によって調整しているという話を本当は書きたかったのだが、多くの人にとってのM-1の例えは、私にとっての車の例えぐらいピンと来ないらしいので自重した。ここでは「書き手の個性」より「伝わりやすさ」の方が大事だと判断したわけだ。)
上のルーブリックの話に戻ると、3つの項目を同じ点数で評価し、もしこれを合計して生徒に返したり、成績に反映させたりするようであれば最悪だ。もちろん、現場の教員が適宜点数の重みづけを変えれば良い話ではあるのだが、英語教師(志望の学生)のために書かれた本としては、そしてコミュニケーションで使える文法知識の獲得の重要性を謳うのであれば尚更、より妥当なルーブリックへの改変可能性が言及されるべきだ。
最後に、「3. 主観的な表現が目立つ」ことについて。「少なく」「不明瞭」「ほどほど」「おおむね」など、人によって大きく揺れそうな評価基準だ。ただ、声の大きさを「○dB以上」などと定めるのも非現実的なので、この辺については個人的には(教室での活動の評価に使う程度であれば)ギリギリ許せる。現実での利用を考えたら厳密さだけを追い求めるわけにはいかないのが評価の現実だ。
ただ、私が飛び抜けて許せないのは「相手と上手くコミュニケーションしている」の「上手く」だ。それが分かるのであればそもそもルーブリックが必要かどうかから見直すべきだろう。
なお、上のルーブリックは笹原・佐藤(2017)『英語テスト作成入門:効果的なテストで授業を変える!』(pp. 93-4)に掲載されているものらしい。
その問題点をここで指摘したわけだが、前著から5年間で改善に至るほどの批判が英語教育界からなされなかったのだとしたら、それも残念なことだ。
生徒観の浅さ
下に引用するように、この本は基本的に授業の楽しさを求めていない。
楽しい活動ではなく飽きさせない活動、努力させるのではなく行動を習慣化させる活動、自律性を高めようと試行錯誤するより、学習者自身やクラスメイトのために責任感をもって行える活動、気づいたらできていたと感じられる活動を考えていく必要があるだろう。
一方で、改訂型PPPの最初のPにおけるsmall talkの条件には「生徒が興味を持って聞ける面白い内容であること」が含まれ、2つ目・3つ目のPにおける活動については「インタラクティブである」「意味のある活動である」といった(Ortega(2007)の提案したEFL環境での練習としての)原則も取り入れいている。楽しさを追い求めるわけではないが、「無機質な英語トレーニングで良い」とはされていない。
しかし、全体を通してどんな内容が生徒にとって興味深くて面白いのか、意味があるのか、インタラクティブなのかという部分が何も考えられていないように思われる。
「生徒の興味を引く」ことについて、実際に使われている例文を見る。なお、教室には色々な生徒がいるので一概に「これは興味を引く/引かない」という評価はできないし、少なくともJohnとMaryしか出てこないような例文よりはマシなのだが、関係代名詞の指導について生徒の興味を引く例文として出てきたものに私は驚いた。
"Captain Tsubasa is a soccer player who can show wonderful skills."
40年前に出版された本の改訂版なのかと、思わず最後のページを確認したほどだ。(仮にそうだとしても例文を差し替えるべきだろう、普通。)
私はたまたま日本全国の26歳の中でもトップクラスのキャプ翼フリークだが、現在の中学生にウケるわけがないというのは流石に分かる。
そしてもっと大事なことだが、上の例文はキャプ翼フリークな私も別に英語学習者として興味を引かれる例文ではない。interestingかどうかは基本的に例文に内在する特性とは考えない方がいい。アーニャや炭治郎やキルアを出しておけば喜ぶだろうみたいな考えは、子どもを舐めている。(まぁ、なんでキャプ翼!?という意味では、実際のところ興味が湧いたのだけど。)
上の例文を出すのならせめてイニエスタがキャプ翼について語るインタビューや、先日パリ・サンジェルマンが来日した際に高橋陽一先生が生で描いたイラストへのメッシやネイマールらの反応でも見せて、(サッカー好きの)子どもたちに「キャプテン翼って何?」と思わせるのが肝、というかもはや子ども達への「礼儀」だろう。(私も学部3年生の時の模擬授業では意味もなく売れてる女優やアイドルを例文に使って、なんなら写真まで出していたが、今では恥じている)
活動が本当に「インタラクティブ」で「意味のある活動」かどうかも確かめたい。
ペアになり、以下の会話について、①役割を決めて、自分のパートをできるだけ暗記して会話しなさい。②次に( )を自分の場合に置き換えて会話しなさい。
A: What kind of person do you want to be in the future?
B: I want to be a person who (can help other people). How about you?
A: I really want to be a person who (can sing songs very well).
最悪だ。
こういう授業のせいで英語の授業が決定的に嫌いになったと言っても過言ではない。
こういうのはもうみんな「寒いよね」って気づいて、英語教育界から駆逐されたかと思っていたが、未だに(英語の先生向けの本で)出てくるのには正直驚きだし、残念だ。
生徒に英語で「将来どんな人になりたいか」を語らせるために私や同僚や中学生・高校生らがどれだけのことをしたか、というのはいつかどこかでちゃんと書いたり話したりした方がいいかもしれない。
過去にそのプロジェクトのクラファンへの協力を呼びかけるnoteを投稿していたので、一応貼っておこうと思う。
こういう全然興味を引かない例文を興味を引く例文として紹介してしまったり、インタラクティブで意味のある活動として(よっぽどのクラスじゃないと誰も本気で語ろうとしないであろう)夢みたいなものを語らせる活動を提案してしまったりする背景には、本書全体に(そして多くの英語科教育法系の本にも)通底する生徒観の浅さ、あるいは粗雑さがある。
第4章で「生徒の発話を促すフィードバック」を何種類かに分けて紹介している。そこから一部引用する。
1. Elicitation (誘出):生徒の発話中に適度に言葉を入れ、生徒の長い発話を引き出す。
S: It was raining but I got up to go jogging.
T: Though it was raining you . . . .
S: Though it was raining I decided to run because running in the rain is OK and comfortable for me. It was like taking a shower. I like it.
教師が短い言葉を挟むことにより、次に話すことを導くことができる。
こういう発話のできる生徒がいないと言いたいわけではない。でも、Elicitationの例としてこれが挙げられると、筆者らの想定している生徒たちが現実と乖離しているのではと考えてしまうのは私だけだろうか。
とは言え、上の例は本来教師のフィードバックとしての発話に注目すべきところなので、まぁ茶番として(おそらく教師のフィードバックなんてなくても)めっちゃ喋れる生徒の例を読まされているんだと思えばいい。
これはどうだろう。活動の繰り返しに関する記述だ。
スピーキング活動でも、"What did you do after school?"という毎回同じ質問を使用する。学習者は質問が分かっているので、"What did you eat?"、"What did you watch on TV?"、"Did you do your homework?"など他の質問も簡単に考えることができるので、学習者は話し続けることができる。さらに、解答をある程度用意することができる。「夕食に茄子食べたけど、茄子って英語で何というのかな」、「お笑い番組って、何ていうのだろう」と思い、事前に分からない単語を調べてくることが期待できる。
私の実力不足でこういう学習者集団を育てたことがないだけかもしれない。だとしたらこれは批判にも何にもならないのだが、本当にこのような生徒のあらわれは「期待できる」のだろうか。私が学習者として冷めすぎているのだろうか?
最後に、もっと深く学習者そのものについて書いているところから、また少し長いが、引用しよう。
最初に目標文法について、明示的に説明し、生徒に理解してもらうのだが、ここで例文を工夫したり、説明を英語で生徒とやり取りしながら行うことも効果的であろう。また演繹的指導ではなく、多くのインプットを与え生徒自身に気づかせる帰納的指導も考えられるが、最終的にはしっかりと解説し、明示的知識を獲得してもらうようにする。ここでの理解が「分かった!」という達成感につながる。次に目標文法を使った練習に入るが、暗記や繰り返しなどオーディオ・リンガル・メソッドに基づく練習を活用する。「言えた」「覚えられた」という小さい成功体験が次の活動への意欲につながり、より認知的負荷の高い、文脈の中でのコミュニカティブな練習へ移行していくことができる。
この文は生徒の情意面について「マインドセット」の観点から語っている部分から引用している。つまり、成長マインドセットで英語学習に取り組ませるには、というまさに生徒の心そのものの議論だ。
生徒の理解や知識の獲得だけでなく、生徒の心情についてもあまりに適当というか自分達に都合の良い書き方しかしない。
暗記や繰り返しが小さい成功体験につながる可能性は否定しないが、「つまらない」という感情につながり、もうその後の授業に乗ってこないという可能性も十分あるだろう。なぜそちら側の可能性についてはこんなにも論じられないのだろう。これは本書に限らず英語教育系の本でよく見る論法でもあるが。
この程度の記述しかしないのであれば、本来極めて複雑な「マインドセット」について論じるなどほとんど無駄に等しく、マインドセットを本当に大事にしたいのであれば、それについて詳しく取り上げた別の文献を案内するにとどめるべきだ。私には「こんな授業では生徒は乗ってこない」という現場の先生の不安や批判的意見を黙殺するための言い訳にしか読めなかった。
おわりに
冒頭に書いたことを(想像すると本当に恐いので、念のため)繰り返すと、本の内容に対して批判的・否定的であったとしても、それは著者に対する悪意、ましてや誹謗中傷の意図に基づくものでは決してない。
どうしても文章から読み取れる子ども観や教育観にまで踏み込むと人格攻撃かのように見えてしまう部分もあるかもしれないが、それも含め(学校英語)教育についての考え方に対する批判である。
ただ、noteを読んだ上で、私なんかのことを心配してくれた知人には感謝している。ありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
