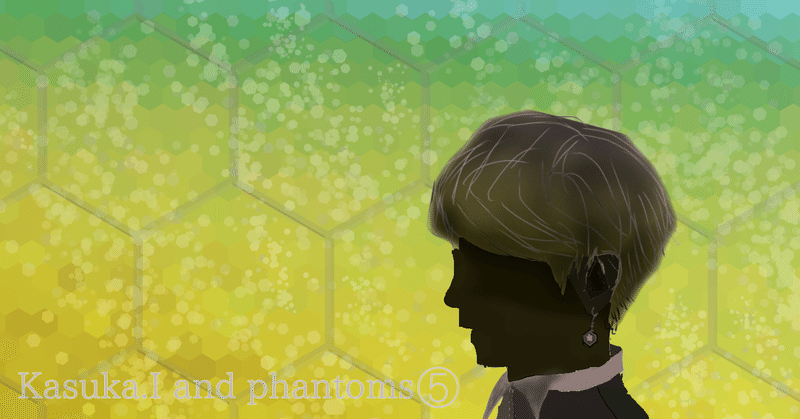
真夏に笑う猫(連作小説:微と怪異⑤)
ジリジリジリジリジー……というアブラゼミの鳴き声が耳の奥でしつこく反響している。
よく晴れた7月中旬の正午過ぎ。N市駅から少し歩いたところにある住宅街には、容赦ない太陽の光を遮るものは何もない。
烈しい熱波をアスファルトが照り返し、道を歩くとさながら焼肉屋の鉄板の上にいるかのような気分を味わえる。
道の両側にある住宅の壁に這わしたツタ植物も、住民が地面にまいたであろうシャワーの水も、この暑さにはとても太刀打ちできない。ただでさえ閑静な住宅街には、全く人の影が見当たらない。
その住宅街を、夕月健太はシャツにネクタイ、スーツのズボンという暑苦しい格好で歩いていた。オフィスにいた時はジャケットも着ていたが外に出た瞬間に脱ぎ、手に持っている。
「……何もこんな日に銀行行かせなくてもいいじゃないか」
夕月はN市内にある中小企業の経理兼庶務(つまり何でもやる)担当だ。
旧態依然を絵に描いたような彼の会社では、熱中症警戒情報が出ようと皆ジャケットにネクタイを締めているし、外に出るのに日傘を持って行こうものなら数日間笑い物にされる。
かくして、会社の中でも比較的若手な彼は、歩いているだけで干物になってしまいそうな真夏日に、無防備な格好で銀行と細々した事務用品を買い足しに外を出歩いている。
少し風が出てきた。こう湿度が高くては生ぬるい空気が掻き回されるだけだが、ほんの少し気分は楽になる。
だが、今頃上司たちは冷房の効いた部屋で冷たいお茶を飲んでいるんだろうな、などという考えが浮かんで、また気分が悪くなった。
しばらく歩いているが、喫茶店はおろか自販機も見当たらない。大通りは人も多いし信号に捕まるし、と近道のつもりで住宅地を突っ切るルートを選んだのが裏目に出た。
鞄のポケットに入れたペットボトルのお茶を一口飲むと、ぬるま湯のような液体が僅かに口と喉を湿らせた。
「…………何やってんだろうな、俺」
夕月は立ち止まり、自分の短い影を見つめてため息をついた。立ち止まっている彼にも、太陽は容赦ない熱波を浴びせる。
ふと、彼は鞄のチャックを開けた。会社名義の口座の通帳とカード、今度の支払いのためにおろした分厚い現金が入っている、銀行の封筒。
耳の奥で反響するセミの声が一段と大きくなる。額から流れる汗が、顎を伝って鞄の中に落ちる。
「…………」
夕月は首を振って、顔を伝う汗を振り払った。だが、自分の中に沸き起こった考えを振り払うことはできない。
「……俺がいなくなっても、誰も気にしやしないだろうな」
なーん。
どこかで、猫の鳴き声がした。
夕月は鞄から顔を上げた。
左側にある古い木造住宅の壁の前に、一匹の黒猫がいた。全身の毛は天鵞絨のようにツヤツヤしている。首輪などはしていないが、野良猫という風体でもない。
猫は、こちらをじっと見つめていた。黄色いビー玉のような眼球に、糸のように細い虹彩。
絵に描いたような黒猫だ、と夕月は思った。こんな暑い日でも、猫は外にいるものだろうか、とも思った。
なーん。
猫はこちらを見つめてまた鳴いた。鳴くと同時にその猫は、口角を吊り上げるように口を開け、口の端から牙をのぞかせる。
まるでぎこちない笑顔のようだ、と夕月は思った。
猫はこちらに背を向け、地面をトコトコと歩いたかと思うと、またこちらを振り返って鳴いた。ついてこい、とでも言いたいのだろうか。
夕月は思わず後を追いかけた。猫はずんずんと路地を進んでいく。
猫が通る道はなぜかどこも日陰が多く、先程の道より温度が2、3度低いように感じられた。自然と汗が引き、あんなにしつこかったセミの声も聞こえなくなった。
代わりに、住宅地のどんどん狭い道へと彼は進むこととなった。
民家と民家の間の、人ひとりしか通らない住民の通行路も、最初は躊躇ったが、猫に促されて通り抜けるうちに、だんだん楽しくなってきた。
狭い道を通るのに邪魔だと思ったジャケットは、捨て置かれた自転車の籠に放り込んだ。ついでにネクタイも外した。
自分と猫以外誰も歩いちゃいない、と思うと、気分が軽くなってきた。
そのうち彼は、猫に行き先を決めてもらうのはなんて楽なんだろう、ということすら思いはじめた。角を何度も曲がり、会社がある方からどんどん離れていっても、彼は気に留めなかった。
この方角をそのまま行けば、いつか港にたどり着く、と彼は気づいた。
港でフェリーのチケットを買って全然知らない街に行ってもいいし、何なら空港への連絡便に乗って、海外に行ってしまってもいい。そう思うと、心が軽やかになっていく。
細い道を何度か抜け、横断歩道のある少し広めの通りに出た。歩行者信号は赤だが、車が来る気配はない。平然と道を横断する猫について行こうとしたその時、
「おーい、そこのお兄さん。トムヤムクン、一緒に飲みませんか?」
変な言葉が、夕月の耳に飛び込んできた。彼は足を止めた。
「よく冷えてるんですよ、トムヤムクン。一緒に、飲んでくれませんか?」
低く、少し気怠げな、女性の声だ。「よく冷えた」「トムヤムクン」を「飲む」。一つひとつの言葉は理解できても、文章としては意味がわからない。
女性は、彼の右手にある建物のドアを細く開き、こちらを覗いていた。
古い木造の民家だと思い込んでいたその建物は、よく見ると「民芸品 IIKI」という看板が出ている。
なーん。
道を渡り切った黒猫は、こちらをじっと見つめて一声鳴いた。その声が、どこか不服そうに聞こえたのは、気のせいだろうか。
「お兄さん、スーツに黒い鞄のお兄さん……」
女性は、ドアの隙間をすり抜けるようにして出てきて、夕月のすぐ横に立った。
「……俺、ですか」
「そう、お兄さん。あ、ここの道、誰もいないと思って猛スピードで通りすぎる車いるから、ちゃんと信号守った方がいいですよ。見通しも悪いし」
道路の向こうに目をやったが、先程の黒猫はどこにもいなくなっていた。道路の反対側は、こちら側と打って変わって、コンクリート製の集合住宅が多いようだった。
その合間に何故か小さな神社があり、境内で盛んに鳴くセミの声がこちら側にも聞こえている。
「そんなことよりお兄さん、トムヤムクン飲みませんか?」
「それは……何かの隠語か何かですか?」
夕月は少し警戒していた。怪しげな店構えの民芸品店から、髪を青色に染めて派手な銀色のイヤリングをつけた女が現れて、警戒しない人間の方が少ないだろう。
「やだなぁ、そのままの意味ですよ」
「実はお客さんに食品メーカー勤めの人がいてね、新商品の試作品作ったから感想聞かせてって言われちゃって。その名も『冷やしておいしい 飲むトムヤムクン』って……トムヤムクンは好きだけど、ちょっと一人で飲む勇気はないなぁって」
「はあ……」
「誰かに一緒に飲んでもらおうと思ったけど、そういう日に限ってお客さんは全然来ない。まあこの暑さじゃ、誰もうちの店にわざわざ来ようと思わないだろうけど」
「そんな時に! お兄さんが通りかかったから、声をかけたんですよ」
「なるほど……?」
女は、一応納得した風な夕月を見て、ニコリと人懐こい笑みを浮かべた。
「どうぞ、中入ってください。トムヤムクンを飲んでもらう以外、何も売りつけたりしませんよ。冷房が効いてますし、つい先日、ウォーターサーバーをつけたばっかりなんですよ。どうぞ」
☆ ☆ ☆
レジ脇に置かれた折りたたみ椅子に座り、夕月はコップになみなみと注がれた赤い液体と対峙していた。その横には、とにかく目立つゴシック体で「飲むトムヤムクン」という書かれた500mlの缶。
店内のはクーラーがきいていて、サーキュレーターまで回っている。奇怪な仮面や人形と一緒に飾られたウィンドベルが風で時折カラカラと鳴っている。
「ささ、どうぞ、飲んでください」
先ほどの女性が店の奥から出てきた。女性はこの店の店主だという。こういう雑貨屋って採算取れるんだろうか、と夕月は密かに思った。
レジ前に置かれた『N市水菜区図書館 こわいお話会』というビラには「怪異研究家 井城微」という名前がある。これが店主の名前だろうか。
「いいき...…かすかさんとおっしゃるんですか?」
「ええ。ああこのイベント、司書さんが常連で、去年から読み聞かせ会やってくれってお願いされてて。意外と好評でね。それ聞いた小学生がたまにこの店に来てくれたりしますよ」
夕月が内心半信半疑なのを悟ったのか、微はいたずらっぽく笑って付け足した。
「あそこに飾ってあるミサンガとか、人気ですよ。目玉の魔除けは気持ち悪いって言われちゃいましたけど...…さあ、飲んでみましょうか」
微はコップの液体の匂いを嗅いだあと、ぐいっ、と一口飲んだ。夕月も覚悟を決めて一口飲む。
口に入れた瞬間、強烈なライムとエビの匂いが鼻を通り抜け、そのあと、爽やかな辛みが口と喉を刺激する。
「...…冷たい、トムヤムクンですね。普通に美味しいですけど」
500mlの缶1本くらい飲みたいかって言われたら、要りませんけど、と夕月は付け加えた。
「うん、うん...…トムヤムクンですね。飲みやすいように薄くはなってるけど。思ったより美味しい」
微は、特に顔色を変えるでもなく、そのままコップの中身を一気にあけた。
夕月も、半ばヤケクソになりながら、コップに残った液体を、一気に喉に流し込んだ。
辛い。そしてそれでも半分ほど残ってしまった。
涙目になった彼を見て、微はウォーターサーバーで紙コップに水を汲み、テーブルに置いた。
「ありがとう...…ございます」
「いえいえ、わざわざこんな暑い中、辛いものを飲ませてしまって……お仕事ですか? この辺りはオフィス街から遠いので、スーツ姿の方は珍しいですね」
微はなんとなしに尋ねた。その言葉に夕月は少しぎくりとしながらも、なんとか答えた。
「...…ええ、まあ。外回りの最中だったんですけど、会社まで近道しようと思ったら、道に迷ってしまったみたいで」
「ああ、確かにこの辺りは路地が入り組んでますよね」
「ええ、細い道が無秩序に並んでいて......」
「この辺り、戦前からある古い住宅が多いんですよ。表通りに近いところだと、戦後の区画整理で随分綺麗になりましたけど、この辺りは昔からの狭い道とかも多いんです」
夕月は先程の道のりを思い出し、微の言葉に頷いた。木造住宅に挟まれた細い道は、確かに昔の面影を残しているものだった。
「そういう古い道なんで、近所の小学生の間で、路地に出る怪異の噂が流れてたりするんですよ」
微は目を輝かせてそう言った。
「怪異...…ですか。お化けとか妖怪みたいな」
夕月は先程のビラに書いてあった彼女の肩書き「怪異研究家」というのを思い出していた。
「そうですね。『すねこすり』『べとべとさん』とか、道でばったり行き合う妖怪って、たくさんいるんですよ」
「へえ...…」
「妖怪は街灯もない暗い夜道に出るのが多いですけど、例えば『口裂け女』は別に夜限定のお化けじゃないですよね。小学生の登下校の時間帯なんで、夕方にしてもまだ明るいはずです」
「じゃあ、こんな暑い真っ昼間に出る怪異もいるんですかね?」
夕月は半ば冗談でそう言ったが、微の返事は意外なものだった。
「いますよ。最近小学生の間で噂になっている、『笑う猫』の話なんて、真夏の真っ昼間に出るって言われてますよ」
「笑う...…猫?」
「『不思議の国のアリス』に出てくる猫みたいな感じですかね? こう、ニイって笑うらしいんです」
そう言うと、微は自分の口角を両手の人差し指で引っ張り上げた。
「夏休みの真っ昼間、塾とかプールの帰りに1人で路地を歩いているとき、『笑っている』猫についていってはいけない、って噂らしいです」
「ついていくと...…どうなるんです?」
夕月が震える声で聞くと、微は顎に手を当てた。
「それがはっきりしないんですよ。どこか遠い世界に連れてかれる、グレてしまうとか、人が変わったように乱暴になるとか、色んなパターンがあって」
「たぶん、まだ情報が錯綜してるんだと思います。そのうち他の都市伝説みたく、『あの世に連れて行かれる』みたいなのに落ち着くんでしょう...…」
「でも共通点を挙げるなら、何かしら理性を失って、小学生でいう『悪いこと』をするようになるってことですかね」
「理性を失う...…」
「妖怪でいえば、『後神』みたいな感じですかね。『後髪を引かれる』って言葉があるように、何か決断しようとするのを引き留めたり、逆に唆したりする怪異」
こう暑いと、何かに唆されたらまかり間違ってしまいそうですよね、といって、微はニヤリと笑った。
夕月は、手の震えを抑えながら、コップに残ったトムヤムクンを一気に飲み干した。辛い。むせて咳が出てくる。
「大丈夫ですか? そんな無理に飲まなくても」
「いや...…この変な飲み物のおかげで、目が覚めた気がします」
微は不思議そうな顔で夕月を見た。
「なんだか顔色悪いようですけど、大丈夫ですか?」
「だ、大丈夫です。そろそろ会社に戻らないと」
「あ、それなら」
微は立ち上がると店の奥から真っ黒な折り畳み傘を持ってきた。
「一緒に飲んでくださったお礼です。『烏の濡れ羽色の日傘』って言うんですけど、前に入荷したけど売れなくて。でもほんとに黒いだけで飾り気がないから、男性にも使いやすいでしょう」
「……ありがとう、ございます」
「黒は魔除けの意味もありますからね。道中、お気をつけて」
無邪気な笑顔を浮かべる微に見送られ、夕月は店を後にした。
もらった日傘は、開くと裏も表も吸い込まれそうな黒色をしていて、日の光を全く通さない。傘のおかげで暑さもマシに感じる。
「……黒は黒でも魔除けの黒、か」
道路の向かい側をふと見ると、神社の入り口にある植え込みの影で、一匹の黒猫が座り込んでいた。
夕月は一瞬、息をのんだ。
だが、黒猫は彼に気づく様子もなく、呑気に顔を洗った後、「にゃおん」と一声鳴いて、陽炎の向こうに消えていった。
ーー
猫の放し飼いは野生動物を捕食するので生態系の脅威になります。あとこの暑さなので、猫のためにも猫はお家にしまいましょうね(とらつぐみ・鵺)
