
イェール大学建築学科(YSoA)について
0. はじめに
昨年9月からアメリカの建築修士課程での留学を始めて、早いもので半年近くが経った。英語のみの環境に身を置いて、常々どこかで日本語をせめて「書かなきゃ」まずいと思いnoteのアカウントを作ってはみたものの、なかなか重い腰が上がらず、箇条書きの下書きを貯め続ける日々を送ってきた。いよいよ一稿投稿できそうなわけだが、noteを始めようと思ったもう一つの大きな理由として、アメリカの建築教育、もっと正確に言えば私の通うイェール大学建築学科(通称:YSoA)の教育やカリキュラムについて共有したいという思いが強かったことが挙げられる(というのも、僕が受験した時はイェールの情報など皆無で、オープンキャンパスまで来てようやくその雰囲気が少しわかるといった有様だった)。そこで今日はザックリとイェールの建築学科について紹介して、今後スタジオ課題やピーターアイゼンマンの形態分析、その他諸々僕が思うことについて投稿していきたいと思っている。
1. イェール大学の場所
イェール大学はアメリカ東海岸、コネチカット州のニューヘイブンという丁度ニューヨークとボストンの間あたりにある街を所在地としている。ニューヨークまでは電車で2時間半、往復30ドル程度で行けるので、週末に遊びに行くには丁度良い距離だと言える。基本的にニューヘイブンには何もないので(笑)、学生は課題が忙しくなければ大体週末はニューヨークに出かけて遊び散らかして戻ってくる。スタジオ講師や教授陣も多くがニューヨークに事務所を持っており、通勤時間を考えて授業は大体午後開始と、夜更かし大好き&朝起きれない僕にとってはとてもありがたい環境である(アイゼンマンだけはなぜか朝9時に来る...)。
ニューヘイブンといえば貧困と治安の悪さでも有名で、キャンパス周辺は人がほとんど居ない団地や黒人居住区が数多くあり、発砲事件や強盗も時折発生している。とは言え、キャンパス内と街の中心部(ダウンタウン)はとても安全で、僕も半年の滞在で一度も危ない目にあったことはない。
ここまで聞くとあまり良いところの無さそうなニューヘイブンだが、実はニューヘイブンはルイスカーン、ポールルドルフ、エーロサーリネン、ゴードンバンシャフト、ロバートヴェンチューリ、チャールズムーアらといった、近代建築に多大な影響を与えた建築家達による作品がわんさかある、建築の宝庫みたいな街なのである。その筆頭がキャンパスの南端に位置する、ポール・ルドルフ設計の我らが建築学科校舎、Yale Art and Architecture Building (1963)、通称ルドルフホールである。


(上:Yale Art and Architecture Building、下:校舎の壁面テクスチュア)
写真の通り、ルドルフの代名詞とも言えるコンクリートによるブルータリズムを前面に押し出したデザインとなっている。壁はどうやらわざわざ三角形のギザギザ付の型枠を使って仕上げたようで、石による素材の粗さとギザギザの精緻さが同居する両義的なテクスチュアとなっている。どうでもいい話だがこのギザギザ、背中を当てると丁度いいところに突起が当たるので講評前に僕はいつもセルフマッサージをして緊張を和らげている(笑)。後述するが、表面から読み取られる建物の量塊性とは裏腹に、内部はとても複雑な構成になっており個人的にはこの建物が大好きなのだが、竣工当時(1963)は大変不評だったようで、ルドルフはその不評に耐えかねて建築学部長(在任期間:1958-1964)の座を降りて以後一切この建物について触れなかったとのことである。ちなみに、この建物の向かいにはルイスカーンを一気にスターダムに押し上げたYale University Art Gallery (1953)、さらにその向かいにはカーンの遺作であり最高傑作との呼び声も高いYale Center for British Art (1974)がある。この2つの建物については、それぞれ丸々記事一本書けてしまうほど奥が深いので、ここではあえて触れないことにする。

(写真手前がYale University Art Gallery、右奥がYale Center for British Art、そのさらに遠く奥にはルドルフの立体駐車場、ケヴィンローチのKnights of Columbus Building (1969)も見える。)
このように、イェール大学、並びにニューヘイブンは、偉大な建築家達の足跡がまとめて見れる、建築学生にとっては舌舐めずりするほど魅力的な環境であり、無論、僕もYSoAのカリキュラム以上にこの学習環境に恋に落ちたと言っても過言ではないのである。



(上からバンシャフトのBeinecke Library (1963)、サーリネンのIngalls Hockey Rink (1958)、Ezra Stilles & Morse College (1962))
2. ルドルフホール
次に僕が惚れ込んだYSoAの校舎内について紹介したい。前述の通り、このルドルフホールは一見シンプルに見える素材と見た目に反して、内部はまるで迷路みたいに複雑な構成になっており、以下の断面パースからもその複雑さがわかる。

(引用元: https://www.dezeen.com/2014/09/26/yale-art-and-architecture-building-paul-rudolph-brutalism/)
ちなみにこの断面パースは、クラシックとモダニズムの大きな違いの一つである「断面図の複雑性」を表すドローイングとしてとても有名で、校舎の3階事務室前にルドルフの手書き図面が堂々と額縁に入れられて飾られている。その仕上がりは数年前に日建設計のドローイング展で見た中野サンプラザの手書き断面パースに匹敵するレベルで、3階に立ち寄る際はいつも一度眺めてから立ち去るようにしている。話が脱線したが、建物の構成としては2階と4階の中央が吹き抜けになっており、さらにその両脇には4階から7階まで採光のための吹き抜けがあり、そのさらに外に学生のスタジオスペースや事務室がロの字状に配置されているといった仕組みである。中央の2階吹き抜けゾーンはギャラリー、4階の吹き抜け、及び6,7階の中央ゾーンは通称ピットと呼ばれており、中間・最終講評の際には学生全員がこのピットに大集合、ピンアップ(プレゼンシートを壁に貼ること)し、先生の前で発表をするようになっている。特に4階で発表する際はピットは大忙しで、5階の縁から他学年の生徒がずらーっと観客として並び、お祭り騒ぎの様相を呈すのである。



(上2つは4階ピットでの講評の様子、3枚目は5階から4階を見下ろす)
余談だが3枚目の写真にある通り、4階ピットでは毎セメスター「ルドルフオープン」と呼ばれるバドミントントーナメントが開催され、学生はペアを組んで任意でトーナメントに参加できる。これが結構ハイレベルなトーナメントで、勝ち上がるとそれなりの景品とトロフィーがもらえる一方、最終講評と準決勝・決勝が同じ週という、勝ち残っても到底ベストコンディションでは戦えないちょっと不思議な大会となっている(笑)イェールは遊びにもかなり力を入れており、まさにwork hard play hardという言葉がぴったりの環境と言える。
お気付きの方もいるかと思うが、中央ピットの床のカーペットは一面オレンジ色になっており、YSoAの間ではパプリカ(Paprika)の愛称で親しまれている。ちなみに学内誌もこれにちなんでPaprika!という名前で出版されている。このカーペットは2008年に前学部長のロバート・A・M・スターン (在任期間:1998-2016)が、建物の全面改装の一環で寄付したカーペットで、それまでのブルータルな印象から一気に明るい雰囲気に校舎内を変えて、皆このカーペットが大好きなのである。
次に学生の作業スペースを紹介する。エントランスからエレベーターを上がって右手に進むと僕らのスタジオがある。スタジオの階は学年によって分かれており、僕ら1年生は6階、2年生は5階、3年生とポスト・プロフェッショナル課程(後述)の子は4階と7階という構成になっている。





(上からエントランス、6階スタジオ入り口、スタジオスペース、6階ピット、僕のデスク)
各学生には前後ろ大きな机とパソコン1台とスクリーン2台が割り当てられており、基本的に前の机で図面なりドローイング作業をして、後ろの机で模型を作るというスタイルがスタンダードのようだ。学生の作業スペースの広さは恐らく東海岸の建築学科の中でも最も良い方らしく、YSoAの売りの一つであると言える。講評のないエスキス(desk crit)の時には、先生が学生のデスクを巡回して、個別に作品について議論するようになっている。前述の通り、上の写真3枚目のような作業スペースがぐるっと4枚目のオレンジ色のピットを囲んでおり、グループで作業する時などはこぞってピットに大集合というわけである。フロアにはレーザーカッターと3Dプリンターも完備されており、印刷する要領で模型なり部材をすぐに作ったり切り出せるのも大きな魅力の一つである。


(上:作業スペース横の3Dプリンター、下:各階に備え付けのレーザーカッター)
続いて地下と7階屋上スペースについて紹介する。まず地下階は2つあり、B1階にはHastings Hallと呼ばれる小さいオーディトリアムがあり、講義やレクチャーの多くはここで行われる。ホールの前の廊下にはカーンの模型やベネチアビエンナーレで展示されたアイゼンマンの金ぴかカンポ・マルツィオ(ピラネージ)の3次元空想模型も展示されている。ホールのデザインは賛否両論あり、どうやら登壇すると壁が迫ってくるように感じて先生たちの間ではとにかく不評のよう。僕は暗い時に眠くなってしまうのをどうにかしてほしい(笑)


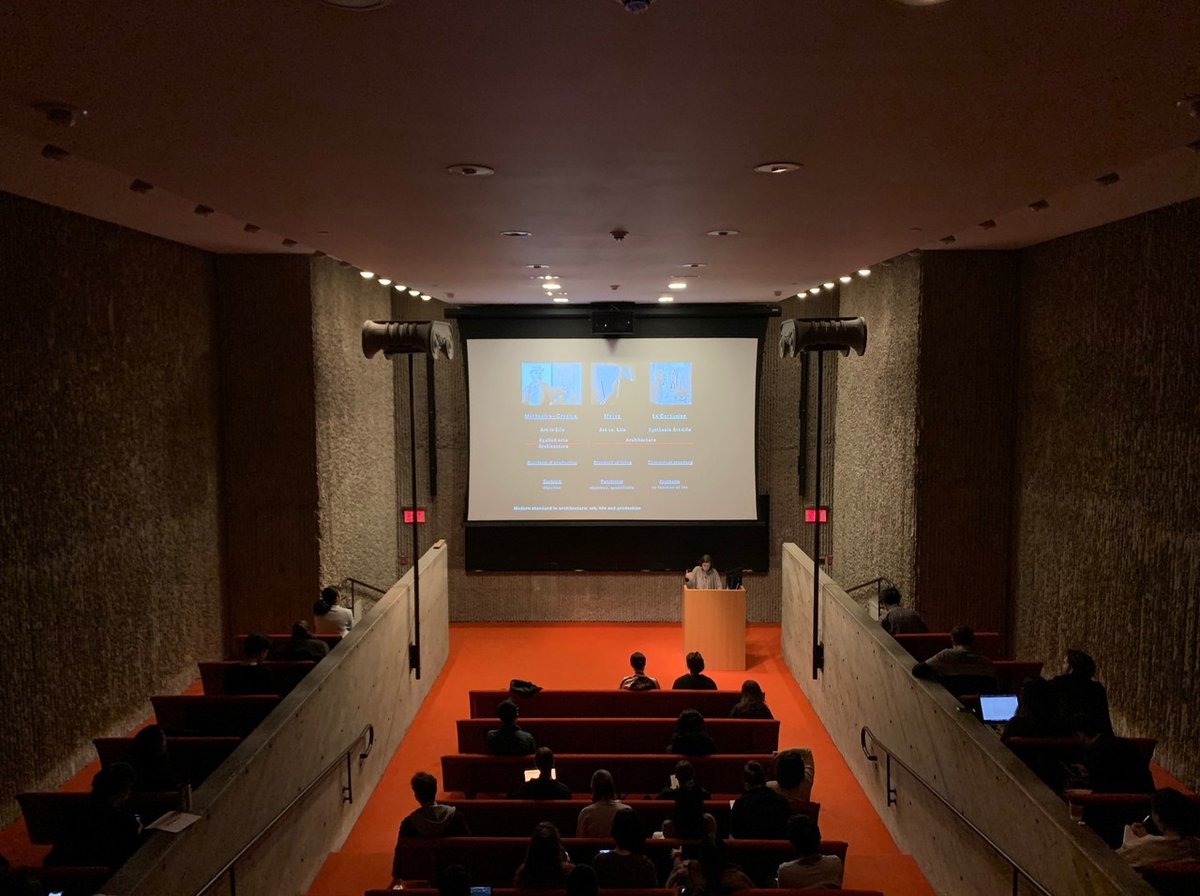
(上からホールへと続く廊下、金ぴかピラネージ、Hastings Hallでの授業の様子)
B2階にはショップと呼ばれる工房スペースがあり、大きい模型や木材、金属を加工する時は基本的にここを使う。ショップにはどデカイカッターやどデカイ研磨機、どデカイCNC Millやロボットアーム、挙げ句の果てには溶接工房まで揃っており、ちょっと僕にはoverwhelmingかつ危険という先入観が拭い去れないため、未だに使うのを若干躊躇してしまうといった有様...。卒業するまでには全部の機械を使いこなせるようになりたいところである。

続いて7階の屋上スペースだが、ここでは毎週金曜日に6on7と呼ばれるパーティーが開催される。毎週交代で1年生がビールなりピザなりお菓子なりを調達してパーティーのテーマを企画し、6時から全学年集まってわいわいやるというわけだ。加えて毎週担当の1年生はテーマに沿ったポスターを作成しなければならず、学長のデボラやアイゼンマン、フォスターゲージなどをクソコラするのが暗黙の了解になっている。残念な事に、屋上でパーティーをしている様子を一枚も撮っていなかったので、下の写真を盛大にライトアップしたイメージを想像してもらいたい。ちなみにこの屋上横にはルドルフ専用の事務室があり、現在はゲストのためのペントハウスになっている。



(上から屋上の様子と屋内で開催した時の6on7、昨年作成したポスター)
最後に僕がこの建物で一番好きな空間、非常階段を紹介してカリキュラムや授業の説明に移りたい。





僕がなぜこの非常階段が好きかというと、上の写真にある通り、各踊り場には建築の模型の他に様々な壁画や彫刻のレプリカ(あるいは本物?)が展示されており、非常階段にも関わらずなかなかインスピレーションに溢れた空間になっているためである。実はこれらの展示物は全てルドルフの私財であり、建築棟が完成した際に寄付したものらしい。この他にも、壁面には宝探しの要領でルドルフのアメジストやコレクションしていた貝殻がところどころ埋め込まれていて、講評前、徹夜続きの夜中に朦朧とした意識でこの階段を上り下りしていると、学長時代に同じく夜中に生徒の作品を巡回して厳しく指導していたルドルフにハッパをかけられているような気がして、頑張れる(ような気がする)のである。

3. YSoAの建築教育
最後にYSoAのカリキュラムについて説明してこの記事を締めくくる事にする。一般的にアメリカの建築修士課程は、
① 建築を学部で専攻しなかった学生でもアプライできる3年間のM.Arch1
② アメリカで5年制の建築学士号を持っている、あるいは他の国で建築士免許の受験資格が与えられる学部を卒業した学生がアプライできる2年間のM.Arch2
の2つに分かれている。僕の場合は「日本で建築士免許の受験資格が与えられる学部を卒業」しているので、M.Arch2にもアプライできたが、実質建築を勉強したのは3年かつ学部が建築学科では無かったため、M.Arch1にアプライする事にした。結果的にこの判断は良かったと今の所思っていて、半年間過ごしてみて体感として2年間の留学はあっという間なので、建築にどっぷり浸かりたいのであれば断然M.Arch1が個人的にはオススメだと思っている。加えて、M.Arch1は単独でアメリカの建築士受験資格が与えられる一方、M.Arch2は資格がもらえないため、海外留学生でアメリカの建築士資格が将来的に欲しい人は必然的にM.Arch1にアプライする必要がある、ということだ。ちなみに前述のポスト・プロフェッショナル課程というのはM.Arch2の事を差している。この他にYSoAではM.E.D(Master of Environmental Design)という修士課程もあり、こちらはM.Arch系のカリキュラムの根幹をなすデザインスタジオが必修ではなく、リサーチが中心の2年プログラムになっている。他校ではさらにややこしい、「M.Arch1の1年目免除」というカリキュラムを提供しているところもあり(YSoAにはない)、受験する場合は各学校のシラバスによく目を通す必要がある。
学生の年齢層というのも僕は留学前一つ気にしていたのだが、僕(現在24歳)で最も若い学生のうちに入る。やはりアメリカは1、2年程働いた後に修士課程に進む学生が多く、日本のように学部から直接修士課程に進む学生はむしろレアである。すでに結婚している学生、子供のいる学生も少なくない。
次にYSoAの詳細のカリキュラムについて紹介する。1年目、2年目は一般的にコアスタジオと呼ばれる、各学期必修の日本で言うところの設計演習があり、このコアスタジオを中心に同じく必修の近代建築史や構造、建築理論、ビジュアライゼーションなどの授業が展開される。普通の授業の単位数が3であるのに比べて、コアスタジオの単位数は9(!!!)もあり、いかにカリキュラムの中でスタジオの比重が高いかがわかる。コアスタジオは基本的にアメリカでブイブイ言わせ始めてる若手建築家や学校の古株先生が講師の場合が多く、これが3年目になるとアドバンスドスタジオという授業に変わり、こちらは世界でブイブイ言わせてる建築家がスタジオの先生になる(あの安藤忠雄、フランクゲーリー、ザハハディドもこのスタジオを教えていた)。3年目はアドバンスドスタジオ以外の授業は自由選択科目となり、好きな授業を年間で5つ取れる。ちなみにM.Arch2の場合はコアスタジオをすっ飛ばして1年目からこのアドバンスドスタジオが必修になり、M.Arch1と比べて1個多くこのスタジオが取れるようになっている(最後の学期はThesisと呼ばれる卒業設計になる。ThesisはM.Arch1には無い)。余談だが、こちらも現在世界でブイブイ言わせてるイギリスの建築家、ノーマンフォスターとリチャードロジャースは共にYSoAの同級生で、このスタジオで意気投合し後にあのハイテク建築スタイルを築いていったとのこと。このカリキュラムの基本構造は聞いたところによると東海岸の建築学科ではほぼ共通と見てよさそうである。
この東海岸共通の基本カリキュラムの中でも特にイェールの良いところは、学生の数が比較的少ないため(1学年50人程度)自由選択科目で好きな授業がほぼ確実に取れるといったところだろう。学生が少ないのは他にもメリットがあり、先生の目が各学生に行き届く、全員の顔と名前が一致する、家族みたいな連帯感が生まれる、などなど良い点が多いと個人的には思っている。
話が東海岸全体まで広がってしまったが、YSoAのM.Arch1のカリキュラムにもう少し深入りすると以下のような構成になっている
・1年目秋
コアスタジオ、近代建築史、ビジュアライゼーション*1、構造*2
・1年目春
コアスタジオ、建築理論、住宅設計*3、構造*2←僕は今ココ
・2年目秋
コアスタジオ、環境設計、アーバンデザイン、自由選択科目
・2年目春
コアスタジオ、建築システム、自由選択科目2つ
・3年目秋
アドバンスドスタジオ、建築実践・マネジメント、自由選択科目2つ
・3年目春
アドバンスドスタジオ、自由選択科目3つ
ここで*印をつけた授業については追加で説明をする必要がある。まず*1のビジュアライゼーションは、1年秋の必修であるものの、さらにこの中に授業の選択肢が3つあり、僕がよく投稿しているピーターアイゼンマンの形態分析1(Formal Analysis 1)がこのうちの1つなのである。他の2つの授業は大変申し訳ないものの眼中になかったため、正直よくわからない。ピーターアイゼンマンをよく知らない人のために説明すると、1950、60年代に革新的な建築理論を展開したコーリンロウの直系の弟子であり、自身も世界的な建築家になったと同時に20世紀、21世紀の建築理論の展開に重要な役割を果たした、御年87歳の建築界の大御所中の大御所なのである。アイゼンマンについてはどこかでまた詳しく書きたいと思っているが、何はともあれ、この形態分析の授業はYSoAで18年間続いている名物授業の一つなのである。
授業の内容は、ルネサンス以降、名目上最初の建築家となったブルネレスキからアルベルティ、ボロミーニやピラネージらの作品を毎週分析するというもので、これに加えて今学期からは形態分析2(Formal Analysis 2)という授業が始まり、こちらはコルビュジエからルイスカーン、レムコールハースなどといった直近の建築家らの作品も分析する。僕はこの授業があったからイェールに来て良かったと思えるほど、毎週大きな影響を受けている。というのも、「建築」という概念そのものが西洋から輸入されたものであり、建築には建築を作る内的なロジックとディシプリンがありそれが西洋ではルネサンスから綿々と受け継がれている、ということに初めて気づかせてくれた授業だからである。もっと分かりやすく言うと、例えばコルビュジエのサヴォワ邸は建築学生なら誰もが知っている作品だが、じゃあその作品のどういった「操作」が他と比べて革新的だったのか、この「操作」を教えてくれる授業が形態分析なのである。日本では(少なくとも僕の学校では)これらの作品の「特徴」や「スタイル」、「背景」については教わったものの、壁や柱、床といったものの「操作」、すなわち設計については教わった記憶が無く、僕からすると「初めて」建築の勉強をしている気すらしてくる授業なのである。カリキュラムの中では、コアスタジオで慣習を打ち破る(!!!)ような新しい建築の可能性を探求しながら、同時に形態分析で過去からの建築の「決まりごと」を勉強する、いわば挟み撃ち的なイメージの授業なのである。(僕の形態分析1のポートフォリオをオンライン公開しているので、興味のある方は次のリンクからぜひ "Formal Analysis 1_Portfolio")


(上 : 形態分析1のブラマンテ回、下 : 形態分析2のルイスカーン回)
次に*2の構造についてだが、これはただ単に構造の勉強をしたことのある学生はこの必修を免除して代わりにもう一つ自由選択科目を取れる、ということである。ちなみに僕は免除することができたため、秋は学科外の林業学科(School of Forestry)の授業を取ってみたが、結果的に日本語でも恐らく難しい専門外の授業を英語で受ける羽目になり、最後の方はてんやわんやであまり良い思い出はない(笑)。そして今学期は構造の代わりに上述の形態分析2を取ることができた、というわけである。
そして最後にもう一つの名物授業である*3の住宅設計(通称:BP=Building Project)についてであるが、これは春学期と夏にかけて全員で住宅を一から設計し、施工も自分たちで行うという、超パワープレイ授業である。内容としては、ニューヘイブンの住宅支援団体であるコロンバスハウスという組織と協力して、ホームレスのための支援住宅を学校の近隣に建てる、というものである。ニューヘイブンの住宅不足と貧困の解決に、建築学科として何かアプローチできないかという希望から、元学部長のチャールズムーアが始めた地域密着型の授業であり、僕たちからしたらいわば学生のうちに実務を経験できる贅沢授業とも言える。お気付きの方もいるかと思うが、この住宅設計とコアスタジオはまさかの同時並行、すなわち一学期にスタジオを2個取るような殺人的なスケジュールなのである。とはいえ、学生の中にはこのBPをやるためにYSoAに来た、という子もいるほどで、イェールのカリキュラムを他の学校と比べて特別なものにする、重要な授業の一つであると言える。秋学期と似たような感じで、春はコアスタジオで住宅(言い忘れたがスタジオの課題も住宅設計)のコンセプチャルな側面を探求し、BPで地域や実務といった社会・構造・材料的な制約と対峙する、といったイメージなのである。

(こちらは現M.Arch1の3年生による作品。何の雑誌主催か忘れたが、この年の世界最優秀建築賞を受賞したらしい...
まとめとして、YSoAのカリキュラムは学年が上がるにつれ授業の自由度が増す一方、1年目は学校の教育思想の根幹を為す必修科目が中心で、古典と現代、デザインコンセプトと社会の要求をそれぞれ両極から抑えてその統合を図る授業構成が特徴的であると言える。
4. 最後に
予定を大幅にオーバーしてつらつらと長文を書きまくってしまったが、最終的に何が言いたいかというと、僕はイェールの建築学科が大好きだということです。もし今年、あるいは今後アメリカに建築留学をする、あるいは考えている日本の学生がいたら、まず実際にその学校のオープンハウスに旅行ついででもいいので行ってみることを強くオススメします(今年はコロナウィルスで厳しいかもしれませんが...)。知名度やウェブ上の情報からはわからない、自分の地肌に合った学校の雰囲気というものが必ずあるはずです。今回紹介しきれなかった事は、次回以降かいつまんで記事にできたらいいなと思っています。

(形態分析の授業の様子 photo credit:何競飛,YSoA, M.Arch1)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
